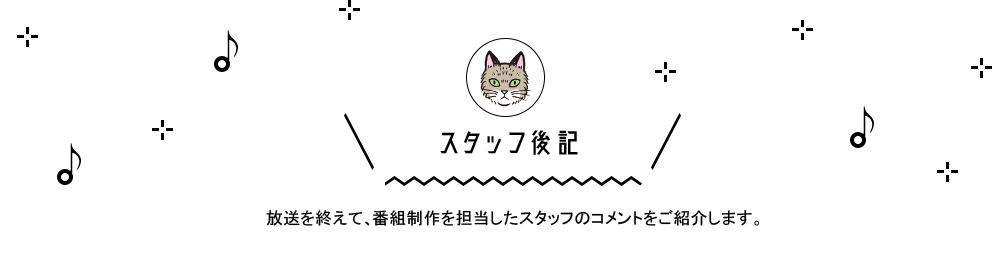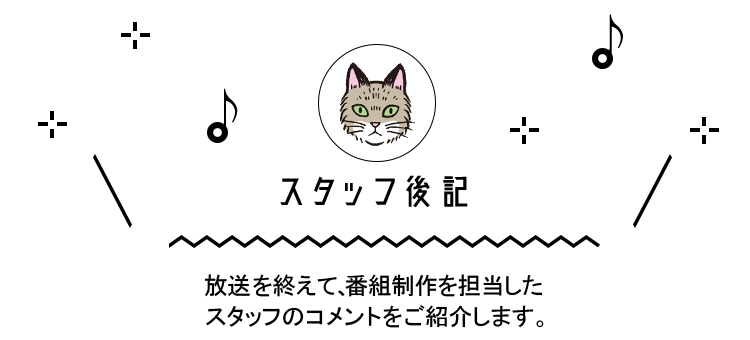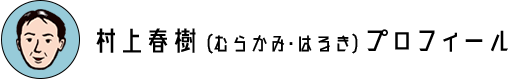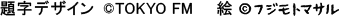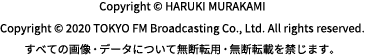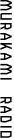


-
こんばんは,村上春樹です。今夜は「村上の一生ものレコード」というタイトルで、僕がいつまでも聴いていたいと大事にしているレコードを紹介したいと思います。それも「これぞ名盤」みたいな鉄板ものはできるだけ外(はず)して、「世間的な評価はともかく、あくまで個人的に偏愛(へんあい)している」みたいなものを取り上げてみたいと思います。
さて、どんな音楽が出てくるでしょうね。お楽しみに。今日は全部そっくりうちのアナログ盤でお送りします。
<オープニング曲>
Donald Fagen「Madison Time」
考えてみれば、ずいぶん長い年月、音楽を熱心に聴き続けています。家でも毎日何かを聴いています。ところが、うちの奥さんは音楽にほとんど興味のない人で、自分から進んで何かを聴くということがまったくありません。どうやら「今、こういう音楽が聴きたい」というような欲求はないみたいです。僕とはずいぶん違います。しかし「これは聴きたくない」という音楽はしっかり一貫(いっかん)してあるみたいで、僕がそういうものをかけると、ぶつぶつ文句を言います。不思議な性格ですね。いや、不思議じゃないのかなあ?長い間結婚生活を送っていると、何が不思議で何が不思議じゃないか、だんだんわからなくなってきます。みなさんのお宅はいかがでしょう?
-
ナット・キング・コールはもともとジャズ・ピアニストとして評価の高い人でしたが、途中で歌手に転向しました。本人はもっとジャズをやりたかったみたいだけど、ポピュラー・ソングを歌う歌手として人気が高くなりすぎて、ジャズ演奏のお声がかからなくなってしまったんです。ピリッと渋い、優れたジャズ・ピアニストだったんですがね。でもこのレコード「アフター・ミッドナイト」では、歌手としてのコールと、ジャズ・ピアニストとしてのコールがうまくかみ合って、聴きごたえのあるパフォーマンスになっています。
ピアノはもちろんコール、そこにゲスト・ミュージシャンとしてファン・ティゾールやスタッフ・スミス、ハリー・エディソン、ウィリー・スミスといった練れた実力派ミュージシャンが加わり、一曲ごとに一人が見事なソロを聴かせてくれます。クラブでバンド演奏を終えたあと、友だちのミュージシャンが遊びに来て、軽くお酒でも飲みながら、自分たちだけの親密な音楽を演奏するという設定でレコードが作られています。洒落(しゃれ)てますね。いつまでも永く聴いていたいレコードです。
スタッフ・スミスの艶やかなヴァイオリン・ソロがフィーチャーされた「夢見るころを過ぎても」を聴いてください。
-
*本文の表記は、ラムゼー提督です。
僕はポール・マッカートニーの音楽が好きです。日本では、というかおそらく世界的に見て、ポールよりはジョン・レノンの音楽のほうが評価がいくぶん高いみたいですね。とくにビートルズの解散後は「ポール・マッカートニーの音楽は商業的だ!堕落している!」みたいに言われることが多かったかもしれない。ポールの音楽にはジョンのような思想性がない、みたいに。まあ、たしかにそうかもしれない。でもポールの作る音楽には彼ならではの、独特の軽みと温かみがあって、それでいて意外に甘ったるくならないんです。僕はそういうところが好きです。もちろんジョン・レノンの音楽も素晴らしいとは思いますけど、それはそれとして……。
で、やたらいっぱいあるポールのアルバムから、どの一枚を選ぶかというと、僕は初期の作品「RAM」を選びます。これ、世間的にそれほど高い評価を受けているアルバムではないみたいだけど、僕はなぜかこれが大好きで、よく聴いています。中でも「アンクル・アルバートとハルゼー提督」が好きです。途中で曲調がガラッと変化するところなんか、いかにもポールという感じでたまらないですよね。
聴いてください。独立後まもないポール・マッカートニーの歌う「アンクル・アルバートとハルゼー提督」
-
映画『羊たちの沈黙』の中で、ハンニバル・レクター博士はガラス張りの独房の中で聴く音楽として、バッハの「ゴルトベルク変奏曲」を選んでいました。グレン・グールドの、亡くなる直前の新しい吹き込みの方ですね。レクター博士、なかなか賢明なチョイスだとは思いますが、もし僕が独房に入れられるとしたら――もちろんぜんぜん入れられたくなんかないですが、もし入れられるとなったら――僕はおそらく同じグレン・グールドの演奏でも、バッハの「イギリス組曲」を「独房の一枚」として選びたいと思います。
「イギリス組曲」、なぜか昔から好きなんですよね。同じグールドが弾いていても、「ゴルトベルク」のような強烈なカリスマ性はないんだけど、一音一音がなぜか僕の心にぎゅんと染みついています。この曲集、並のピアニストが普通に弾くとけっこう退屈な音楽になってしまいがちなんだけど、グールドの演奏は聴きどころ満載で、何度聴いても飽きません。とくに左手が、生きた動物のように強靱(きょうじん)に動き回る様を目の当たりにしていると、わくわくしてしまいます。右手の内省に対する左手の自我、みたいな構図なのかなあ。
グールドの演奏では、ブラームスの曲集も好きで、どっちにしようかとちょっと迷ったんだけど、やはりバッハは深いです。繰り返し聞くのなら、どうしてもこちらになります。
組曲第一番の一曲目「プレリュード」を聴いてください。
-
テナー・サックスの名手、スタン・ゲッツは長いキャリアの中で数々の名盤を残していますが、僕はそれほど世評(せひょう)の高くない「Stan Getz in Stockholm」をあえて「一生もの」の一枚として選択しました。「オーバー・ザ・レインボー」を聴いてください。
このレコードはタイトルのとおり、ゲッツがスウェーデンで録音したものです。バックのリズムセクションはすべてスウェーデンのミュージシャンです。
1955年の録音ですが、ゲッツはこの時期、麻薬とアルコールの濫用(らんよう)で身体がぼろぼろになって、ヨーロッパに逃げのびているような状態でした。おまけに感染症にかかって、重い肺炎を患い、しばらくのあいだ演奏活動もストップしていました。それでもなんとか体調を回復し、久しぶりに楽器を手に取って、現地のミュージシャンと共にスタジオに入り、レコーディングを行います。
でもこれがいいんですよね。決して意欲的なアルバムでもないし、取り上げられた曲も無難なスタンダードばかりだし、いつもとは違う環境で、おまけに肺炎あがりの身で、なんだか恐る恐る楽器を吹いているようなところもあるんだけど、そのぶん虚心坦懐(きょしんたんかい)というか、生来(せいらい)の歌心が穏やかに湧き出ていて、ゲッツ・ファンとしては、そのあたりがなんともいえず愛おしいんです。好調時のゲッツの熱っぽさは残念ながらここではうかがえませんが、そのぶん彼のアイドルであったレスター・ヤングを彷彿(ほうふつ)とさせる、温かくたおやかな演奏になっています。そんなわけで、僕はあくまで個人的にこのレコードをひいきにしております。
-
エルヴィス・プレスリーもその長いキャリアの中で、実に数多くのアルバムを出していて、一枚を選ぶのにたいへん苦労します。僕は彼が陸軍を除隊したあとにおこなった一連の吹き込み――「サッチ・ア・ナイト」なんかが入っているやつですね――そのあたりが個人的に好きなんだけど、一枚のレコードだけを選べと言われたら、やはりこの最も初期のアルバム、1956年にリリースされた彼のデビューLP「Elvis Presley」に手が伸びてしまいます。レコード会社はRCA。これはまた、僕が最初に買ったエルヴィスのレコードでもあります。高校時代、レコードが擦(す)り切れるまで聴き込みました。だから今日おかけするのは後日、新たに買い直したレコードです。
このアルバムの中で僕がいちばん気に入っている曲を聴いてください。
「ワン・サイディッド・ラブ・アフェア」です。「ブルー・ムーン」もいいですが、これは以前にこの番組でおかけしたことがあります。二十歳になったばかりのエルヴィスの歌声は、メーターが振り切れるくらい力強く、そして異様なばかりに生々しいです。
-
今夜は「村上の一生ものレコード」というタイトルで、僕が大事にしていつまでも聴いていたいというレコードをおかけしています。
アーサー・プライソックは日本ではあまり知られていませんが、ビリー・エクスタインの流れを汲む黒人歌手で、深いバリトン・ヴォイスでアメリカ本国ではずいぶん人気を博していたようです。ジャズというよりはクルーナーに近い歌手です。でも、このカウント・ベイシーとの共演盤では、気持ちよく軽快にスイングするベイシー・バンドをバックに、しっかりジャズっぽく決めています。ちょうどコルトレーンをバックにしたときのジョニー・ハートマンみたいに。
聴いていただく曲は「What Will I Tell My Heart」。君と別れたこと、相手が他人なら、なんとでも言い訳できる。でも僕自身のハートに向かって、いったいどう説明すればいいんだろう? うーん、切ない失恋の歌ですね。
僕はたしか17歳のときに、神戸の元町商店街の日本楽器でこの輸入盤を買い求めました。17歳の少年が、どうしてこんな渋い内容のレコードを選んで買うことになったのか、そのへんの経緯はよく覚えていませんが、とにかくこのレコードをすっかり気に入ってしまい、長年にわたる僕の愛聴盤になっています。伝説的録音エンジニア、ルディー・ヴァン・ゲルダーの録音がとりわけ素晴らしく、とくにフレディ・グリーンの刻むリズム・ギターがくっきり明瞭に聞こえるところが、なんとも言えず良いです。
-
永遠の好青年、ジェームズ・テイラー。僕は彼の作品はだいたい全部揃えていますが、中でもいちばん好んで聴いているのは、「Walking Man」だと思います。
リチャード・アヴェドンのモノクロ写真を使ったレコード・ジャケットも秀逸(しゅういつ)だけど、中身の方も素晴らしい出来です。何度聴いても心がじんわりと和みます。まるで居心地の良い座り馴(な)れた椅子に座ったみたいな。
収められたオリジナル曲はどれもそれぞれに、するめのような長持ちのする味わいがあるし、デヴィッド・スピノザのアレンジも見事です。ブレッカー・ブラザーズもバック・バンドに入っています。1974年の録音、この時代の最良のサウンドがレコード全体にぎっしりと詰まっているみたいです。


- Clarinet Quintet K. 581 Allegro
Members Of The Vienna Octet
Mozart Clarinet Quintet K.581 Divertimento In F K.247
London Records
-
モーツァルトの室内楽曲で「一生もの」として選びたいものは、なにしろいっぱいあります。カルテットの「ハイドン・セット」とか、弦楽五重奏曲とかね。でもクラリネット好きの僕としては、最終的にはやはりイ長調のクラリネット・クインテットを選びたいと思います。いかにもウィーン風のたおやかな雰囲気を持つ名曲です。クラリネット協奏曲もいいですが、こちらの方が音楽の構造がより立体的に見通せて、何度聴いても飽きません。
そんなわけで、この曲、優れた演奏はたくさんあるんだけど、いかにもウィーンという風情(ふぜい)が濃く漂う、ウィーン八重奏団メンバーの演奏したレコードを選びました。肩の力がすっと抜けていて、でも音楽の背骨は半端なくまっすぐ伸びています。ウィーン八重奏団はウィーン・フィルハーモニーの楽団員で構成された室内楽団で、ここでは名手アルフレート・ボスコフスキーがクラリネット・ソロを受け持っています。1963年の古い録音ですが、実に聴き飽きしないんですよね、これが。頭から尻尾までピュアなモーツァルトが詰まっています。
「クラリネット五重奏曲」の第一楽章「アレグロ」を聴いてください。
-
なにはともあれ、ドアーズを外すわけにはいきませんよね。「ストレンジ・デイズ」にしようか、「ザ・ドアーズ」にしようかけっこう迷ったんですが、結局彼らのデビュー・アルバム「ザ・ドアーズ」を入れることにしました。「ライト・マイ・ファイア(Light My Fire)」のはいっているやつですね。
「ソウル・キッチン」を聴いてください。「君のソウル・キッチンで一晩眠らせてほしい。君のやさしいストーブで僕の心を温めてほしい」。ジム・モリソン・ワールド、まさに全開というところですね。うちにあるLPはオリジナル・モノラルです。タイトなモノラル録音でじっくり聴いてください。
このアルバムを聴くと、彼らの音楽のコンセプトがそもそもの最初から既に強固に確立されていたことがわかります。「奇跡的に」という言葉を使いたくなるくらい、びしっと完成されたアルバムです。適当につくられたトラックがひとつもありません。どれをとってもしっかり聴き応えがあります。
-
ピアニストのビル・エヴァンズが1962年にリバーサイド・レコードから出したアルバム、「インタープレイ」、これは僕が最初に買ったエヴァンズのレコードですが、どうしてこれを買ったのか、これもまたよく覚えていません。どうしてでしょうね? というのは、エヴァンズのリーダー・アルバムはピアノ・トリオ編成の演奏が中心で、管楽器が入ったものは数が少ないからです。そして世間的に人気があるのも、だいたいがピアノ・トリオものです。でもなぜか僕はトランペットのフレディ・ハバードと、ギターのジム・ホールが入った、ちょっとユニークなクインテット編成のこのアルバムからビル・エヴァンズの世界に入っていって、そこが僕にとっての原点みたいになっています。
エヴァンズのリリカルなピアノに、トランペットとギターの加わったサウンドがなんとも言えず心地よいんですよね。もちろんエヴァンズのピアノ・トリオものも愛聴していますが、個人的なチョイスの一枚となると、僕は最終的にこの「インタープレイ」というアルバムを選ぶような気がします。
時間まで聴いてください。タイトル曲の「インタープレイ」、エヴァンズの書いたクールなブルーズ曲です。これもまた、うちにあるモノラル盤なので、モノラルの音で聴いてください。
- 今日のクロージング音楽は、アルトサックス奏者ポ-ル・デズモンドの演奏する「ロマンス・デ・アモール」、「禁じられた遊び」のテーマです。

-
「村上の一生ものレコード」いかがでしたか? すべてアナログ・レコード、かけていて楽しかったです。このレコードも入れたい、あのレコードも入れたいと、けっこう悩みました。積み残しがいっぱいあります。できればまた続編をやりたいですね。
さて、今月の言葉は、僕が以前通っていたスポーツジムの壁に貼ってあった格言です。誰が考えたのか知らないけど、とにかくとても的確で、とても切実な格言でした。こういうものです。「筋肉はつきにくく、落ちやすい。贅肉(ぜいにく)はつきやすく、落ちにくい」
うーん、まさにそのとおりですね。「筋肉はつきにくく、落ちやすい。贅肉はつきやすく、落ちにくい」。ラジオの前で「うん、実にそのとおりだ」と肯(うなず)いておられる方も多いのではないでしょうか? 逆だといいんですが、なかなかそううまくはいきません。いちどついた贅肉、落ちにくいですよねえ。よくわかります。
「熊の宴会」って言葉ご存じですか? 僕が作ったんですが。
がんばって、日々堅実にダイエットを続けてきたのに、ある日夜中にふと目が覚めて、まるで何かのスイッチがぱちんと入ったみたいに理性のコントロールが失われ、本能の赴(おもむ)くままに暴飲暴食をしてしまう。冷蔵庫の中のものをがつがつ食べ漁(あさ)り、ビールもぐいぐい飲んでしまう。そして翌朝目覚めて、テーブルの上の空しい残骸(ざんがい)を目にして、「ああ、いけない、また熊の宴会をやっちまった」と悔やみます。あなたにはそういう経験ありませんか?
熊の宴会、怖いですよね。
それではまた来月。
- レコード全盛期には生まれていなかったので、レコードというともっぱら中古。新譜を目当てに買った経験はありません。でも中古だからこそ、ずっと探していたものが旅先で見つかったり、久しぶりに行った店で本日入荷の棚にあったり、自分じゃ買わないけど父親のお下がりで新たに出会ったりと、そういう巡りあわせというか出会いがある気がしていて、レコードが好きな理由はそれが大きい気がします。「一生もの」、これからたくさん見つけるぞー!(ADルッカ)
- 今回の村上RADIOは、村上春樹さんの一生ものレコード。神回だと思います。続編もお楽しみに。(キム兄)
- はて、僕にとって一生もののレコードは何だろう?そう思って久しぶりにレコード棚を探って出て来たのがビートルズ『レット・イット・ビー』でした。中学時代、地元の武蔵境の新聖堂に行って、それまで「一生」懸命集めた板垣退助の百円札20枚で、思い切って(何しろ初めて買うLPだったから記念に)買ったのでした。お札を数えた店主は、僕に大きなモノクロのビートルズのポスターをプレゼントしてくれました。(延江GP)
- 僕の一生ものは中学生の時に買ったヴィンテージエレキギターの写真集です。1957年製のレアカラーのストラトキャスターの写真を見て興奮してました。今見てもムラムラします。引いてますか? 誰にだってキモい一面はあるはず…。(CAD伊藤)
- いわゆるミニマリストでモノにあまり興味がありません。収集癖も皆無です。でも「一生ものレコード特集」はレコードというモノの堆積ではなく、音楽という無限の世界の入り口でした。音楽も小説もラジオも目に見えない。だから面白いのかもしれません(構成ヒロコ)
- レコードにはモノとしての固有の記憶が刻印されていますよね。買った店の佇まい、ジャケットの色彩やデザイン、初めて聴いた時のわくわく感……。それにしても村上さんの「一生もの」のレコード・コレクションは村上さんの生き方、小説の世界そのものです。ナット・キング・コールからドアーズまで、曲が登場するたびに物語を思い出しながらじっくり楽しく聴きました。個人的には「一生もの」の本も考えたくなりました。(エディターS)
1949(昭和24)年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。’79年『風の歌を聴け』(群像新人文学賞)でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』(野間文芸新人賞)、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(谷崎潤一郎賞)、『ノルウェイの森』、『国境の南、太陽の西』、『ねじまき鳥クロニクル』(読売文学賞)、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』(毎日出版文化賞)、最新長編小説に『騎士団長殺し』がある。『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』、『パン屋再襲撃』などの短編小説集、『ポートレイト・イン・ジャズ』(絵・和田誠)など音楽に関わる著書、『村上ラヂオ』等のエッセイ集、紀行文、翻訳書など著訳書多数。多くの小説作品に魅力的な音楽が登場することでも知られる。海外での文学賞受賞も多く、2006(平成18)年フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、’09年エルサレム賞、’11年カタルーニャ国際賞、’16年アンデルセン文学賞を受賞。