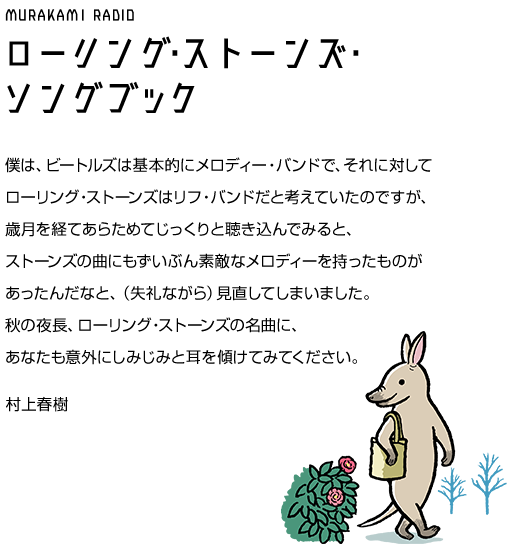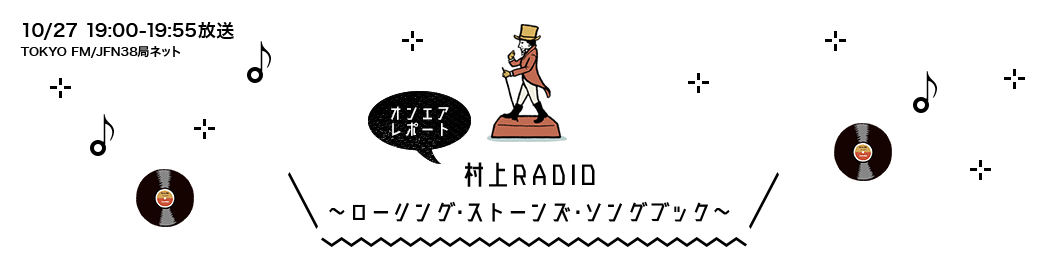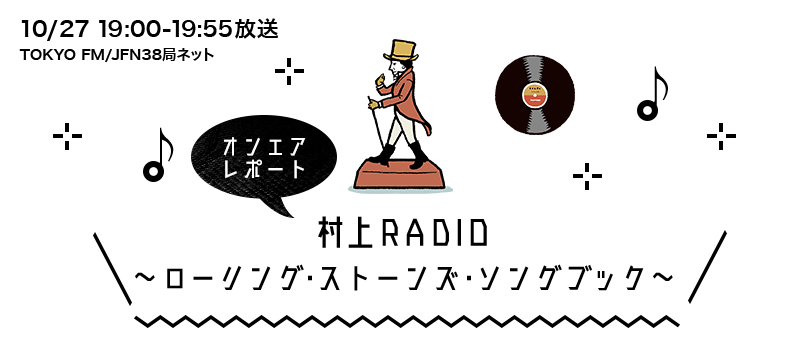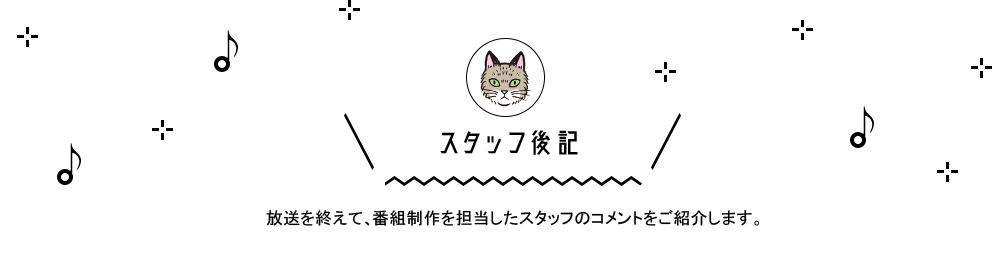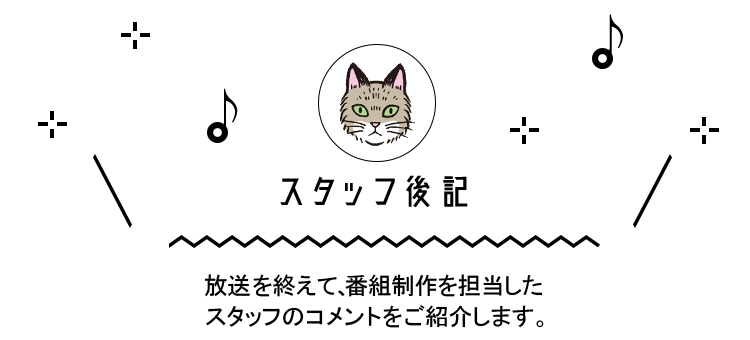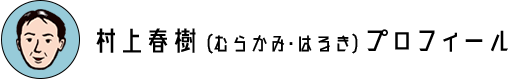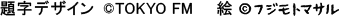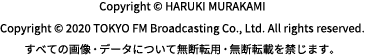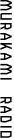


-
こんばんは。村上春樹です。村上RADIO、今日はローリング・ストーンズ・ソングブックをお届けします。この前にやったソングブック・シリーズはマット・デニスでした。マット・デニスからストーンズ、考えてみればかなりの飛躍ですね。しかしそういう大胆さがこの番組の持ち味です。見る前に飛べ。そう、大胆な飛躍こそが人生の醍醐味(だいごみ)です。
とはいえ、みなさんも着地にだけはくれぐれも気をつけてくださいね。思い切って飛んだはいいけど、着地する場所がなかったなんてことになると、とても困ります。
というわけでとにかく、ローリング・ストーンズ・ソングブック、元気にぶちかましましょう。
Let's Spend The Night Together!
Let's Spend The Night Together!(テーマ)
ローリング・ストーンズが結成されたのは1962年ですから、僕はその登場時からずっと、リアルタイムで彼らの音楽を聴き続けてきたことになります。ビートルズ、ストーンズ、そしてビーチ・ボーイズは、10代の僕にとっての素敵なバックグラウンド・ミュージックの役割をつとめてくれました。
でも実を言うとその当時、僕はストーンズもビートルズもビーチ・ボーイズも、レコードを買ったことがありませんでした。ただの1枚も。ラジオのスイッチを入れれば、それこそいやというほど彼らのヒットソングが流れていたから、レコードを買う必要もなかった。本当に至るところにまんべんなく流れていたんです。まるで記憶の中の部屋に貼られた壁紙みたいに……。


- As Tears Go By
Marianne Faithfull
Marianne Faithfull's Greatest Hits
London -
それではまず初期のヒット曲からいきましょう。「As Tears Go By(涙あふれて)」。この曲はもともとはストーンズの持ち歌ではなく、ミック・ジャガーとキース・リチャーズがマリアンヌ・フェイスフルのために共作し、提供したものです。
1964年、マリアンヌ・フェイスフルの歌でヒットして、ミックとフェイスフルはそれが縁で恋人同士になりました。ストーンズがこの曲を録音したのはその翌年、1965年のことです。とても美しいメロディーを持った曲ですね。マリアンヌ・フェイスフルの歌で聴いてください。
「As Tears Go By」、涙あふれて。
マリアンヌ・フェイスフル、可憐な歌声ですが、やがてドラッグと酒と煙草で身を持ち崩し、声を潰してしまいます。でもがらりと変わったハスキーな声で再起し、独特なスタイルを持つ個性派の歌手となります。僕は1997年に来日した彼女のコンサートに行きましたが、クルト・ワイルの曲ばかりを歌う内容で、心が揺さぶられました。「ああ、彼女もしっかり成長したんだな」と痛感しました。


- Beast Of Burden
Buckwheat Zydeco
Shared Vision 2 The Songs Of The Rolling Stones
Mercury -
次は「Beast Of Burden」、1978年にリリースされたアルバム『Some Girls』の中の1曲で、ビルボード誌の8位まで上がりました。僕が個人的に好きな曲の1つです。ザディコ(Zydeco)音楽の代表的シンガー、バックウィート・ザディコが歌います。「Beast Of Burden」。
Beast Of Burdenというのは、重い荷物を運ばされる動物のことですね。使役動物。君にいいように利用されるのはうんざりだ、もうくたくただ、みたいな歌詞です。なんか切実ですよね。


- Satisfaction
Otis Redding
Otis Redding Live In Europe
Voly Records -
僕は基本的にいえば、ビートルズは旋律を重視する「メロディー・バンド」、ストーンズはリズミカルなリフを重視する「リフ・バンド」というふうに捉えていたのですが、こうしてじっくり聴き直してみると、ミック&キースのチームが作った曲にも魅力的なメロディーを持つものがけっこうありますね。あらためて見直しました。
ストーンズはもともとがアメリカの黒人音楽、リズム&ブルーズをコピーすることを目的として結成されたバンドで、ブライアン・ジョーンズが中心になってその路線が維持されていました。でも1964年に企画された全米公演が今一つの成績に終わり、強力なオリジナル曲なしにはブレークできないと悟ったミックとキースは、チームを組んで本格的に作曲を始めます。そして1965年に「(I Can't Get No)Satisfaction(サティスファクション)」で大ブレークし、ビートルズのライバル・バンドにのしあがっていきます。
オーティス・レディングの歌で聴いてください。「(I Can't Get No)Satisfaction 」、ヨーロッパでの公演のライブです。スタジオ録音も素晴らしいですけど、このライブはほんとに火傷しちゃいそうなくらいホットです。
オーティス、すさまじい歌唱ですね。この曲はアレサ・フランクリンからディーヴォ、トム・ジョーンズに至るまで本当に数多くの歌手にカバーされていまして、どれにしようかとあれこれ迷っちゃうんだけど、オーティスの見事なカバーは、やはり外すわけにはいきません。


- (I Can't Get No) Satisfaction #1
The Beach Boys
Beach Boys' Party! Uncovered And Unplugged
Capitol - 今バックでかかっているのは、ビーチ・ボーイズの歌っているバージョンですが、オーティスのまさに対極にあるというか、聴き比べるとなんか微笑ましいですね。


- Sympathy For The Devil
Bryan Ferry
Jagger / Richard Songbook
CONNOISSEUR COLLECTION -
さて、これも僕が個人的に愛好する曲です。「Sympathy For The Devil」、「悪魔を憐(あわ)れむ歌」というか、「悪魔に気持ちを寄せる歌」ですね。この曲が発表されたとき、ストーンズは悪魔崇拝者だという根拠のない噂が飛び交って、ちょっとしたスキャンダルみたいになりました。
この曲のバックで「ウー・ウー」というお囃子(はやし)みたいなバックコーラスが入るんだけど、これがいいんですよね。僕も聴いていて、つい「ウー・ウー」と声を出してしまいます。
この「ウー・ウー」は録音スタジオのコントロール・ルームでプロデューサーが曲に合わせて「ウー・ウー」と口ずさんでいたのを、「それ、いいじゃん」ということで取り入れたんだそうです。このブライアン・フェリーのカバーでも、「ウー・ウー」は聴くことができます。
聴いてください、ブライアン・フェリーがカバーする「Sympathy For The Devil」、悪魔を憐れむ歌。


- Wild Horses
Otis Clay
Contemporary Blues Interpret The Rolling Stones
KRB -
いろんなブルーズ歌手がストーンズの曲を歌うトリビュート・アルバムがありまして、『Contemporary Blues Interpret The Rolling Stones』っていうタイトルなのですが、黒人ブルーズをコピーすることからキャリアを開始したストーンズの持ち歌が、本場の黒人ブルーズ歌手たちにカバーされるというのは、彼らにとってはやはり感無量だったんじゃないでしょうか。
その中からオーティス・クレイの歌う「Wild Horses(ワイルド・ホーセズ)」を聴いてください。野生の馬のことですね。とても良い曲です。1971年にリリースされたアルバム『スティッキー・フィンガーズ』に入っていました。僕はその頃、新宿の小さなレコード店でアルバイトをやっていまして、このアルバムをたくさん売ったことを覚えています。アンディ・ウォーホルがデザインした、例のジッパー付きブルージーンのジャケットのやつです。「ワイルド・ホーセズ」、オーティス・クレイ。


- Bitch
Herbie Mann
London Underground
Atlantic -
「ワイルド・ホーセズ」と同じアルバムに入っていたのが、この「ビッチ」です。LPのB面の1曲目でした。ストーンズって、刺激的というか、問題のあるタイトルをつけるのが好きみたいですね。ビッチ、雌犬、ふしだらな女。しかしこの曲のリフはいつ聴いてもかっこいいです。ビリビリきます。
ジャズ・フルートのハービー・マンの演奏で聴いてください。『ロンドン・アンダーグラウンド』というアルバムに収められています。大ヒットしたアルバム『メンフィス・アンダーグラウンド』の続編、英国版ですね。ロンドンのスタジオでの録音で、マンさんはイギリスの若いミュージシャンたちと共演しています。ここでギターのソロをとっているのは、オリジナルの「ビッチ」にも参加していたミック・テイラー、かっこいいです。
さっき、ストーンズは基本的にリフ・バンドで、ビートルズはメロディー・バンドだと言いましたが、もちろんそんなに単純にぴったり割り切れるものではありません。1960年代後半を併走してきた2つのバンドは、それぞれに相手を刺激し、それぞれに影響を与えています。ビートルズにもハードなリフを持った曲がありますし、ストーンズにも美しいメロディーを持った曲があります。このように2つの卓越したバンドが競って活躍したことによって、60年代のロックは目覚ましい深まりを見せていったということになると思います。
ビートルズは1970年前後にあえなく空中分解してしまいましたが、ストーンズはメンバーを1人、また1人と失いながらも現役バンドとして活動し続けています。ミックとキースは今でもがっちり手を組んでいます。その2つのバンドの違いがどこにあったのか? もちろん僕にも詳しいところはわかりませんが、いちばんの原因はたぶんストーンズが「おれたちは所詮、悪ガキのロックンローラーなんだ」と開き直っていたからじゃないかと思うんです。ビートルズのように、ラブ&ピースとか、東洋哲学とか、そういうカウンターカルチャーの精神的な側面に惹かれたりすることはなかった。もちろん少しはありましたけど、それほど強い影響は受けなかった。とにかくロックンロール一筋でやってきた。それが長年にわたってバンドとしての結束を維持できた1つの要因じゃないかと、僕は思うんですが。


- Honky Tonk Women
Travis Tritt
Stone Country
Beyond Music -
カントリー歌手のトラヴィス・トリットが「ホンキー・トンク・ウィメン」を歌います。この曲ってけっこうカントリーっぽいところがありますよね。
僕は1991年だっけな、92年だっけな、ニューヨークのシェア・スタジアム(Shea Stadium)でストーンズの公演を聴いたことがあります。ニューヨーク・メッツの球場ですね。(※メッツの現在の本拠地はシティ・フィールド。シェア・スタジアムは旧本拠地。取り壊しで今はありません)そのときはこの「ホンキー・トンク・ウィメン」が派手な見せ場になっていました。しかしストーンズのコンサートって、観終わったときに、「お腹いっぱいになった」という満足感がありますよね。最後に「サティスファクション」で思い切り盛り上がってね。
そのとき僕の後ろの席に日本人の若い男の子4人組がいまして、その子たちはストーンズの曲に合わせて全曲合唱するんです。かなりマイナーな曲も、新しい曲も、全部英語の歌詞を暗記していて。「うーん、すごいなあ」と感心しちゃいました。ストーンズ・ファンって、そういう熱狂的な人が多いんですかねえ。


- Ruby Tuesday
Melanie
Jagger / Richard Songbook
CONNOISSEUR COLLECTION -
「ルビー・チューズデイ」も忘れがたい曲ですね。1967年にシングル・カットされて、アメリカのヒット・チャートでは1位を獲得しています。ストーンズって最初のうちは、口当たりのいい、いわゆる「リバプール・サウンド」に比べて「かなり乱暴なバンド」っていう印象があったんだけど、この頃になると「へえ、こういうのもちゃんとできるんだ」みたいな穏やかな優しい曲を発表し始め、一般的な人気も獲得していきます。とはいえ本質はやはり「かなり乱暴なバンド」なんですけどね。
メラニーが歌います。「ルビー・チューズデイ」


- Satisfaction
Don Patterson
Satisfaction!
Prestige -
今日のクロージング音楽はジャズ・オルガン奏者ドン・パターソンのトリオが演奏する「(I Can't Get No) Satisfaction」です。
ローリング・ストーンズ・ソングブック、いかがでしたでしょうか? 今日おかけしたのはみんな、もう半世紀以上も前に作られた音楽なんですが、今聴いても心をリアルタイムで揺さぶってくれます……と僕は思うんですが、若い人たちはどう感じるんでしょうね? 感想を聞きたいところです。
しかし、ミック・ジャガーが80歳になってもまだバリバリの現役でステージに立って「サティスファクション」を熱唱しているなんて、10代の僕には想像もできませんでした。キース・リチャーズが元気に長生きするなんてこともね。

-
今日の言葉は、「ローリング・ストーンズ特集」に合わせて「転がる石には苔がむさない」です。英国のことわざで、原文は「A rolling stone gathers no moss」。
この言葉には2種類の意味あいがありまして、もともとは「仕事をコロコロ変える人は大成しない。人生には忍耐が必要なんだ」という、いかにも英国風の意味だったのですが、アメリカに渡ってからは「活発に自己ポジションを変えていく人は古くさくならなくてよろしい」というニュアンスで、転がることが肯定的に捉(とら)えられることが多くなりました。イギリス人は苔が好きで、アメリカ人はあまり苔がすきじゃないのかもしれないですね。国民性の違いかもね。
そういえば日本の国歌にも「苔のむすまで」という一節があります。うーん、日本人はきっと苔が好きなんでしょうね。苔が出てくる国歌なんて、世界中、他にはないんじゃないかな。僕も苔は割に好きです。アイスランドは緑の苔だらけの国で、旅行していてとても楽しかったです。
もし僕が石だったら、あまり転がらないでなるべくじっとしているかもね。
それではまた来月
- 今回個人的に興味深かったのは、ローリング・ストーンズとビートルズの比較考証でした。歳を重ねてベテランになっても若いころのフレッシュな感性を保ち続けるのって、結構難しいです。ミック・ジャガーさん、81歳。いやー、すごいですね(構成ヒロコ)
- 『パイレーツ・オブ・カリビアン』のジャック・スパロウはキース・リチャーズがモデルなんだそうですね。破天荒でロックなライフスタイルを半世紀以上続けてきて、今なお現役のロックスターであるローリング・ストーンズは映画の世界以上の怪物な気がします。Windwosのマークを見るとあの曲が頭の中に流れてきたり、「She's a Rainbow」を聞くとカラフルなパソコンを思い出したりする自分はいつの間にかもうおっさんなのですね。(CAD伊藤)
- 今回の村上RADIOは、1アーティスト/1グループにフォーカスするソングブックシリーズのローリング・ストーンズ回でした。ストーンズの曲がラジオから聞こえてくることは以前より少なくなったかもしれませんが、改めて様々なアーティストの解釈でアップデートされた名曲群を聞いてると、新たな発見と共に普遍的な強靭さを感じます。そこに解散せずサステナブルな集団を維持するヒントも隠れてるのかもしれません。見る前に飛べ!(キム兄)
- 村上DJはこの番組で自ら「カバーの鬼」と言ってきましたが、今回のストーンズ・カバーもどれも思わずうなる選曲です。3曲目の“I Can't Get No Satisfaction”は、「あれこれ迷っちゃうんだけど、オーティスの見事なカバーはやはりはずすわけにはいかない」と言いつつ、ビーチ・ボーイズによるカバーもしっかり紹介しています。初秋の夜のローリング・ストーンズ、びりびりきます!(エディターS)
- 正直あまり通らずにきたローリング・ストーンズ。今回のソングブックで多方面から知ることができました。もっと勉強してみます!ところでストーンズに並ぶほどの長寿バンドは今後も生まれるんでしょうかね。仲直りしたOasisがそうなったら面白いですね、(笑)(ADルッカ)
- もう何年も前のこと。ローリングストーンズにインタビューしたことがあります。ホテルオークラで。キース・リチャーズはずっとタバコを吸い続け、でもとても丁寧に僕の質問に答えてくれました。振り返ればミック・ジャガーがいて。なんて奇跡的な場所にいるんだろうと、春樹さんの言う『永遠の悪ガキたち』に会えて幸せでした。(延江GP)
1949(昭和24)年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。’79年『風の歌を聴け』(群像新人文学賞)でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』(野間文芸新人賞)、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(谷崎潤一郎賞)、『ノルウェイの森』、『国境の南、太陽の西』、『ねじまき鳥クロニクル』(読売文学賞)、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』(毎日出版文化賞)、最新長編小説に『騎士団長殺し』がある。『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』、『パン屋再襲撃』などの短編小説集、『ポートレイト・イン・ジャズ』(絵・和田誠)など音楽に関わる著書、『村上ラヂオ』等のエッセイ集、紀行文、翻訳書など著訳書多数。多くの小説作品に魅力的な音楽が登場することでも知られる。海外での文学賞受賞も多く、2006(平成18)年フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、’09年エルサレム賞、’11年カタルーニャ国際賞、’16年アンデルセン文学賞を受賞。