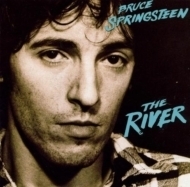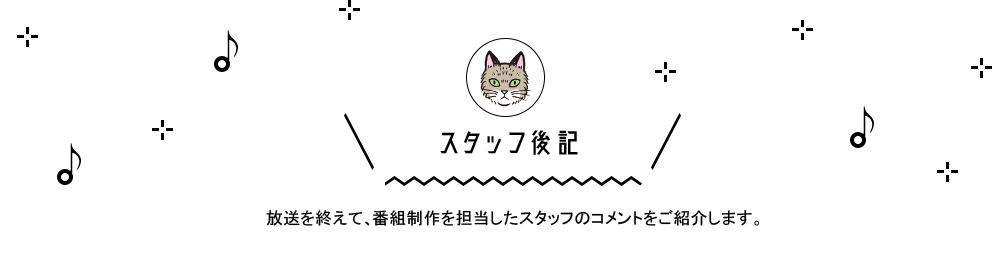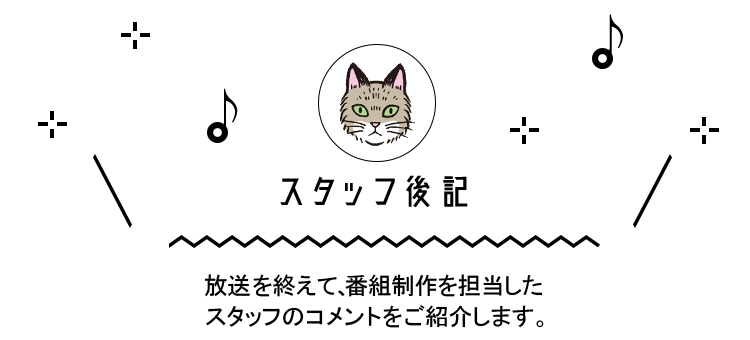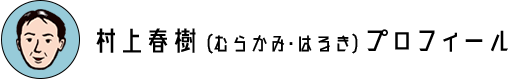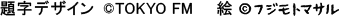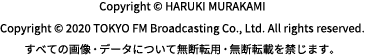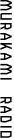


-
こんばんは、村上春樹です。
村上RADIO、今日は「村上春樹の書いた小説の中に出てくる音楽」特集の第二夜です。
一回目は8月にやったんですが、一度ではとても紹介しきれなかったので、二度に分けました。
なんか上下巻の本みたいですね。今日が上下の下です。
さて、僕の応援するヤクルトスワローズがとうとうリーグ優勝しました。おめでとうございます。僕はシーズンが始まる前、今年もどうせ最下位だろうと予測していたんですが、見事に外れてしまいました。スワローズ、どこまでも予測がつかないチームなんです。優勝したなんてまだ実感が湧かないというか、きつねにつままれたような気分です。はっと目が覚めたらタイガースが優勝してたりしてね、困ります。
ウサギの銀ちゃん(46、女性、東京都)
夏の終わりの暑い夕方、秋刀魚を焼きながら、ラジオを聞いていました。ラジオがよく聞こえるように換気扇を止めていたので、台所はモクモクしていました。皆さん、コメントも興味深く素敵で、リクエストも「そうそうその曲、印象的ですよね」と思うものばかりでした。同じ作品を読んで、同じ気持ちになる人が、この空の下にいると思うと、なんだか力が湧きますね。
今日も、みなさんからのリクエスト・メールを紹介しながら聴いていきます。
あなたの聴きたい曲がかかりますでしょうか?
-
こーちゃん(大阪府、60代、会社員、男性)
「ダンス・ダンス・ダンス」でレンタカーの中で、カセットテープから流れるローリング・ストーンズの楽曲「ゴーイン・トゥー・ア・ゴーゴー」に合わせて歌うシーンが、今でもずっと印象的で好きです。
「ゴーイン・トゥー・ア・ゴーゴー」、懐かしいなあ。いいですよ、かけましょう……とうちのレコード棚を探してみたんだけど、見当たりませんでした。でもよく考えたら、それもそのはず、僕が持っていたのはカセットテープでした。この小説を書いたときはイタリアに住んでいて、ラジカセとウォークマンしか持っていなかったんです。だから、もっぱらカセットテープで音楽を聴いていました。
ほんとはローマで買ったカセットテープでこの曲をかけたいんですけど、残念ながらどっかにいっちゃったので、今日はCDで聴いてください。“Going To A Go-Go”、ストーンズ、かっこいいです。僕はスーツケースをかつぎあげてトランクに放り込み、雪の降りしきる道路をゆっくりと何処にいくともなく車を走らせた。ユキはショルダー・バッグの中からカセットテープを出して、カー・ステレオに入れ、スイッチを押した。……ストーンズが「ゴーイン・トゥー・ア・ゴーゴー」を歌った。「この曲知ってる」と僕は言った。「昔ミラクルズが歌ったんだ。スモーキー・ロビンソンとミラクルズ。僕が十五か十六の頃」「へえ」とユキは興味なさそうに言った。「ゴオイン・トゥ・ア・ゴッゴ」と僕も曲にあわせて歌った。
(『ダンス・ダンス・ダンス』より)
- それからリクエストはなかったんだけど、ついでにというか、黒人ドゥワップ・グループ、The Dellsの歌う「ダンス・ダンス・ダンス」も聴いてください。多くの人はこの小説のタイトルはビーチボーイズの曲からとったと思われているみたいだけど、実はこのデルズの「ダンス・ダンス・ダンス」からとりました。これもカセットテープに入れたものをよく聴いていて、すっかり気に入って、本のタイトルにしちゃいました。これはアナログLPで聴いてください。
-
次は『ねじまき鳥クロニクル』から、ロッシーニの「泥棒かささぎ」序曲を聴いてください。
味にこだわる猫(神奈川県、50代、女性)
「ねじまき鳥クロニクル」に出てくるロッシーニ『泥棒かささぎ』序曲、スパゲティーを茹でる時はなんとなくこれを口ずさんでいます。
アサヒ(埼玉県、50代、男性)
ロッシーニの『泥棒かささぎ』をリクエストします。七年ぐらい前、録画しておいたクラシック番組を見たときのことです。『泥棒かささぎ』がかかり、「おお、これは『ねじまき鳥クロニクル』の冒頭の場面で流れる音楽じゃないか」と嬉しくなったとき、私はあまりの偶然に息を飲んでしまいました。なんとそのとき私は、小説そのままに、妻の帰りを待ちながらスパゲティーを茹でていたのです。
うーん、はい。僕もスパゲティーを茹でるとき、よくこの曲を思い出します。
でもこの小説が出たとき、どこかの文芸批評家に批判されたんです。日本人の普通の男は一人で家にいて、昼食に自分のためにスパゲティーを茹でたりはしない。だから話として現実的じゃないって。でもね、僕は一人でよく昼食にスパゲティーを茹でてましたね、現実的に。
それではロッシーニの「泥棒かささぎ」序曲、クラウディオ・アバト指揮ロンドン交響楽団の演奏、LPで聴いてください。10分ほどかかる曲ですが、しっかり全部かけますね。台所でスパゲティーをゆでているときに、電話がかかってきた。僕はFM放送にあわせてロッシーニの『泥棒かささぎ』の序曲を口笛で吹いていた。スパゲティーをゆでるにはまずうってつけの音楽だった。
<収録中のつぶやき>
(『ねじまき鳥クロニクル 第1部泥棒かささぎ編』より)
最初は「ねじまき鳥と火曜日の女たち」という短編小説を書いて、それから長編に伸ばしたんですよね。最初はこの(スパゲティーの)パラグラフしか頭になかったんだけど、なんとかなるだろうと。書き続けてなんとかなったけど。だいたいそういうのが多い(笑)。ロッシーニを聴きながらスパゲティーを茹でていると、電話のベルがいきなり鳴って、知らない女がわけのわからないことを言い始めるというシチュエーションが必要だった。電話のベルが聞こえたとき、無視してしまおうかとも思った。スパゲティーはゆであがる寸前だったし、クラウディオ・アバトは今まさにロンドン交響楽団をその音楽的ピークに持ち上げようとしていたのだ。しかしそれでもやはり僕はガスの火を弱め、居間に行って受話器をとった。……
「十分間時間をほしいの」、唐突に女がそう言った。
(『ねじまき鳥クロニクル 第1部泥棒かささぎ編』より)
-
最近クラッシックの中古レコード買いに目覚めたプラケースより紙ジャケ派(東京都、60代、会社員)
ブル-ス・スプリングスティーンのハングリー・ハート。最近の作品の「騎士団長殺し」で出てきますが、CDではなくアナログ盤・二枚組のリバーからと言うところが春樹さんらしいです。この曲についてはネットでみると、もっと以前の「ダンス・ダンス・ダンス」にも出ていたようですが、これは覚えていませんでした。
ワタナベノエル(神奈川県、60代、自営業、男性)
『ダンス・ダンス・ダンス』に出てくるブルース・スプリングスティーンの「ハングリー・ハート」。私が働きはじめた頃のヒットソングです。満たされない心、孤独。でも誰かの温もりが欲しい。あの頃の自分を思い出します。40年以上前の曲ですが、現代にも通じるメッセージだと思います。
そうか、“Hungry Heart”、『騎士団長殺し』でも『ダンス・ダンス・ダンス』でも出していたんですね。どちらもすっかり忘れていました。
この曲、好きなんです。かけましょう。もちろん二枚組アナログLPでおかけします。
-
今日は村上春樹の書いた小説の中に出てくる音楽特集の第二夜です。次は『アフターダーク』です。
梨子(愛知県、40代、女性)
「アフターダーク」に出てくる、スガシカオさんの「バクダン・ジュース」をお願いします。というのは、私は20代前半からスガシカオさんを知って、それ以降ミーハーなファンだからです。今も、よく聞きたくなって聞いています。
はちじろっぷん(三重県、50代、女性)
スガシカオさんの「バクダン・ジュース」どんな音楽なんだろうってすごく興味を持って、でも怖くてなかなか聴けなかった。(気に入らなかったら…と思うと怖かったのです。でも数年後やっと聴いて、結果現在スガマニアです。春樹さん、ステキな曲をありがとうございます。
『アフターダーク』に「バクダン・ジュース」が出てきましたっけ? どっかで出した覚えはあるんだけど、どこで出したかはわからなくなっていました。どんなところで出したっけなあ? でもとにかく『アフターダーク』ってちょっと暗めの、シュールな感じの小説なので、スガさんのこの歌の雰囲気はしっかり合っているかもしれませんね。
僕はこの「バクダン・ジュース」という曲の歌詞が好きなんです。何かストーリーはそこにあるんだけど、その話の内容は明らかにされない……みたいな世界が、彼の曲にはけっこう多いんです。そういうところ、いいですよね。作詞家としても優れた人です。一昨年、「村上JAM」にも来て、歌ってくれました。聴いてください。スガシカオ「バクダン・ジュース」。
「セブンイレブン」の店内。高橋はトロンボーンのケースを肩にかつぎ、真剣な目つきで食料品を選んでいる。アパートの部屋に戻って眠り、目を覚ましたときに食べるためのものだ。店内にはほかに客の姿はない。天井のスピーカーからはスガシカオの『バクダン・ジュース』が流れている。 彼はプラスチックの容器に入ったツナサラダのサンドイッチを選び、それから牛乳のパックを手に取って、ほかのものと日付を見比べる。牛乳は彼の生活にとって大きな意味を持つ食品なのだ。どんな細かいこともおろそかにはできない。
(『アフター・ダーク』より)


- LOUISE
ART TATUM
THE GENIUS OF ART TATUM #3
CLEF RECORDS -
次は短編小説「木野」の中に出てきた曲をかけます。「木野」は「ドライブ・マイ・カー」と同じく、短編集『女のいない男たち』に収められていた作品です。これも暗くて、シュールな話です。暗くて、シュールな話――僕の場合けっこう多いかもね。僕は上田秋成(江戸時代後期の文人。「雨月物語」の作者)へのオマージュみたいな気持ちでこの小説を書きました。作者個人的にはけっこう好きな作品です。まあ、作者がどう思おうと、読者の皆さんの知ったことではないんですけど。
ダンゴムシダンゴムシ(静岡県、50代、会社員、男性)
「木野」に出てくるアート・テイタムのソロピアノのレコードをリクエストします。きっと、今の僕の気持ちに似合っているはずだから。
アネモネ(岩手県、40代、専業主婦、女性)
短編集『女のいない男たち』の中の5編目「木野」で同名主人公が「木野」という自分の店のバーで聴くアート・テイタムのソロ・ピアノのレコードは、実際どのレコードだったのか? 興味があり、その中の曲をリクエストしたいと思います。曲はおまかせします。
僕は小説の中で「アート・テイタムのソロ・ピアノ」と書いたんだけど、曲名までは考えませんでした。だから今考えます。うちのレコード棚にはアート・テイタムの古いソロ・アルバムだけでLP11枚もありました。けっこうたくさんありますね。えーと、何がいいかな? はい、これでいきます。僕の大好きな曲「ルイーズ」(“LOUISE”)、1954年の録音です。客がまったく来ない店で、木野は久しぶりに心ゆくまで音楽を聴き、読みたかった本を読んだ。乾いた地面が雨を受け入れるように、ごく自然に孤独と沈黙と寂寥を受け入れた。よくアート・テイタムのソロ・ピアノのレコードをかけた。その音楽は今の彼の気持ちに似合っていた。
<収録中のつぶやき>
誰かを幸福にすることもできず、むろん自分を幸福にすることもできない。だいたい幸福というのがどういうものなのか、木野にはうまく見定められなくなっていた。かろうじて彼にできるのは、そのように奥行きと重みを失った自分の心が、どこかにふらふらと移ろっていかないように、しっかりと繋ぎとめておく場所をこしらえておくくらいだった。「木野」という路地の奥の小さな酒場が、その具体的な場所になった。
(『女のいない男たち』所収 「木野」より)
ウラディミール・ホロヴィッツがアート・テイタムを聴きに行ったという話があるんだ。バージョンが二つあって、どちらがほんとかわからないんだけどね。一つはウラディミール・ホロヴィッツがアート・テイタムのピアノを聴きにいって、あまりのテクニックのすごさに感心し、驚愕して、もう一回聴きにいって、また聴きに行きたいと言ったという話。もう一つは素晴らしいけど、一回でもういいと言ったという話。どちらが本当かわからない(笑)。でもそのテクニックに驚愕したということは本当みたいですね。


- South Of The Border
MEL TORME
¡OLE TORME!
Vreve -
次は、『国境の南、太陽の西』に出てくるナット・キング・コールが歌う「国境の南」です。
よくある佐藤(東京都、40代、女性)
「本当に存在する曲なのだろうか?」と検索をかけてしまいました。果たして、ナット・キング・コールの「国境の南」をリクエストする方はいるでしょうか? そんなところも楽しみにしています。
ナット・キング・コールが歌う「国境の南」……実はそんなレコードは存在しないんです。僕は子どもの頃に耳にした記憶があって、小説の中に自然に出しちゃったんですけど、調べてみたらそんなものは存在しなかった。僕の思い違いだったんです、しっかりと。でもまあ、それも小説の仕掛けみたいで面白いかも知れないと思ってそのままにしておきました。レコードを探し回った方がおられたら、申し訳ないとは思うんですが……すみません。
「国境の南」(“South Of The Border”)、今日はメル・トーメの歌で聴いてください。「オレ、トーメ!」っていうアルバムに入っているんですが、このレコード、とてもいいです。副題は「メル・トーメ、国境の南に行く」。……僕らは昔のようにソファーに並んで座って、ナット・キング・コールのレコードをターンテーブルに載せた。ストーブの火が赤く燃えて、それがブランディー・グラスに映っていた。島本さんは両脚をソファーの上にあげ、腰の下に折り込むようにして座っていた。そして片手を背もたれに載せ、片手を膝の上に置いていた。昔と同じだ。あの頃の彼女はたぶんあまり脚を見られたくなかったのだ。そしてその習慣が、手術で脚を治した今でもまだ残っているのだ。ナット・キング・コールは『国境の南』を歌っていた。その曲を聴くのは本当に久しぶりだった。
「実を言うと、子どもの頃この曲を聴きながら、僕は国境の南にはいったい何があるんだろうといつも不思議に思っていたんだ」と僕は言った。
「私もよ」と島本さんは言った。
(『国境の南、太陽の西』より)


- Mack The Knife
BOBBY DARIN
THE ULTIMATE BOBBY DARIN
WARNER SPECIAL PRODUCTS -
次は、『スプートニクの恋人』の中の一節です。
『スプートニクの恋人』は1999年に刊行された僕のいわゆる「中編小説」です。すみれちゃんっていう女の子が「僕」は好きなんだけど、彼女は年上の女性に激しく恋をしてしまう……という話でした。
「ねえ」とすみれは言った。
にゃあ(猫山さんの声)
「うん?」
「もし私がレズビアンになっちゃったとしても、今までどおりお友だちでいてくれる?」
「たとえ君がレズビアンになったとしても、それとこれとはまた別の話だ。君のいない僕の生活は、『マック・ザ・ナイフ』の入っていない『ベスト・オブ・ボビー・ダーリン』みたいなものだ」
すみれは目を細めて僕の顔を見た。「比喩のディテイルがもうひとつよく理解できないんだけど、それはつまりすごくさびしいっていうことなの?」
「だいたいそういうことになるかな」と僕は言った。
(『スプートニクの恋人』より)


- Le Mal du Pays
Lazar Berman
ANNEES DE PELERINAGE
DEUTSCHE GRAMMOPHON -
今日のクロージング音楽は、ラザール・ベルマンの演奏するリスト「ル・マル・デュ・ペイ」(“Le Mal du Pays”)です。ピアノ曲集「巡礼の年」の中の一曲。『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』という小説の中で、この曲は大事な役を果たしています。この曲には思いのほかたくさんのリクエストをいただきました。最後におかけします。
「牛にうしなうものなし」さん、三重県・三十歳・女性
人を許し、受け入れ、新しい自分になるには、つくるのようにぎりぎりの戦いを越えなければならない。村上さんとこの曲を聴いたら、戦いの先にある希望をしっかりと感じ取って、また戦場に戻れる気がします。

-
今回は「今日の言葉」はありません。
かわりに小説の中の文章を読みます。
過ぎ去った時間が鋭く尖った長い串となって、彼の心臓を刺し貫いた。無音の銀色の痛みがやってきて、背骨を凍てついた氷の柱に変えた。その痛みはいつまでも同じ強さでそこに留まっていた。彼は息を止め、目を堅く閉じてじっと痛みに耐えた。アルフレート・ブレンデルは端正な演奏を続けていた。曲集は「第一年・スイス」から「第二年・イタリア」へと移った。
今夜は、僕の小説に出てくる音楽をいろいろおかけしました。音楽を聴いて、また本を読み返したくなったという方がいらっしゃったとしたら、とても嬉しいです。読み返してください。それでは。
そのとき彼はようやくすべてを受け入れることができた。魂のいちばん底の部分で多崎つくるは理解した。人の心と人の心は調和だけで結びついているのではない。それはむしろ傷と傷によって深く結びついているのだ。痛みと痛みによって、脆さと脆さによって繋がっているのだ。悲痛な叫びを含まない静けさはなく、血を地面に流さない赦しはなく、痛切な喪失を通り抜けない受容はない。それが真の調和の根底にあるものなのだ。
(『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』より)
- 今回は僕らスタッフにとっても夢のような企画でした。村上春樹RADIOが始まる前、みんなで春樹さんの著作を持ち寄って輪読会を開き、春樹さんの作品に出てくる音楽をラインナップしたのです。そんな3年前を思い出しました。(延江GP)
- 今回の村上RADIOは、「村上作品に出てくる音楽」特集の第2弾です。今回は何といっても「国境の南、太陽の西」に出てくる“ナット・キング・コールが歌う「国境の南」”。現実には存在せず、この小説の中にしかない音楽を、村上さんが番組の中で具現化してくださいました。必聴です!(キム兄)
- 村上作品にでてくる音楽の1と2。リスナーのみなさんと一緒につくる「村上RADIO」でした。読者の数だけ「ノルウェイの森」があり「世界の終り」がある。それがとても興味深かったです。村上さんの小説を同時代に日本語で楽しむことができるって、とても幸せなことですね。(構成ヒロコ)
- 初めてART TATUMの「LOUISE」を聞いた時、感動して涙が出そうになりました。。(周りに人もいたので、涙はこらえました。)もっと早くにこの曲を知りたかったなあ…ともなりましたが、これからもこんな素敵な音楽を沢山聴いて、共有したいなと思いました。(AD桜田)
- 8月に引き続き、「MUSIC IN MURAKAMI」と題して、村上春樹作品の中に出てくる音楽の特集を行いました。このシリーズ、3,4,5もありそう…。そして今月10月1日に、早稲田大学に「国際文学館~村上春樹ライブラリー」がオープンしました。現役の作家が自身の朗読を読んだり、トークをする催し、「Authors Alive!~作家に会おう~」もスタートです。村上RADIOシートも頂きましたので、ご興味ある方はプレゼント応募ページよりぜひ!(レオP)
- 遠い記憶を辿るように、村上さんは曲を紹介しながら小説の一節を朗読した。ストーンズの“Going To A Go-Go”に始まり、クロージングにはラザール・ベルマン演奏のリスト「ル・マル・デュ・ペイ」“Le Mal du Pays”が静かに流れた。音楽と言葉が精妙に組み合わされた番組構成は、そのまま「村上春樹」の物語だ。音楽を聴いて小説を読み返してくれたら嬉しい、と村上さんは言う。The Dells「ダンス・ダンス・ダンス」とカセットテープ、ロッシーニ「泥棒かささぎ」とスパゲティ、『アフターダーク』と「バクダン・ジュース」、上田秋成と「ルイーズ」、そして『国境の南』と存在しないレコード。うーん、聴くのが先か、読むのが先か……。迷っていたら、何だかブルース・スプリングスティーンの「ハングリー・ハート」が聴きたくなってきた。(エディターS)
1949(昭和24)年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。’79年『風の歌を聴け』(群像新人文学賞)でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』(野間文芸新人賞)、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(谷崎潤一郎賞)、『ノルウェイの森』、『国境の南、太陽の西』、『ねじまき鳥クロニクル』(読売文学賞)、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』(毎日出版文化賞)、最新長編小説に『街とその不確かな壁』がある。『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』、『パン屋再襲撃』などの短編小説集、『ポートレイト・イン・ジャズ』(絵・和田誠)など音楽に関わる著書、『村上ラヂオ』等のエッセイ集、紀行文、翻訳書など著訳書多数。多くの小説作品に魅力的な音楽が登場することでも知られる。海外での文学賞受賞も多く、2006(平成18)年フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、’09年エルサレム賞、’11年カタルーニャ国際賞、’16年アンデルセン文学賞を受賞。