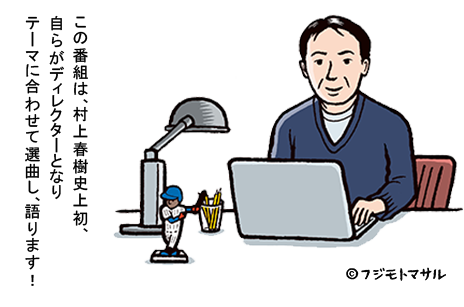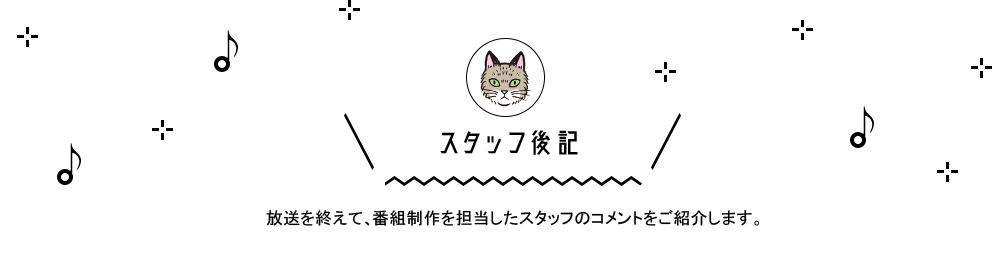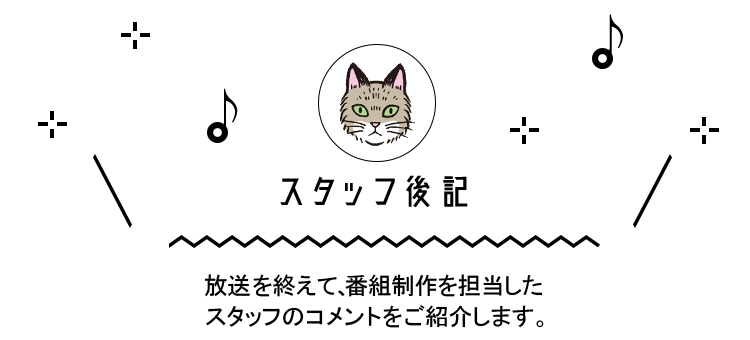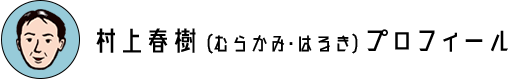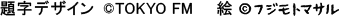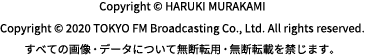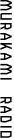

Madison Time ボサノヴァバージョン~

美雨こんにちは、坂本美雨です。「村上春樹 produce MURAKAMI JAM ~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova~supported by Salesforce」いよいよスタートです!さて、「村上RADIO」が始まって、2年半になりますね。
村上もう、そんなになるんですね。
美雨はい、そしてこの「村上JAM」の開催は、2回目となります!
村上1回目はかなり手探り状態で一所懸命やっていたんですけど、2回目はなにかテーマを設けたほうがいいということで、ボサノヴァでいくことになりました。こういう緊張する時代ですけれど、少しでもリラックスして楽しんでいただければと思います。
美雨村上JAM、今回はボサノヴァがテーマということで、オープニングソングMadison Timeもボサノヴァバージョンでスタートしました。今回は一人でも多くの方に音楽を届けたいとの思いで、オンラインでの開催となっています。会場は定員を通常の半分にして、お集まりいただいています。感染対策を徹底して、開催しています。みなさん声援はどうぞ盛大な拍手でお願いいたします。
総合プロデュースは村上春樹さん、そして音楽監督はジャズピアニストの大西順子さんです。
ゴージャスなミュージシャンのみなさんにも集まっていただきました。今日限りの編成“村上JAMボサノヴァバンド”です。大西さんからバンドのみなさんをご紹介いただけますでしょうか。
大西はい、今回集まってくれたすばらしいミュージシャンです。まずはこの方から。わたくしの相棒として本当に長い間演奏をしてくれていますけれども、素晴らしいベーシストです、井上陽介。
彼も最近わたしのトリオやカルテットで活躍してくれています、若手の星といわれています、吉良創太(ドラム)。そしてわたしは、この方をわたしのバンドに引き入れることが長いこと夢だったんですけど、ようやく実現したと思ったらコロナでなかなか活動ができていないんですけど、今年も頑張って一緒にやっていきたいと思います、日本のパーカッション界を背負って立つ方です、大儀見元(おおぎみ・げん)。そしてこの方はジャズだけでなく日本のJ-POPの世界などでも引っ張りだこで、なかなか忙しい方なんですけど、最近ご縁があって何度かわたしのプロジェクトに参加してくれることもありまして、素晴らしいピアニストです、吉田サトシ。
フルートを持っているこの方は本来テナー奏者なんですけど、いつも「フルートもうまいんだからフルートを吹かせてくれ吹かせてくれ」と言ってくるんですけど、今日はよかったですね、たくさんフルートが吹けて。頑張ってがんがん吹いてくださいね。作曲の才能も素晴らしくて、日本の最終兵器と言われております、吉本章紘。
そしてこの方とは、わたしが25、26歳くらい、30年も前になりますかね。初めてお目にかかった時、日本にこんな素晴らしい音を出すテナーの方がいらっしゃるんだと本当にびっくりしたのを覚えております。何年かに一度は必ずお会いするんですけど、最後にお会いしたのは10年前でしたっけ?(笑) 昨日リハーサルで久しぶりにご一緒しまして、相変わらずの素晴らしい音色、歌心にしびれました。今日はみなさんもしびれてください。テナーサックス、山口真文(やまぐち・まぶみ)。以上のメンバーです。
本来ボサノヴァバンドではなく、ごりごりのジャズバンドなんですけど、今日はがんばってボサノヴァをやっていきたいと思います、よろしくお願いします。


美雨春樹さん、ボサノヴァをテーマにしようとおっしゃっていましたが、なぜボサノヴァだったのでしょう?
村上個人的に昔からボサノヴァが大好きなんですよね。ミュージシャンの人でボサノヴァが嫌いだっていう人はあんまりいないんですよね。だからテーマとしてはいいんじゃないかなと思って、ボサノヴァでいこうと思ったんですけど。
美雨春樹さんとボサノヴァの関係というのは?
村上僕が最初にボサノヴァを聴いたのは1964年くらい、「イパネマの娘」が流行ったとき、僕は高校生だったんですよね。これはすごいと思って、それ以来しびれっぱなしになっています。
美雨作品の中にも登場しますね。
村上そうなんです。知らない間に出てきているし、スタン・ゲッツの伝記まで訳しちゃったしね。
美雨2019年に出版されました。分厚い本に取り組まれていましたね。
大西さんはジャズ界を率いてこられましたけど、ボサノヴァと今回聴いてどう思いましたか。
大西そのときは、すでに小野リサちゃんが参加することが決まっていたので、リサちゃんについていけばいいと思っていたら、春樹さんに「ボサノヴァなんだけど、いつものように燃え狂ってくれ」とお願いされまして、かなり今回は悩みました。やはりボサノヴァはジャズミュージシャンのマテリアルの中で不可欠なものになっているので、多少の解釈の違いはありながらも、わたしたちなりに頑張ってみようかと。
村上でも、順子さんの演奏ずいぶん聴いているけど、ボサノヴァは一度もないですよね。
大西え、そんなことないですよ。完全にボサノヴァではないけれど、いわゆるイーブン・エイスというかたちのリズムで結構いろんな曲が入ったCDを春樹さんにことあるごとにお届けしています。
村上そうだっけ?
大西あらためて聴いてください(笑)。
村上だから順子さんにボサノヴァをやってくださいと言うのは、虎に火の輪っかをくぐらせるみたいな、そんな気持ちで頼んだんですけど。
美雨ではボサノヴァといえばこの方、お招きしましょう。小野リサさん!
小野リサさん、よろしくお願いします。今日のスペシャルゲストですけれども、リサさんはブラジル生まれでいらっしゃいますね。10歳までブラジルに住まわれていました。ボサノヴァは住んでいたら自然と耳にし、自然と身に付くものなんでしょうか。
小野わたしが生まれたころはボサノヴァがラジオでかかっていたり、そのころの人々はボサノヴァが生まれてすごくショックを受けたんですね。新しいものだったのです。その前の音楽が朗々と歌い上げるような懐メロとか、丘の上のサンバだったりしたんですけど、そんな中で中間の心地よい音楽が生まれて、皆さんワクワクしてたと思います。
村上「イパネマの娘」とか「コルコバード」っていやと言うほど歌ったでしょう? 僕もいやというほど聴いてきたんだけど、でも不思議に飽きないですよね。
小野そうなんです、なんでしょうね。
村上リズムとハーモニーがすごく特殊で魅力的なんだと思います。だから次にこのコードが来るとわかっていても、来るとぐっときちゃうところがある。
小野そうですね。ボサノヴァのリズムは、「チクタク、チクタク」と4分の2拍子なんですけど、うちの父が心臓の鼓動と同じなんだと言っていて。そのリズムとハーモニーがやはりテンションが少し入ってパステルになって・・・・・・。
村上でも、(アントニオ・カルロス・)ジョビンのコードって普通じゃないですよね。
小野たくさんの曲をジョビンは作曲されましたけども、もともとはクラシックがとても好きだったみたいで、その影響もあって、クラシック音楽をポピュラーにしたいというところがあると思います。
美雨リサさんが「ボサノヴァはアメリカ人よりも、もしかしたら日本人のほうが得意かもしれない」と仰っていたのが印象的でした。
小野アメリカの音楽はジャズもロックもオフビートで、リズムの捉え方が反対なんですよね。サンバもボサノヴァもオンビートで、日本の音楽、古い音楽もお祭りの音楽もオンビートなのです。
美雨アントニオ・カルロス・ジョビンはボサノヴァの創始者と言われていますけれど、今回はボサノヴァがテーマということで、特にアントニオ・カルロス・ジョビンの楽曲に特化してお送りしようということになっております。ということで、小野リサさん、演奏をお願いします。


村上個人的に昔からボサノヴァが大好きなんですよね。ミュージシャンの人でボサノヴァが嫌いだっていう人はあんまりいないんですよね。だからテーマとしてはいいんじゃないかなと思って、ボサノヴァでいこうと思ったんですけど。
美雨春樹さんとボサノヴァの関係というのは?
村上僕が最初にボサノヴァを聴いたのは1964年くらい、「イパネマの娘」が流行ったとき、僕は高校生だったんですよね。これはすごいと思って、それ以来しびれっぱなしになっています。
美雨作品の中にも登場しますね。
村上そうなんです。知らない間に出てきているし、スタン・ゲッツの伝記まで訳しちゃったしね。
美雨2019年に出版されました。分厚い本に取り組まれていましたね。
大西さんはジャズ界を率いてこられましたけど、ボサノヴァと今回聴いてどう思いましたか。
大西そのときは、すでに小野リサちゃんが参加することが決まっていたので、リサちゃんについていけばいいと思っていたら、春樹さんに「ボサノヴァなんだけど、いつものように燃え狂ってくれ」とお願いされまして、かなり今回は悩みました。やはりボサノヴァはジャズミュージシャンのマテリアルの中で不可欠なものになっているので、多少の解釈の違いはありながらも、わたしたちなりに頑張ってみようかと。
村上でも、順子さんの演奏ずいぶん聴いているけど、ボサノヴァは一度もないですよね。
大西え、そんなことないですよ。完全にボサノヴァではないけれど、いわゆるイーブン・エイスというかたちのリズムで結構いろんな曲が入ったCDを春樹さんにことあるごとにお届けしています。
村上そうだっけ?
大西あらためて聴いてください(笑)。
村上だから順子さんにボサノヴァをやってくださいと言うのは、虎に火の輪っかをくぐらせるみたいな、そんな気持ちで頼んだんですけど。
美雨ではボサノヴァといえばこの方、お招きしましょう。小野リサさん!
小野リサさん、よろしくお願いします。今日のスペシャルゲストですけれども、リサさんはブラジル生まれでいらっしゃいますね。10歳までブラジルに住まわれていました。ボサノヴァは住んでいたら自然と耳にし、自然と身に付くものなんでしょうか。
小野わたしが生まれたころはボサノヴァがラジオでかかっていたり、そのころの人々はボサノヴァが生まれてすごくショックを受けたんですね。新しいものだったのです。その前の音楽が朗々と歌い上げるような懐メロとか、丘の上のサンバだったりしたんですけど、そんな中で中間の心地よい音楽が生まれて、皆さんワクワクしてたと思います。
村上「イパネマの娘」とか「コルコバード」っていやと言うほど歌ったでしょう? 僕もいやというほど聴いてきたんだけど、でも不思議に飽きないですよね。
小野そうなんです、なんでしょうね。
村上リズムとハーモニーがすごく特殊で魅力的なんだと思います。だから次にこのコードが来るとわかっていても、来るとぐっときちゃうところがある。
小野そうですね。ボサノヴァのリズムは、「チクタク、チクタク」と4分の2拍子なんですけど、うちの父が心臓の鼓動と同じなんだと言っていて。そのリズムとハーモニーがやはりテンションが少し入ってパステルになって・・・・・・。
村上でも、(アントニオ・カルロス・)ジョビンのコードって普通じゃないですよね。
小野たくさんの曲をジョビンは作曲されましたけども、もともとはクラシックがとても好きだったみたいで、その影響もあって、クラシック音楽をポピュラーにしたいというところがあると思います。
美雨リサさんが「ボサノヴァはアメリカ人よりも、もしかしたら日本人のほうが得意かもしれない」と仰っていたのが印象的でした。
小野アメリカの音楽はジャズもロックもオフビートで、リズムの捉え方が反対なんですよね。サンバもボサノヴァもオンビートで、日本の音楽、古い音楽もお祭りの音楽もオンビートなのです。
美雨アントニオ・カルロス・ジョビンはボサノヴァの創始者と言われていますけれど、今回はボサノヴァがテーマということで、特にアントニオ・カルロス・ジョビンの楽曲に特化してお送りしようということになっております。ということで、小野リサさん、演奏をお願いします。


One Note Samba("Samba de uma Nota Só")小野リサ

CORCOVADE「コルコバード」小野リサ

おいしい水(“AGUA DE BEBER”)小野リサ

美雨小野リサさん、ありがとうございました。どうぞこちらへ。
村上素敵な演奏でした。ポルトガル語ってホントにボサノヴァに合ってます。スペイン語で歌うと全然雰囲気が違っちゃうんですよね。
小野スペイン語はもっときちんとしているんですよ。
村上ポルトガル語のふわっとした雰囲気とリズムがすごくよく合っている気がします。僕の友達でもボサノヴァにハマってポルトガル語を勉強したという人が結構いるんですよ。
小野ボサノヴァを演奏するようになったり、サンバに凝り始めると、ポルトガル語にハマることが多いみたいですね。
美雨ボサノヴァとかジャズとか、境目がない本当に美しい音楽でした。
小野順子さんのアレンジのおかげです。
美雨春樹さんは以前「村上RADIO」の中でアントニオ・カルロス・ジョビンさんの言葉を引用しました。
「僕ら、ブラジル人のつくる音楽はどうして美しいのだろう? その理由はひとつ、幸福よりは哀しみの方が美しいものだからだ」。この言葉も美しいですけれど。
村上ブラジルの社会情勢というのは、当時そんなに幸福なものではなかったんですよね。ボサノヴァが出てきたころは軍事政権が国を掌握して、いろんな人が海外に亡命したり、ブラジルに帰れなくなったりして、ジョビンもずいぶんひどい目にあっていますよね。いまはボサノヴァっていうとカフェのおしゃれな音楽みたいになっているけど、本当はそういう哀しみも結構含まれているんだと僕は感じるんだけど。
小野そうですね、国の情勢がなかなか安定しなくて。でもそんな中でも、ブラジル人はすごく前向きなんです。カーニバルでは一年分働いたお金を衣装に使って発散するという明るさが素敵だと思います。
美雨どうもありがとうございました。小野リサさんでした。どうぞ大きな拍手を!


村上素敵な演奏でした。ポルトガル語ってホントにボサノヴァに合ってます。スペイン語で歌うと全然雰囲気が違っちゃうんですよね。
小野スペイン語はもっときちんとしているんですよ。
村上ポルトガル語のふわっとした雰囲気とリズムがすごくよく合っている気がします。僕の友達でもボサノヴァにハマってポルトガル語を勉強したという人が結構いるんですよ。
小野ボサノヴァを演奏するようになったり、サンバに凝り始めると、ポルトガル語にハマることが多いみたいですね。
美雨ボサノヴァとかジャズとか、境目がない本当に美しい音楽でした。
小野順子さんのアレンジのおかげです。
美雨春樹さんは以前「村上RADIO」の中でアントニオ・カルロス・ジョビンさんの言葉を引用しました。
「僕ら、ブラジル人のつくる音楽はどうして美しいのだろう? その理由はひとつ、幸福よりは哀しみの方が美しいものだからだ」。この言葉も美しいですけれど。
村上ブラジルの社会情勢というのは、当時そんなに幸福なものではなかったんですよね。ボサノヴァが出てきたころは軍事政権が国を掌握して、いろんな人が海外に亡命したり、ブラジルに帰れなくなったりして、ジョビンもずいぶんひどい目にあっていますよね。いまはボサノヴァっていうとカフェのおしゃれな音楽みたいになっているけど、本当はそういう哀しみも結構含まれているんだと僕は感じるんだけど。
小野そうですね、国の情勢がなかなか安定しなくて。でもそんな中でも、ブラジル人はすごく前向きなんです。カーニバルでは一年分働いたお金を衣装に使って発散するという明るさが素敵だと思います。
美雨どうもありがとうございました。小野リサさんでした。どうぞ大きな拍手を!


MY FUNNY VALENTINE 大西順子 + MURAKAMI JAM ボサノヴァ・バンド

村上あんまりないんだけど、高校時代に何度かチョコレートみたいなものをもらった覚えがあります。僕の高校時代だからずいぶん昔なんだけど、その頃からバレンタインデーってあったんですね。石器時代がちょっと終わった頃というか(笑)、かなり昔だけど。
美雨ホワイトデーはありましたか。
村上なかったです。義理チョコもなかったです。だから義理チョコとかホワイトデーとかが出てきてから、日本の「恵方巻き」みたいな感じになってきたよね。あまり興味がなくなってきて……。
美雨今年はもらいましたか?
村上ええ、いくつかいただきました。とても幸福な気持ちでいますけど。
美雨さあ、この村上JAMは第一部と第二部に分かれていますけれども、第一部を締めくくるのは「バレンタイン」が曲名に入ったナンバーです。“MY FUNNY VALENTINE”。これは大西さん、ジャズの中でもよく演奏される曲ですよね。
大西ちょっとボサノヴァとは違うナンバーなんですけど“MY FUNNY VALENTINE”ほど日本で親しまれているスタンダードナンバーもないんじゃないでしょうか。
美雨春樹さん、これ歌詞がすごくかわいいんですよね。
村上これは、本当は女の人が男性に向かって歌う歌なんです。バレンタインというのは男の子の名前です。バレンタイン君というのは変な顔をしているんですね。「マイ・ファニー・バレンタイン」だから、すごくファニーな顔をしていて、顔を見ていると笑っちゃうし、写真うつりは悪いし、口を開くとバカ丸出しなんだけど、でも好きなんだよという、とても素敵な歌です。でも日本ではチェト・ベイカーとかフランク・シナトラとか男性が歌った“MY FUNNY VALENTINE”のほうが有名なんです。
美雨たしかに、その印象がありました。
村上でも、本当は女の人が歌う歌なんです。
美雨そうなんですか。今日は歌なしのインストゥルメンタル・バージョンですけれども、ボサノヴァ・アレンジも加えつつ演奏していただきます。では第一部の最後の曲です。“MY FUNNY VALENTINE”。

美雨大西順子さん率いるMURAKAMI JAMボサノヴァ・バンドの皆さんでした。ありがとうございました。
「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァ~」第一部、終了です。
第二部にはギタリスト、村治佳織さんが登場します。春樹さんの朗読もあります。ジャズピアニストのレジェンド山下洋輔さんもご登場です。
「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァBlame it on the Bossa Nova」、第二部もお楽しみに!
「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァ~」第一部、終了です。
第二部にはギタリスト、村治佳織さんが登場します。春樹さんの朗読もあります。ジャズピアニストのレジェンド山下洋輔さんもご登場です。
「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァBlame it on the Bossa Nova」、第二部もお楽しみに!
Madison Time ボサノヴァバージョン~

第二部はギタリスト村治佳織さん、ピアニスト山下洋輔さんを迎えます。僕の朗読と村治佳織さんのギター演奏のコラボもあります。坂本美雨さんもボサノヴァを歌います。坂本さんはいつも僕を手伝ってくれてますけど、本職の歌手として今夜は歌を披露してくれます。では、「村上JAM~いけないボサノヴァ~」第二部です。
美雨というわけで、今回は春樹さんのお姿が見られる貴重な機会です(笑)
村上見てもしょうがないですけどね、ホントに。
美雨本当に春樹さんはいるんだと思っていらっしゃる方も……。
村上実在しないという人もいるんだよね。架空の存在じゃないかと。
美雨だんだん信じてきました。
村上別に信じなくてもいいんだけど(笑)。
美雨いよいよお待ちかねの朗読パート、その前にこの方をお招きしたいと思います。ギタリストの村治佳織さんです。
村上こんにちは。
村治こんにちは。
美雨お美しい……。
村治ボサノヴァの明るいイメージでお花のついた衣装を選びました。
村上南米的な、というか。
美雨2019年の第一回目の村上JAMを客席で観てくださっていましたね。
村治入口のちょっと後のあたりで。それこそいまおっしゃっていたように、「村上春樹さんて本当に存在されるんだろうか」と思っていたんですけど、村上JAMで目にして、いらっしゃるんだと思いました。
美雨そのときはコロナのコの字もなかったので、打ち上げがありまして。打ち上げに参加されたんですよね。
村治すみません、出演者でもないのに。
村上打ち上げでギターを演奏していただいて、本当に素晴らしかったです。ところで、ひとつ伺いたいことがあるんですけど。一日にどれくらい練習するんですか。
村治子どものころ、小学校に入る前は30分からで、だんだん延ばしていって平均して3~4時間、長い時は5時間、そんな風にずっと10代20代を過ごしてきたんです。でも最近はメリハリをつけようと思って、レコーディングの後とか、忙しい仕事が続いたあとは何日間か弾かないという日も設けています。
村上僕も何種類か楽器をやろうと思って勉強したことがあったんですけど、すぐにだめになっちゃう。練習が嫌いなんですよね。小説家のいいところは練習しなくていいところなんですよね。文章の練習なんてしたことがないんです。
村治でも、毎日なにかしら書かれますか?
村上それは原稿料をもらいながら書いているから練習とは言えないですね(笑)。


村上見てもしょうがないですけどね、ホントに。
美雨本当に春樹さんはいるんだと思っていらっしゃる方も……。
村上実在しないという人もいるんだよね。架空の存在じゃないかと。
美雨だんだん信じてきました。
村上別に信じなくてもいいんだけど(笑)。
美雨いよいよお待ちかねの朗読パート、その前にこの方をお招きしたいと思います。ギタリストの村治佳織さんです。
村上こんにちは。
村治こんにちは。
美雨お美しい……。
村治ボサノヴァの明るいイメージでお花のついた衣装を選びました。
村上南米的な、というか。
美雨2019年の第一回目の村上JAMを客席で観てくださっていましたね。
村治入口のちょっと後のあたりで。それこそいまおっしゃっていたように、「村上春樹さんて本当に存在されるんだろうか」と思っていたんですけど、村上JAMで目にして、いらっしゃるんだと思いました。
美雨そのときはコロナのコの字もなかったので、打ち上げがありまして。打ち上げに参加されたんですよね。
村治すみません、出演者でもないのに。
村上打ち上げでギターを演奏していただいて、本当に素晴らしかったです。ところで、ひとつ伺いたいことがあるんですけど。一日にどれくらい練習するんですか。
村治子どものころ、小学校に入る前は30分からで、だんだん延ばしていって平均して3~4時間、長い時は5時間、そんな風にずっと10代20代を過ごしてきたんです。でも最近はメリハリをつけようと思って、レコーディングの後とか、忙しい仕事が続いたあとは何日間か弾かないという日も設けています。
村上僕も何種類か楽器をやろうと思って勉強したことがあったんですけど、すぐにだめになっちゃう。練習が嫌いなんですよね。小説家のいいところは練習しなくていいところなんですよね。文章の練習なんてしたことがないんです。
村治でも、毎日なにかしら書かれますか?
村上それは原稿料をもらいながら書いているから練習とは言えないですね(笑)。


Moonlight In Rio「ムーン・ライト・イン・リオ」演奏:村治佳織

朗読・村上春樹 + ギター演奏 村治佳織「イパネマの娘」他

その前にちょっとアントニオ・カルロス・ジョビンの話をしたいと思います。1960年代にアンディ・ウィリアムスという歌手がいて、「アンディ・ウィリアムス・ショー」という一時間のテレビ番組を持っていました。特にアンディ・ウィリアムスのファンというわけでもなかったけど、僕はそれを毎週見ていました。とにかく毎週出てくるゲストが素晴らしいんです。あるとき、僕が高校の2年生くらいのころだったかな、アントニオ・カルロス・ジョビンがゲストで出てきてギターを弾いて歌って、アンディ・ウィリアムスとデュエットして、本当に素晴らしい音楽だったんです。だけど、そのジョビンが歌っている前にビジネススーツを着た男が二人いて、べちゃくちゃとお喋りをしている。僕は「お前らなあ、カルロス・ジョビン様が歌っているときに、そんな時に話すか!」と頭にきたのを覚えていてずっと記憶に残っていました。この間、「ベスト・オブ・アンディ・ウィリアムス・ショー」というのをやっていて、ジョビンがでてくるシーンをやっていたんですよ。やっぱりその二人のビジネスマンがずーっと喋ってるんですよね。それでまた頭にきて……。演奏は素晴らしかったですけど、そんな思い出があります。あんまり朗読と関係ないですけど(笑)。
今から読むのは、僕が40年くらい前、1982年に書いた短い小説作品です。それに手を入れて、もう少し短くして、今日読みます。アントニオ・カルロス・ジョビンへのオマージュみたいな話になっています。もうずいぶん長い間、読み返していなかったんですけど、ボサノヴァ特集で読むには良いかもなと思って机の奥からひっぱり出してきました。
タイトルは「1963年と1982年のイパネマ娘」という題です。読みます。
「1963年と1982年のイパネマ娘」
1963年、イパネマの娘はただ海を見つめていた。そしていま、1982年のイパネマ娘もやはり同じように海を見つめている。彼女はあれから齢をとらないのだ。彼女はイメージの中に封じ込められたまま、時の海の中をひっそりと漂っている。もし齢をとっていたとしたら、もうかれこれ四十に近いはずだ。もちろんそうじゃないということもあり得るだろうけれど、もはやすらりとしてもいないかもしれないし、それほど日焼けもしてはいないかもしれない。彼女にはもう三人も子供がいるし、日焼けは肌を傷めるのだ。まだそこそこに綺麗かもしれないけれど、二十年前ほど若くはない。
しかしレコードの中では彼女はもちろん齢をとらない。スタン・ゲッツのヴェルヴェットのごときテナー・サクソフォンの上では、彼女はいつも十八で、クールでやさしいイパネマ娘だ。ターン・テーブルにレコードを載せ、針を落とせば彼女はすぐに姿を現わす。
「好きだといいたいけれど
僕のハートをあげたいけれど…・・・」
この曲を聴くたびに僕は高校の廊下を思い出す。暗くて、少し湿った、高校の廊下だ。天井は高く、コンクリートの床を歩いていくとコツコツと音が反響する。北側には幾つか窓があるのだが、すぐそばまで山がせまっているものだから、廊下はいつも暗い。そして大抵しんとしている。
なぜ「イパネマの娘」を耳にするたびに高校の廊下を思い出すことになるのか、僕にはよくわからない。脈略なんてまるでないのだ。
いったい1963年のイパネマ娘は、僕の意識の井戸にどんな小石を放り込んでいったのだろう?
高校の廊下といえば、僕はコンビネーション・サラダを思い出す。レタスとトマトとキュウリとピーマンとアスパラガス、輪切りたまねぎ、そしてピンク色のサウザン・アイランド・ドレッシング。もちろん高校の廊下のつきあたりにサラダ専門店があるわけじゃない。高校の廊下のつきあたりにはドアがあって、ドアの外にはぱっとしない25メートル・プールがあるだけだ。
どうして高校の廊下が僕にコンビネーション・サラダを思い出させるのだろうか?ここにもやはり脈略なんてない。
「昔むかし」とある哲学者が書いている。「物質と記憶とが形而上学的深淵によって分かたれていた時代があった」
1963年と1982年のイパネマ娘は形而上学的な熱い砂浜を音もなく歩きつづけている。とても長い砂浜で、穏やかな白い波が打ちよせている。風はない。水平線の上には何も見えない。潮の匂いがする。太陽はひどく暑い。
僕はクーラー・ボックスから缶ビールを取り出し、ふたをあける。もう何本飲んでしまったかな?まあ、いいや。どうせすぐに汗になって出ていってしまうんだ。
彼女はまだ歩きつづけている。その日焼けした長身には原色のビキニがぴたりとはりついている。
「やあ」と僕は声をかけてみる。
「こんちは」と彼女は言う。
「ビールでも飲まない?」
「いいわね」と彼女は言う。
我々はビーチ・パラソルの下で一緒にビールを飲む。
「ところで」と僕は言う。「たしか1963年にも君をみかけたよ。同じ場所で、同じ時刻にね」
「ずいぶん古い話じゃないこと?」
「そうだね」
彼女は一息でビールを半分飲み、缶にぽっかりと開いた穴を眺める。
「でも会ったかもしれないわね。1963年でしょ? えーと、1963年……うん、会ったかもしれない」
「君は年齢(とし)をとらないんだね?」と僕は言う。
「だって私は形而上学的な女の子なんだもの」
僕は言う。
「あの頃の君は僕になんて気づきもしなかったよ。いつもいつも海ばかり見ていた」
「あり得るわね」と彼女は言った。そして笑った。
僕は言う。
「そんなに歩き続けて足の裏が熱くない?」
「大丈夫よ。私の足の裏はとても形而上学的にできているから。見てみる?」
「うん」
彼女はすらりとした足をのばして、足の裏を僕に見せてくれた。それはたしかに素晴らしく形而上学的な足の裏だった。僕はそこにそっと指を触れてみた。熱くもないし、冷たくもない。彼女の足の裏に指を触れると、微かな波の音がした。波の音までもが、とても形而上学的だ。
「君のことを考えるたびに、僕は高校の廊下を思い出すんだ」と僕は言う。
「どうしてだろうね?」
「人間の本質は複合性にあるのよ」と彼女は簡単に言う。
「ふうん」と僕は言う。
彼女は言う。
「意識なんて人の心の一部にすぎない。そして私はただの……形而上学的な足の裏を持った女の子なの」
そして1963年と1982年のイパネマ娘はももについた砂を払い、立ちあがる。「ビールをどうもありがとう」
「どういたしまして」
時々、地下鉄の車両の中で彼女に出会うことがある。そのたびに彼女は〈あの時はビールをどうもありがとう〉式の微笑(ほほえみ)を僕に送ってくれる。あれ以来我々はもうことばは交わさないけれど、それでも心はどこかでつながっているんだという気はする。どこでつながっているのかは僕にはわからない。きっとどこか遠い世界にある奇妙な場所にその結びめはあるのだろう。
1963年と1982年のイパネマ娘は今も熱い砂浜を歩きつづける。
レコードの最後の一枚が擦り切れるまで、彼女は休むことなく歩きつづける。
村上どうもありがとうございました。(……会場から拍手)
美雨春樹さん、いかがでしたか。
村上緊張しましたね、伴奏が素敵だったですね。
美雨素敵でした。村治さんが最初に演奏してくださったのはなんという曲ですか?
村治ルイス・ボンファ、こちらもブラジルの名ギタリストの方の作品です。”Moonlight In Rio”でした。わたしもちゃきちゃきの江戸っ子なので、リオの下町の明るい雰囲気をリンクさせて弾いてみようかなと思いました。
美雨そして春樹さんとのコラボレーション、「1963年と1982年のイパネマ娘」の朗読のうしろで弾いていらっしゃって。
村治こちらは必ず「イパネマの娘」で始まって終わろうというのはあったんですけど、ずっと同じことを弾いていても仕方ないので、途中はヴィラ=ロボスというブラジルが産んだクラシックの大巨匠なんですけれど、この方の曲からメロディから少し拝借して、即興的にアレンジしたりなどして。本当に心地いいですね。
村上はい、ジェット・ストリームでした(笑)。
美雨春樹さんの物語の中で、「イパネマの娘」から始まっていろいろな情景を漂って、またその曲に戻ってくるということで、ぐっと来ました。

美雨春樹さん、いかがでしたか。
村上緊張しましたね、伴奏が素敵だったですね。
美雨素敵でした。村治さんが最初に演奏してくださったのはなんという曲ですか?
村治ルイス・ボンファ、こちらもブラジルの名ギタリストの方の作品です。”Moonlight In Rio”でした。わたしもちゃきちゃきの江戸っ子なので、リオの下町の明るい雰囲気をリンクさせて弾いてみようかなと思いました。
美雨そして春樹さんとのコラボレーション、「1963年と1982年のイパネマ娘」の朗読のうしろで弾いていらっしゃって。
村治こちらは必ず「イパネマの娘」で始まって終わろうというのはあったんですけど、ずっと同じことを弾いていても仕方ないので、途中はヴィラ=ロボスというブラジルが産んだクラシックの大巨匠なんですけれど、この方の曲からメロディから少し拝借して、即興的にアレンジしたりなどして。本当に心地いいですね。
村上はい、ジェット・ストリームでした(笑)。
美雨春樹さんの物語の中で、「イパネマの娘」から始まっていろいろな情景を漂って、またその曲に戻ってくるということで、ぐっと来ました。

美雨それでは「MURAKAMI JAM~いけないボサノヴァ~」、いよいよ終盤です。今日最後のスペシャルゲストをご紹介します。ジャズピアニストの山下洋輔さんです。
美雨よろしくお願いします。
山下お久しぶりです。
美雨演奏活動がもう60年に及びますけれど。日本のジャズ界を率いていらっしゃいました。春樹さんも山下さんのレコードを何枚も持っていらっしゃるとか。
村上もちろん、何枚も持ってます。僕は日本にボサノヴァが入ってきたころ、まだ高校生だったんですけど、山下さんはもうその頃ジャズミュージシャンとして活躍されていたんですよね。
山下はい、ちょうどやっておりました。渡辺貞夫さん、ナベサダさんが1965年にアメリカから帰ってこられて日本のミュージシャンを集めてセッションバンドをやったんです。そこに僕は招かれて、大変嬉しかったんだけど、そのとき貞夫さんが、最初のセットはバリバリのビバップをやって、セカンドでボサノヴァをやったんです。それが初めて生で聴くボサノヴァでした。
村上それまではハードバップみたいのをやっていたんですよね?
山下そうですね。
村上急にボサノヴァやれって言われて、どうでした?
山下難しかったです。独特の和音があって、ビル・エヴァンスみたいなとてもしゃれた和音がありましてね、それが楽譜になっていて、こういうふうに弾きなさいと、ボサノヴァの楽譜になってるんです。ちょうど1962年にジョビンがニューヨークのカーネギーホールでやったんですね、その数年後ですからね。
村上やっぱりコードが難しいんですか、ボサノヴァは。
山下そうでもないですが、カルロス・ジョビンさんのコードというのは独特でね。すごくジャズの名曲そっくりなんですよ。だからみんながジョビンさんはジャズに影響を受けたんでしょうと言うんですが、「いいえ、わたくしはそういうことはしません」と最後まで言っておられました。
村上お会いになったことがあるんですよね。
山下そうなんです。実はヴァーブ・レコード(Verve Records:1956年創立のアメリカのジャズレコード会社)の50周年のお祭りがカーネギーホールでありまして、わたくし日本から一人だけ呼ばれていって、ジョビンさんも来ていて、記者会見があったときに座ったら隣がジョビンさんでした。みんなジョビンさんに質問するんですが、わたしには一つも質問が来なくて(笑)。ヴァーブ・レコードがジョビンさんに言わせたがるわけですよ。ジャズの影響でこのような曲ができたんでしょう、と。するとジョビンさんは、「いいえ、わたくしはジャズは知りません」なんて、誰が聞いても変な答えを隣でしているのを、まざまざと目撃しました。もう歳を取られていて、すべてはブラジルでできたんだと言いたかったんでしょうね。
村上歳をとると頑固になるんですね。
山下そうですよ(笑)。


美雨よろしくお願いします。
山下お久しぶりです。
美雨演奏活動がもう60年に及びますけれど。日本のジャズ界を率いていらっしゃいました。春樹さんも山下さんのレコードを何枚も持っていらっしゃるとか。
村上もちろん、何枚も持ってます。僕は日本にボサノヴァが入ってきたころ、まだ高校生だったんですけど、山下さんはもうその頃ジャズミュージシャンとして活躍されていたんですよね。
山下はい、ちょうどやっておりました。渡辺貞夫さん、ナベサダさんが1965年にアメリカから帰ってこられて日本のミュージシャンを集めてセッションバンドをやったんです。そこに僕は招かれて、大変嬉しかったんだけど、そのとき貞夫さんが、最初のセットはバリバリのビバップをやって、セカンドでボサノヴァをやったんです。それが初めて生で聴くボサノヴァでした。
村上それまではハードバップみたいのをやっていたんですよね?
山下そうですね。
村上急にボサノヴァやれって言われて、どうでした?
山下難しかったです。独特の和音があって、ビル・エヴァンスみたいなとてもしゃれた和音がありましてね、それが楽譜になっていて、こういうふうに弾きなさいと、ボサノヴァの楽譜になってるんです。ちょうど1962年にジョビンがニューヨークのカーネギーホールでやったんですね、その数年後ですからね。
村上やっぱりコードが難しいんですか、ボサノヴァは。
山下そうでもないですが、カルロス・ジョビンさんのコードというのは独特でね。すごくジャズの名曲そっくりなんですよ。だからみんながジョビンさんはジャズに影響を受けたんでしょうと言うんですが、「いいえ、わたくしはそういうことはしません」と最後まで言っておられました。
村上お会いになったことがあるんですよね。
山下そうなんです。実はヴァーブ・レコード(Verve Records:1956年創立のアメリカのジャズレコード会社)の50周年のお祭りがカーネギーホールでありまして、わたくし日本から一人だけ呼ばれていって、ジョビンさんも来ていて、記者会見があったときに座ったら隣がジョビンさんでした。みんなジョビンさんに質問するんですが、わたしには一つも質問が来なくて(笑)。ヴァーブ・レコードがジョビンさんに言わせたがるわけですよ。ジャズの影響でこのような曲ができたんでしょう、と。するとジョビンさんは、「いいえ、わたくしはジャズは知りません」なんて、誰が聞いても変な答えを隣でしているのを、まざまざと目撃しました。もう歳を取られていて、すべてはブラジルでできたんだと言いたかったんでしょうね。
村上歳をとると頑固になるんですね。
山下そうですよ(笑)。


Desafinado「デサフィナード」ピアノ:山下洋輔 歌:坂本美雨

山下そうですね、やりましたねぇ。
美雨その曲を今日初めてライブで一緒に演奏させていただきます。きょう、この「MURAKAMI JAM」が始まってから、ずーっと緊張してきたんですが、いよいよこの時が来てしまいました。
村上美雨さんは司会と歌の二役で活躍してくれて、とても緊張しておられます。
美雨頭がごっちゃになっていますけど、温かい目で見守ってください。「デサフィナード」”Desafinado”という曲ですけども、この曲は調子っぱずれという意味で……。
山下そういう意味なのね? 不思議だなあ。
美雨ちょっと変わったメロディとコード進行で。
山下確かにコード進行でいうと、シブイといいますか、お、やってるなというか。なんとかセブン、フラットファイブとかいうコードが出てきまして、素晴らしい曲ですね。
美雨そんなラブソングをお届けします。


美雨ありがとうございました。山下洋輔さんでした。(会場拍手)
今日はたっぷりとボサノヴァを味わってきました。ボサノヴァを改めて生で聴いて、いかがですか。
村上やっぱりボサノヴァの優しさというか、テンダネスみたいな感じが伝わってくるんですよね。このリズムってなんか癒されるんですよね。
美雨優しさとおっしゃいましたけど、春樹さんがこの「MURAKAMI JAM」に寄せて書かれた文章で「なにが世界を救うだろう、愛は消えても親切は残る」と書いていらっしゃいました。
村上そうなんです。「愛は消えても親切は残る」っていうのはアメリカの小説家カート・ヴォネガットの小説の中の言葉なんですけど、僕はすごく好きで、この間ラジオ番組で紹介したら、倦怠期を迎えた夫婦の方々から、よくわかるととてもたくさんメールをいただきまして。でも、親切心に救われるといいなと思いますけど(笑)
美雨コロナでいろいろな影響がでていると思います。差別とか偏見とか、そういったものも表面に出てきていますけど、その中でいま「愛と親切」がとても大切ではないでしょうか。
村上僕は音楽というのは、本当にそういうものだと思います。人を癒し、親切心みたいなものを搔き立ててくれるのがいい音楽じゃないかなというふうに思うんですよね。
美雨村上RADIOでも春樹さんの選曲でいつもそうした思いで届けてくださっていますね。
村上「身勝手な選曲と、ほどほどの音質」でお送りしています(笑)。
今日はたっぷりとボサノヴァを味わってきました。ボサノヴァを改めて生で聴いて、いかがですか。
村上やっぱりボサノヴァの優しさというか、テンダネスみたいな感じが伝わってくるんですよね。このリズムってなんか癒されるんですよね。
美雨優しさとおっしゃいましたけど、春樹さんがこの「MURAKAMI JAM」に寄せて書かれた文章で「なにが世界を救うだろう、愛は消えても親切は残る」と書いていらっしゃいました。
村上そうなんです。「愛は消えても親切は残る」っていうのはアメリカの小説家カート・ヴォネガットの小説の中の言葉なんですけど、僕はすごく好きで、この間ラジオ番組で紹介したら、倦怠期を迎えた夫婦の方々から、よくわかるととてもたくさんメールをいただきまして。でも、親切心に救われるといいなと思いますけど(笑)
美雨コロナでいろいろな影響がでていると思います。差別とか偏見とか、そういったものも表面に出てきていますけど、その中でいま「愛と親切」がとても大切ではないでしょうか。
村上僕は音楽というのは、本当にそういうものだと思います。人を癒し、親切心みたいなものを搔き立ててくれるのがいい音楽じゃないかなというふうに思うんですよね。
美雨村上RADIOでも春樹さんの選曲でいつもそうした思いで届けてくださっていますね。
村上「身勝手な選曲と、ほどほどの音質」でお送りしています(笑)。
Samba De Orfeu「オルフェのサンバ」MURAKAMI JAM ボサノヴァ・バンド

村上「オルフェのサンバ」、映画「黒いオルフェ」の中で有名になった曲で、素晴らしい曲です。これ僕はフィナーレにやってほしいとリクエストしたんですけど、これは乗れます。
美雨踊り出してくださったらうれしいです。MURAKAMI JAM ボサノヴァバンド、“Samba De Orfeu”!
イパネマの娘 “Garota De Ipanema”(アンコール曲)MURAKAMI JAMスペシャル・セッション

村上別に二人で歌を歌うわけじゃなくて・・・・・・(笑)。
美雨なにをデュエットしましょうか。アンコールといえば、やはりあの曲でしょうか?
村上そうですね、これで終わらないとボサノヴァ・セッションは終わらないという例の曲をやっていただきます。
美雨ではアンコール曲「イパネマの娘」をみんなで演奏したいと思います。みなさんもう一度ステージにお集まりいただきましょう。大西順子さん、「村上JAMボサノヴァバンド」の皆さん! 村治佳織さん! 小野リサさん! そして山下洋輔さん!
美雨村上JAMスペシャル・セッションでした!「村上春樹 produce MURAKAMI JAM ~いけないボサノヴァ Blame it on the Bossa Nova~supported by Salesforce」ご案内は坂本美雨と……。
村上村上春樹でした。
美雨・村上どうもありがとうございました。

小野リサとっても楽しかったです、とにかく演奏しているときが一番楽しいので、自分も楽しんでいるので、ほんとにいろんな音が聴こえて。まあ会話みたいなものですので。心の会話みたいな。
村治佳織村上春樹さんに声をかけていただいて、素晴らしい共演者の方にも恵まれて、ステージができてほっとしています。ギターの音で村上さんの作品の世界を、その物語をつくった方の朗読を聴きながら、舞台美術のような役目ができるように音で色付けできるというのは、特別な経験だったと思います。やっぱりお客様の存在あってこそのライブ感、いまこの瞬間を生きているんだなということをお客様も演奏者も感じられると思うんですよね。お互いにエネルギー交換をして、お互いが元気な気持ちになってまた日常に戻っていくという、やっぱりこれは必要なものですよね、人間にとって。
山下洋輔とっても楽しかったですよ。村上先生ともこうやってちゃんとお会いするのは初めてだし。あの方はとてもジャズに詳しくて、もともとジャズ喫茶のマスターだった方ですから。一度お店まで行きました。ジャズ界から出た人ということで、わたしたちもとても誇りにしております。
村上春樹より
「MURAKAMI JAM」いかがでしたか。ボサノヴァって素敵ですよね、心がリラックスします。
ここで「MURAKAMI JAM」に参加してくれた皆さんにお礼を言いいいたいと思います。
まず「MURAKAMI JAMボサノヴァバンド」のメンバー
大西順子さん、山口真文さん、吉本章紘さん、吉田サトシさん、大儀見元さん、吉良創太さん、井上陽介さん、そして山下洋輔さん。
小野リサさん、村治佳織さん、坂本美雨さん、素敵な演奏、そしてサポートを、ありがとうございました。
「MURAKAMI JAM」、3回目もある・・・・・・かもしれません。楽しみに待っていてください。
そして「村上RADIO」4月のテーマ、もう決まっていますよ。「花咲くメドレー特集」です。僕は、昔からメドレーって聴くの好きなんです。なんか幕の内弁当みたいでいいですよね、いろんなものが入って。そういう素敵なメドレーを僕のうちにあるレコードやCDから選んでみました。
では、今夜はここまで。またお会いしましょう。
「MURAKAMI JAM」いかがでしたか。ボサノヴァって素敵ですよね、心がリラックスします。
ここで「MURAKAMI JAM」に参加してくれた皆さんにお礼を言いいいたいと思います。
まず「MURAKAMI JAMボサノヴァバンド」のメンバー
大西順子さん、山口真文さん、吉本章紘さん、吉田サトシさん、大儀見元さん、吉良創太さん、井上陽介さん、そして山下洋輔さん。
小野リサさん、村治佳織さん、坂本美雨さん、素敵な演奏、そしてサポートを、ありがとうございました。
「MURAKAMI JAM」、3回目もある・・・・・・かもしれません。楽しみに待っていてください。
そして「村上RADIO」4月のテーマ、もう決まっていますよ。「花咲くメドレー特集」です。僕は、昔からメドレーって聴くの好きなんです。なんか幕の内弁当みたいでいいですよね、いろんなものが入って。そういう素敵なメドレーを僕のうちにあるレコードやCDから選んでみました。
では、今夜はここまで。またお会いしましょう。
- ボサノバをテーマにした村上JAM、楽しんでいただけましたでしょうか。実は小野リサさんと大西順子さんは初共演だったそう。初めての競演とは思えない、あたたかなコミュニケーションに、仕事を忘れうっとりしました。そして、坂本美雨さんの透き通る歌声。「I LOVE YOU」が歌詞だとわかっていても、自分に言われているような気がしてしまう、声の引き込み力。そして、村治佳織さんのギターのパワーに、生ギターで春樹さんが朗読を披露するという、なんという贅沢な時間だったでしょうか。コロナで家にいる時間が増えている今だからこそ、配信でも皆様に楽しんでいた だけるように、と、生ライブと配信を組み合わせた今回の企画。音楽と言葉の力を頂き、幸せなバレンタインデイになりました。(レオP)
- いまや村上RADIOの名物コーナーとなった村上DJの「今日の最後の言葉」。第18回の村上RADIOでは、アントニオ・カルロス・ジョビンの言葉でした。「僕ら、ブラジル人のつくる音楽はどうして美しいのだろう? その理由はひとつ、幸福よりは哀しみの方が美しいものだからだ」。その美しくも切ない言葉を思い出しながら、「MURAKAMI JAM」の放送を聴いたリスナーも多かったと思います。ボサノヴァの創始者ジョビンと間近で接したという山下洋輔さんのステージは素敵でしたね。タモリさんとの逸話を始め、多くの著作がある山下洋輔さん。洋輔さんのピアノで美雨さんが歌った「デサフィナード」は忘れがたい一曲になりました。小野リサさんが歌うボサノヴァの名曲、大西順子さんや井上陽介さんのJAZZYな演奏、村治佳織さんの魅惑のギター、そして村上春樹さんの「イパネマの娘」の朗読……。閉塞感のあるコロナの時代に、村上さんが心をこめて贈る「ボサノヴァJAM」は、オンビートのリズムと哀しみの影の中で、たしかに僕たちの心の奥まで届いたと感じます。(エディターS)
- 2月14日と3月29日の「村上JAM」。緊急事態宣言下で行われた2回目となる「村上JAM」は、とろりとするボサノヴァライブになるかと思いきや、とても熱いライブイベントとなりました。その熱量は、会場で体験して下さった方や配信を視聴された方、そしてもちろん「村上JAM」を体験されてない方にも、音声だけの形而上学的なラジオ版で、必ず伝わると思います。(キム兄)
- いつもとは違って夜10時からの2時間でした。お楽しみいただけましたか? ライブはやはり夜が似合います。コロナで、これまでのようにライブ会場にはいけなくなっていますが、そのぶん、ラジオで「一夜限りのボサノヴァライブ」お部屋で🎧で大きな音でお聞きいただくと、大西順子音楽監督のダイナミックな演奏と踊るようなアレンジがたっぷり楽しめます。そして、レジェンド山下洋輔さん繊細なタッチも。それにしても村治佳織さんのギターに乗った春樹さんの自作リーディング!「1963年と1982年のイパネマ娘」これは今回のために特別に春樹さんがアレンジしたもの。 かおりんこと、村治佳織さんはこの作品を読み込んで演奏してくれました。(延江GP)
- ボサノヴァに心ほぐれ、村上さんの言葉に元気をもらう、そんな村上JAMでした。村上さんの朗読と村治佳織さんのギター演奏のコラボも素敵でした。村上さんが朗読した「1963年と1982年のイパネマ娘」のオリジナル作品は、短編集『カンガルー日和』に収録されています。(構成ヒロコ)
1949(昭和24)年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。’79年『風の歌を聴け』(群像新人文学賞)でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』(野間文芸新人賞)、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(谷崎潤一郎賞)、『ノルウェイの森』、『国境の南、太陽の西』、『ねじまき鳥クロニクル』(読売文学賞)、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』(毎日出版文化賞)、最新長編小説に『騎士団長殺し』がある。『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』、『パン屋再襲撃』などの短編小説集、『ポートレイト・イン・ジャズ』(絵・和田誠)など音楽に関わる著書、『村上ラヂオ』等のエッセイ集、紀行文、翻訳書など著訳書多数。多くの小説作品に魅力的な音楽が登場することでも知られる。海外での文学賞受賞も多く、2006(平成18)年フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、’09年エルサレム賞、’11年カタルーニャ国際賞、’16年アンデルセン文学賞を受賞。