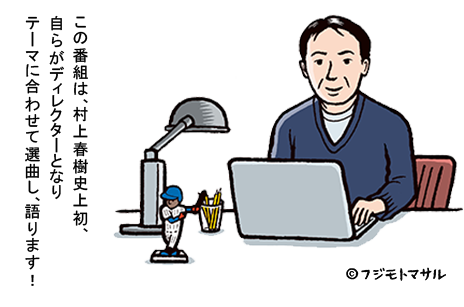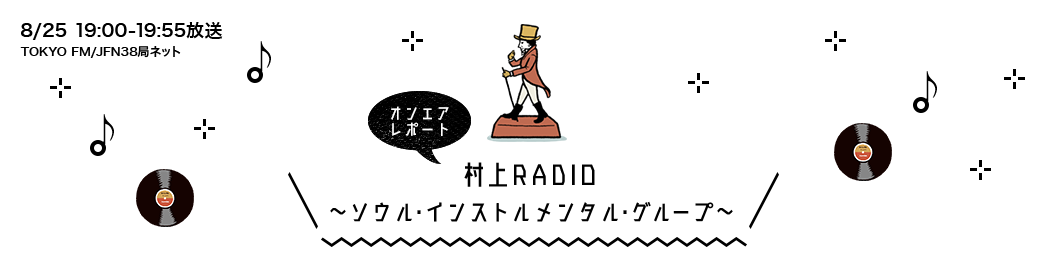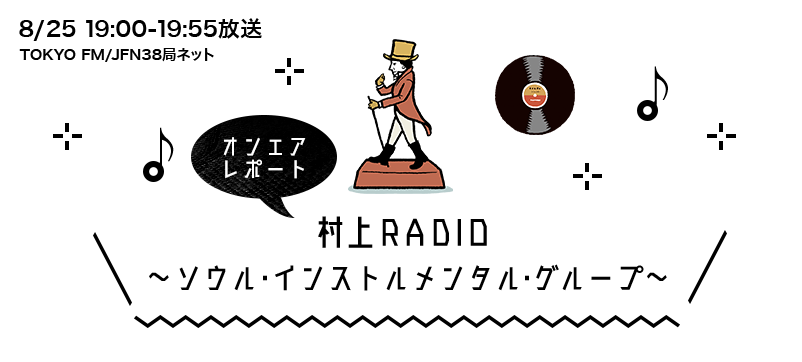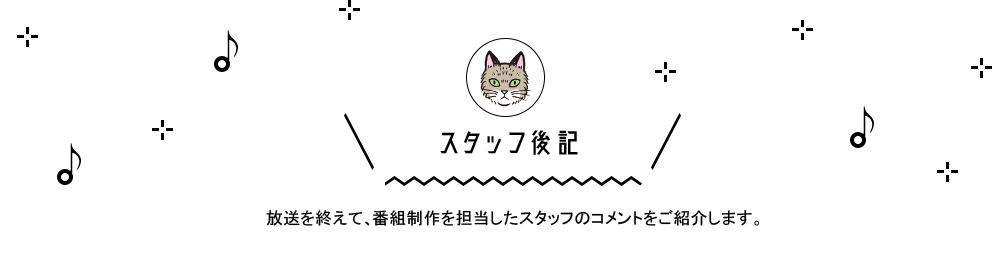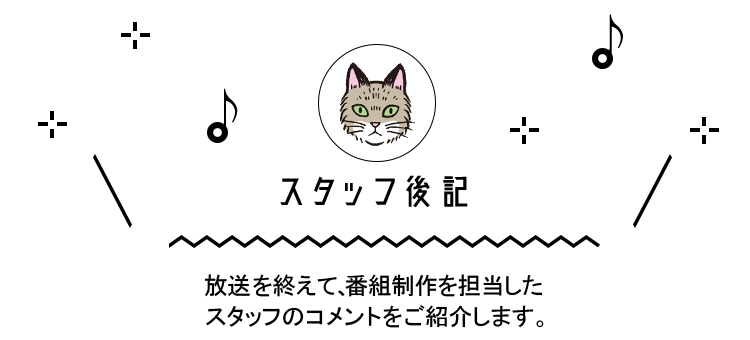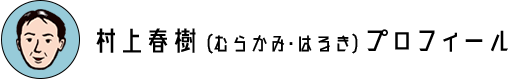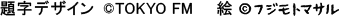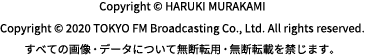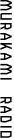


-
こんばんは、村上春樹です。
村上RADIO、今夜は1960年代の「ソウル・インストルメンタル・グループ」の特集です。ここのところ僕はブッカー・T&ザ・MG’s(Booker T. & the M.G.'s)のリーダー、ブッカーT・ジョーンズの自伝を読んでいまして、本のタイトルは『Time Is Tight: My Life, Note by Note』っていうんですが、読んでいるとなんかじわじわ懐かしい気持ちになって、そのへんの音楽を久しぶりに聴き直していました。その流れで、今夜は「ソウル・インストルメンタル・グループ」特集、行ってみますね。 よければお付き合いください。
<オープニング曲>
Donald Fagen「Madison Time」
ブッカー・T&ザ・MG’sはもともと、テネシー州メンフィスにあるスタックス・レコードのスタジオにたむろしていた若いバック・ミュージシャンたちが、適当にこしらえたバンドだったんです。そんな彼らが1962年に待ち時間の暇つぶしに作って録音した曲「グリーン・オニオン」がたまたま全米大ヒットして、その勢いでなんかそのまま常設バンドになってしまった……そういう行き当たりばったりな成り行きでした。なにしろブッカーTはまだそのとき高校生だったんです。でもそれにもかかわらずというか、彼らは結果的にソウル・ミュージックのひとつのスタイルを打ち立てることになり、今では偉大なレジェンドと見なされています。10数年前に、亡くなったアル・ジャクソンJr.を除いたオリジナル・メンバーで来日して、青山のブルーノートで演奏したんですが、それはもうかっこよかったですね。今の時代にも十分通用する音楽でした。びりびりと痺(しび)れました。


- Hip Hug-Her
Booker T. & The MG's
Hip-Hug-Her
Stax Records -
今夜は1960年代のソウル・インストルメンタル・グループの特集です。
まずはそのブッカー・T& The MG'sからいきます。このバンドはいわゆるインターレイシャル・バンド、つまり白人と黒人の混合バンドです。1960年代の南部ではきわめて珍しいケースで、他にはこういう例は見当たりません。
4人編成で、キーボードのブッカーTとドラムズのアル・ジャクソンJr.は黒人、ギターのスティーヴ・クロッパーとベースのドナルド・ダック・ダンは白人です。当時の南部はセグレゲーション(人種分離)が厳しかったし、人種混合バンドは双方の側から冷ややかな目で見られ、やりにくいことが多かったようですが、彼らが長期間にわたって同じメンバーでバンドを維持し、目覚ましい成果をあげることができたのは、4人が音楽的理解によって密接に結ばれていたからでしょうね。
1967年のヒット曲「ヒップ・ハグ・ハー」を聴いて下さい。
彼らのオリジナル曲で、全米ヒット・チャートの35位を記録しています。理屈抜きでご機嫌、快調なリズムです。


- Fuquawi
Booker T. & The MG's
Melting Pot
Stax Records -
ブッカー・T&ザ・MG’sは4人しかメンバーがいないシンプルな構成なんだけど、単調さをほとんど感じさせません。一本調子になるということがないんです。一曲一曲それぞれにそれぞれの工夫があります。彼らが多彩なサウンドを作り出すことに心を配ったということが、その理由としてあげられると思います。
当時のオルガンというと、ばしばし派手に弾きまくるスタイルが多かったんですが、ブッカーTは、一台のオルガンから実に巧妙に、さまざまな音を引き出していきます。そしてスティーヴ・クロッパーはまさにギターの魔術師です。ブッカーTはスティーヴ・クロッパーについてこのように語っています。
「スティーヴはものすごくサウンドにこだわる男なんだ。彼は1本のテレキャスから、セッティングを変更することなく、実にさまざまな音を引き出すことができる。指使いを変え、ピックを変え、アンプを替えるだけでね。スティーヴと一緒に演奏していて何より楽しいのは、彼が僕以外の唯一の独奏楽器奏者でありながら、まるでビッグ・グループで演奏しているような気持ちにさせられることだね」
1971年に発表された、彼らの最後のアルバム『メルティング・ポット』から「フクゥワイ」という曲を聴いてください。
<収録中のつぶやき>
このバンドは生で聴くと、ドナルド・ダック・ダンのベースがいかにすごいかということがよくわかるんです。レコードだとちょっとわかりにくいけど、生で聴くとすごくよくわかる。


- Jump Back
King Curtis
King Curtis Plays The Great Memphis Hits / King Size Soul
Koch Records -
次はキング・カーティスをいきます。キング・カーティスは1934年、テキサス州フォートワースの生まれ。幼い頃からサックスの音色に取り憑かれて、まだ10代のうちからスタジオ・ミュージシャンとして活動を始めます。最初はウィントン・ケリーやらナット・アダレイなんかと組んでジャズをやっていて、プレスティッジ・レコードから何枚かレコードを出していますが、あまりうまくいかなくて、それならとR&B路線に乗り換えて、そちらで成功を収めました。いわゆるブロー・テナーですが、派手に吹きまくるだけじゃなくて、堅実なテクニックも備えています。
1964年にルーファス・トマスがヒットさせた「ジャンプ・バック」を聴いてください。


- Memphis Soul Stew
King Curtis
Live At Fillmore West
ATCO -
キング・カーティスはアトランティック・レコードの専属になり、ハウスバンドとしてアレサ・フランクリンなどのバックを務めます。そして1971年3月、サンフランシスコのクラブ「フィルモア・ウェスト」にアレサ・フランクリンの前座、及びバックバンドとして出演します。それが評判を呼んで、その演奏はレコード化されました。これ、ほんとにすばらしいアルバムです。しかしその5ヵ月後、カーティスさんは自宅近くで麻薬患者と口論になり、ナイフで刺されて亡くなってしまいます。まだ37歳という若さでした。惜しいっていうか、気の毒ですね。
その「フィルモア・ウェスト」のライブ盤から聴いてください。「メンフィス・ソウル・シチュー」。
この曲の短いスタジオ・バージョンはこの番組で前に一度かけたことがあります。スガシカオさんがゲスト出演されたときです。「キング・カーティス、最高だね」と2人で盛り上がりました。今日は長いフル・バージョンで聴いてください。メンフィス・サウンドの作り方を、料理のレシピの形を借りて解説していきます。それがとにかくかっこいいんです。
オルガンはビリー・プレストン、ギターはコーネル・デュプリー、エレピがトルーマン・トーマス、ベースはジェリー・ジェモット、ドラムズはバーナード・パーディ、コンガがパンチョ・モラレス、それにプラスしてメンフィス・ホーンズという強力な顔ぶれです。聴いてください。
「メンフィス・ソウル・シチュー」。
<収録中のつぶやき>
(曲に合わせつつ……)ここでベースが入ってきて、ここでドラムが入って、コーネル・デュプリーのギターが入る、かっこいいでしょ。そしてオルガンのビリー・プレストン。さらにメンフィス・ホーンズ、コンガが入る。で、本人のキング・カーティス……。
-
ジュニア・ウォーカーはアーカンソー州の出身。1931年の生まれ。1995年に亡くなっています。本名はオートリー・デウォルト・ジュニア、子ども時代自転車がなくて、どこにいくにも歩いていったので、仲間から「ウォーカー」と呼ばれていたそうです。そこからジュニア・ウォーカーという通り名が生まれました。
インディアナ州サウス・ベンドで育った彼は、サキソフォンの演奏に夢中になり、仲間のミュージシャンたちと、R&Bバンドを結成し、地元で人気を得ていきました。ファッツ・ドミノやボ・ディドリーのヒットソングのカバーがそのバンドの主なレパートリーでした。
彼らはモータウン・レコードのスタッフに認められ、そこのハウスバンドのような存在になります。またそれと並行して、彼ら自身の音楽のレコーディングも始めたんだけど、なかなかヒット曲に恵まれませんでした。でも試行錯誤を重ねて、やがて「ショットガン」の大ヒットによって、モータウンの売れっ子バンドのひとつになっていきます。
ジュニア・ウォーカーはなぜか多くの若い英国のミュージシャンに影響を与えました。ミック・ジョーンズはこのように語っています。「ジュニアは音楽仲間のあいだではとても高く評価されていた。多くのギタリストが、彼のサックスのリフを借用している。エリック・クラプトンでも、ジェフ・ベックでも誰でもいい。訊(き)いてみな。自分たちがジュニア・ウォーカーのサックス演奏にインスパイアされたことを、彼らは喜んで認めるはずだ」
僕は一度、もう40年くらい前のことになりますが、ドイツのハンブルクのディスコで彼らの生演奏を聴いたことがあります。熱々の演奏で、そりゃ楽しかったです。客もみんなノリノリでした。
2曲続けて聴いてください。歌が入りますが、気にしないでください。このバンドの売り物はあくまでインストルメンタル演奏にあって、歌はいわば商売上の添え物に過ぎないんです。
「What Does It Take (To Win Your Love)(君の愛を得るためには何をすればいいのか)」そして「Walk In The Night(夜を歩く)」。
<収録中のつぶやき>
高校時代にこういう音楽をよく聴いていたんだよな。ラジオでずっと聴いていた。そのころのラジオはいい音楽をかけていたんだよ(笑)。
-
次はバーケイズです。バーケイズはもともと「River Arrows」というアマチュア・バンドで、メンバーのうちの何人かはメンフィスの床屋で働いていました。その床屋はスタックス・レコードのスタジオの近所にありまして、オーティス・レディングがたまたまそこをひいきにしていました。
その若者たちがバンド活動をしていることを知っていたオーティスは、一度スタジオに遊びに来いよと誘いまして、そこで彼らの演奏が水準の高いものであることを知り、「じゃあ、MG'sに次ぐハウスバンドに仕立てようじゃないか」ということになりました。そしてバンド名をバーケイズと改めた彼らのオリジナル曲「ソウル・フィンガー」は予想外の大ヒットとなりました。
続けて聴いてください。「Humpin'」と「In The Hole」。
オーティス・レディングは、彼らを前座兼バックバンドとして伴って全米ツアーに出たのですが、不運にも移動中の自家用飛行機が墜落し、オーティス自身も、バーケイズの4人のメンバーも、帰らぬ若者たちとなってしまいました。でも運良く生き残った2人のメンバーは、ショックから立ち直ると、新たにメンバーを加えてバーケイズを再結成しました。
そして1970年に事実上解散状態となったMG'sのあとを継いで、スタックスのハウスバンドのような位置につくことになります。メンバーがオール黒人のバーケイズは、人種混合だったMG'sに比べると、ずっとファンキーでアグレッシブで、のちにボーカルを加えて、「ブラック・ロック」や「ファンキー」と呼ばれる音楽に近いものになっていきます。
-
次は意外にもべンチャーズをいってみます。もちろんベンチャーズは白人バンドで、ソウル・インストルメンタル・グループというカテゴリーには入りませんが、彼らも1960年代後半になると、黒人たちのグループのパワフルな演奏に注目し、その手法を積極的に取り入れていきます。聴いてみると「え、これがベンチャーズ?」という本格的に黒っぽいサウンドです。
彼らがマーキーズのヒットソング「ラスト・ナイト」とブッカー・T&ザ・MG’sの「グリーン・オニオン」を演奏します。ホーンやオルガンを導入して、なかなかかっこいいですけど、「じゃあ、ベンチャーズの持ち味って何なんだ?」と言われるとちょっと困っちゃうかもね。
聴いてください。べンチャーズの演奏する「Last Night」、そして「Green Onions」。


- Lil' Darlin'
Lyle Ritz
No Frills - Jazz Ukulele and Bass
Flea Market Music -
今日のクロージング音楽はライル・リッツのウクレレ演奏で「リル・ダーリン」です。ライル・リッツはジャズ・ウクレレ演奏の名手ですが、ビーチボーイズのファンには「ペット・サウンズ」のバックでベースを弾いていた人として有名ですね。ウクレレだけでは営業していけないので、腕の良いスタジオ・ミュージシャンとしてベースを弾いていたんです。しかし同じ4弦でも、ウクレレとウッド・ベース、楽器の大きさはずいぶん違いますよね。
さて、ブッカーT・ジョーンズの自伝によれば、音楽の絆で結ばれていたMG's4人のメンバーの間にも、時代の経過と共に微妙な亀裂が入ってきます。1968年にマーティン・ルーサー・キングが暗殺され、黒人社会に大きな衝撃が走り、それを境としてブラックパワーが急速に盛り上がってくるわけですが、白人のスティーヴ・クロッパーにはその出来事の意味がうまく呑み込めずに、ブッカーTはそこに失望を感じます。そしてそのような気持ちのずれは、やがてバンドの解体へと繋がっていきます。そのへんのくだりを読んでいると、MG'sのファンとしてはやはり淋しかったですね。素晴らしい音楽も、政治や社会状況とは無縁でいられないんだなあと。

-
今日の言葉はチャールズ・シュルツさんのものです。
シュルツさんは漫画「ピーナッツ」の作者ですね。スヌーピーとチャーリー・ブラウンが出てくる漫画。彼はこう言っています。
「人生は10段変速の自転車に似ている。大抵の人は使わないギアをいくつも持っている」
うーん、そう言われればたしかにそうですね。僕もけっこう長く生きていますけど、「考えてみれば、これまで一度も使ったことがなかったよ」というギアが自分の中にいくつもあります。でも「せっかくあるんだから、ひとつ使ってみようか」とか思っても、おそらくはもう使わないでしょうね。ま、いまさら面倒だということもあるけど、所詮はそういうのが人生なんだから。人生の選択肢は数多くあっても、僕らが実際に選ぶ道って、結局は限られているんですね。
それではまた来月。
- 村上DJは「懐かしのアトランティック・ソウル特集」(2023年4月)でスガシカオさんと60年代のソウルミュージックを熱くファンキーに語っていますが、今回もご機嫌な曲が次々かかります。4曲目の「メンフィス・ソウル・シチュー」ライブ盤は圧巻。スタジオで曲を聴きながら、「かっこいいでしょ」と村上DJはすごく楽しそうでした。ビリー・プレストンのオルガン、コーネル・デュプリーのギター、そしてキング・カーティス……たしかに、ぜんぶかっこいい!(エディターS)
- ソウルと聞くとニーナ・シモンやアレサ・フランクリンといったボーカルを思い浮かべがちでしたが、今回の特集はその意味で新しく自分の中に入ってきました。いやあ、めちゃくちゃかっこいいですね。冷房ガンガンの部屋より、少し暑いくらいの部屋でぜひ聞き込んでみてください!(ADルッカ)
- 晩夏のソウルのインストゥルメンタルは不良なグルーヴで色っぽいです。灼熱に身を焦がした残り香というか。こんな音楽を聴きながら、青春に別れを告げるのですね。(延江GP)
- この夏は自家製ジンジャーエールづくりにはまりました。ジンジャーエールの甘口辛口。辛口になにが入っているか知っていましたか?唐辛子なんですね。そんなことも知らずに「大人のジンジャーエールは辛口に限るよね~」とのたまっていた自分のなんと恥ずかしいことか。ソウルインストゥルメンタル特集は強めの辛口ジンジャーエールが相性抜群です(構成ヒロコ)
- インストゥルメンタルというとジャズやフュージョンを思い浮かべますが、ソウルのインスト曲もカッコいいですね!この暑い夏に熱いソウルミュージックを聴くのは、猛暑日に蒙古タンメンを食べるような爽快さがあります!!(CAD伊藤)
- 今回の「村上RADIO」は、ソウルインスト特集。残暑厳しいこの季節にぴったり合う特集でした。熱帯夜のお供に、グルーブ感のある歌のない音楽をご堪能ください。そして次回の「村上RADIO」は、歌詞の世界に進んでいきます。(キム兄)
1949(昭和24)年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。’79年『風の歌を聴け』(群像新人文学賞)でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』(野間文芸新人賞)、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(谷崎潤一郎賞)、『ノルウェイの森』、『国境の南、太陽の西』、『ねじまき鳥クロニクル』(読売文学賞)、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』(毎日出版文化賞)、最新長編小説に『騎士団長殺し』がある。『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』、『パン屋再襲撃』などの短編小説集、『ポートレイト・イン・ジャズ』(絵・和田誠)など音楽に関わる著書、『村上ラヂオ』等のエッセイ集、紀行文、翻訳書など著訳書多数。多くの小説作品に魅力的な音楽が登場することでも知られる。海外での文学賞受賞も多く、2006(平成18)年フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、’09年エルサレム賞、’11年カタルーニャ国際賞、’16年アンデルセン文学賞を受賞。