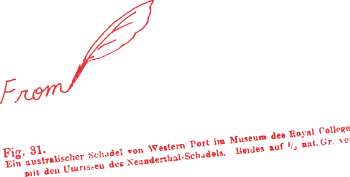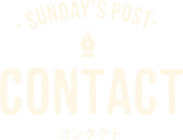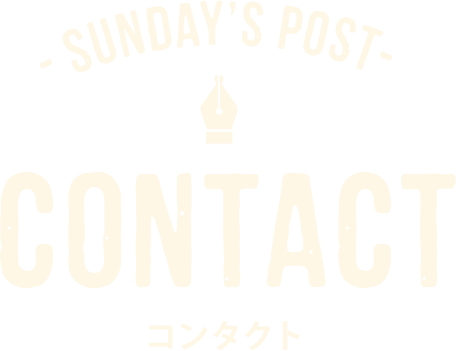そうめん研究家 ソーメン二郎さんが登場!
-

- 2023/08/06
そうめん研究家のソーメン二郎さんをお迎えして
 今回は、そうめん研究家のソーメン二郎さんをお迎えしました。
今回は、そうめん研究家のソーメン二郎さんをお迎えしました。
小山「そうめん研究家なんですね」
 ソーメン「生まれが奈良県の桜井市という田舎で、家が三輪そうめんを作っている製麺所をやっていまして。いま現在、職人さんが高齢化になって70代、80代の方がやっていて、跡継ぎがいないということで製麺所がどんどん廃業しているんですね。それで夏しか食べないものを年中食べていただきたい、ニーズを増やしていけたら、ちょっとでも長くそうめん文化は続くだろうということで、ソーメン二郎という名前になっています」
ソーメン「生まれが奈良県の桜井市という田舎で、家が三輪そうめんを作っている製麺所をやっていまして。いま現在、職人さんが高齢化になって70代、80代の方がやっていて、跡継ぎがいないということで製麺所がどんどん廃業しているんですね。それで夏しか食べないものを年中食べていただきたい、ニーズを増やしていけたら、ちょっとでも長くそうめん文化は続くだろうということで、ソーメン二郎という名前になっています」
小山「基本は三輪そうめんだけど、それに限らず全国のそうめんを食べてほしい、ということですね」
ソーメン「麺類みな兄弟ですから」
宇賀「そもそも、そうめんって何種類くらいあるんですか?」
ソーメン「製麺所は、各地にいっぱいあって、軒数でいうと手延べそうめんの製麺所は800軒以上あります」
宇賀「そんなに!」
ソーメン「揖保乃糸は兵庫県で、400軒あります。半分です」
 小山「揖保乃糸、というのは商品名じゃないんですか?」
小山「揖保乃糸、というのは商品名じゃないんですか?」
ソーメン「組合なんですよ」
小山・宇賀「知らなかった!」
ソーメン「兵庫県のそうめんの組合が作っているブランドが『揖保乃糸』なんです」
小山「揖保乃糸も何十種類もあるわけですか?」
ソーメン「何種類かランクがありますね。赤帯、黒帯みたいな。兵庫県のそうめん組合に400軒の製麺所が、決められたブランドの基準で作って納めるんです。奈良県の場合は三輪素麺の組合。長崎の場合は島原そうめん。揖保乃糸はブランド名ですけど、そうじゃない言い方は“播州そうめん”といいますね」
小山「それ聞いただけでも、今日は得した気がしました。てっきり、揖保乃糸という会社があるんだと思っていました」
 薫堂さんと宇賀さんのために、ソーメン二郎さんは冷たいそうめんとオリジナルのつけだれを3種類、用意してくださいました。
薫堂さんと宇賀さんのために、ソーメン二郎さんは冷たいそうめんとオリジナルのつけだれを3種類、用意してくださいました。
小山「食べ方ってあるんですか? 流儀とか」
ソーメン「めんつゆも麺自体も冷やして、冷たい状態で食べる。意外とぬるい状態で食べる人、多いんですよね。まずそこから」
宇賀「今回、つけだれを作ってきていただいているんですよね」
ソーメン二郎さんお手製のつけだれ。1つ目は、「はちみつと玉ねぎすりおろしそうめん」。
 宇賀「おいしい! さっぱり! 甘味もある」
宇賀「おいしい! さっぱり! 甘味もある」
ソーメン「めんつゆで旨みが出るんですね、ミツカンの追いがつおつゆです。そこに玉ねぎをすりおろします。みじん切りではなくて、すりおろしてください。少し甘めになりますので。甘いんですけど、辛みが残っている状態ではちみつを入れると、ちょうどいい塩梅になるんです」
小山「めちゃくちゃおいしいです! 最近食べたそうめんつゆの中でいちばんおいしいです」
ソーメン「嬉しいですね」
2つ目は、「室町風ごまだれそうめん」。
ソーメン「昔、醤油がない時代は(そうめんを)お酢で食べていたんですよね。これにもお酢がちょっと入っています。あとは梅肉、にんにく、ごまですね」
宇賀「おいしい、これも! 酸味のあるごまだれですね」
小山「酸味がいい!」
ソーメン「室町時代ではこんな食べ方をしていたんじゃないか、っていう話もあるんです」
宇賀「暑い時にいいですね」
ソーメン「これ、めんつゆが入ってないんですよ。しゃぶしゃぶ用のごまだれってあるじゃないですか、ミツカンさんのですけど。そこに、梅肉、ニンニク、お酢。クルミを砕いて入れて食べてもいいです。室町時代はクルミを貴族の方は食べていたんですよね」
小山「クルミの香ばしいナッティな感じがいいですね」
宇賀「食べ応えも出ますね」
 そして3つ目は、「タイ風そうめん」。
そして3つ目は、「タイ風そうめん」。
ソーメン「これも追いがつおつゆがベースになっているんですが、ちょっとタイ料理風です。ナンプラー、お酢が入っています」
宇賀「うん、アジアですね!」
ソーメン「ちょっとこれを入れてください」
宇賀「ジャスミンティー!? このおつゆに?」
ソーメン「同じ量くらい、多めに入れてください」
宇賀「そば湯みたいですね」
小山「うん、合う! 急に軽やかになりますね」
宇賀「おしゃれですね!」
ソーメン「もう、どなたでもできます。今日、スーパーで買ってきた食材ばかりですから」
宇賀「面白いですね。こんなにいろんな食べ方があるんだ」
小山「そうめん、深い。どれもおいしいですよ」
ソーメン「よく『そうめん飽きた』なんて言うじゃないですか。『またそうめん?』とか、そうめんって悪者になるでしょう。僕、いつも傷ついていたんですよ。めんつゆをそのまま食べるのがワンパターンで飽きているっていうことですよね。めんつゆに工夫をすれば、ずっと食べられると思います」
 薫堂さん、宇賀さんも絶賛のソーメン二郎さんのつけだれ。皆さんもぜひ、作ってみてください!
薫堂さん、宇賀さんも絶賛のソーメン二郎さんのつけだれ。皆さんもぜひ、作ってみてください!
【はちみつと玉ねぎすりおろしそうめん】
オリーブオイル・・・大さじ3
めんつゆ・・・大さじ2
はちみつ・・・小さじ1
玉ねぎ(すりおろし)・・・適量
【室町風ごまだれそうめん】
ごまドレッシング・・・大さじ3
お酢・・・小さじ1
梅肉・・・適量
にんにく・・・適量
クルミ・・・適量
【タイ風そうめん】
めんつゆ・・・大さじ3
お酢・・・小さじ1
ナンプラー・・・小さじ1
しょうが、ねぎ、茗荷・・・適量
*味変でジャスミンティー100ml
宇賀「そうめんの歴史っていつ頃から始まっているんですか?」
ソーメン「実は古くてですね、ルーツの話になると1200年といわれています。中国が唐の時代ですね。遣唐船という船で、中国と九州と行ったり来たりした時代。そうめんの原型である、ドーナツみたいなものがあるんですよ。“索餅(さくべい)”っていいます。長崎では“よりより”というお菓子ですね」
小山「あれがそうめんの原型なんですか?」
 ソーメン「あれが実はルーツといわれています。よりよりというのは、“こより”ですよね。そうめんも実は1本ではなく、こよりの状態で延ばし、延ばして1本になっています。だからコシが強いんですね。それが中国のお菓子として1,200年前にはあったと。唐の時代、皇帝のお子さんが亡くなって、すごく疫病が流行ったことがあって、『あの子が好きだった索餅をお供えしよう』とお供えをしたら、疫病がピタッとやんだ。そのお子さんが亡くなったのが7月7日、七夕の日。だから七夕の日にはそうめんのルーツである索餅をお供えする。その文化が日本の宮中にも来たんです」
ソーメン「あれが実はルーツといわれています。よりよりというのは、“こより”ですよね。そうめんも実は1本ではなく、こよりの状態で延ばし、延ばして1本になっています。だからコシが強いんですね。それが中国のお菓子として1,200年前にはあったと。唐の時代、皇帝のお子さんが亡くなって、すごく疫病が流行ったことがあって、『あの子が好きだった索餅をお供えしよう』とお供えをしたら、疫病がピタッとやんだ。そのお子さんが亡くなったのが7月7日、七夕の日。だから七夕の日にはそうめんのルーツである索餅をお供えする。その文化が日本の宮中にも来たんです」
小山「そばとそうめんはどっちが早かったんですか?」
ソーメン「歴史的にはそうめんですね。江戸時代にはもう“そうめん”といわれていましたけど、“さくべい”、“さくへい”、“さくめん”、“そうめん”……みたいな感じで名前が変わっていくんです。鎌倉、室町時代の時に“さくめん”、“さうめん”、江戸時代に“そうめん”」
小山「漢字の“素麺”は当て字なんですね」
ソーメン「そうですね、古文書の資料によると、そうやって平仮名の表記が変わっていっています。江戸時代の頃から“そうめん”で、夏に食べるというのが確立したと伝わっています」
 宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、これまで受け取ったり書いたりした中で、心に残っているお手紙はありますか?」
宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、これまで受け取ったり書いたりした中で、心に残っているお手紙はありますか?」
ソーメン「実は、亡くなった親父が郵便局員で。奈良県の桜井郵便局っていうところで、親父はボイラー技師で設備をやっていて。僕はそこのボイラールームで幼い頃を過ごしていて、宿題をしたり郵便局の中の散髪屋さんに行ったりしていました。
学校の先生から、大人になってからも年賀状をいただくじゃないですか。でもだんだんいただかなくなる。『先生、元気にされているのかな』と思い出して、実家に帰った時に訪ねてみようかな、と思うんです。年賀状は実家に帰ると見ますね。ひとこと書いてあるじゃないですか、年賀状っていまだにいいなあと思います」
宇賀「そして今日は、『今、想いを伝えたい人』に宛てたお手紙を書いてきていただいているんですよね」
ソーメン「今の流れだと、亡くなった親父に……ってなるんですけど、泣いて話せなくなると思うんで、3匹飼っている猫に手紙を書いてきました」
ソーメン二郎さんが、3匹の猫に宛てたお手紙の朗読は、ぜひradikoでお聞きください(8月13日まで聴取可能)。
宇賀「今日の放送を聞いて、ソーメン二郎さんにお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。責任をもってご本人にお渡しします。
【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST ソーメン二郎さん宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」
ソーメン二郎さん、ありがとうございました!
ソーメン二郎さんプロデュースによる「ソーメン二郎の半生そうめんセット」が販売中です。
三輪山勝製麺さんと作った半生そうめんと、宮崎県の高千穂峡しいたけつゆのセットです。こちらもぜひ、チェックしてみてください!
「ソーメン二郎の半生そうめんセット」
ソーメン二郎さん 公式Webサイト
ソーメン二郎さん SNS
 ソーメン「生まれが奈良県の桜井市という田舎で、家が三輪そうめんを作っている製麺所をやっていまして。いま現在、職人さんが高齢化になって70代、80代の方がやっていて、跡継ぎがいないということで製麺所がどんどん廃業しているんですね。それで夏しか食べないものを年中食べていただきたい、ニーズを増やしていけたら、ちょっとでも長くそうめん文化は続くだろうということで、ソーメン二郎という名前になっています」
ソーメン「生まれが奈良県の桜井市という田舎で、家が三輪そうめんを作っている製麺所をやっていまして。いま現在、職人さんが高齢化になって70代、80代の方がやっていて、跡継ぎがいないということで製麺所がどんどん廃業しているんですね。それで夏しか食べないものを年中食べていただきたい、ニーズを増やしていけたら、ちょっとでも長くそうめん文化は続くだろうということで、ソーメン二郎という名前になっています」小山「基本は三輪そうめんだけど、それに限らず全国のそうめんを食べてほしい、ということですね」
ソーメン「麺類みな兄弟ですから」
宇賀「そもそも、そうめんって何種類くらいあるんですか?」
ソーメン「製麺所は、各地にいっぱいあって、軒数でいうと手延べそうめんの製麺所は800軒以上あります」
宇賀「そんなに!」
ソーメン「揖保乃糸は兵庫県で、400軒あります。半分です」
 小山「揖保乃糸、というのは商品名じゃないんですか?」
小山「揖保乃糸、というのは商品名じゃないんですか?」ソーメン「組合なんですよ」
小山・宇賀「知らなかった!」
ソーメン「兵庫県のそうめんの組合が作っているブランドが『揖保乃糸』なんです」
小山「揖保乃糸も何十種類もあるわけですか?」
ソーメン「何種類かランクがありますね。赤帯、黒帯みたいな。兵庫県のそうめん組合に400軒の製麺所が、決められたブランドの基準で作って納めるんです。奈良県の場合は三輪素麺の組合。長崎の場合は島原そうめん。揖保乃糸はブランド名ですけど、そうじゃない言い方は“播州そうめん”といいますね」
小山「それ聞いただけでも、今日は得した気がしました。てっきり、揖保乃糸という会社があるんだと思っていました」
 薫堂さんと宇賀さんのために、ソーメン二郎さんは冷たいそうめんとオリジナルのつけだれを3種類、用意してくださいました。
薫堂さんと宇賀さんのために、ソーメン二郎さんは冷たいそうめんとオリジナルのつけだれを3種類、用意してくださいました。小山「食べ方ってあるんですか? 流儀とか」
ソーメン「めんつゆも麺自体も冷やして、冷たい状態で食べる。意外とぬるい状態で食べる人、多いんですよね。まずそこから」
宇賀「今回、つけだれを作ってきていただいているんですよね」
ソーメン二郎さんお手製のつけだれ。1つ目は、「はちみつと玉ねぎすりおろしそうめん」。
 宇賀「おいしい! さっぱり! 甘味もある」
宇賀「おいしい! さっぱり! 甘味もある」ソーメン「めんつゆで旨みが出るんですね、ミツカンの追いがつおつゆです。そこに玉ねぎをすりおろします。みじん切りではなくて、すりおろしてください。少し甘めになりますので。甘いんですけど、辛みが残っている状態ではちみつを入れると、ちょうどいい塩梅になるんです」
小山「めちゃくちゃおいしいです! 最近食べたそうめんつゆの中でいちばんおいしいです」
ソーメン「嬉しいですね」
2つ目は、「室町風ごまだれそうめん」。
ソーメン「昔、醤油がない時代は(そうめんを)お酢で食べていたんですよね。これにもお酢がちょっと入っています。あとは梅肉、にんにく、ごまですね」
宇賀「おいしい、これも! 酸味のあるごまだれですね」
小山「酸味がいい!」
ソーメン「室町時代ではこんな食べ方をしていたんじゃないか、っていう話もあるんです」
宇賀「暑い時にいいですね」
ソーメン「これ、めんつゆが入ってないんですよ。しゃぶしゃぶ用のごまだれってあるじゃないですか、ミツカンさんのですけど。そこに、梅肉、ニンニク、お酢。クルミを砕いて入れて食べてもいいです。室町時代はクルミを貴族の方は食べていたんですよね」
小山「クルミの香ばしいナッティな感じがいいですね」
宇賀「食べ応えも出ますね」
 そして3つ目は、「タイ風そうめん」。
そして3つ目は、「タイ風そうめん」。ソーメン「これも追いがつおつゆがベースになっているんですが、ちょっとタイ料理風です。ナンプラー、お酢が入っています」
宇賀「うん、アジアですね!」
ソーメン「ちょっとこれを入れてください」
宇賀「ジャスミンティー!? このおつゆに?」
ソーメン「同じ量くらい、多めに入れてください」
宇賀「そば湯みたいですね」
小山「うん、合う! 急に軽やかになりますね」
宇賀「おしゃれですね!」
ソーメン「もう、どなたでもできます。今日、スーパーで買ってきた食材ばかりですから」
宇賀「面白いですね。こんなにいろんな食べ方があるんだ」
小山「そうめん、深い。どれもおいしいですよ」
ソーメン「よく『そうめん飽きた』なんて言うじゃないですか。『またそうめん?』とか、そうめんって悪者になるでしょう。僕、いつも傷ついていたんですよ。めんつゆをそのまま食べるのがワンパターンで飽きているっていうことですよね。めんつゆに工夫をすれば、ずっと食べられると思います」
 薫堂さん、宇賀さんも絶賛のソーメン二郎さんのつけだれ。皆さんもぜひ、作ってみてください!
薫堂さん、宇賀さんも絶賛のソーメン二郎さんのつけだれ。皆さんもぜひ、作ってみてください!【はちみつと玉ねぎすりおろしそうめん】
オリーブオイル・・・大さじ3
めんつゆ・・・大さじ2
はちみつ・・・小さじ1
玉ねぎ(すりおろし)・・・適量
【室町風ごまだれそうめん】
ごまドレッシング・・・大さじ3
お酢・・・小さじ1
梅肉・・・適量
にんにく・・・適量
クルミ・・・適量
【タイ風そうめん】
めんつゆ・・・大さじ3
お酢・・・小さじ1
ナンプラー・・・小さじ1
しょうが、ねぎ、茗荷・・・適量
*味変でジャスミンティー100ml
宇賀「そうめんの歴史っていつ頃から始まっているんですか?」
ソーメン「実は古くてですね、ルーツの話になると1200年といわれています。中国が唐の時代ですね。遣唐船という船で、中国と九州と行ったり来たりした時代。そうめんの原型である、ドーナツみたいなものがあるんですよ。“索餅(さくべい)”っていいます。長崎では“よりより”というお菓子ですね」
小山「あれがそうめんの原型なんですか?」
 ソーメン「あれが実はルーツといわれています。よりよりというのは、“こより”ですよね。そうめんも実は1本ではなく、こよりの状態で延ばし、延ばして1本になっています。だからコシが強いんですね。それが中国のお菓子として1,200年前にはあったと。唐の時代、皇帝のお子さんが亡くなって、すごく疫病が流行ったことがあって、『あの子が好きだった索餅をお供えしよう』とお供えをしたら、疫病がピタッとやんだ。そのお子さんが亡くなったのが7月7日、七夕の日。だから七夕の日にはそうめんのルーツである索餅をお供えする。その文化が日本の宮中にも来たんです」
ソーメン「あれが実はルーツといわれています。よりよりというのは、“こより”ですよね。そうめんも実は1本ではなく、こよりの状態で延ばし、延ばして1本になっています。だからコシが強いんですね。それが中国のお菓子として1,200年前にはあったと。唐の時代、皇帝のお子さんが亡くなって、すごく疫病が流行ったことがあって、『あの子が好きだった索餅をお供えしよう』とお供えをしたら、疫病がピタッとやんだ。そのお子さんが亡くなったのが7月7日、七夕の日。だから七夕の日にはそうめんのルーツである索餅をお供えする。その文化が日本の宮中にも来たんです」小山「そばとそうめんはどっちが早かったんですか?」
ソーメン「歴史的にはそうめんですね。江戸時代にはもう“そうめん”といわれていましたけど、“さくべい”、“さくへい”、“さくめん”、“そうめん”……みたいな感じで名前が変わっていくんです。鎌倉、室町時代の時に“さくめん”、“さうめん”、江戸時代に“そうめん”」
小山「漢字の“素麺”は当て字なんですね」
ソーメン「そうですね、古文書の資料によると、そうやって平仮名の表記が変わっていっています。江戸時代の頃から“そうめん”で、夏に食べるというのが確立したと伝わっています」
 宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、これまで受け取ったり書いたりした中で、心に残っているお手紙はありますか?」
宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、これまで受け取ったり書いたりした中で、心に残っているお手紙はありますか?」ソーメン「実は、亡くなった親父が郵便局員で。奈良県の桜井郵便局っていうところで、親父はボイラー技師で設備をやっていて。僕はそこのボイラールームで幼い頃を過ごしていて、宿題をしたり郵便局の中の散髪屋さんに行ったりしていました。
学校の先生から、大人になってからも年賀状をいただくじゃないですか。でもだんだんいただかなくなる。『先生、元気にされているのかな』と思い出して、実家に帰った時に訪ねてみようかな、と思うんです。年賀状は実家に帰ると見ますね。ひとこと書いてあるじゃないですか、年賀状っていまだにいいなあと思います」
宇賀「そして今日は、『今、想いを伝えたい人』に宛てたお手紙を書いてきていただいているんですよね」
ソーメン「今の流れだと、亡くなった親父に……ってなるんですけど、泣いて話せなくなると思うんで、3匹飼っている猫に手紙を書いてきました」
ソーメン二郎さんが、3匹の猫に宛てたお手紙の朗読は、ぜひradikoでお聞きください(8月13日まで聴取可能)。
宇賀「今日の放送を聞いて、ソーメン二郎さんにお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。責任をもってご本人にお渡しします。
【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST ソーメン二郎さん宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」
ソーメン二郎さん、ありがとうございました!
ソーメン二郎さんプロデュースによる「ソーメン二郎の半生そうめんセット」が販売中です。
三輪山勝製麺さんと作った半生そうめんと、宮崎県の高千穂峡しいたけつゆのセットです。こちらもぜひ、チェックしてみてください!
「ソーメン二郎の半生そうめんセット」
ソーメン二郎さん 公式Webサイト
ソーメン二郎さん SNS
皆さんからのお手紙、お待ちしています
毎週、お手紙をご紹介した方の中から抽選で1名様に、大分県豊後高田市の「ワンチャー」が制作してくださったSUNDAY’S POSTオリジナル万年筆をプレゼントします。引き続き、皆さんからのお手紙、お待ちしています。日常のささやかな出来事、薫堂さんと宇賀さんに伝えたいこと、大切にしたい人や場所のことなど、何でもOKです。宛先は、【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST】までお願いします。
今週の後クレ
 今回のメッセージは、神奈川県〈アピタテラス横浜綱島郵便局〉松下元気さんでした!
今回のメッセージは、神奈川県〈アピタテラス横浜綱島郵便局〉松下元気さんでした!「数年前に癌で他界した祖母は、生前、離れて暮らす私宛てへのお歳暮に『いつもありがとう』という添え書きを入れてくれていました。抗がん剤の副作用がつらいと聞いていたのですが、そんな中、一言でも一生懸命書いてくれたということが嬉しく、その時の添え書きは今もお守り代わりに大切に保管しています。 私にとって手紙とは、その人とのつながりというか、同じ時間を生きた証だと思っています。」
MORE

この番組ではみなさんからの手紙を募集しています。
全国の皆さんからのお便りや番組で取り上げてほしい場所
を教えてください。
〒102-8080 東京都千代田区麹町1-7
SUNDAY'S POST宛