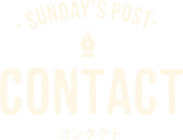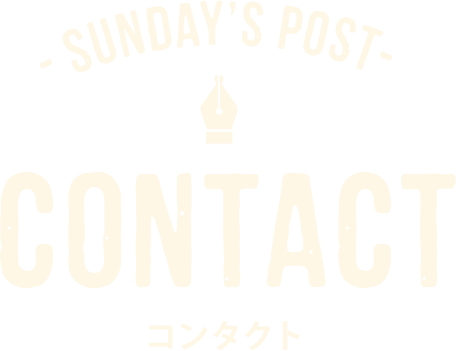イチロー氏、中田英寿氏など名だたる一流にインタビュー 小松成美さん
-

- 2023/04/23
ノンフィクション作家の小松成美さんが登場!
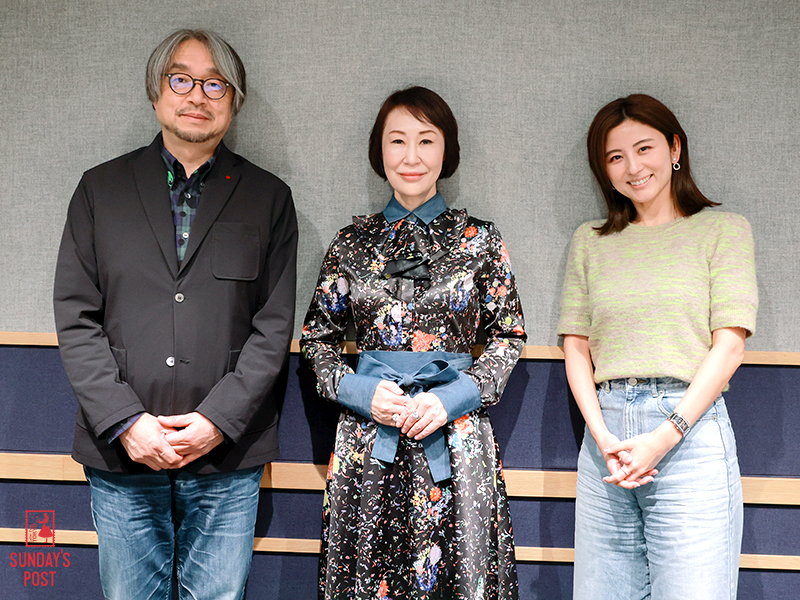 小山「宇賀さん、今日のゲストはですね、私が宇賀なつみをアップグレードするためにお呼びしました」
小山「宇賀さん、今日のゲストはですね、私が宇賀なつみをアップグレードするためにお呼びしました」宇賀「えっ、どなたですか?」
小山「女性の作家です。宇賀さんは『じゆうがたび』で作家としてデビューをして、なかなかいい売れ方をしています。そこで考えたのが、宇賀なつみをもっと売れる本物の作家にしたいと思いまして。『宇賀なつみ一流作家への道』その序章です」
宇賀「そんな道が拓かれていたんですね!」
小山「イチローさんとか、中田英寿さん、YOSHIKIさんなど、数多くの一流の方の本を出版されているノンフィクション作家の小松成美さんがいらっしゃいます」
スタジオには、ノンフィクション作家の小松成美さんをお迎えしました。
宇賀「小松さんはトップアスリートからアーティスト、クリエイターまで様々な人物ルポルタージュ、スポーツノンフィクション、インタビューやエッセイ、コラム、小説を執筆されています。イチローさんであったり、中田英寿さんであったり、五郎丸歩さん、元横綱の白鵬さん。さらに女優の森光子さん、YOSHIKIさんと本当にすごい方ばっかりなんですね」
小山「どうやったらこんな方々にインタビューができて本が書けるものなんですか?」
 小松「そうですね、本当に出版社や編集者の力を借りてこうした方と出会わせていただいたり、私が好きだという情熱を持ってその方にインタビューをお受けいただくというケースもございます」
小松「そうですね、本当に出版社や編集者の力を借りてこうした方と出会わせていただいたり、私が好きだという情熱を持ってその方にインタビューをお受けいただくというケースもございます」
宇賀「小松さんから企画されることもあるんですね」
小松「ほとんどそうですね。3分の1くらいは出版社から」
小山「最初にうまくいったというか、いちばん売れたのは何だったんですか?」
小松「それはまさに中田英寿さんのノンフィクションでした。19歳で出会った孤高のアスリートだったんですね。当時からものすごく個性的で、周囲との衝突を厭わない青年だったので『理解をされない』と苦しんでいた時代でもあったのですけども、サッカー記者ではない私のような者に、サッカーのことや人生のことを何でも話してくださって。2人で『本を作ろう!』と」
 宇賀「それはどうやって始まったんですか?」
宇賀「それはどうやって始まったんですか?」
小松「私が彼のサッカーを見て、直感的なんですけど、彼こそ日本をW杯に連れて行ってくれる人だと思ったんです。それで19歳の彼にインタビューをしたんですけど、彼が哲学を持っているということがわかったんですね。孤独に耐えて、けれど自分を貫くという。彼のサッカーを書きながら人生を書くということ。それを19歳から彼が引退をする29歳まで10年間、続けることができたんですけど、その本はたくさんの方に読んでいただけました」
宇賀「本当に深いところまで話し合われるんですね」
小松「私自身は、ものすごく好奇心が旺盛で聞きたがりなんですね。イチローさんに『なぜあなただけこんなにヒットが打てるんですか?』と聞いたことがあったんです。編集者たちは『プロ中のプロに何でそんな子どものような質問をするんだ』と紛糾したんですけども、イチローさんだけが腕を組んで、熟考をして答えてくれたんです」
 小山「なんて言ったんですか?」
小山「なんて言ったんですか?」
小松「『なぜ僕が打てるか、今から考えます。他のバッターと違うところがあるはずだから、僕は今まで小松さんにそれを聞かれるまで、誰にも質問をされたことがなかったから考えたことがなかったけれども、今考えてみますね』と、答えてくれたんですね。その時に、思いの丈を素直に届けるということが、その方自身も知らない境地に届くことがあるのだなと思って、ストレートに話を聞いてよかったなとその時に思いました」
小山「その時の答えは何だったんですか?」
小松「イチローさんってID野球をしないんですね。絶対に自分の目で球種を察知する。体の重心を腰で取って、ストライクゾーンがものすごく広かったんです。イチロー・ストライクゾーンがあったんですね。ボールまで打ててしまっていた、ということが4割に近い打率だったんだなあ、と。そして誰よりも目がよかった。選球眼は本当に球界一だったと、ご自身でもその当時はおっしゃっていました」
 宇賀「ジャンルは違えども一流の方たちにたくさん取材をされてきて、そういう方達に共通していることって何かありましたか?」
宇賀「ジャンルは違えども一流の方たちにたくさん取材をされてきて、そういう方達に共通していることって何かありましたか?」
小松「これでもかというくらいユニークで、エッジが立ってキャラクターは濃いんですけども、同時に共通することもあるんですね。1つは自分を貫く力。これが本当に強いです。自分がどのポジションに立って、誰に何を言うのか、伝えるのか。ご自身の中で決めたことを絶対に曲げないです。それが炎上しようがチーム内から批判を浴びようが、これが自分の信じた正しい道なのだと思えばそれを貫くんですよね。その先に必ずチームプレイに繋がっていったり、勝利に繋がっていったりするので、最後は理解されてみんなが迎え入れるというシーンも何度もあったんですけども、その貫く力が圧倒的に強いです。そしてもう1つは、ゴールをゴールと思わない。普通人は成績を収めたり、勝利を得たりすると、よくやった自分を褒めたいと思うはずなんですけれども、その方達はそれをただのラインだと思うんです。自分が目指す高みはこんなところではないと。『今晩だけは喜びますが、明日からは次のゴールに向かって次のラインに向かって走りますので、小松さんついてきてください』といつもおっしゃっていました」
 小山「いつも最初に聞くことは決めているんですか?」
小山「いつも最初に聞くことは決めているんですか?」
小松「ものすごく調べて、質問を何十個も作っていくんですね。でも、行った瞬間にはそれを消去して、真っ白にすることを心がけておりまして。その場で思ったことを聞きます」
宇賀「生意気ですみません、私も本の中でまったく同じことを書いていまして……インタビューをする時に事前に調べて行くんだけれども、お会いしたらその瞬間に全部消す、というのを書いていました」
小松「同じだ!」
宇賀「やっぱり予定調和になっちゃうとつまらないですもんね。新鮮なリアクションもできなくなりますし」
小松「インタビューを本当に受け慣れている方は『次はこういう質問だろうな』とか、『こういうクエスチョンで来るんだろうな』と思っていらっしゃるので、むしろその期待を裏切るというか、突発的に聞いています」
宇賀「嬉しい、今、やってきたことにマルをもらえたような気がしています」
 宇賀「今、いちばん話を聞いてみたい人は誰ですか?」
宇賀「今、いちばん話を聞いてみたい人は誰ですか?」
小山「きっと大谷翔平じゃないですか?」
小松「大谷さんが日本ハムファイターズからメジャーに行った頃から、彼の野球を彼はどんな言葉で表現するのかなということに興味があったので、本当にいつか機会があったらインタビューしたいなと思っていたんですけども、なかなか1 on 1の対面のインタビューをする機会がなくて。記者の方にはとても闊達にお話になるんですけど、なかなか難しい。いつか叶えば、WBCの舞台で見えたこと、感じたことを聞いてみたいと思います」
宇賀「お話をうかがっただけでわくわくしますね。さて、この番組は『お手紙』をテーマにお送りしているのですけども、小松さんはお手紙はよく書かれますか?」
小松「インタビューのお願いをする時には、やっぱり便箋に万年筆で今でも手紙を書きます」
宇賀「これまで受け取ったりご自身で書いたりした中で、心に残っているお手紙はありますか?」
 小松「手紙をもらうってこんな気持ちになるんだな、ということが数年前にありまして。その手紙は晩年の石原慎太郎さんからの手紙だったんですね。私が石原さんの本の書評を新聞に書いたんです。それを石原さんが読んでくださいまして。そこには、〈僕はもう書評というものにアレルギーがあって、大嫌いだった。そして、もう何十、何百と書評を書かれたけど、今まで一度も好きになったことが、いいと思ったことがなかった。けれど小松さんが書いた書評を読んで、本当に本を書いてきてよかったと思った〉という手紙をくださったんですね」
小松「手紙をもらうってこんな気持ちになるんだな、ということが数年前にありまして。その手紙は晩年の石原慎太郎さんからの手紙だったんですね。私が石原さんの本の書評を新聞に書いたんです。それを石原さんが読んでくださいまして。そこには、〈僕はもう書評というものにアレルギーがあって、大嫌いだった。そして、もう何十、何百と書評を書かれたけど、今まで一度も好きになったことが、いいと思ったことがなかった。けれど小松さんが書いた書評を読んで、本当に本を書いてきてよかったと思った〉という手紙をくださったんですね」
小山「それは何が違っていたんですか?」
小松「私も本当に体が震えてしまったんですけど、正直に、老いた石原さんの姿を『痛々しい』と書いたんですよ。病に抗って、それでも懸命に書く姿。その執念の姿を書いたんですね。それを灯台にたとえて、石原慎太郎は灯台である、という原稿を書いたんですけど、〈僕の原稿をそんなふうに読んでくれてありがとう〉と手紙をくださいました」
宇賀「すごいことですね」
小松「亡くなられたあとに、その手紙を読んで、石原さんはこの手紙の中に生きていらっしゃるなと思えるので手紙の素晴らしさを改めて思ったところです」
宇賀「今日は『いま想いを伝えたい方』に宛てたお手紙を書いてきてくださったんですよね」
小松「私も本当に日々、たくさんの方に手紙をいただいたり取材の折に手紙を書いたりしているんですけれども、この方へも実は最初、手紙を書いたんです。中村勘三郎さんへの手紙です」
小松さんが中村勘三郎さんへ宛てたお手紙の朗読は、ぜひradikoでお聞きください(4月30日まで聴取可能)。
宇賀「今日の放送を聞いて、小松さんにお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。責任をもってご本人にお渡しします。
【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST 小松成美さん宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」
 小松成美さん、ありがとうございました!
小松成美さん、ありがとうございました!
宇賀「小松さんはトップアスリートからアーティスト、クリエイターまで様々な人物ルポルタージュ、スポーツノンフィクション、インタビューやエッセイ、コラム、小説を執筆されています。イチローさんであったり、中田英寿さんであったり、五郎丸歩さん、元横綱の白鵬さん。さらに女優の森光子さん、YOSHIKIさんと本当にすごい方ばっかりなんですね」
小山「どうやったらこんな方々にインタビューができて本が書けるものなんですか?」
 小松「そうですね、本当に出版社や編集者の力を借りてこうした方と出会わせていただいたり、私が好きだという情熱を持ってその方にインタビューをお受けいただくというケースもございます」
小松「そうですね、本当に出版社や編集者の力を借りてこうした方と出会わせていただいたり、私が好きだという情熱を持ってその方にインタビューをお受けいただくというケースもございます」宇賀「小松さんから企画されることもあるんですね」
小松「ほとんどそうですね。3分の1くらいは出版社から」
小山「最初にうまくいったというか、いちばん売れたのは何だったんですか?」
小松「それはまさに中田英寿さんのノンフィクションでした。19歳で出会った孤高のアスリートだったんですね。当時からものすごく個性的で、周囲との衝突を厭わない青年だったので『理解をされない』と苦しんでいた時代でもあったのですけども、サッカー記者ではない私のような者に、サッカーのことや人生のことを何でも話してくださって。2人で『本を作ろう!』と」
 宇賀「それはどうやって始まったんですか?」
宇賀「それはどうやって始まったんですか?」小松「私が彼のサッカーを見て、直感的なんですけど、彼こそ日本をW杯に連れて行ってくれる人だと思ったんです。それで19歳の彼にインタビューをしたんですけど、彼が哲学を持っているということがわかったんですね。孤独に耐えて、けれど自分を貫くという。彼のサッカーを書きながら人生を書くということ。それを19歳から彼が引退をする29歳まで10年間、続けることができたんですけど、その本はたくさんの方に読んでいただけました」
宇賀「本当に深いところまで話し合われるんですね」
小松「私自身は、ものすごく好奇心が旺盛で聞きたがりなんですね。イチローさんに『なぜあなただけこんなにヒットが打てるんですか?』と聞いたことがあったんです。編集者たちは『プロ中のプロに何でそんな子どものような質問をするんだ』と紛糾したんですけども、イチローさんだけが腕を組んで、熟考をして答えてくれたんです」
 小山「なんて言ったんですか?」
小山「なんて言ったんですか?」小松「『なぜ僕が打てるか、今から考えます。他のバッターと違うところがあるはずだから、僕は今まで小松さんにそれを聞かれるまで、誰にも質問をされたことがなかったから考えたことがなかったけれども、今考えてみますね』と、答えてくれたんですね。その時に、思いの丈を素直に届けるということが、その方自身も知らない境地に届くことがあるのだなと思って、ストレートに話を聞いてよかったなとその時に思いました」
小山「その時の答えは何だったんですか?」
小松「イチローさんってID野球をしないんですね。絶対に自分の目で球種を察知する。体の重心を腰で取って、ストライクゾーンがものすごく広かったんです。イチロー・ストライクゾーンがあったんですね。ボールまで打ててしまっていた、ということが4割に近い打率だったんだなあ、と。そして誰よりも目がよかった。選球眼は本当に球界一だったと、ご自身でもその当時はおっしゃっていました」
 宇賀「ジャンルは違えども一流の方たちにたくさん取材をされてきて、そういう方達に共通していることって何かありましたか?」
宇賀「ジャンルは違えども一流の方たちにたくさん取材をされてきて、そういう方達に共通していることって何かありましたか?」小松「これでもかというくらいユニークで、エッジが立ってキャラクターは濃いんですけども、同時に共通することもあるんですね。1つは自分を貫く力。これが本当に強いです。自分がどのポジションに立って、誰に何を言うのか、伝えるのか。ご自身の中で決めたことを絶対に曲げないです。それが炎上しようがチーム内から批判を浴びようが、これが自分の信じた正しい道なのだと思えばそれを貫くんですよね。その先に必ずチームプレイに繋がっていったり、勝利に繋がっていったりするので、最後は理解されてみんなが迎え入れるというシーンも何度もあったんですけども、その貫く力が圧倒的に強いです。そしてもう1つは、ゴールをゴールと思わない。普通人は成績を収めたり、勝利を得たりすると、よくやった自分を褒めたいと思うはずなんですけれども、その方達はそれをただのラインだと思うんです。自分が目指す高みはこんなところではないと。『今晩だけは喜びますが、明日からは次のゴールに向かって次のラインに向かって走りますので、小松さんついてきてください』といつもおっしゃっていました」
 小山「いつも最初に聞くことは決めているんですか?」
小山「いつも最初に聞くことは決めているんですか?」小松「ものすごく調べて、質問を何十個も作っていくんですね。でも、行った瞬間にはそれを消去して、真っ白にすることを心がけておりまして。その場で思ったことを聞きます」
宇賀「生意気ですみません、私も本の中でまったく同じことを書いていまして……インタビューをする時に事前に調べて行くんだけれども、お会いしたらその瞬間に全部消す、というのを書いていました」
小松「同じだ!」
宇賀「やっぱり予定調和になっちゃうとつまらないですもんね。新鮮なリアクションもできなくなりますし」
小松「インタビューを本当に受け慣れている方は『次はこういう質問だろうな』とか、『こういうクエスチョンで来るんだろうな』と思っていらっしゃるので、むしろその期待を裏切るというか、突発的に聞いています」
宇賀「嬉しい、今、やってきたことにマルをもらえたような気がしています」
 宇賀「今、いちばん話を聞いてみたい人は誰ですか?」
宇賀「今、いちばん話を聞いてみたい人は誰ですか?」小山「きっと大谷翔平じゃないですか?」
小松「大谷さんが日本ハムファイターズからメジャーに行った頃から、彼の野球を彼はどんな言葉で表現するのかなということに興味があったので、本当にいつか機会があったらインタビューしたいなと思っていたんですけども、なかなか1 on 1の対面のインタビューをする機会がなくて。記者の方にはとても闊達にお話になるんですけど、なかなか難しい。いつか叶えば、WBCの舞台で見えたこと、感じたことを聞いてみたいと思います」
宇賀「お話をうかがっただけでわくわくしますね。さて、この番組は『お手紙』をテーマにお送りしているのですけども、小松さんはお手紙はよく書かれますか?」
小松「インタビューのお願いをする時には、やっぱり便箋に万年筆で今でも手紙を書きます」
宇賀「これまで受け取ったりご自身で書いたりした中で、心に残っているお手紙はありますか?」
 小松「手紙をもらうってこんな気持ちになるんだな、ということが数年前にありまして。その手紙は晩年の石原慎太郎さんからの手紙だったんですね。私が石原さんの本の書評を新聞に書いたんです。それを石原さんが読んでくださいまして。そこには、〈僕はもう書評というものにアレルギーがあって、大嫌いだった。そして、もう何十、何百と書評を書かれたけど、今まで一度も好きになったことが、いいと思ったことがなかった。けれど小松さんが書いた書評を読んで、本当に本を書いてきてよかったと思った〉という手紙をくださったんですね」
小松「手紙をもらうってこんな気持ちになるんだな、ということが数年前にありまして。その手紙は晩年の石原慎太郎さんからの手紙だったんですね。私が石原さんの本の書評を新聞に書いたんです。それを石原さんが読んでくださいまして。そこには、〈僕はもう書評というものにアレルギーがあって、大嫌いだった。そして、もう何十、何百と書評を書かれたけど、今まで一度も好きになったことが、いいと思ったことがなかった。けれど小松さんが書いた書評を読んで、本当に本を書いてきてよかったと思った〉という手紙をくださったんですね」小山「それは何が違っていたんですか?」
小松「私も本当に体が震えてしまったんですけど、正直に、老いた石原さんの姿を『痛々しい』と書いたんですよ。病に抗って、それでも懸命に書く姿。その執念の姿を書いたんですね。それを灯台にたとえて、石原慎太郎は灯台である、という原稿を書いたんですけど、〈僕の原稿をそんなふうに読んでくれてありがとう〉と手紙をくださいました」
宇賀「すごいことですね」
小松「亡くなられたあとに、その手紙を読んで、石原さんはこの手紙の中に生きていらっしゃるなと思えるので手紙の素晴らしさを改めて思ったところです」
宇賀「今日は『いま想いを伝えたい方』に宛てたお手紙を書いてきてくださったんですよね」
小松「私も本当に日々、たくさんの方に手紙をいただいたり取材の折に手紙を書いたりしているんですけれども、この方へも実は最初、手紙を書いたんです。中村勘三郎さんへの手紙です」
小松さんが中村勘三郎さんへ宛てたお手紙の朗読は、ぜひradikoでお聞きください(4月30日まで聴取可能)。
宇賀「今日の放送を聞いて、小松さんにお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。責任をもってご本人にお渡しします。
【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST 小松成美さん宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」
 小松成美さん、ありがとうございました!
小松成美さん、ありがとうございました!皆さんからのお手紙、お待ちしています
毎週、お手紙をご紹介した方の中から抽選で1名様に、大分県豊後高田市の「ワンチャー」が制作してくださったSUNDAY’S POSTオリジナル万年筆をプレゼントします。引き続き、皆さんからのお手紙、お待ちしています。日常のささやかな出来事、薫堂さんと宇賀さんに伝えたいこと、大切にしたい人や場所のことなど、何でもOKです。宛先は、【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST】までお願いします。
今週の後クレ
 今回のメッセージは、三重県〈志摩越賀郵便局〉谷口裕亮さんでした!
今回のメッセージは、三重県〈志摩越賀郵便局〉谷口裕亮さんでした!「志摩越賀郵便局のある三重県志摩市は、リアス式海岸を中心とした自然豊かな地域です。海岸を一望する展望台があり、そこからの眺めは絶景です。穏やかな気候も特徴で、ゆったりした時間を過ごすことができます。 大学生のとき、アルバイト先でお客さまからもらった手紙があります。手紙には手書きで私のお客さま対応についてお褒めの言葉が書かれていました。とても嬉しかったですし、保管して何回も読ませていただきました。やはり手紙でいただくと、より気持ちが伝わってきます。 この経験があり、接客にやりがいを感じたため、私は今、地域貢献を大事にしている郵便局で働いています。」
MORE

今週も大阪からお届け! 紙芝居界の革命児・紙芝居屋のガンチャンが登場
-

- 2025/04/20

大阪・関西万博がスタート! 万博愛好家の藤井秀雄さんが登場
-

- 2025/04/13

旅する料理人 三上奈緒さんが登場
-

- 2025/04/06

この番組ではみなさんからの手紙を募集しています。
全国の皆さんからのお便りや番組で取り上げてほしい場所
を教えてください。
〒102-8080 東京都千代田区麹町1-7
SUNDAY'S POST宛