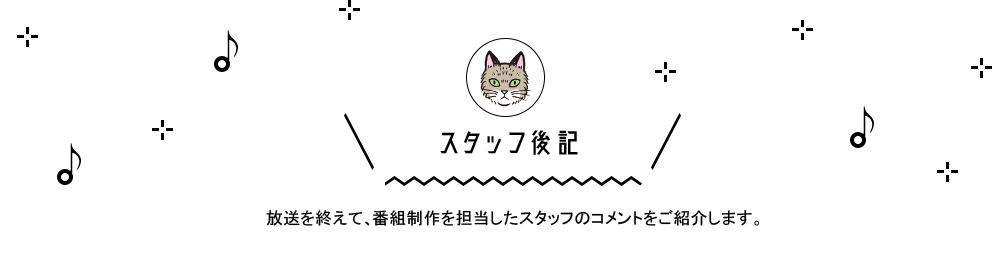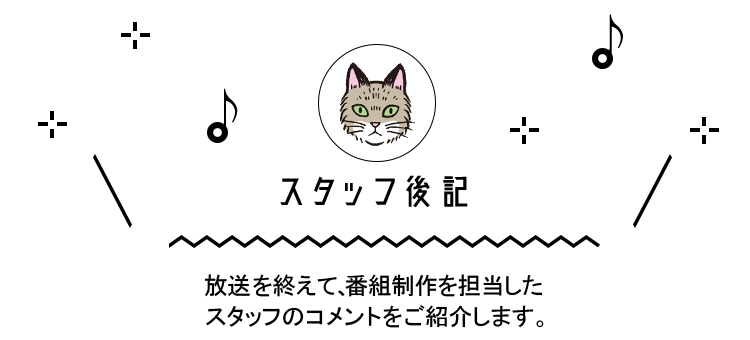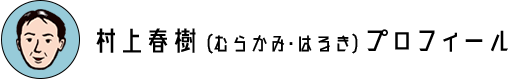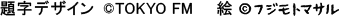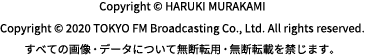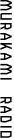


-
こんばんは。村上春樹です。村上RADIO、今夜はダイレクト・カッティングで録音されたアナログ・レコードを集めてみました。
「ダイレクト・カッティングってなんだ?」という方もおそらくたくさんいらっしゃるでしょうね。短く説明すれば、かつてのLP時代、まず一度アナログ・テープに録音した音楽を、テープの段階で切り貼りして編集し、それをディスクにカッティングしていたわけですが、そのテープの段階をパスして、直接ディスクにカッティングしちゃおう、というのがダイレクト・カッティングです。アナログ・テープからデジタルの時代に移って、この方式もおおむね意味を失い、廃れてしまいましたが、優れたダイレクト・カッティング録音には、今聴いてもはっとさせられる緊迫感が漂っています。その辺を味わってください。
<オープニングテーマ曲>
Donald Fagen「Madison Time」
ダイレクト・カッティングは、テープ編集のプロセスを省いてあるぶん、クリアで原音に近い音になっているわけですが、なにしろ編集ができないものですから、演奏を間違えたら、あとでそこだけちょっと録り直して……なんてことは不可能です。つまりぶっつけ本番、一発勝負です。だから演奏するほうも、録音するほうも緊張します。その気合いで音楽の質がぐっと高まることもありますし、それと同時に、緊張で堅くなっちゃうミュージシャンも中には出てくるかもしれません。そういう「真剣勝負」の面白さも、ダイレクト・カッティング録音の醍醐味になっているんです。


- Greensleeves
The L.A. Four
Going Home
East Wind -
今日はダイレクト・カッティングで録音されたレコードを特集します。
まず、L.A. Fourの「グリーンスリーブズ」を聴いてください。ギターのローリンド・アルメイダを中心としたカルテット、フルートがバド・シャンク、ベースがレイ・ブラウン、ドラムズがシェリー・マンという、西海岸在住の一流ミュージシャンをそろえた顔ぶれです。1977年の録音、録音場所はカリフォルニアですが、制作は日本フォノグラムで、録音スタッフは日本から出張した日本人が中心になっています。アルメイダのアコースティック・ギターの音色がとりわけ美しいです。
いまからちょっとかけますね。(よいしょ……)3曲目ですね。
本当は、こういう特集はできるだけ大きなスピーカーでがっつり聴いてもらいたいんです。そうしないと、そこにある音のクリアさやダイナミズムがよくわからないから。でも最近はradikoで放送を聴く人が中心になっているみたいで、残念といえばちょっと残念ですね。もちろん聴いていただけるだけで嬉しいんだけど、ぼくらの世代は、「スピーカーと正面から向き合って音楽を聴く」という行為に慣れちゃっているので、そういう傾向は、やはりいくぶん寂しくもあります。


- Un Chain My Heart
Roy Ayers Quartet
Comin' Home Baby
Denon -
次はレイ・チャールズの歌で有名な「アンチェイン・マイ・ハート」。演奏するのはロイ・エアーズ・カルテット。メンバーはロイ・エアーズのヴァイブ、ソニー・シャーロックのギター、ミロスラフ・ヴィトウスのベース、ブルーノ・カーのドラムズーー要するに当時のハービー・マンのグループから親分のマンさんが抜けた編成ですね。これは彼らが来日したときに、日本コロムビアが制作したレコードですが、契約の関係でマンさんは参加できなくて、サイドメンだけで演奏しました。でもね、親分抜きでもこれがずいぶんいいんです。ノリが黒くて、グルーヴィー。とくにこの頃のロイ・エアーズって、脂が乗っています。
録音も素晴らしい出来です。ダイレクト・カッティングの上に45回転盤なので、音がクリアで、ダイナミック・レンジも向上しています。
昔はオーディオ・ショップに行ってスピーカーなんかの試聴をすると、よくダイレクト・カッティングのレコードをかけてくれました。でもこれがちょっと問題でして、それほど大したことないスピーカーでも、録音がいいものだから、音がすごくきれいにダイナミックに聞こえちゃうんです。で、機械を買って帰ってうちで聴いてみると、「なんだ?」みたいなことになったりします。
だから僕なんかはオーディオ装置の試聴をしたいときには、よく自分のうちのレコードを持っていきました。スタン・ゲッツの昔のモノラル盤とか、普通の音質の普段聴き慣れたものを持っていくんです。そうすると機械の特性みたいなのが、シビアにわかります。あまり良い顔はされないみたいでしたけど。


- Rainy Days And Mondays
Ann Burton
He's Funny That Way
Lob -
次はボーカルをいきます。アン・バートンの歌う「雨の日と月曜日は(Rainy Days And Mondays)」。ロジャー・ニコルズの作った名曲です。アン・バートンはケン・マッカーシーのピアノだけをバックに、しっとりインティメイトに歌い上げます。
このアルバムは1977年に彼女が来日したときに、東京のパイオニア・スタジオで録音されました。当時はダイレクト・カッティング技術に関しては、日本がずば抜けて優秀だったんです。
ダイレクト・カッティングって、いろんな現実的困難を乗り越えなくてはならない、苦労を伴う作業だったと思うのですが、現場のみなさんがよくがんばっていたみたいで、素敵な優秀な録音が数多く残されています。日本の技術者の人って、きっと一生懸命努力するのが得意なんでしょうね。じっと聴いていると、そういう真剣な空気がひしひしと伝わってきます。にじみ出てくるというか。


- Someday My Prince Will Come
Herbie Hancock
The Piano
CBS Sony -
次はソロ・ピアノを聴いてください。ハービー・ハンコックが「いつか王子様が」を演奏します。これも日本での録音です。1978年10月に東京、信濃町のCBS・ソニー信濃町スタジオで録音されました。ピアノはまっさら新品のスタインウェイが使用されました。素晴らしい音です。
ダイレクト・カッティングって、片面に3曲入っていたら、ぶっ通し連続でその3曲を演奏しなくちゃならないんです。途中でちょっと休憩してお茶を飲んで、うぐいす餅を食べて……みたいなことはできません。だから演奏するほうも、けっこうくたくたになってしまいます。また、片面に収録できる時間も20分くらいに限られていますから、つい長くなって収まりきらなかったということも起こります。何かと苦労は絶えません。でもそういう「待ったなし」みたいな状況が、しばしば緊迫した優れた演奏を生むことがあります。このハンコックの演奏も瑞々しい美しさをたたえています。


- Lady Soul
Lee Ritenour
Sugar Loaf Express Featuring Lee Ritenour
JVC -
次はリー・リトナーをいきます。リー・リトナー、一世を風靡しましたね。このリー・リトナーが率いるグループ、ジェントル・ソウツが日本ビクターのために吹き込んだ、ダイレクト・カッティングの第2弾「シュガー・ローフ・エクスプレス」からの1曲です。デイヴ・マシューズが書いたソウルフルな曲。「Lady Soul」。
リトナーと、特別ゲスト、エリック・ゲイルとのツー・ギターの絡みがご機嫌です。キャラクターは違いますが、それぞれに個性的な良い味を出していますよね。とくにエリック・ゲイルの切れの良いバッキングは、聴き惚れてしまいます。リトナーがどうしてもエリック・ゲイルと共演したいということで、このレコーディングのために、わざわざNYから呼び寄せたんだそうです。この日が2人の初顔合わせだったんだけど、ぴったり息があっていますね。
キーボードはパトリス・ラッシェン、ベースはエイブラハム・ラボリエル、ドラムズはハーヴィー・メイソン、パーカッションがスティーヴ・フォアマン。1977年、ロサンゼルスのケンダン・スタジオでの録音です。
そういえば、数年前にホノルルの「ブルーノート」でリトナーのグループのライブを聴いたのですが、息子さんのウェズリー・リトナーがドラムズを受け持っていて、「そうか、かつてのやんちゃなギター少年、リー・リトナーにも、もうこんな立派な息子がいるんだ」と、ふと感心してしまいました。時の流れは速いです。


- Farandole
Lorin Maazel and The Cleveland Orchestra
Falla • Bizet • Tchaikovsky • Berlioz
Telarc Records -
ジャズとかフュージョン系の音楽が続いたので、ここでがらりと雰囲気をかえてクラシックを聴いてください。ビゼーの作曲した「アルルの女」第2組曲から「ファランドール」。演奏はロリン・マゼールの指揮する名門、クリーヴランド管弦楽団です。
クラシック音楽のダイレクト・カッティングってあまり見かけないのですが、この演奏は、なかなか素敵です。オーケストラの「一発勝負録音」って、人数が多いだけに、いろいろ困難を伴うと思うのですが、さすが名手揃いのクリーヴランド管弦楽団だけあって、手落ちや抜かりはありません。大きいスピーカーで大きな音で聴くと、ごつんと迫力あります。


- A Child Is Born
Dave Grusin
Discovered Again!
Sheffield Lab -
デイヴ・グルーシンのピアノと、ロン・カーターのベースが、サド・ジョーンズの名曲「ア・チャイルド・イズ・ボーン」を美しく紡(つむ)ぎ上げます。最後のほうで加わってくるヴァイブはラリー・バンカー。うっとりとする見事な演奏です。1976年の録音です。
ダイレクト・カッティングの録音って、だいたい1970年代の後半に集中しています。このアルバムは「シェフィールド」というダイレクト・カッティングを得意とする、オーディオ・ファイル、つまりオーディオ愛好家をターゲットにしたレコード会社から出ています。音質にはずいぶんこだわっていて、アルバムの解説にはピアノの調律師の名前までクレジットされています。この会社、本格的なジャズをリリースすることは珍しいのですが、このグルーシンのアルバムはとくに出来が良く、長年にわたって僕の愛聴盤のひとつになっています。


- Thursday's Child
Ann Burton
Some Other Spring
Lob -
最後にもう1曲、再びアン・バートンの歌を聴いてください。さっきおかけした曲とは異なるアルバムに入っているものですが、これもやはりダイレクト・カッティングで、日本で録音されています。録音は1980年、場所も同じ東京のパイオニア・スタジオです。前回の東京吹き込みのアルバムの評判が良かったので、またやろうということになったみたいです。
バックのピアノはフランス・エルセン、ベースはヴィクター・カイハツ。曲は「サーズデイズ・チャイルド(Thursday's Child)」です。前に何度か「ウェンズデイズ・チャイルド」という曲をおかけしたことがあるのですが、今回はその翌日・木曜日の子どもについての歌です。
「木曜日生まれの子どもは、遠くまで行かなくてはならない……」。取り上げられることのあまりない古い歌ですが、なかなか深い味わいがあります。アン・バートンって、ときどきこういうちょっと珍しい、趣味の良い曲を掘り出してきて歌いますよね。そういえば、デヴィッド・ボウイも「サーズデイズ・チャイルド」という同じタイトルの曲を歌っていますが、これはまた違う曲です。

-
今日はダイレクト・カッティング録音のアナログ・レコードだけを使ってお送りしました。全体を通して、何か独特の雰囲気みたいなものを感じ取っていただけたとしたら幸いです。ダイレクト・カッティングって、ただ音質が優れているというだけではなく、そこには何かしら独特の佇まいがあるんです。
今回こうして久しぶりにまとめて聴き直してみて、強くそのように感じました。1枚薄膜がとれて、ミュージシャンと、よりじかに、率直にコンタクトしているような、そんな雰囲気が感じ取れます。今の時代、ダイレクト・カッティングが再評価されてもいいんじゃないかという気が、個人的にはするのですが。コンピュータなんかでいじられすぎた音楽って、時としてけっこう疲れますよね。
今日の言葉は伝説的な名ヴァイオリニスト、ユーディ・メニューヒンさんの言葉です。彼は音楽についてこのように語っています。「音楽は混沌から秩序をつくりだす。なぜなら、リズムは異なるものに一致を、メロディーはばらばらなものに一貫性を、ハーモニーは相容れないものに和をもたらすからだ」
うーん、なるほど。僕らが優れた音楽を聴いたときに、深く感動し、身体から不純物が洗い流されるように感じたりするのは、きっとそういうことなんですね。ものごとのあるべき姿が、そこにすっと浮かび上がってくるというか。そういう瞬間はやがて消えてしまいますが、そういう瞬間があったという記憶はしっかり残ります。みなさんもできるだけたくさん、優れた音楽を聴いてください。
それではまた来月。
- ぶっつけ本番で演奏を直接ディスクにカッティングしちゃおう、というダイレクト・カッティング。では、小説ならどうなるのか……。3月1日に開かれた村上DJと川上未映子さんの朗読会は、まさにダイレクト・カッティングならぬダイレクト・リーディングだった(早稲田大学大隈講堂で開催)。世界中でまだ誰も読んだことのない短編小説が、二人の人気作家自身の声でダイレクトに読まれたのだ。1000名を超える聴衆も、朗読する小説家も独特な緊張感に包まれ、早春の夜の夢のような、ごつんと迫力のある朗読会だった。良き音楽と同じように、われわれの人生には優れた小説が必要なのですね。(エディターS)
- 疑問を頭に浮かべながら収録を迎えましたが、始まるや否やレコードとは思えない程クリアでダイナミックな音にびっくり。まさに目の前で演奏されているかのような、そんな世界にグッと引き込まれていました。Youtubeでも一発撮りの企画「The First Take」が人気ですが、村上DJの言うようにダイレクト・カッティングが再評価される日も近いのではないでしょうか。ヘッドフォンもいいですが、大きなスピーカーで聴ける方。是非ともお試しあれ!(ADルッカ)
- 子どものころはレコードでした。童謡は大きな絵本のように歌詞をめくりながら。くるみ割り人形のレコードも聴いたなあ。なんで針が溝をすべると音が出るのか、すごく不思議だった。正直いまも理屈はよくわかりません。でもレコードのほうが音楽と時間の関係を密接に感じられる気がしました。その感覚はいまも変わりません(構成ヒロコ)
- ダイレクトカッティングには一発勝負の緊張感と潔さが詰まっています。人生の一瞬を切り取ったような。日本のみの限定盤ハービーハンコックの『ザ・ピアノ』は若き日のハービーの気迫がみなぎり、思わず深呼吸してしまいました。春樹さん、教えていただき、ありがとうございました😊(延江GP)
- 今回の村上RADIOはダイレクトカッティングによるレコード特集です。これらの曲を収録スタジオの大きなスピーカーで聴くと、とても生々しく緊張感が伝わる音像でしたが、果たしてラジオでどこまで伝わっているでしょうか。今回はなるべく大音量でお楽しみください。(キム兄)
- 今回は実際にたくさんのレコードを所蔵している村上春樹さんだからこそ可能な、村上RADIOならではの企画ですね。作り込まれたレコードとは違った、とても生々しい雰囲気が魅力的です。最近はアナログレコードが復活しているといいますが、ダイレクトカッティングで制作する設備はあまり残っていないそうで、とても貴重な音源だと思います!(CAD伊藤)
1949(昭和24)年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。’79年『風の歌を聴け』(群像新人文学賞)でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』(野間文芸新人賞)、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(谷崎潤一郎賞)、『ノルウェイの森』、『国境の南、太陽の西』、『ねじまき鳥クロニクル』(読売文学賞)、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』(毎日出版文化賞)、最新長編小説に『騎士団長殺し』がある。『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』、『パン屋再襲撃』などの短編小説集、『ポートレイト・イン・ジャズ』(絵・和田誠)など音楽に関わる著書、『村上ラヂオ』等のエッセイ集、紀行文、翻訳書など著訳書多数。多くの小説作品に魅力的な音楽が登場することでも知られる。海外での文学賞受賞も多く、2006(平成18)年フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、’09年エルサレム賞、’11年カタルーニャ国際賞、’16年アンデルセン文学賞を受賞。