第557回 2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー
2025/12/12
先日、2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤーが発表されました。
今年の対象になったのは国産車・輸入車の合計35台。
選考委員60名が、それぞれ10台に投票して集まったポイント数で、まずは10ベストカーが決定。
その中から日本カー・オブ・ザ・イヤー、インポート・カー・オブ・ザ・イヤー、
デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー、テクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤーが決まります。

対象車を見渡すと、今のクルマのトレンドが見えてきます。
日本自動車ジャーナリスト協会 会長で日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考委員
菰田潔さんによると、目立つのはまずCO2排出量=燃費。
燃料消費が少なければCO2排出も少なくなるということで
そのためにエンジン付きでもハイブリッド車が当たり前になっています。
次に安全性。衝突したときの乗員の安全性は当然として、
レーダーやカメラを使ったADAS=先進運転支援システムによる
自動ブレーキなどの衝突被害を軽減する機能も多くの車に付いています。
もちろん運転の楽しさも重要。
エンジンやトランスミッションなど、最新のもので走りを良くしたり
あるいはハンドリング性能を磨き上げているクルマが増えています。
例えば、ホンダのプレリュードも非常に楽しい車でハンドリング性能すごくいいそう。
また、フォルクスワーゲンのID.Buzzは、全然クルマを知らない人が、
走っているのを見て「面白い」「カッコいい」「乗ってみたい」と言うそうで
そういうふうに注目するような車が増えいるとのことでした。
そんなトレンドの中で、今回10ベスト・カーに選ばれたのは以下の車種です。



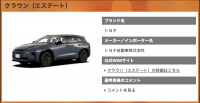






この中から日本カー・オブ・ザ・イヤーに選ばれたのはスバル フォレスター。
走行性能、実用性、快適性、オフロード性能、そしてスバルが一貫して
重視してきた安全性を高い次元で融合したSUVとして高く評価された。
待望のストロングハイブリッド(S:HEV)の採用により、独自技術である
水平対向エンジンは、燃費性能と走りの愉しさを両立する
“SUBARUらしい環境エンジン”へと進化。
さらに、アイサイトXをはじめとした先進運転支援技術や、
歩行者だけでなくサイクリストの傷害低減にも寄与するエアバッグなど、
安全装備の進化も高い評価を集めた。
との評価を受けました。
「ぶつからない車」というテレビCMで有名になったスバルのアイサイト。
これはカメラで障害物を発見し、ブレーキがかかり避ける機能。
現在では法律もできてADASを装備する車が増え、こうした性能が一般的になりました。
菰田さんによると、新型フォレスターはゼロ次安全といって
走る前の段階から死角を少なくする点に注力をして設計したとか。
ピラーが邪魔にならないような形にして、ドアミラーの形状と取り付け位置を工夫して
隙間からきちんと障害物を発見できるようにしてあるということです。
また、歩行者だけではなく、サイクリストなどのぶつかった場合、
傷害低減にも寄与するボンネットエアバッグなどの安全装備の進化も充実している点で
目を見張るところがあると菰田さんはおっしゃっていました。
海外では車同士の衝突や自車がどこかに衝突して死傷する事故が多いですが、
自動車が歩行者や自転車利用者と衝突して交通弱者が死傷する事故が多い日本。
それに対して非常に大きな対策を施したという車になっているわけです。
菰田さんは、それを評価しながらも私たちドライバーが、
クルマの機能や性能に寄りかかるだけではいけないと警鐘を鳴らします。
あくまでもキーポイントはドライバー。
いくら最新の安全装置が付いていたとしても、ドライバー自身が安全運転しようという
意識を持って事故を起こさないように細心の注意を払って運転しなければなりません。
安全装置はドライバーの「ついうっかり」を助けてくれる可能性があるだけ。
我々ドライバーも意識をバージョンアップして、
楽しみながら、安全に配慮して、ハンドルを握るようにしましょう。
今年の対象になったのは国産車・輸入車の合計35台。
選考委員60名が、それぞれ10台に投票して集まったポイント数で、まずは10ベストカーが決定。
その中から日本カー・オブ・ザ・イヤー、インポート・カー・オブ・ザ・イヤー、
デザイン・カー・オブ・ザ・イヤー、テクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤーが決まります。

対象車を見渡すと、今のクルマのトレンドが見えてきます。
日本自動車ジャーナリスト協会 会長で日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考委員
菰田潔さんによると、目立つのはまずCO2排出量=燃費。
燃料消費が少なければCO2排出も少なくなるということで
そのためにエンジン付きでもハイブリッド車が当たり前になっています。
次に安全性。衝突したときの乗員の安全性は当然として、
レーダーやカメラを使ったADAS=先進運転支援システムによる
自動ブレーキなどの衝突被害を軽減する機能も多くの車に付いています。
もちろん運転の楽しさも重要。
エンジンやトランスミッションなど、最新のもので走りを良くしたり
あるいはハンドリング性能を磨き上げているクルマが増えています。
例えば、ホンダのプレリュードも非常に楽しい車でハンドリング性能すごくいいそう。
また、フォルクスワーゲンのID.Buzzは、全然クルマを知らない人が、
走っているのを見て「面白い」「カッコいい」「乗ってみたい」と言うそうで
そういうふうに注目するような車が増えいるとのことでした。
そんなトレンドの中で、今回10ベスト・カーに選ばれたのは以下の車種です。



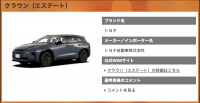






この中から日本カー・オブ・ザ・イヤーに選ばれたのはスバル フォレスター。
走行性能、実用性、快適性、オフロード性能、そしてスバルが一貫して
重視してきた安全性を高い次元で融合したSUVとして高く評価された。
待望のストロングハイブリッド(S:HEV)の採用により、独自技術である
水平対向エンジンは、燃費性能と走りの愉しさを両立する
“SUBARUらしい環境エンジン”へと進化。
さらに、アイサイトXをはじめとした先進運転支援技術や、
歩行者だけでなくサイクリストの傷害低減にも寄与するエアバッグなど、
安全装備の進化も高い評価を集めた。
との評価を受けました。
「ぶつからない車」というテレビCMで有名になったスバルのアイサイト。
これはカメラで障害物を発見し、ブレーキがかかり避ける機能。
現在では法律もできてADASを装備する車が増え、こうした性能が一般的になりました。
菰田さんによると、新型フォレスターはゼロ次安全といって
走る前の段階から死角を少なくする点に注力をして設計したとか。
ピラーが邪魔にならないような形にして、ドアミラーの形状と取り付け位置を工夫して
隙間からきちんと障害物を発見できるようにしてあるということです。
また、歩行者だけではなく、サイクリストなどのぶつかった場合、
傷害低減にも寄与するボンネットエアバッグなどの安全装備の進化も充実している点で
目を見張るところがあると菰田さんはおっしゃっていました。
海外では車同士の衝突や自車がどこかに衝突して死傷する事故が多いですが、
自動車が歩行者や自転車利用者と衝突して交通弱者が死傷する事故が多い日本。
それに対して非常に大きな対策を施したという車になっているわけです。
菰田さんは、それを評価しながらも私たちドライバーが、
クルマの機能や性能に寄りかかるだけではいけないと警鐘を鳴らします。
あくまでもキーポイントはドライバー。
いくら最新の安全装置が付いていたとしても、ドライバー自身が安全運転しようという
意識を持って事故を起こさないように細心の注意を払って運転しなければなりません。
安全装置はドライバーの「ついうっかり」を助けてくれる可能性があるだけ。
我々ドライバーも意識をバージョンアップして、
楽しみながら、安全に配慮して、ハンドルを握るようにしましょう。
第556回 同じ方向に進むバイクとの接触・衝突に注意
2025/12/05
前方に向かってクルマを走らしている時、二輪車が追い抜いていく、
また、二輪車がクルマの前で位置どりを変えて追い越していく事があります。
こうしたシーンでは接触や追突事故の危険があり
クルマ側に非がないとしても気をつけなければいけません。

今回、お話をお聞きしたモーターサイクルジャーナリストで
ライディングインストラクターの佐川健太郎さんによると
教習所でも習うとおり、バックミラーだけではなく目視で直接確認することが大事。
人間の視野は、おおよそ左右180度。
そして、バックミラーで見られる真後ろを中心に90度。
つまり、前方を向いて、バックミラーを見ても
左右ともに後ろの45度を確認することができていません。
必ず首を振って目視で確認して下さい。
人間の視野は、おおよそ左右180度。
バックミラーで後方をカバーできる範囲が、真後ろを起点に左右約90度。
前方を向いて、バックミラーを見るという行為だと、
左右ともに後ろの45度を確認することができていません。
必ず首を振って目視で確認して下さい。

さらにクルマの車線変更については、
二輪車に乗っているライダーとの感覚の違いを意識しましょう。
バイクは車に比べて軽快な乗り物。
一瞬で視覚に入ってくる、死角から飛び出してくる、という性質があります。
クルマのドライバーからすると急に現れるというふうに見えるかもしれませんが
バイク側から見ると普通に走っているだけだったりするので感覚にズレがあります。
佐川健太郎さんの提言は、クルマのドライバーが2〜3秒の観察時間をおくこと。
その時間を作ることで、バイクが急に現れても回避できたり、動きを観察できます。
その余裕を持って車線変更アクションに入って下さい。

そして、注意すべきは特に渋滞時にありがちな
二輪車がクルマの間を縫うようにして先へこうとするすり抜け運転に対して、
接触、追突しないための注意点やクルマの操作。
まず、気をつけるべきは急な車線変更をしないこと。
急ハンドル、急ブレーキなどの急な動作、操作が増えるほど接触可能性が高くなります。
車・バイクのドライバー・ライダーの反応速度は約2秒。
操作するまでに1秒。その後の求めた作動に移るまでに1秒。
その約2秒の余裕を持つと事故を回避できる確率が高くなると言われています。
そのように、ライダーが反応できる時間を少し余計にとることが
お互い事故を防ぐ大事なポイントになります。

事故防止には二輪車側の注意とルールに則ったライディングも必要です。
なるべくあまり追い抜き・追い越しはしない。
特に市街地は何が起きるかわかりません。
道路脇から歩行者だとか自転車が飛び出してくる可能性もあります。
それらを前提にして、あえて追い越しをするのであれば
十分な横の間隔や空間を確保した上で行いましょう。
1.5mは車との横の間隔を開けて追い越しというのが佐川さんの指摘。
渋滞時に猛スピードで右から左からすり抜けていくのはやめましょう。
それは法律的には安全運転義務違反。
それによって先を急いでいても大して時間は変わりません。
余裕を持った運転をするよう心がけて下さい。
交通社会を構成する四輪車、二輪車。
運転をするドライバー、ライダーともに思いやりと配慮、
そして、注意意識を持って、事故が起きないよう気をつけましょう。
また、二輪車がクルマの前で位置どりを変えて追い越していく事があります。
こうしたシーンでは接触や追突事故の危険があり
クルマ側に非がないとしても気をつけなければいけません。

今回、お話をお聞きしたモーターサイクルジャーナリストで
ライディングインストラクターの佐川健太郎さんによると
教習所でも習うとおり、バックミラーだけではなく目視で直接確認することが大事。
人間の視野は、おおよそ左右180度。
そして、バックミラーで見られる真後ろを中心に90度。
つまり、前方を向いて、バックミラーを見ても
左右ともに後ろの45度を確認することができていません。
必ず首を振って目視で確認して下さい。
人間の視野は、おおよそ左右180度。
バックミラーで後方をカバーできる範囲が、真後ろを起点に左右約90度。
前方を向いて、バックミラーを見るという行為だと、
左右ともに後ろの45度を確認することができていません。
必ず首を振って目視で確認して下さい。

さらにクルマの車線変更については、
二輪車に乗っているライダーとの感覚の違いを意識しましょう。
バイクは車に比べて軽快な乗り物。
一瞬で視覚に入ってくる、死角から飛び出してくる、という性質があります。
クルマのドライバーからすると急に現れるというふうに見えるかもしれませんが
バイク側から見ると普通に走っているだけだったりするので感覚にズレがあります。
佐川健太郎さんの提言は、クルマのドライバーが2〜3秒の観察時間をおくこと。
その時間を作ることで、バイクが急に現れても回避できたり、動きを観察できます。
その余裕を持って車線変更アクションに入って下さい。

そして、注意すべきは特に渋滞時にありがちな
二輪車がクルマの間を縫うようにして先へこうとするすり抜け運転に対して、
接触、追突しないための注意点やクルマの操作。
まず、気をつけるべきは急な車線変更をしないこと。
急ハンドル、急ブレーキなどの急な動作、操作が増えるほど接触可能性が高くなります。
車・バイクのドライバー・ライダーの反応速度は約2秒。
操作するまでに1秒。その後の求めた作動に移るまでに1秒。
その約2秒の余裕を持つと事故を回避できる確率が高くなると言われています。
そのように、ライダーが反応できる時間を少し余計にとることが
お互い事故を防ぐ大事なポイントになります。

事故防止には二輪車側の注意とルールに則ったライディングも必要です。
なるべくあまり追い抜き・追い越しはしない。
特に市街地は何が起きるかわかりません。
道路脇から歩行者だとか自転車が飛び出してくる可能性もあります。
それらを前提にして、あえて追い越しをするのであれば
十分な横の間隔や空間を確保した上で行いましょう。
1.5mは車との横の間隔を開けて追い越しというのが佐川さんの指摘。
渋滞時に猛スピードで右から左からすり抜けていくのはやめましょう。
それは法律的には安全運転義務違反。
それによって先を急いでいても大して時間は変わりません。
余裕を持った運転をするよう心がけて下さい。
交通社会を構成する四輪車、二輪車。
運転をするドライバー、ライダーともに思いやりと配慮、
そして、注意意識を持って、事故が起きないよう気をつけましょう。
第555回 冬は3つの”急”な運転はNG
2025/11/28
積雪や凍結など、他の季節にはない危険がある冬の道路。
そこに3つの”急”なクルマの操作が重なると交通事故の原因になります。
ブレーキが利かずに前の車にぶつかる、曲がり過ぎて車線から逸脱する、
車がスピンしてコントロール不能になるといったことが起こり得るからです。

危険な3つの“急”な運転とは「急ハンドル」「急ブレーキ」「急な加速」。
ふだんクルマを運転している方であれば危ないことは経験的に分かっているはず。
ただ、冬は特に危ないことを、しっかり認識しておきましょう。
急ハンドルが危険なのは、スピードが出ている状態。
ハンドル切ると車が方向転換を始まりますが、
急だと方向転換が早く、想定していたよりもまわってしまう可能性があります。
ひどい場合には、後輪から滑ってスピンしてしまうこともあるので要注意です。
急ブレーキは、タイヤのグリップ力を超えてスリップしてしまうことがあります。
スリップすればスピンしてしまいますし、スピンしなくてもスリップした事により
停止距離が伸びて前の車に追突してしまうかもしれません。
急加速は逆にスピードが遅い時にホイールスピンしやすくなります。
信号からスタートするところが危険。
他の車を追い越す時もホイールスピンが危険なので、急加速しないこと。
姿勢が乱れて、思わぬ方向に車が進んでしまったりするので危険です。

路面への積雪、凍結に注意してクルマを走行させる中で、
特に危険度が高いところがあることも知っておきましょう。
橋の上やトンネルの出入口は風がよく通るので、空気が冷えて路面凍結が起こりがち。
また、日光が当たらずに、一日中日陰になっている場所も要注意です。
そうしたところでは、濡れて見えるけど、実は凍っていることが往々にしてあります。
それが「ブラックアイスバーン」と呼ばれている現象で
普通のウエット路面よりも五倍も六倍も滑りやすくいので気をつけましょう。
さらに信号で多くのクルマが停止するところは圧雪路になりやすいもの。
そうしたところでは、ブレーキの使用にも最新の注意を払います。

いつもの運転“急”な操作をしていないドライバーは、
冬の運転でも自ら危険を招くことは少ないでしょう。
ふだんから急ハンドル、急ブレーキ、急加速をしないという姿勢が大切です。
最後に、凍結路面は気温がマイナスにならなくても発生します。
気温が3度を下回るぐらいになると、路面の凍結の可能性が高くなります。
最近の車はメーターの機器に氷マークが出てくる車種も多いので、
表示を確認しつつ、出ていたら路面に配慮して運転するようにして下さい。
そこに3つの”急”なクルマの操作が重なると交通事故の原因になります。
ブレーキが利かずに前の車にぶつかる、曲がり過ぎて車線から逸脱する、
車がスピンしてコントロール不能になるといったことが起こり得るからです。

危険な3つの“急”な運転とは「急ハンドル」「急ブレーキ」「急な加速」。
ふだんクルマを運転している方であれば危ないことは経験的に分かっているはず。
ただ、冬は特に危ないことを、しっかり認識しておきましょう。
急ハンドルが危険なのは、スピードが出ている状態。
ハンドル切ると車が方向転換を始まりますが、
急だと方向転換が早く、想定していたよりもまわってしまう可能性があります。
ひどい場合には、後輪から滑ってスピンしてしまうこともあるので要注意です。
急ブレーキは、タイヤのグリップ力を超えてスリップしてしまうことがあります。
スリップすればスピンしてしまいますし、スピンしなくてもスリップした事により
停止距離が伸びて前の車に追突してしまうかもしれません。
急加速は逆にスピードが遅い時にホイールスピンしやすくなります。
信号からスタートするところが危険。
他の車を追い越す時もホイールスピンが危険なので、急加速しないこと。
姿勢が乱れて、思わぬ方向に車が進んでしまったりするので危険です。

路面への積雪、凍結に注意してクルマを走行させる中で、
特に危険度が高いところがあることも知っておきましょう。
橋の上やトンネルの出入口は風がよく通るので、空気が冷えて路面凍結が起こりがち。
また、日光が当たらずに、一日中日陰になっている場所も要注意です。
そうしたところでは、濡れて見えるけど、実は凍っていることが往々にしてあります。
それが「ブラックアイスバーン」と呼ばれている現象で
普通のウエット路面よりも五倍も六倍も滑りやすくいので気をつけましょう。
さらに信号で多くのクルマが停止するところは圧雪路になりやすいもの。
そうしたところでは、ブレーキの使用にも最新の注意を払います。

いつもの運転“急”な操作をしていないドライバーは、
冬の運転でも自ら危険を招くことは少ないでしょう。
ふだんから急ハンドル、急ブレーキ、急加速をしないという姿勢が大切です。
最後に、凍結路面は気温がマイナスにならなくても発生します。
気温が3度を下回るぐらいになると、路面の凍結の可能性が高くなります。
最近の車はメーターの機器に氷マークが出てくる車種も多いので、
表示を確認しつつ、出ていたら路面に配慮して運転するようにして下さい。


