�����Υ����� JA����presents �ʤ�ۤ�!���̰���
Every Friday 7:20��7:27
���̥롼���ƻϩ���𡢸��̰����˴ؤ���ǿ��ȥԥå����ʤɤ��轵�狼��䤹���Ҳ𤷤ޤ���
��481����ԼԤ�ƻϩ������λ���
2024/06/28
����ϸ�����ˡ�� ���̻��� ����ʬ�ϥ����ʥ�������ˤ���
�����Υǡ��������դ�Ф�����ԼԤ����̻��Τ������䤹�����ˤĤ��Ƥ��������ޤ�����
�ޤ��ϡ���ǯ����˷ٻ�ģ��ȯɽ������������
������ǯ�θ��̻��� ��˴�Կ����Ž��Կ���
����ޤ˾���� / �����ȥХ��˾���� / �����ΡȾ����̡ɤǸ����
��˴�Կ�����ԼԤ��Ǥ�¿���Ȥ���������³���Ƥ���
��ǯ������5ǯ��973�ͤ����Τ�36.3%�Ǥ���

����˽Ž��Կ��ˤĤ��Ƥ⡢
��ǯ����ԼԤ��Ǥ�¿��7,171�ͤ����Τ�25.9%��
�����˸��̻��Τ�˴���ʤä���������߷ס��̤˸����6�䶯��ƻϩ������Ǥ���

�����ξ����Ƨ�ޤ�����ǥ�������ˤ�������Ϥ��á�
������λ��Τˤϡ�������ƻ�ޤ��ϲ�����ƻ�ն������λ���
������ƻ�Τʤ���������λ��Τ�����ޤ���
���������ƻϩ������λ��ΤˤĤ��Ƹ��椷�Ƥ���
������졼�ŵ� ������ҡ����� ���餵��ˤ���Ƚ�������Τ�
�� ������ƻ������λ��ΤǤϼ�ξ�οʹ�������ľ�ʤ��ⱦ����¿��
�� ������ƻ���ʤ����Ǥϼ�ξ��ľ���椬¿��
����ϲ�����ƻ������λ��ΤǤϡ�
ñϩ�β�����ƻ�������������ˤ������ξ�����λ��Τ�¿��
�դ˲�����ƻ���ʤ���������Ǥ�ñϩ�ˤ�������Τ�¿�����Ȥ�ȿ�Ǥ��Ƥ���ȹͤ����
�����λ��Τ������ͭ�λ������ץǡ�������ʬ�Ϥ����Ȥ���
���̻��Τη����¿���ּ�ξľ����פȡֱ�����פˤĤ��ơ�
�ֲ�����ƻ��̵ͭ�פȡ������̤˻�˴�Ž����ΤȤʤä����פƤߤ�ȡ�
����ּ�ξľ����λ�˴�Ž�����Ψ�פ�¾����⤤���Ȥ��狼�ä��Ȥ����ޤ���
��ξ����®���뱦������Ф���ľ�����®�٤��⤤�ޤ�
��ԼԤȾ��ͤ��Ƥ��뤳�Ȥ˵������Ƥ���ȹͤ�����ȤΤ��ȤǤ�����

��ԼԤβ�����ƻ�ʳ��Ǥ�ƻϩ�β��Ǥϡ�
����ԼԲ��Ƕػߡפ�ɸ����������Ϥ������NG��
ɸ�����ʤ�������ꤢ��ޤ�����ξ��ľ����ľ������ӽФ��٤϶ػߤ���Ƥ��ޤ���
����Ǥϡ���ԼԤΤɤ���װ�����β�����λ��ΤˤĤʤ��äƤ���Τ���
���� ���餵��ˤ��ȡ���ԼԤο�Ū�װ��ϰ�����ǧ�ʤ���������ǧ�Խ�ʬ��
����ˤϡֺ����������ǧ�������ɡ��⤦�����ϳ�ǧ���ʤ��ä��פȤ������Ȥ�
�ְ��١�����ξ�����ǧ����������¦����μ�ξ����ᤴ�������
���٤⤦�����ΰ�����ǧ�ʤ��ä��פʤɤ��������ޤ���
�����ǡ�����Ϥ����ޤ�¿���ʤ���ΤΡ������٤��뤬¿���ʤ��Ū�װ��Ȥ��Ƥϡ�
������®�ٴ��Ф���ä��פ��Ƚ�Ǥθ��ꡢ����¾�פ�������
��®�ٴ��Фθ���פϡ����ǤǤ���Ȼפ������ƻϩ�˽Ф����
��ξ��®�ٴ����ܶᴶ����ä�ǧ�����Ʋ��Ǥ������ޤǤ˼�ξ�����Ƥ��ޤ���������
��Ƚ�Ǹ��ꡢ����¾�פϡ���˲��ǤǤ���Ȼפä��ʤɤλפ����ߤˤ���Ƚ�Ǥʤɡ�
�и���������β��ǤǤϻפä�����ƻϩ���Ǥ˻��֤�������Τ�
���Ȥ����®�٤��ξ�Ȥΰ��ִط���ͽ¬����ä���̤ȹͤ�����ȤΤ��ȤǤ�����

�ְ�����ǧ�ʤ��פ�ǯ��˴ط��ʤ����������¿���Τǵ���Ĥ��Ʋ�������
��Ƚ�Ǥθ���פϡ����¿�����Ȥ����դ��ޤ��礦��
�����ơ���Ƭ�ǰ��Ѥ����ٻ�ģ��ȯɽ�������������
�����θ��̻��Τϡ��ä�65�аʾ夬����Ĥ���٤����Ȥ��狼��ޤ���
��ǯ��65��̤���������λ�Կ���258�ͤ�
������Ф���65�аʾ��662�͡�
���Τ���65��̤���β�����ƻ�������51�ͤǡ����褽20%��
������ƻ�ʳ��������55�ͤǡ����褽21%��
�����ǡ�65�аʾ�β�����ƻ�������149�͡����褽23%��
������ʬ�Υѡ�����ơ����Ϥ��ޤ��Ѥ��ޤ��Ϳ���¿����
������ƻ�ʳ��������337�ͤǡ����褽51%��
�������65��̤������30���¿�����Ϳ��⤫�ʤ�������282��¿����

�ȤΤޤ��˹������������������դ�¥(���ʤ�)���Ĥġ�
��֤�ȿ�ͺ����Ѥ������Ʋ�������
�ɥ饤�С���Ω��Ǥϡ��ä���֤ϥ��ԡ��ɤ�Ф���������
��ԼԤ��ФƤ��뤫�⤷��ʤ���ǽ����ǰƬ�˥ϥ�ɥ��ޤ��礦��
�����Υǡ��������դ�Ф�����ԼԤ����̻��Τ������䤹�����ˤĤ��Ƥ��������ޤ�����
�ޤ��ϡ���ǯ����˷ٻ�ģ��ȯɽ������������
������ǯ�θ��̻��� ��˴�Կ����Ž��Կ���
����ޤ˾���� / �����ȥХ��˾���� / �����ΡȾ����̡ɤǸ����
��˴�Կ�����ԼԤ��Ǥ�¿���Ȥ���������³���Ƥ���
��ǯ������5ǯ��973�ͤ����Τ�36.3%�Ǥ���

����˽Ž��Կ��ˤĤ��Ƥ⡢
��ǯ����ԼԤ��Ǥ�¿��7,171�ͤ����Τ�25.9%��
�����˸��̻��Τ�˴���ʤä���������߷ס��̤˸����6�䶯��ƻϩ������Ǥ���

�����ξ����Ƨ�ޤ�����ǥ�������ˤ�������Ϥ��á�
������λ��Τˤϡ�������ƻ�ޤ��ϲ�����ƻ�ն������λ���
������ƻ�Τʤ���������λ��Τ�����ޤ���
���������ƻϩ������λ��ΤˤĤ��Ƹ��椷�Ƥ���
������졼�ŵ� ������ҡ����� ���餵��ˤ���Ƚ�������Τ�
�� ������ƻ������λ��ΤǤϼ�ξ�οʹ�������ľ�ʤ��ⱦ����¿��
�� ������ƻ���ʤ����Ǥϼ�ξ��ľ���椬¿��
����ϲ�����ƻ������λ��ΤǤϡ�
ñϩ�β�����ƻ�������������ˤ������ξ�����λ��Τ�¿��
�դ˲�����ƻ���ʤ���������Ǥ�ñϩ�ˤ�������Τ�¿�����Ȥ�ȿ�Ǥ��Ƥ���ȹͤ����
�����λ��Τ������ͭ�λ������ץǡ�������ʬ�Ϥ����Ȥ���
���̻��Τη����¿���ּ�ξľ����פȡֱ�����פˤĤ��ơ�
�ֲ�����ƻ��̵ͭ�פȡ������̤˻�˴�Ž����ΤȤʤä����פƤߤ�ȡ�
����ּ�ξľ����λ�˴�Ž�����Ψ�פ�¾����⤤���Ȥ��狼�ä��Ȥ����ޤ���
��ξ����®���뱦������Ф���ľ�����®�٤��⤤�ޤ�
��ԼԤȾ��ͤ��Ƥ��뤳�Ȥ˵������Ƥ���ȹͤ�����ȤΤ��ȤǤ�����

��ԼԤβ�����ƻ�ʳ��Ǥ�ƻϩ�β��Ǥϡ�
����ԼԲ��Ƕػߡפ�ɸ����������Ϥ������NG��
ɸ�����ʤ�������ꤢ��ޤ�����ξ��ľ����ľ������ӽФ��٤϶ػߤ���Ƥ��ޤ���
����Ǥϡ���ԼԤΤɤ���װ�����β�����λ��ΤˤĤʤ��äƤ���Τ���
���� ���餵��ˤ��ȡ���ԼԤο�Ū�װ��ϰ�����ǧ�ʤ���������ǧ�Խ�ʬ��
����ˤϡֺ����������ǧ�������ɡ��⤦�����ϳ�ǧ���ʤ��ä��פȤ������Ȥ�
�ְ��١�����ξ�����ǧ����������¦����μ�ξ����ᤴ�������
���٤⤦�����ΰ�����ǧ�ʤ��ä��פʤɤ��������ޤ���
�����ǡ�����Ϥ����ޤ�¿���ʤ���ΤΡ������٤��뤬¿���ʤ��Ū�װ��Ȥ��Ƥϡ�
������®�ٴ��Ф���ä��פ��Ƚ�Ǥθ��ꡢ����¾�פ�������
��®�ٴ��Фθ���פϡ����ǤǤ���Ȼפ������ƻϩ�˽Ф����
��ξ��®�ٴ����ܶᴶ����ä�ǧ�����Ʋ��Ǥ������ޤǤ˼�ξ�����Ƥ��ޤ���������
��Ƚ�Ǹ��ꡢ����¾�פϡ���˲��ǤǤ���Ȼפä��ʤɤλפ����ߤˤ���Ƚ�Ǥʤɡ�
�и���������β��ǤǤϻפä�����ƻϩ���Ǥ˻��֤�������Τ�
���Ȥ����®�٤��ξ�Ȥΰ��ִط���ͽ¬����ä���̤ȹͤ�����ȤΤ��ȤǤ�����

�ְ�����ǧ�ʤ��פ�ǯ��˴ط��ʤ����������¿���Τǵ���Ĥ��Ʋ�������
��Ƚ�Ǥθ���פϡ����¿�����Ȥ����դ��ޤ��礦��
�����ơ���Ƭ�ǰ��Ѥ����ٻ�ģ��ȯɽ�������������
�����θ��̻��Τϡ��ä�65�аʾ夬����Ĥ���٤����Ȥ��狼��ޤ���
��ǯ��65��̤���������λ�Կ���258�ͤ�
������Ф���65�аʾ��662�͡�
���Τ���65��̤���β�����ƻ�������51�ͤǡ����褽20%��
������ƻ�ʳ��������55�ͤǡ����褽21%��
�����ǡ�65�аʾ�β�����ƻ�������149�͡����褽23%��
������ʬ�Υѡ�����ơ����Ϥ��ޤ��Ѥ��ޤ��Ϳ���¿����
������ƻ�ʳ��������337�ͤǡ����褽51%��
�������65��̤������30���¿�����Ϳ��⤫�ʤ�������282��¿����

�ȤΤޤ��˹������������������դ�¥(���ʤ�)���Ĥġ�
��֤�ȿ�ͺ����Ѥ������Ʋ�������
�ɥ饤�С���Ω��Ǥϡ��ä���֤ϥ��ԡ��ɤ�Ф���������
��ԼԤ��ФƤ��뤫�⤷��ʤ���ǽ����ǰƬ�˥ϥ�ɥ��ޤ��礦��
��480�Ҥɤ���ܿ�����
2024/06/21
���̻��Τ˴ؤ��ơ����6��פȤ������դ�ʹ�������ȤϤ���ޤ�����
6��Ͼ�����������ޤ��ܿ�������Τ�¿�����Ȥ������ޤ줿��Ρ�
�ɥ饤�С��γ�����ˤϻҶ������ΰ������뤿��
���줰��ⵤ��Ĥ��Ƥ������������Ȼפ��ޤ���
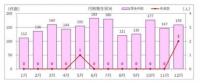
��Υ���դϷٻ�ģ��ȯɽ������ǯ�ΡֻҶ��θ��̿ͿȻ���ȯ�������ס�
�Ļ�������������������ط��������ΤǤ���
�Ǥ���̻��Τ����äƤ���Ϳ���¿���Τ�6���183�͡�
������7�� – 180�͡�10�� – 177�͡�3�� – 160�ͤȤ����硣
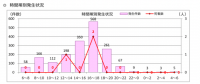
�����ơ���Υ���դϻ����̤˸�����Ρ�
����Ū��¿���Τ������4��〜6����568�͡�
�����Ǹ��2��〜4����350�͡����6��〜8����261�͡�
��������������ϳع�������äơ���ʬ���������줿����ƻ��
���뤤�ϽΤ佬�����˵ޤ��Ǹ��������桢����ʸ��ʤ���������ޤ���
���μ���¿���Τ�����8��〜10���Ǥ�����������й����֤Ǥ��礦��
���Υǡ����Ϸٻ�ģ�ˤ�����פʤΤǡ�
�쳵����������ƤϤޤ�ʤ����⤷��ޤ���
�����������������뤳�Ȥ�Ф��Ƥ����Ʋ�������

��ž��ʳؤ��������� �ǥ������ꥨ���� ��ɽ������
������������ˤ��ȡ��Ҥɤ�ϴ������������㤤¸�ߡ�
�֤α���������ɤǻ�Ѥ���ФƤ���Ȥ�����ħ������ޤ���
����˥ɥ饤�֥쥳�������α�����3�������Ƥ����������ˤ���
��ƻ�����������ӽФ��ʤɡ�����������ӽФ���¿����ħ�����뤽���Ǥ���
��������ι�ư�ϰϤ�ͤ���ȡ��Ǥ����դ��٤�������ƻϩ��
�ϰ����餹�ͤ��Ȥ�����פ�ƻϩ�˽Ф�ޤǤ����Ѥ���
���ڸ��̾ʤ�����Ǥ���5.5m̤����ƻ�Ǥ���
����ƻ�ʤΤǴ���Ū�˸����˲�����ƻ�修��Ϥʤ�
�Ҥɤ⤬���ӽФ��Ƥ����ܿ����Ƥ��ޤ����Τ��ͤ����ޤ���
�ּ֤��̤뤫��Ҷ������ӽФ��Ƥ��ʤ��������פȤ�
�ֻҶ�����Ϥ����餬�����Ƥ���פȻפäƤ��ޤ��ȼ֤λ��Τ��ɤ��ޤ���
�Ҷ��Ĥ������Ϥ����˸�®����褦�ˤ��ޤ��礦��

����ƻϩ�θ����ϴ���Ū�˸��̤��������Τǽ��Ե�̳������ޤ���
�ޤ���®��10�����ʲ�����Ȥ����ȡ�
�ͿȻ��Τϻ�®30km/h��Ķ����Ȼ�˴Ψ��2.7%��
�Ȥ�������®30km/h�ޤ���0.9%�ޤ��㤯�ʤ�
��®20km/h�ޤ���0.4%�ˤޤ��㤯�ʤ�ޤ���
�����ơ�����ƻϩ�ˤϤʤ�٤��֥졼�������֤��ֹ����֥졼���פǿ������뤳�ȡ�
�������뤫��֥졼�������֤���������֤���0.2�á�
���ä�0.2�äȻפ����⤷��ޤ�������Ū������®�٤��㤤����ƻϩ�ʤΤ�
�֥졼�����Ƨ��С��⤷��λ�������β���˷Ҥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���

�⤷������ȡ����Ф˥���ޤ�ž����ͤ����դ��٤����פ�
�����פ����㤵���줵��⤤��ä���뤫�⤷��ޤ���
�������ɥ饤�С��Ϻٿ������դ�ʧ���٤��Ǥ�����
�Ҥɤ�δ�����ư���ʤ���л��Τϵ����ʤ��Τ���¡�
���Ҥ����ƻϩ�δ������뤳�Ȥ����ڤǤ���
1�ͤdz��Ф�����ʤɡ����ä������մ����ޤ��礦��
ͼ������ˤ�ȿ�ͺ��ȤˤĤ���褦��θ���Ƥ����Ʋ�������
�ɥ饤�С����ݸ�ԡ����줾���Ω�줫�顢
�Ҥɤ⤬����ޤ��ܿ�������Τ�1�ĤǤ⸺�餹�褦���Ϥ�������ΤǤ���
������������
6��Ͼ�����������ޤ��ܿ�������Τ�¿�����Ȥ������ޤ줿��Ρ�
�ɥ饤�С��γ�����ˤϻҶ������ΰ������뤿��
���줰��ⵤ��Ĥ��Ƥ������������Ȼפ��ޤ���
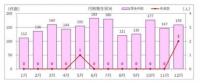
��Υ���դϷٻ�ģ��ȯɽ������ǯ�ΡֻҶ��θ��̿ͿȻ���ȯ�������ס�
�Ļ�������������������ط��������ΤǤ���
�Ǥ���̻��Τ����äƤ���Ϳ���¿���Τ�6���183�͡�
������7�� – 180�͡�10�� – 177�͡�3�� – 160�ͤȤ����硣
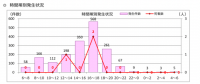
�����ơ���Υ���դϻ����̤˸�����Ρ�
����Ū��¿���Τ������4��〜6����568�͡�
�����Ǹ��2��〜4����350�͡����6��〜8����261�͡�
��������������ϳع�������äơ���ʬ���������줿����ƻ��
���뤤�ϽΤ佬�����˵ޤ��Ǹ��������桢����ʸ��ʤ���������ޤ���
���μ���¿���Τ�����8��〜10���Ǥ�����������й����֤Ǥ��礦��
���Υǡ����Ϸٻ�ģ�ˤ�����פʤΤǡ�
�쳵����������ƤϤޤ�ʤ����⤷��ޤ���
�����������������뤳�Ȥ�Ф��Ƥ����Ʋ�������

��ž��ʳؤ��������� �ǥ������ꥨ���� ��ɽ������
������������ˤ��ȡ��Ҥɤ�ϴ������������㤤¸�ߡ�
�֤α���������ɤǻ�Ѥ���ФƤ���Ȥ�����ħ������ޤ���
����˥ɥ饤�֥쥳�������α�����3�������Ƥ����������ˤ���
��ƻ�����������ӽФ��ʤɡ�����������ӽФ���¿����ħ�����뤽���Ǥ���
��������ι�ư�ϰϤ�ͤ���ȡ��Ǥ����դ��٤�������ƻϩ��
�ϰ����餹�ͤ��Ȥ�����פ�ƻϩ�˽Ф�ޤǤ����Ѥ���
���ڸ��̾ʤ�����Ǥ���5.5m̤����ƻ�Ǥ���
����ƻ�ʤΤǴ���Ū�˸����˲�����ƻ�修��Ϥʤ�
�Ҥɤ⤬���ӽФ��Ƥ����ܿ����Ƥ��ޤ����Τ��ͤ����ޤ���
�ּ֤��̤뤫��Ҷ������ӽФ��Ƥ��ʤ��������פȤ�
�ֻҶ�����Ϥ����餬�����Ƥ���פȻפäƤ��ޤ��ȼ֤λ��Τ��ɤ��ޤ���
�Ҷ��Ĥ������Ϥ����˸�®����褦�ˤ��ޤ��礦��

����ƻϩ�θ����ϴ���Ū�˸��̤��������Τǽ��Ե�̳������ޤ���
�ޤ���®��10�����ʲ�����Ȥ����ȡ�
�ͿȻ��Τϻ�®30km/h��Ķ����Ȼ�˴Ψ��2.7%��
�Ȥ�������®30km/h�ޤ���0.9%�ޤ��㤯�ʤ�
��®20km/h�ޤ���0.4%�ˤޤ��㤯�ʤ�ޤ���
�����ơ�����ƻϩ�ˤϤʤ�٤��֥졼�������֤��ֹ����֥졼���פǿ������뤳�ȡ�
�������뤫��֥졼�������֤���������֤���0.2�á�
���ä�0.2�äȻפ����⤷��ޤ�������Ū������®�٤��㤤����ƻϩ�ʤΤ�
�֥졼�����Ƨ��С��⤷��λ�������β���˷Ҥ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���

�⤷������ȡ����Ф˥���ޤ�ž����ͤ����դ��٤����פ�
�����פ����㤵���줵��⤤��ä���뤫�⤷��ޤ���
�������ɥ饤�С��Ϻٿ������դ�ʧ���٤��Ǥ�����
�Ҥɤ�δ�����ư���ʤ���л��Τϵ����ʤ��Τ���¡�
���Ҥ����ƻϩ�δ������뤳�Ȥ����ڤǤ���
1�ͤdz��Ф�����ʤɡ����ä������մ����ޤ��礦��
ͼ������ˤ�ȿ�ͺ��ȤˤĤ���褦��θ���Ƥ����Ʋ�������
�ɥ饤�С����ݸ�ԡ����줾���Ω�줫�顢
�Ҥɤ⤬����ޤ��ܿ�������Τ�1�ĤǤ⸺�餹�褦���Ϥ�������ΤǤ���
������������
��479��������Ϥθ��̰����ؤμ���Ȥ�
2024/06/14
���ܳ��ϤǤ����������̻��Τ�ʤ�������γ�ư���Ԥ��Ƥ��ơ�
����˴ؤ�äƤ����������ޤ���
������������Ƥ���֤ʤ�ۤɡ����̰����ס�
����ϴ�긩�Ⱥ��츩�ǹԤ��Ƥ������Ȥߤ��������ޤ�����

��ǯ4���긩 ����ĮΩ�����쾮�ع��λ�Ƹ�γ�����144̾��
���ȷٻ��𤫤�֥ԥ��åݿ����פ˰Ѿ�����ޤ�����
����ϴ�긩�٤Υޥ����åȡ֤Ԥ��ݡפ�ȿ�ͺब����ԥ��äȤ���¤�졣
�֤Ԥ��ݡפ��ϸ��������Ƹ�ú�ȡ����͡�����������
�ֱ��˥�ޥ������˥�ޥ����פΰ��ᤫ��Ĥ���줿
��������Ϣ�ۤ����롢��γ�����������ޤ������դˤ����ڥ�����饯������

���Ρ֤Ԥ��ݡפ˥���ޤΥ饤�Ȥ�������ȥԥ��äȸ���ȿ�ͺ�Ĥ����⤯���Ȥ���
����Į�Ǥϡ֥ԥ��åݡפȤ���ȿ�ͺब����ޤ�����
�����쾮�ع��λ�Ƹ�γ�����ϡ�Ψ�褷�ơ֥ԥ��åݡפ�Ĥ����⤯���Ȥ�
��ʬ�οȤ���ʤ��顢���̰�����PR���뤳�Ȥ������줿�ΤǤ���
�в������˻Ҥɤ⤬��ʬ�οȤ���ȤȤ�˸��̰�����Ҳ�˥��ԡ��뤷��
��������Ȥˤ���Ω�ĤȤ�����Ū���ͤ���줿�ܺ��Ǥ���


��긩��Ǥϥԥ��åݿ���⤬�Ϥޤ�����ʿ��30ǯ�ˤϸ��̻��λ�˴�Կ���59�͡�
���Τ�������ԼԤ�������ƻ�Ǹ��̻��Τ�˴���ʤä�����19�ͤ���ǯ�������á�
�����ơ���������2�ͤ������Ȥ��顢5ǯ���˾������θ��̻����ɻ��к��ΰ�ĤȤ��ơ�
���ع��λ�Ƹ��ȿ�ͺ����ѿ�ʰѰ��֥ԥ��åݿ����פȤ��ưѾ����뤳�Ȥˤ��ޤ�����
����Į�ˤϾ��ع��ο��ϣ��ġ�
1����2ǯ���ġ֥ԥ��åݿ����פ�Ѿ����Ƥ��ޤ���

��λ�����ع��Ǥ�ȿ�ͺ�����Ѥ�ͭ�����Ȥ������Ȥ�
�ϰ�θ��̰�����������Τ����£���Ƥ�餤��
�̳ػ���ȿ�ͺ�Τ����������Ѥ����в��������Ƹ������ȤΤ��ȡ�
��ʸ���Ȥ��ƺ��դ��Ƥ��Ƥ���Τ��Ѥ��������餺�˹��ǯ�Ǥ����Ѥ��Ƥ���
���줬���̰����˷Ҥ��äƤ���Ȼפ��ޤ��פȤ����Τ�
����Į�����̳�� �����ɺҲ� ��ƣ�ӡ���Ĺ�Τ��äǤ�����
�ޤ����֤������������ʳ�ư��1��1�ͤ��������ƷҤ��Ƥ��Ȥ�
���̰������¸��Ǥ���ȹͤ��Ƥ��ޤ��פȹ�ƣ����Ϥ��ä���äƤ��ޤ�����

�����ơ��⤦���Ĥ��Ҳ𤷤��Τϡ�
��ǯ�θ��̻��Τλ�˴�Կ���13�ͤ�47��ƻ�ܸ��ǺǤ⾯�ʤ��ä����츩�����ꡣ
���츩�Ǥ�2ǯ���˸��̰����Υޥ����åȥ���饯�����֥ޥ˥㡼�פ��������ޤ�����

���츩����̱�Ķ��� ���餷�ΰ����¿��ݡ����̻����ɻ� �����к��� ��Ĺ���������Ҥ���ˤ���
�ޥ˥㡼�Υե�͡���ϡ֥ޥ���С��������ġ����ޥ˥㡼�ס�
�����ܤ�ǭ�Ǥ������ץ��ե�����ˤϡȺ��츩��οͿȸ��̻���ȯ�����������Կ���
�������ȥ�٥��ò���������¿��ʸ��̴Ķ����˾�ษ̱��
�������פ�����������פȤ��������������ɤȤ���Τ������Ǥ���
�դ���ޥ˥㡼�Ϻ��츩�������֤Υ�������ο�Ф�������˱����
�ɥ饤�С��ΰ�����ž��äƤ���Ȥ��������
����Ǹ��̰�����Ϣ�Υ��٥�Ȥ�������ʤɤ��о줷��
���츩��θ��̻��Τξ����������ž���������ư��ԤäƤ��ޤ���

��������ιͤ��Ǥϵ�ǯ������Ǥθ��̻��λ�˴�ԺǾ�ã����
ʿ��30ǯ�˥������Ȥ������̻��Τ�ʤ���Saga Blue Project��
�ٻ���ط����ؤˤ���͡��ʼ���Ȥߤη�̤Ǥ��礦�Ȥ������ȤǤ�����
����ʻ�������ּ֤������ʾ��ʪ�Ǥ���ȿ�̡�
���̻�˴���Τ�����̿��å��ƻ��ˤ�ʤäƤ��ޤ����Ȥä���ͤ���
ƻϩ�����Ѥ���ͤ������Τ��Ȥߤ��������礤�ʤ�����̰������ؤ�Ƥ���������С�
������ؤΥ�å������������Ʋ������ޤ�����

����˴ؤ�äƤ����������ޤ���
������������Ƥ���֤ʤ�ۤɡ����̰����ס�
����ϴ�긩�Ⱥ��츩�ǹԤ��Ƥ������Ȥߤ��������ޤ�����

��ǯ4���긩 ����ĮΩ�����쾮�ع��λ�Ƹ�γ�����144̾��
���ȷٻ��𤫤�֥ԥ��åݿ����פ˰Ѿ�����ޤ�����
����ϴ�긩�٤Υޥ����åȡ֤Ԥ��ݡפ�ȿ�ͺब����ԥ��äȤ���¤�졣
�֤Ԥ��ݡפ��ϸ��������Ƹ�ú�ȡ����͡�����������
�ֱ��˥�ޥ������˥�ޥ����פΰ��ᤫ��Ĥ���줿
��������Ϣ�ۤ����롢��γ�����������ޤ������դˤ����ڥ�����饯������

���Ρ֤Ԥ��ݡפ˥���ޤΥ饤�Ȥ�������ȥԥ��äȸ���ȿ�ͺ�Ĥ����⤯���Ȥ���
����Į�Ǥϡ֥ԥ��åݡפȤ���ȿ�ͺब����ޤ�����
�����쾮�ع��λ�Ƹ�γ�����ϡ�Ψ�褷�ơ֥ԥ��åݡפ�Ĥ����⤯���Ȥ�
��ʬ�οȤ���ʤ��顢���̰�����PR���뤳�Ȥ������줿�ΤǤ���
�в������˻Ҥɤ⤬��ʬ�οȤ���ȤȤ�˸��̰�����Ҳ�˥��ԡ��뤷��
��������Ȥˤ���Ω�ĤȤ�����Ū���ͤ���줿�ܺ��Ǥ���


��긩��Ǥϥԥ��åݿ���⤬�Ϥޤ�����ʿ��30ǯ�ˤϸ��̻��λ�˴�Կ���59�͡�
���Τ�������ԼԤ�������ƻ�Ǹ��̻��Τ�˴���ʤä�����19�ͤ���ǯ�������á�
�����ơ���������2�ͤ������Ȥ��顢5ǯ���˾������θ��̻����ɻ��к��ΰ�ĤȤ��ơ�
���ع��λ�Ƹ��ȿ�ͺ����ѿ�ʰѰ��֥ԥ��åݿ����פȤ��ưѾ����뤳�Ȥˤ��ޤ�����
����Į�ˤϾ��ع��ο��ϣ��ġ�
1����2ǯ���ġ֥ԥ��åݿ����פ�Ѿ����Ƥ��ޤ���

��λ�����ع��Ǥ�ȿ�ͺ�����Ѥ�ͭ�����Ȥ������Ȥ�
�ϰ�θ��̰�����������Τ����£���Ƥ�餤��
�̳ػ���ȿ�ͺ�Τ����������Ѥ����в��������Ƹ������ȤΤ��ȡ�
��ʸ���Ȥ��ƺ��դ��Ƥ��Ƥ���Τ��Ѥ��������餺�˹��ǯ�Ǥ����Ѥ��Ƥ���
���줬���̰����˷Ҥ��äƤ���Ȼפ��ޤ��פȤ����Τ�
����Į�����̳�� �����ɺҲ� ��ƣ�ӡ���Ĺ�Τ��äǤ�����
�ޤ����֤������������ʳ�ư��1��1�ͤ��������ƷҤ��Ƥ��Ȥ�
���̰������¸��Ǥ���ȹͤ��Ƥ��ޤ��פȹ�ƣ����Ϥ��ä���äƤ��ޤ�����

�����ơ��⤦���Ĥ��Ҳ𤷤��Τϡ�
��ǯ�θ��̻��Τλ�˴�Կ���13�ͤ�47��ƻ�ܸ��ǺǤ⾯�ʤ��ä����츩�����ꡣ
���츩�Ǥ�2ǯ���˸��̰����Υޥ����åȥ���饯�����֥ޥ˥㡼�פ��������ޤ�����

���츩����̱�Ķ��� ���餷�ΰ����¿��ݡ����̻����ɻ� �����к��� ��Ĺ���������Ҥ���ˤ���
�ޥ˥㡼�Υե�͡���ϡ֥ޥ���С��������ġ����ޥ˥㡼�ס�
�����ܤ�ǭ�Ǥ������ץ��ե�����ˤϡȺ��츩��οͿȸ��̻���ȯ�����������Կ���
�������ȥ�٥��ò���������¿��ʸ��̴Ķ����˾�ษ̱��
�������פ�����������פȤ��������������ɤȤ���Τ������Ǥ���
�դ���ޥ˥㡼�Ϻ��츩�������֤Υ�������ο�Ф�������˱����
�ɥ饤�С��ΰ�����ž��äƤ���Ȥ��������
����Ǹ��̰�����Ϣ�Υ��٥�Ȥ�������ʤɤ��о줷��
���츩��θ��̻��Τξ����������ž���������ư��ԤäƤ��ޤ���

��������ιͤ��Ǥϵ�ǯ������Ǥθ��̻��λ�˴�ԺǾ�ã����
ʿ��30ǯ�˥������Ȥ������̻��Τ�ʤ���Saga Blue Project��
�ٻ���ط����ؤˤ���͡��ʼ���Ȥߤη�̤Ǥ��礦�Ȥ������ȤǤ�����
����ʻ�������ּ֤������ʾ��ʪ�Ǥ���ȿ�̡�
���̻�˴���Τ�����̿��å��ƻ��ˤ�ʤäƤ��ޤ����Ȥä���ͤ���
ƻϩ�����Ѥ���ͤ������Τ��Ȥߤ��������礤�ʤ�����̰������ؤ�Ƥ���������С�
������ؤΥ�å������������Ʋ������ޤ�����

��478�ʤ��饹�ޥ۱�ž�ˤ��������
2024/06/07
�ٻ�ģ�ˤ��ȡ�����5ǯ�Ρ֤ʤ��饹�ޥۡפ˵�������
��˴�ԡ��Ž��Ԥ��Ф����̻��Τϲ��������Ͽ���ޤ�����
����˥��ޡ��ȥե��礫���ʤ��ʤä�����
��ž�桢�Ĥ����ޥۤ����Ƥ��ޤ���
����ϥ⡼������饤������ƣ��ε������ˤ��ä�Ǥ�
���δ����ˤĤ���õ��ޤ�����

��ǯ�Υ��ޡ��ȥե������ڤǡ����ޥۤβ��̤��ꡢ
���ʤ��鱿ž���뤳�Ȥˤ����Τ������ޤ�����
���ޥۤʤɤ˵��������˴�Ž����Τ�
2013ǯ��ǯ��69�狼��2018ǯ��107������á�
�����ȼ�ä�2019ǯ12���ƻϩ����ˡ������
�֤ʤ��鱿ž�פ��Ф���ȳ§����������ޤ�����
���η�̡���2020ǯ�ˤ�66��˸���ޤ�����
��������Ƥ����ä�ž���ơ���ǯ2023ǯ�ϲ���¿��122��Ǥ�����

�֤ʤ��鱿ž�פˤ����̻��Τϡ��ɤ�ʥѥ�����¿���Τ���
������ˡ�� ���̻�������ʬ�ϥ�����Ĵ���ˤ���
ľ��ƻϩ��ľ�����Ի��ʤɤ����Ū�����Ȼפ����������Ǥλ��Τ�¿���Τ���ħ��
�����߷פǸ���ȡ����ͻ��Τ�����Ū��¿���ʤäƤ��ޤ���
���ޥۡ����Ӥ����Ѥ�������Ū�ξ���74.1%�����ͻ��Ρ�������Ū����40.5%���ͻ��Ρ�
���������ͻ��Τγ��ϡ����ޥ�����ѤǤ�36.0%��
�����˥��ޥۤ˵�����줿���Ȥ����ͻ��Τθ����ˤʤäƤ��뤫���狼��ޤ���
�����ơ����ޥ۵����λ���ȯ�����ι�ư����
������Ū�Ǥ���8�䤬ľ�ʻ���������Ū�Ǥ���6�䤬ľ�ʻ����ä��Ȥ����ǡ���������ޤ���
�����������ä�ľ�ʻ������ͻ��Τ�¿���Τ�
��ľ�ʤ���������ספȻפäƥ��ޥۤ��ˤ��Ƥ��ޤ�
���ε��δˤߤ����Τ�Ƥӹ���Ǥ���Ȥ������ȤǤ��礦��

���ޥۡ����ӤΤʤ��鱿ž�ˤ����Τϻ�˴Ψ���⤤�Τ���ħ��
2023ǯ�θ��̻������פˤ��ȡ����ޥۤ��������������Ѥ������λ�˴����Ψ��
���Ѥ��Ƥʤ�������٤���3.8�ܡ�������ǧ�����ƿȹ����ƾ��ͤ������
�����˵��Ť������ͤ�����Ǥϼ������������㤦����Ǥ��礦��
�����ơ�ľ�ʻ��Υ���ޤϷ빽��®�٤��ФƤ��ơ�
���������դ�û�����֤Ǥ��äƤ⤫�ʤ�ε�Υ�����Ԥ��ޤ���
��®40km/h�Υ���ޤ�1�ô֤���11m��2�ô֤Ǥ���22m��
��®60km�Ǥ�1�ô֤���17m��2�ô֤Ǥ�33m��
���ο�������Ɀž��˥��ޥۤ���������̤뤳�Ȥϴ������Ȥ狼��ޤ���

���ʤߤ˥���ꥫ�α�͢��ƻϩ���̰����ɤϡ���ž��Υɥ饤�С������ޡ��ȥե��������
��å�����������������Τˤ�������֤ϡ�ʿ��4.6�äȤ����ǡ�����ȯɽ���Ƥ��ޤ���
���äƤߤ�С������4.6�á��ܤ��ԤäƱ�ž���Ƥ���Τ�Ʊ����
�ܤ��Ԥä�4.6�ñ�ž���ƤߤƤȸ����Ƥ�����ɥ饤�С��Ϥ��ʤ��Ǥ��礦��
���ޥۡ��������äʤɤ��������Фˤ���٤��Ǥ���

����Ǥϱ�ž��Υ��ޥۤ�ɤ����Ƥ����٤�����
�Ÿ����ڤ�Τ����ۤǤ����������⤤���ʤ��ʤ��
�ֺܥۥ�����˥��ޥ����Τ���ꤷ�ƥɥ饤�֥⡼�ɤˤ��ޤ��礦��
�ɤ����Ƥ����ä�ɬ�פʻ��ϥ��ԡ�������Ȥäƥϥե�ǻ��Ѥ��Ƥ���������
���ޥۤ��ʥ�����˻Ȥ����ϡ���������������˹Ԥʤ����ȡ�
���̤����뤷�ʤ��褦�ˤ��Ʋ�������
��˴�ԡ��Ž��Ԥ��Ф����̻��Τϲ��������Ͽ���ޤ�����
����˥��ޡ��ȥե��礫���ʤ��ʤä�����
��ž�桢�Ĥ����ޥۤ����Ƥ��ޤ���
����ϥ⡼������饤������ƣ��ε������ˤ��ä�Ǥ�
���δ����ˤĤ���õ��ޤ�����

��ǯ�Υ��ޡ��ȥե������ڤǡ����ޥۤβ��̤��ꡢ
���ʤ��鱿ž���뤳�Ȥˤ����Τ������ޤ�����
���ޥۤʤɤ˵��������˴�Ž����Τ�
2013ǯ��ǯ��69�狼��2018ǯ��107������á�
�����ȼ�ä�2019ǯ12���ƻϩ����ˡ������
�֤ʤ��鱿ž�פ��Ф���ȳ§����������ޤ�����
���η�̡���2020ǯ�ˤ�66��˸���ޤ�����
��������Ƥ����ä�ž���ơ���ǯ2023ǯ�ϲ���¿��122��Ǥ�����

�֤ʤ��鱿ž�פˤ����̻��Τϡ��ɤ�ʥѥ�����¿���Τ���
������ˡ�� ���̻�������ʬ�ϥ�����Ĵ���ˤ���
ľ��ƻϩ��ľ�����Ի��ʤɤ����Ū�����Ȼפ����������Ǥλ��Τ�¿���Τ���ħ��
�����߷פǸ���ȡ����ͻ��Τ�����Ū��¿���ʤäƤ��ޤ���
���ޥۡ����Ӥ����Ѥ�������Ū�ξ���74.1%�����ͻ��Ρ�������Ū����40.5%���ͻ��Ρ�
���������ͻ��Τγ��ϡ����ޥ�����ѤǤ�36.0%��
�����˥��ޥۤ˵�����줿���Ȥ����ͻ��Τθ����ˤʤäƤ��뤫���狼��ޤ���
�����ơ����ޥ۵����λ���ȯ�����ι�ư����
������Ū�Ǥ���8�䤬ľ�ʻ���������Ū�Ǥ���6�䤬ľ�ʻ����ä��Ȥ����ǡ���������ޤ���
�����������ä�ľ�ʻ������ͻ��Τ�¿���Τ�
��ľ�ʤ���������ספȻפäƥ��ޥۤ��ˤ��Ƥ��ޤ�
���ε��δˤߤ����Τ�Ƥӹ���Ǥ���Ȥ������ȤǤ��礦��

���ޥۡ����ӤΤʤ��鱿ž�ˤ����Τϻ�˴Ψ���⤤�Τ���ħ��
2023ǯ�θ��̻������פˤ��ȡ����ޥۤ��������������Ѥ������λ�˴����Ψ��
���Ѥ��Ƥʤ�������٤���3.8�ܡ�������ǧ�����ƿȹ����ƾ��ͤ������
�����˵��Ť������ͤ�����Ǥϼ������������㤦����Ǥ��礦��
�����ơ�ľ�ʻ��Υ���ޤϷ빽��®�٤��ФƤ��ơ�
���������դ�û�����֤Ǥ��äƤ⤫�ʤ�ε�Υ�����Ԥ��ޤ���
��®40km/h�Υ���ޤ�1�ô֤���11m��2�ô֤Ǥ���22m��
��®60km�Ǥ�1�ô֤���17m��2�ô֤Ǥ�33m��
���ο�������Ɀž��˥��ޥۤ���������̤뤳�Ȥϴ������Ȥ狼��ޤ���

���ʤߤ˥���ꥫ�α�͢��ƻϩ���̰����ɤϡ���ž��Υɥ饤�С������ޡ��ȥե��������
��å�����������������Τˤ�������֤ϡ�ʿ��4.6�äȤ����ǡ�����ȯɽ���Ƥ��ޤ���
���äƤߤ�С������4.6�á��ܤ��ԤäƱ�ž���Ƥ���Τ�Ʊ����
�ܤ��Ԥä�4.6�ñ�ž���ƤߤƤȸ����Ƥ�����ɥ饤�С��Ϥ��ʤ��Ǥ��礦��
���ޥۡ��������äʤɤ��������Фˤ���٤��Ǥ���

����Ǥϱ�ž��Υ��ޥۤ�ɤ����Ƥ����٤�����
�Ÿ����ڤ�Τ����ۤǤ����������⤤���ʤ��ʤ��
�ֺܥۥ�����˥��ޥ����Τ���ꤷ�ƥɥ饤�֥⡼�ɤˤ��ޤ��礦��
�ɤ����Ƥ����ä�ɬ�פʻ��ϥ��ԡ�������Ȥäƥϥե�ǻ��Ѥ��Ƥ���������
���ޥۤ��ʥ�����˻Ȥ����ϡ���������������˹Ԥʤ����ȡ�
���̤����뤷�ʤ��褦�ˤ��Ʋ�������


