�����Υ����� JA����presents �ʤ�ۤ�!���̰���
Every Friday 7:20��7:27
���̥롼���ƻϩ���𡢸��̰����˴ؤ���ǿ��ȥԥå����ʤɤ��轵�狼��䤹���Ҳ𤷤ޤ���
��ǯ���������ٻ����������δ��Ԥ�����Į��
���̻�˴���Τ������Ȥʤ�ޤ�����
���̻��λ�˴�Ԥʤ��Ȥ����Τϡ�����Į�Ǥ�2002ǯ����³���Ƥ��ޤ�����
���Ԥ����פ��Ĥ�1960ǯ�ʹߤǽ��ơ�
�����С�¾�ˤ��ǯ����˴���Υ������ä���Į¼�Ϥ���ޤ�����
1�Ĥ���Ȥ���1��Ǥ��˴���Τ�̵�����Ƥ�������
�ɤ�ʼ���ȤߤƤ����Τ������Ƥ���Τ����������ʹ���ޤ�����

���Ԥο���2��ߤ�128,404�ͤǻ��������5���ܤ�¿����
����Į��1��25�����ߤ�5,796�͡�
����Į�Ͽ���6��ͤ������ʤ��ȤϤ���2002ǯ������̻��λ�˴�ԥ�����
������������Ȥ��Ȼפ��ޤ������������إ���ӥʡ��Ȥγ��Ȥ���
��������ϰ�ΰ�Ѥ����Ƥ����ϰ衣
���ٻ���θ��̴�����Ȫů�Ȥ���ˤ���
���Ԥȹ��縩���ݻԤ��ֹ�ƻ2�椬�̤äƤ���
�ä�īͼ���̶е����å�����ˤϤ��ʤ�θ����̤�����ޤ���
���ˤϸ����̤�¿���Τ���ƻ���ʤ��ʤɤζ�𤬤��ä������Ǥ���
����20ǯ�֤�ƻϩ�Ķ����������ʤ�
Į�Υ��ߥ�˥ƥ��Х��Ǹ������̤����ݤ��줿����
�ؿͲ�γ�ư������Ǯ���ǹ�������ˬ��Ƹ��̰�����Ƴ��ʤ�
��ƻ�ʥܥ��ƥ�����ư���¤�����ΤǤϤʤ����ȤΤ��ȤǤ�����

�����δ��Ԥϲ��˹�ʻ�����ä��Τǡ����ߤδ��Ԥ��ϰϤǸ����
����44ǯ�ˤ�50�Ͷ���������̻��Τˤ�ä�̿����Ȥ��ޤ�����
���θ塢ʿ�������äƤ�2������λ�Կ���³���Ƥ��ޤ�����
ʿ��29ǯ��10�ͤ�Ǹ��1��˿�ܤ��Ƥ��뤽���Ǥ���
���ԤǸ��ߤΤȤ����Ǹ�θ��̻�˴���Τ�����3ǯ9��21����
�¤�1ǯ��ͥ��Ķ����1ǯ5�������³���Ƥ��ޤ�

���ٻ���Ǥϸ��̻����к��Τ���
����ޤ��͡��ʸ��̰����Υ����ڡ����ع��Ǥθ��̶�����
����Ԥ����оݤθ��̰������ä˽��褫���Ϥ�����Ƥ��������Ǥ���
���������桢��ǯ7��黳�����٤ϲ�����ƻ����Լ�ͥ���Ű�줵���뤿��
�ֲ�����ƻ�ϥ�ɥ�����ư�פȤ�����ư�����ȡ�
����ϡ���ԼԤ��Ϥ�ޤ����ɥ饤�С��Ϥ���ˤɤ����פȸ��ä���ޤ����Τˤ���
���⤤�ΰջ����̤�ޤ�Ȥ�����Τǡ�������äƤ������Ȥ�
������ƻ����Լ�ͥ��Ȥ����ռ��Ϥ��ʤ�Ű�줵��Ƥ��Ƥ����
��Ȫ����Ϥ��ä���äƤ��ޤ�����
�ޤ������ٻ���Ϲ���Ԥα�ž�ȵ�����Ǽ�Կ������÷����ˤ���
���Ԥ��ԤäƤ�����ǯ�ֺ���2��4000��ʬ�Υ����������ѷ�����դ���
������������ν������٤��¤�����ΤǤϤʤ�������Ȫ����
�����������٤�¾�ξ��礤�Х��ʤɤ��Ȥ߹�碌�뤳�Ȥ�
����Ԥϻ���������餹�����������������礭�����夷
��ž�ȵ�����Ǽ���䤹�����Ķ������ۤ���Ƥ���Ȼפ�����Ȫ����
�ޤ�������Ǥϸ��̰����ܥ��ƥ����γ�ư�����˳�ȯ��
���̰�����ռ����Ƥ�餦�Ȥ������Ȥ˷Ҥ��äƤ���Ȼפ���
��Ȫ����Ϥ��ä���äƤ��ޤ�����

��������ȸ���줿���夫�顢���ܤǤϹ���(��)���ơ�
���̰����η��س�ư��ܺ����Ԥ��Ƥ��ޤ�����
���ٻ������Ǥ���̰�����Ĺǯ����Ȥ�Ǥ��ơ�
�����ؤ��Ƽ¤�����Ȥ������ȤǤ��礦��
ǯ��������1��23���ˤϸ��̻�˴���Υ����ε�ǰ��ŵ���Ԥ��
�ط��Ԥ���������¿��������夬�ä������Ǥ���
��Ȫ����ϸ��̻��ΤϤ��ġ��ɤ��ǵ����뤫�狼��ʤ��ȶ�ʴ�����
����ޤ�ž�������ƻϩ���⤯����
���Τ��Ȥ�Ƭ���Ҷ��ˤ����ƹ�ư���Ʋ������Ȥ��ä���äƤ��ޤ�����
���θ��դ�Ф��Ƥ����Ʋ�������
���̻�˴���Τ������Ȥʤ�ޤ�����
���̻��λ�˴�Ԥʤ��Ȥ����Τϡ�����Į�Ǥ�2002ǯ����³���Ƥ��ޤ�����
���Ԥ����פ��Ĥ�1960ǯ�ʹߤǽ��ơ�
�����С�¾�ˤ��ǯ����˴���Υ������ä���Į¼�Ϥ���ޤ�����
1�Ĥ���Ȥ���1��Ǥ��˴���Τ�̵�����Ƥ�������
�ɤ�ʼ���ȤߤƤ����Τ������Ƥ���Τ����������ʹ���ޤ�����

���Ԥο���2��ߤ�128,404�ͤǻ��������5���ܤ�¿����
����Į��1��25�����ߤ�5,796�͡�
����Į�Ͽ���6��ͤ������ʤ��ȤϤ���2002ǯ������̻��λ�˴�ԥ�����
������������Ȥ��Ȼפ��ޤ������������إ���ӥʡ��Ȥγ��Ȥ���
��������ϰ�ΰ�Ѥ����Ƥ����ϰ衣
���ٻ���θ��̴�����Ȫů�Ȥ���ˤ���
���Ԥȹ��縩���ݻԤ��ֹ�ƻ2�椬�̤äƤ���
�ä�īͼ���̶е����å�����ˤϤ��ʤ�θ����̤�����ޤ���
���ˤϸ����̤�¿���Τ���ƻ���ʤ��ʤɤζ�𤬤��ä������Ǥ���
����20ǯ�֤�ƻϩ�Ķ����������ʤ�
Į�Υ��ߥ�˥ƥ��Х��Ǹ������̤����ݤ��줿����
�ؿͲ�γ�ư������Ǯ���ǹ�������ˬ��Ƹ��̰�����Ƴ��ʤ�
��ƻ�ʥܥ��ƥ�����ư���¤�����ΤǤϤʤ����ȤΤ��ȤǤ�����

�����δ��Ԥϲ��˹�ʻ�����ä��Τǡ����ߤδ��Ԥ��ϰϤǸ����
����44ǯ�ˤ�50�Ͷ���������̻��Τˤ�ä�̿����Ȥ��ޤ�����
���θ塢ʿ�������äƤ�2������λ�Կ���³���Ƥ��ޤ�����
ʿ��29ǯ��10�ͤ�Ǹ��1��˿�ܤ��Ƥ��뤽���Ǥ���
���ԤǸ��ߤΤȤ����Ǹ�θ��̻�˴���Τ�����3ǯ9��21����
�¤�1ǯ��ͥ��Ķ����1ǯ5�������³���Ƥ��ޤ�

���ٻ���Ǥϸ��̻����к��Τ���
����ޤ��͡��ʸ��̰����Υ����ڡ����ع��Ǥθ��̶�����
����Ԥ����оݤθ��̰������ä˽��褫���Ϥ�����Ƥ��������Ǥ���
���������桢��ǯ7��黳�����٤ϲ�����ƻ����Լ�ͥ���Ű�줵���뤿��
�ֲ�����ƻ�ϥ�ɥ�����ư�פȤ�����ư�����ȡ�
����ϡ���ԼԤ��Ϥ�ޤ����ɥ饤�С��Ϥ���ˤɤ����פȸ��ä���ޤ����Τˤ���
���⤤�ΰջ����̤�ޤ�Ȥ�����Τǡ�������äƤ������Ȥ�
������ƻ����Լ�ͥ��Ȥ����ռ��Ϥ��ʤ�Ű�줵��Ƥ��Ƥ����
��Ȫ����Ϥ��ä���äƤ��ޤ�����
�ޤ������ٻ���Ϲ���Ԥα�ž�ȵ�����Ǽ�Կ������÷����ˤ���
���Ԥ��ԤäƤ�����ǯ�ֺ���2��4000��ʬ�Υ����������ѷ�����դ���
������������ν������٤��¤�����ΤǤϤʤ�������Ȫ����
�����������٤�¾�ξ��礤�Х��ʤɤ��Ȥ߹�碌�뤳�Ȥ�
����Ԥϻ���������餹�����������������礭�����夷
��ž�ȵ�����Ǽ���䤹�����Ķ������ۤ���Ƥ���Ȼפ�����Ȫ����
�ޤ�������Ǥϸ��̰����ܥ��ƥ����γ�ư�����˳�ȯ��
���̰�����ռ����Ƥ�餦�Ȥ������Ȥ˷Ҥ��äƤ���Ȼפ���
��Ȫ����Ϥ��ä���äƤ��ޤ�����

��������ȸ���줿���夫�顢���ܤǤϹ���(��)���ơ�
���̰����η��س�ư��ܺ����Ԥ��Ƥ��ޤ�����
���ٻ������Ǥ���̰�����Ĺǯ����Ȥ�Ǥ��ơ�
�����ؤ��Ƽ¤�����Ȥ������ȤǤ��礦��
ǯ��������1��23���ˤϸ��̻�˴���Υ����ε�ǰ��ŵ���Ԥ��
�ط��Ԥ���������¿��������夬�ä������Ǥ���
��Ȫ����ϸ��̻��ΤϤ��ġ��ɤ��ǵ����뤫�狼��ʤ��ȶ�ʴ�����
����ޤ�ž�������ƻϩ���⤯����
���Τ��Ȥ�Ƭ���Ҷ��ˤ����ƹ�ư���Ʋ������Ȥ��ä���äƤ��ޤ�����
���θ��դ�Ф��Ƥ����Ʋ�������
��411��ž�֤θ����ǤΥ롼��
2023/02/17
���ѼԤ������뼫ž�֡�
�����ǡ����δ�����ž���Ҳ�����ˤʤäƤ��ޤ���
��ž�֤˾�����ϸ��̵�§���äƤ���Ǥ��礦����
������äˡָ����פ��̹Ԥ�����Υ롼����������ޤ�����

����ָ����פ˸��ꤹ��Τϡ�
��ž�ֻ��Τϸ�����¿�����顣
����Ԥμ�ž�֤���Ϳ�������̻��Τ�ƻϩ�����̤˸����
����4ǯ�ϡ�������47.9 %�������ն5.9 % ��Ⱦ���ʾ塣
��ž�֤˾������ä˸����Ȥ����ն�˵���Ĥ��ʤ���Ф����ޤ���

��ž�֤ΰ�������¥�ʰѰ���ë�ij����ˤ���ˤ���
��ǯ������Ԥ���ˤȤ�С������ˤ����Ƽ�ž�ֻ��ΤǺǤ�¿���Τ�
���������ä������������Ȥ������˺�����ƻϩ�����褿
��ư�֡���ž�֤Ƚв�Ƭ�˾��ͤ�����Τ�34%��
����¿���Τ�����ž�֤����˶ʤ���������˶ʤ������
���������褿��ư�֡���ž�֤Ȥξ����ܿ����Τ�29%�Ǥ�����

�����ˤ�浡�����֥ѥ������������� ��ޤ�����
���Τθ����Ȥʤ�롼���ȿ�Ƥ��ޤ�������ƻϩ������3�ġ�
�� ��ƻ����ԼԲ����ӤϤʤ�����ξ�Ѥο��浡�������������
��ž�֤ϥ����Ʊ�͡����ο���˽������Ȥˤʤ�ޤ���
���ʤߤ���ԼԤ�Ʊ���Ǥ���
�� ��ξ�ѿ��浡����Լ��ѿ��浡���������
��ž�֤ϼ�ƻ�����뤳�Ȥ�゙��§�ʤΤǼ�ξ�ѿ��浡�˽����ޤ���
����゙�����㳰Ū����ƻ���̹Ԥ��Ƥ������ϡ�
��ԼԤ�����м�ž�֤���ߤꡢ��Լ��ѿ��浡�˽��äƼ�ž�֤����Ϥ�ޤ���
��ž�֤˾�ä��Ϥ���ϡ���ξ�ѿ��浡�˽����ޤ���
�� ���浡���ʤ�����
ɬ�����������ǰ����ߡ�
�����ơ��������ǧ������ǡ����ǡ����ޡ����ޤ��ޤ���
����¾���ּ�ž�����ѿ��浡�פ����Լԡ���ž�����ѿ��浡�פ��������
����������ο��浡�˽����ޤ���

�롼����ޤ�����ǡ������Ǥ����������������ԤǤ���
�ޤ��Ϻ��ޡ�
���ޤξ��Ǥ��礭�����Τˤʤ꤫�ͤʤ��Τϡ�
Ʊ�������ޤ��褦�Ȥ��뼫ư�֤˴������ޤ�Ƥ��ޤ����ȡ�
���λ��Τ��ɤ�����ˤϿ��椬�ĤˤʤäƤ⤤���ʤ�ʤ��餺
����ޤ���˺��ޤ���Τ��ǧ���ʤ���夫���ä��꺸�ޤ��뤳�ȡ�
�ޤ�����ư�֤κ���ϩ��������Ǥ⼫ž�֤�ɬ�������Ф�¦���̤뤳�ȡ�
³���Ʊ��ޤξ�硢��ž�֤���ư�֤䥪���ȥХ��Τ褦��
����������̤äƱ��˶ʤ��äƤϸ��̰�ȿ�ǻ��Τθ����Τ�ȡ�
�����ˤ������̤ο��浡���Ĥˤʤä��顢�ޤ���ľ�ʤ���ȿ��¦���Ϥꡢ
��ž�֤��������Ѥ��Ʊ��ޤ��������ο��浡���Ĥˤʤä���
�ƤӲ��Ǥ��ƿʹԤ�����ƻ������Ȥ�������Ǥ���
���浡���ʤ������α��ޤ�Ʊ�ͤǤ���

�ֿ���Τʤ������Ǥϼ�ʬ�����̥롼����äƤ��Ƥ�
���̥롼��˰�ȿ���Ƥ��뼫ư�֡���ž�֤��������뤳�Ȥ�
���Τ˴������ޤ�Ƥ��ޤ���ǽ��������ޤ���
ɬ���������֤ơ�������ǧ�Ƥ��鲣�ǡ����ޡ����ޤƲ������פ�
��ž�֤ΰ�������¥�ʰѰ����ë�ij�����϶������ä���äƤ��ޤ�����
�ޤ����ְ����ߤ��ʤ��סֿ���̵�뤷�Ƥ��ޤ��פȤ�����ž�����Ѥˤ�
�ּ�ư�֤���ʤ���������פ������פȤ����פ����ߤ�ֵޤ��Ǥ뤫��פȤ��������Թ礬����
�ֲ�����ƻ��ž�֤˾�ä��Ϥ�פΤϸ��̥롼����μ��Τʤ����餭�Ƥ��ޤ������ij�����
�����ɤ���ʬ�����Ѥλ����Ĥ�ľ���ƤߤƲ�������
��ž�֤ϡ������ޤǼ�ξ�Ǥ���
�롼����äư����˾�ꡢ�ڤ�����Ŭ�ʼ�ž�֥饤�դ�ڤ���Dz�������

�����ǡ����δ�����ž���Ҳ�����ˤʤäƤ��ޤ���
��ž�֤˾�����ϸ��̵�§���äƤ���Ǥ��礦����
������äˡָ����פ��̹Ԥ�����Υ롼����������ޤ�����

����ָ����פ˸��ꤹ��Τϡ�
��ž�ֻ��Τϸ�����¿�����顣
����Ԥμ�ž�֤���Ϳ�������̻��Τ�ƻϩ�����̤˸����
����4ǯ�ϡ�������47.9 %�������ն5.9 % ��Ⱦ���ʾ塣
��ž�֤˾������ä˸����Ȥ����ն�˵���Ĥ��ʤ���Ф����ޤ���

��ž�֤ΰ�������¥�ʰѰ���ë�ij����ˤ���ˤ���
��ǯ������Ԥ���ˤȤ�С������ˤ����Ƽ�ž�ֻ��ΤǺǤ�¿���Τ�
���������ä������������Ȥ������˺�����ƻϩ�����褿
��ư�֡���ž�֤Ƚв�Ƭ�˾��ͤ�����Τ�34%��
����¿���Τ�����ž�֤����˶ʤ���������˶ʤ������
���������褿��ư�֡���ž�֤Ȥξ����ܿ����Τ�29%�Ǥ�����

�����ˤ�浡�����֥ѥ������������� ��ޤ�����
���Τθ����Ȥʤ�롼���ȿ�Ƥ��ޤ�������ƻϩ������3�ġ�
�� ��ƻ����ԼԲ����ӤϤʤ�����ξ�Ѥο��浡�������������
��ž�֤ϥ����Ʊ�͡����ο���˽������Ȥˤʤ�ޤ���
���ʤߤ���ԼԤ�Ʊ���Ǥ���
�� ��ξ�ѿ��浡����Լ��ѿ��浡���������
��ž�֤ϼ�ƻ�����뤳�Ȥ�゙��§�ʤΤǼ�ξ�ѿ��浡�˽����ޤ���
����゙�����㳰Ū����ƻ���̹Ԥ��Ƥ������ϡ�
��ԼԤ�����м�ž�֤���ߤꡢ��Լ��ѿ��浡�˽��äƼ�ž�֤����Ϥ�ޤ���
��ž�֤˾�ä��Ϥ���ϡ���ξ�ѿ��浡�˽����ޤ���
�� ���浡���ʤ�����
ɬ�����������ǰ����ߡ�
�����ơ��������ǧ������ǡ����ǡ����ޡ����ޤ��ޤ���
����¾���ּ�ž�����ѿ��浡�פ����Լԡ���ž�����ѿ��浡�פ��������
����������ο��浡�˽����ޤ���

�롼����ޤ�����ǡ������Ǥ����������������ԤǤ���
�ޤ��Ϻ��ޡ�
���ޤξ��Ǥ��礭�����Τˤʤ꤫�ͤʤ��Τϡ�
Ʊ�������ޤ��褦�Ȥ��뼫ư�֤˴������ޤ�Ƥ��ޤ����ȡ�
���λ��Τ��ɤ�����ˤϿ��椬�ĤˤʤäƤ⤤���ʤ�ʤ��餺
����ޤ���˺��ޤ���Τ��ǧ���ʤ���夫���ä��꺸�ޤ��뤳�ȡ�
�ޤ�����ư�֤κ���ϩ��������Ǥ⼫ž�֤�ɬ�������Ф�¦���̤뤳�ȡ�
³���Ʊ��ޤξ�硢��ž�֤���ư�֤䥪���ȥХ��Τ褦��
����������̤äƱ��˶ʤ��äƤϸ��̰�ȿ�ǻ��Τθ����Τ�ȡ�
�����ˤ������̤ο��浡���Ĥˤʤä��顢�ޤ���ľ�ʤ���ȿ��¦���Ϥꡢ
��ž�֤��������Ѥ��Ʊ��ޤ��������ο��浡���Ĥˤʤä���
�ƤӲ��Ǥ��ƿʹԤ�����ƻ������Ȥ�������Ǥ���
���浡���ʤ������α��ޤ�Ʊ�ͤǤ���

�ֿ���Τʤ������Ǥϼ�ʬ�����̥롼����äƤ��Ƥ�
���̥롼��˰�ȿ���Ƥ��뼫ư�֡���ž�֤��������뤳�Ȥ�
���Τ˴������ޤ�Ƥ��ޤ���ǽ��������ޤ���
ɬ���������֤ơ�������ǧ�Ƥ��鲣�ǡ����ޡ����ޤƲ������פ�
��ž�֤ΰ�������¥�ʰѰ����ë�ij�����϶������ä���äƤ��ޤ�����
�ޤ����ְ����ߤ��ʤ��סֿ���̵�뤷�Ƥ��ޤ��פȤ�����ž�����Ѥˤ�
�ּ�ư�֤���ʤ���������פ������פȤ����פ����ߤ�ֵޤ��Ǥ뤫��פȤ��������Թ礬����
�ֲ�����ƻ��ž�֤˾�ä��Ϥ�פΤϸ��̥롼����μ��Τʤ����餭�Ƥ��ޤ������ij�����
�����ɤ���ʬ�����Ѥλ����Ĥ�ľ���ƤߤƲ�������
��ž�֤ϡ������ޤǼ�ξ�Ǥ���
�롼����äư����˾�ꡢ�ڤ�����Ŭ�ʼ�ž�֥饤�դ�ڤ���Dz�������

��410���ꥸ��������ݤȤ�
2023/02/10
�㤨�С��̳�ƻ��ʿ���Τ褦�ʷ�ʪ���礭���ڤʤɤξ㳲ʪ���ʤ�
360�� �볦�������������ǥ����Ʊ�Τξ��ͻ��Τ������뤳�Ȥ�����ޤ���
���Υ����פλ��Τϡ֥��ꥸ��������ݡפȸƤФ�ޤ���

�֥��ꥸ���פȤϾ��ͤ��̣�����ñ�졣
�ʹ֤λ볦�ˤ�������30�٤Ρ��濴����פ�
���κ�����¦�Ρּ��ջ���פ�����ޤ���
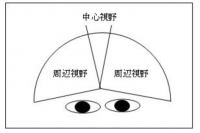
���濴����פ�ʪ��٤������뤳�Ȥ�Ŭ���Ƥ���
�ּ��ջ���פϲ�����ư���Τ�Ȥ館��Τ�Ŭ���Ƥ���Τ�
�ʹ֤ϡּ��ջ���פǰ۾��ư�����Τ����濴����פǾܺ٤���ϡ���ǧ���ޤ���
�Ǥ⡢���ջ���ϡ�ư���ʤ���Τ�ǧ�����ˤ����Ȥ�����������
ľ�Ѥ˸��븫�̤����ɤ�ƻϩ��Ʊ���褦��®�٤Ǹ����˸����ä�����
�⤦1��Υ���ޤ����äƤ⡢����¸�ߤ˵��Ť��ޤ���
����ϥ���ޤ����Ǥʤ������ȥХ��Ǥ�
�ޤ������Ե������Ǥⵯ���뤳�ȤǤ���

��ʡ�縩�����Ԥθ����Ǿ��Ѽ֤ȷڼ�ư�֤����ͤ��Ʒڼ�ư�֤���塣
4�ͤ�˴���ʤ�Ȥ����ˤޤ������Τ������ޤ�����
���λ��Τ����������������˸����餷���ɤ�
����ˤϥ֥졼���κ���̵���ä����Ȥ���
���ꥸ��������ݤ������ǤϤʤ����ȹͤ����Ƥ��ޤ���
����Ĥ������Τϥ��ꥸ��������ݤˤ�뼫ư�ֻ��Τ��维���˷Ҥ���䤹�����ȡ�
���̹��ؤ�������̳�ƻ��� ���ظ���ʡ��븶�������ˤ���
���ߤ��μ�ư�֤˵��Ť��������ԡ��ɤ���Ȥ������ͤ��뤫�顣
�ޤ���ľ�Ѥˤ֤Ĥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
�ּ�ˤ�äƤϲ�����ξ��ͤ˼夤��Τ⤢��
���⤬�٤�ƾ�äƤ���ͤ��Ф����礭�ʾ⤬���ޤ���
����ˤ�ä��ﳲ���礭���ʤäƻ�˴���Τ˻�뤳�Ȥ⤢��ޤ���
�����餷����ļ�Į�ʤΤǥ��ԡ��ɤ�Ф������Ԥ��Ƥ��뤳�Ȥ�
�礭�ʻ��ΤˤʤäƤ��ޤ��װ���1�ĤˤʤäƤ���褦�Ǥ���

�к���1�Ĥ�ľ�Ѥ˸���ƻϩ��¿�����Ϥ�������ˤϵ���Ĥ��뤳�ȡ�
�ʤ��äƤ���ƻϩ�Ǥϥ��ꥸ��������ݤϵ����ޤ���
�ı����ʤ���ˤ���ޤä�����ƻ���������
�������ռ�Ū�˼��ߤäƺ�����褦�ˤ��ޤ��礦��
�����ơ�����Ρ�ͥ��ƻϩ�פ��̤��뤳�ȤǤ���������ƻϩ�Ϥɤ��餫��ͥ�衣
���Τ��Ȥ�ռ����Ĥġ��ɤ��餬ͥ�褫ʬ����ˤ������ϡ�
�����ߤ���Ĥ��DZ�ž����褦�ˤ��Ʋ�������
���٤˥��ꥸ��������ݤ�������䤹�����ʳ��������Ϥ�����
���괷��Ƥ���ͤ��������鵤��Ĥ��Ƥ���Ǥ��礦��
�Գڡ�ι�Ԥʤɤ��Τ�ʤ����ϡ��Դ���ʾ���ž������ˤϡ�
�����ʥӤ�ƻϩ�Ķ����ǧ���뤳�Ȥ⿴�����ƥ��ꥸ��������ݤ��ɤ��ޤ��礦��

360�� �볦�������������ǥ����Ʊ�Τξ��ͻ��Τ������뤳�Ȥ�����ޤ���
���Υ����פλ��Τϡ֥��ꥸ��������ݡפȸƤФ�ޤ���

�֥��ꥸ���פȤϾ��ͤ��̣�����ñ�졣
�ʹ֤λ볦�ˤ�������30�٤Ρ��濴����פ�
���κ�����¦�Ρּ��ջ���פ�����ޤ���
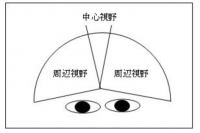
���濴����פ�ʪ��٤������뤳�Ȥ�Ŭ���Ƥ���
�ּ��ջ���פϲ�����ư���Τ�Ȥ館��Τ�Ŭ���Ƥ���Τ�
�ʹ֤ϡּ��ջ���פǰ۾��ư�����Τ����濴����פǾܺ٤���ϡ���ǧ���ޤ���
�Ǥ⡢���ջ���ϡ�ư���ʤ���Τ�ǧ�����ˤ����Ȥ�����������
ľ�Ѥ˸��븫�̤����ɤ�ƻϩ��Ʊ���褦��®�٤Ǹ����˸����ä�����
�⤦1��Υ���ޤ����äƤ⡢����¸�ߤ˵��Ť��ޤ���
����ϥ���ޤ����Ǥʤ������ȥХ��Ǥ�
�ޤ������Ե������Ǥⵯ���뤳�ȤǤ���

��ʡ�縩�����Ԥθ����Ǿ��Ѽ֤ȷڼ�ư�֤����ͤ��Ʒڼ�ư�֤���塣
4�ͤ�˴���ʤ�Ȥ����ˤޤ������Τ������ޤ�����
���λ��Τ����������������˸����餷���ɤ�
����ˤϥ֥졼���κ���̵���ä����Ȥ���
���ꥸ��������ݤ������ǤϤʤ����ȹͤ����Ƥ��ޤ���
����Ĥ������Τϥ��ꥸ��������ݤˤ�뼫ư�ֻ��Τ��维���˷Ҥ���䤹�����ȡ�
���̹��ؤ�������̳�ƻ��� ���ظ���ʡ��븶�������ˤ���
���ߤ��μ�ư�֤˵��Ť��������ԡ��ɤ���Ȥ������ͤ��뤫�顣
�ޤ���ľ�Ѥˤ֤Ĥ��뤳�Ȥˤʤ�ޤ���
�ּ�ˤ�äƤϲ�����ξ��ͤ˼夤��Τ⤢��
���⤬�٤�ƾ�äƤ���ͤ��Ф����礭�ʾ⤬���ޤ���
����ˤ�ä��ﳲ���礭���ʤäƻ�˴���Τ˻�뤳�Ȥ⤢��ޤ���
�����餷����ļ�Į�ʤΤǥ��ԡ��ɤ�Ф������Ԥ��Ƥ��뤳�Ȥ�
�礭�ʻ��ΤˤʤäƤ��ޤ��װ���1�ĤˤʤäƤ���褦�Ǥ���

�к���1�Ĥ�ľ�Ѥ˸���ƻϩ��¿�����Ϥ�������ˤϵ���Ĥ��뤳�ȡ�
�ʤ��äƤ���ƻϩ�Ǥϥ��ꥸ��������ݤϵ����ޤ���
�ı����ʤ���ˤ���ޤä�����ƻ���������
�������ռ�Ū�˼��ߤäƺ�����褦�ˤ��ޤ��礦��
�����ơ�����Ρ�ͥ��ƻϩ�פ��̤��뤳�ȤǤ���������ƻϩ�Ϥɤ��餫��ͥ�衣
���Τ��Ȥ�ռ����Ĥġ��ɤ��餬ͥ�褫ʬ����ˤ������ϡ�
�����ߤ���Ĥ��DZ�ž����褦�ˤ��Ʋ�������
���٤˥��ꥸ��������ݤ�������䤹�����ʳ��������Ϥ�����
���괷��Ƥ���ͤ��������鵤��Ĥ��Ƥ���Ǥ��礦��
�Գڡ�ι�Ԥʤɤ��Τ�ʤ����ϡ��Դ���ʾ���ž������ˤϡ�
�����ʥӤ�ƻϩ�Ķ����ǧ���뤳�Ȥ⿴�����ƥ��ꥸ��������ݤ��ɤ��ޤ��礦��

��409������゙�μ֤��̹�ͥ���̤�ͥ��ƻϩ
2023/02/03
���̻��Τ�Ⱦ���ʾ夬��������ȯ�����Ƥ��ޤ���
�����Ϥ��줾����Ū�Ϥ˸����ä����륯��ޤ��Ԥ���ꡣ
�����ơ�Ʊ������Լԡ���ž�֤˾��ͤ⤤�ޤ���
�ɥ饤�С����餬������Ƥӹ��ޤʤ��褦
�����ǤΥ���ޤ�ͥ��롼�������ޤ��Ƥ����ޤ��礦��

2017ǯ�θ��̻��Τ˴ؤ���ٻ�ģ��ȯɽ���Ȥ�
������ˡ�� ���̻�������ʬ�ϥ������ޤȤ�ǡ����ˤ���
�ͿȻ��Τ�54%�������ǵ����Ƥ��ޤ���
��������
���浡�����������16%
���浡���ʤ�������24.3%
�����նᡡ��������13.8��
�����ˤϥɥ饤�С��Ρּ�ʬ��ͥ��פȤ����פ��㤤��
̵���ʱ�ž�����ꤽ���Ǥ��͡�
�����ǤΥ���ޤ�ͥ���̡�
����ϥ���ޤ�ž��������ʬ���äƤ���Ȼפ��ޤ�����ľ�ʡ����ޡ����ޤν硣
�����ơ����椬��������Ǵ��������߽Ф��䤹���Τϡ�
�����Ĥ��䤹���Ȼפ��ޤ��������֤�ľ�ʼ֤δط��Ǥ��礦��

�⡼����饤������ƣ��ε������ˤ���
�����Τ� 71.8%�����浡�Τ��������ȯ�����Ƥ��ޤ���
����¿���������и�ľ�ʼ֤�ȯ�����٤졣
�ʹ֤��濴�������40�١�
�и�ľ�ʼ����ȱ�����ޤǻ��������褦�Ȥ����
����Ȥ��Ƥ� 90 �٤���120 �٤��餤���Ϥ�ɬ�פ�����ޤ���
�����顢�������ƻϩ��������ԼԤ����뤷�Ƥ����
�и�ľ�ʼ֤�ȯ�����٤�뤳�Ȥ�����ޤ���
�⤦1�ġ����֤Υɥ饤�С�����ľ�ʼ֤������̲�Ǥ���פ�
Ƚ�Ǥ��Ƥ��ޤä��Ȥ�������������Ω�äƤ���Ȥ����ޤ���
�ޤ����Ƕ�Ǥ�����α����椬�ФƤ��鱦�ޤ��Ƥ���֤��Ф���
�ֿ��椬�Ѥ�ä�¦��ľ�ʼ֤�̵���˸����˿�����
���֤Ȥ֤Ĥ��륱�����������Ƥ���Ȥ������⤢�뤽���Ǥ���
�����ϵ���Ĥ��ʤ���Ф����ʤ�����¿���Ǥ�����
�ޤ��������Ƥ���̵����������˶ʤ���ޤ��礦��
�ޤ���ľ�ʼ֤�Ω��λ��ϡ����ޤ��褦�Ȥ��Ƥ��륯��ޤ����դ��ޤ��礦��

����ޤ�ͥ���̤ǡְִ㤤�פ�ֻפ��㤤�פ������䤹�Τ�����Τʤ�������
�ɤΤ褦��ͥ��֤Ϸ�ޤ�Τ���
�ޤ���ͥ��ƻϩ���狼����Ĥ�ɸ�������֤���Ƥ���ƻϩ�ǤϤ���˽����ޤ���
ɸ�����ʤ�ƻϩ�Ǥϥ����饤��������ͥ��ƻϩ��
�����饤�ʤ����ƻϩ��������������ͥ��ƻϩ��
ɸ���䥻���饤�ʤ���ƻϩ��������Ƚ��ˤ�������
��ξ�ˤϺ���ͥ��Υ롼�뤬���ꡢ��ʬ�κ�����ФƤ�������ޤ�ͥ��Ȥʤ�ޤ���
�Ф��Ƥ����Ʋ�������

���椬�ʤ������Ǥ����Ԥˤϵ���Ĥ��Ʋ�������
ƣ��ε������˰�����ž�Υݥ���Ȥ�ʹ�����ޤ�����
�����֤�������ϡ����μ֤������Ǹ�®�����ꡢ
�����ߤ����ǽ��������ȹͤ��ƤĤ��Ƥ����Ȥ������Ȥ����ڡ�
�����θ��̤������������Ǥϥ����֥ߥ顼��褯����Ȥ����Τ����ܡ�
�����֥ߥ顼���ʤ���С����ä�����ԡ������ߤ��ƺ����ΰ������ǧ���롣
���ޤ��Ϻ�����֤���Ť��Ƥ������ϼ�ʬ������ͥ��ƻϩ���Ȥ��Ƥ�
��Ť��Ƥ���֤���®���Ƥ��뤫�ɤ����ä�������å���
��®���뵤�ۤ��ʤ���С���ʬ���ߤޤäƤ��ᤴ��������������
�ޤ����ö�Ū�Ǥ������ɥ饤�֥쥳�����������֤��뤳�Ȥ�
��꿵�Ť˱�ž���褦�Ȥ����ռ��Ť��ˤʤ�Ȳ��⤷�Ʋ������ޤ�����
����ޤ�ͥ���̤Υ롼��ä����ǧ������
�����α�ž��褦�ˤ��ޤ��礦��

�����Ϥ��줾����Ū�Ϥ˸����ä����륯��ޤ��Ԥ���ꡣ
�����ơ�Ʊ������Լԡ���ž�֤˾��ͤ⤤�ޤ���
�ɥ饤�С����餬������Ƥӹ��ޤʤ��褦
�����ǤΥ���ޤ�ͥ��롼�������ޤ��Ƥ����ޤ��礦��

2017ǯ�θ��̻��Τ˴ؤ���ٻ�ģ��ȯɽ���Ȥ�
������ˡ�� ���̻�������ʬ�ϥ������ޤȤ�ǡ����ˤ���
�ͿȻ��Τ�54%�������ǵ����Ƥ��ޤ���
��������
���浡�����������16%
���浡���ʤ�������24.3%
�����նᡡ��������13.8��
�����ˤϥɥ饤�С��Ρּ�ʬ��ͥ��פȤ����פ��㤤��
̵���ʱ�ž�����ꤽ���Ǥ��͡�
�����ǤΥ���ޤ�ͥ���̡�
����ϥ���ޤ�ž��������ʬ���äƤ���Ȼפ��ޤ�����ľ�ʡ����ޡ����ޤν硣
�����ơ����椬��������Ǵ��������߽Ф��䤹���Τϡ�
�����Ĥ��䤹���Ȼפ��ޤ��������֤�ľ�ʼ֤δط��Ǥ��礦��

�⡼����饤������ƣ��ε������ˤ���
�����Τ� 71.8%�����浡�Τ��������ȯ�����Ƥ��ޤ���
����¿���������и�ľ�ʼ֤�ȯ�����٤졣
�ʹ֤��濴�������40�١�
�и�ľ�ʼ����ȱ�����ޤǻ��������褦�Ȥ����
����Ȥ��Ƥ� 90 �٤���120 �٤��餤���Ϥ�ɬ�פ�����ޤ���
�����顢�������ƻϩ��������ԼԤ����뤷�Ƥ����
�и�ľ�ʼ֤�ȯ�����٤�뤳�Ȥ�����ޤ���
�⤦1�ġ����֤Υɥ饤�С�����ľ�ʼ֤������̲�Ǥ���פ�
Ƚ�Ǥ��Ƥ��ޤä��Ȥ�������������Ω�äƤ���Ȥ����ޤ���
�ޤ����Ƕ�Ǥ�����α����椬�ФƤ��鱦�ޤ��Ƥ���֤��Ф���
�ֿ��椬�Ѥ�ä�¦��ľ�ʼ֤�̵���˸����˿�����
���֤Ȥ֤Ĥ��륱�����������Ƥ���Ȥ������⤢�뤽���Ǥ���
�����ϵ���Ĥ��ʤ���Ф����ʤ�����¿���Ǥ�����
�ޤ��������Ƥ���̵����������˶ʤ���ޤ��礦��
�ޤ���ľ�ʼ֤�Ω��λ��ϡ����ޤ��褦�Ȥ��Ƥ��륯��ޤ����դ��ޤ��礦��

����ޤ�ͥ���̤ǡְִ㤤�פ�ֻפ��㤤�פ������䤹�Τ�����Τʤ�������
�ɤΤ褦��ͥ��֤Ϸ�ޤ�Τ���
�ޤ���ͥ��ƻϩ���狼����Ĥ�ɸ�������֤���Ƥ���ƻϩ�ǤϤ���˽����ޤ���
ɸ�����ʤ�ƻϩ�Ǥϥ����饤��������ͥ��ƻϩ��
�����饤�ʤ����ƻϩ��������������ͥ��ƻϩ��
ɸ���䥻���饤�ʤ���ƻϩ��������Ƚ��ˤ�������
��ξ�ˤϺ���ͥ��Υ롼�뤬���ꡢ��ʬ�κ�����ФƤ�������ޤ�ͥ��Ȥʤ�ޤ���
�Ф��Ƥ����Ʋ�������

���椬�ʤ������Ǥ����Ԥˤϵ���Ĥ��Ʋ�������
ƣ��ε������˰�����ž�Υݥ���Ȥ�ʹ�����ޤ�����
�����֤�������ϡ����μ֤������Ǹ�®�����ꡢ
�����ߤ����ǽ��������ȹͤ��ƤĤ��Ƥ����Ȥ������Ȥ����ڡ�
�����θ��̤������������Ǥϥ����֥ߥ顼��褯����Ȥ����Τ����ܡ�
�����֥ߥ顼���ʤ���С����ä�����ԡ������ߤ��ƺ����ΰ������ǧ���롣
���ޤ��Ϻ�����֤���Ť��Ƥ������ϼ�ʬ������ͥ��ƻϩ���Ȥ��Ƥ�
��Ť��Ƥ���֤���®���Ƥ��뤫�ɤ����ä�������å���
��®���뵤�ۤ��ʤ���С���ʬ���ߤޤäƤ��ᤴ��������������
�ޤ����ö�Ū�Ǥ������ɥ饤�֥쥳�����������֤��뤳�Ȥ�
��꿵�Ť˱�ž���褦�Ȥ����ռ��Ť��ˤʤ�Ȳ��⤷�Ʋ������ޤ�����
����ޤ�ͥ���̤Υ롼��ä����ǧ������
�����α�ž��褦�ˤ��ޤ��礦��



