�����Υ����� JA����presents �ʤ�ۤ�!���̰���
Every Friday 7:20��7:27
���̥롼���ƻϩ���𡢸��̰����˴ؤ���ǿ��ȥԥå����ʤɤ��轵�狼��䤹���Ҳ𤷤ޤ���
��356�ޤ��ο�������ž��Ϳ����ƶ�
2022/01/28
�������Ȥ��̶Ф��륯��ޤ�İ���Ʋ����äƤ�������¿���Ǥ��礦��
��˷�����ꡢ�Ф���������˻��֤������ä����ī�α�ž�ϵޤ�������
�����Υ���ޤǤΤ��Ф�����֡����ޤǤ��夫�ʤ��ȡ��פȵޤ����Ȥ⤢��Ǥ��礦��
�Ǥ⡢�Ǥ뵤�����ϴ��������Τ�Ͷȯ�����ͤޤ���
����϶彣��� ��ر� �����Ǹ��̿����ؤ�����λ�Ʋ�� ��§����ˤ��ä�Ǥ�
�ֵޤ��ο�������ž��Ϳ����ƶ��פ��������ޤ�����

��ž�˸¤餺����������ǵޤ��Dz�������Ϥ���
������������夫�������ˤʤä��ꡢ�Ӥäݤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ���
��ž�Ǥ�Ʊ�����Ȼ�Ʋ�������ϸ����ޤ���
��ä���Ȥ������Ťʾ��֤Dz����˵ޤ���ʬ���������Ƥߤ��
���ޤꤤ�������ˤϤ����ʤ��������ʤȻפ��ޤ���͡�
Ƚ�Ǥ���롢��ư��ְ㤨�롢�����¿����
�����ޤα�ž�����ƤϤ��ȡ�
�ޤ��������ϥ��ԡ��ɤ�Ф����Ȥ˷Ҥ���ޤ���
����ޤ�ž���Ƥ��������������9�䤬��Ф��顣
���ԡ��ɤ�Ф��о����̤�¿���ʤꡢ�����������롢
������Ф��ƿʹ֤������Ϥˤϸ³������롣
������ü����ӤǤ�����®40km�����Ԥ���ɥ饤�С��λ������100�١�
���줬��®130km�ˤʤ����30�٤ˤޤǶ����ʤ�ޤ���
�Ĥޤꡢ�������б��Ǥ��ʤ��ɵ���ɤ������Ƥ����櫓�Ǥ���
�����ơ������Ǥ���夭�����ΤǼ����ѹ������ˤ˹Ԥ���
���椬�Ѥ�����Ȥ��Ƥ���Τ˻ߤޤ餺���ͤù���Ǥ�����
�⤦��������������ޤ���

�����ơ��ޤ��Ǥ뱿ž��¾�δ����ˤ�Ҥ����ǽ��������ޤ���
���ˤʤꡢ�Ӥ��ʤ뤿�ᡢ�����걿ž�ȼ������줫�ͤޤ���
����������¾�Υɥ饤�С��Τ����걿ž��Ͷȯ�����ǽ���⤢��ޤ���
���Τ��Ȥ�Ƭ���Ҷ����֤��Ƥ����ޤ��礦��
����ʻ��֤ˤʤ�ʤ��褦��
�����ޤ�����ž�ʤ��ݥ���Ȥϣ��Ĥ���Ȼ�Ʋ�������ϸ����ޤ���
1�Ĥ�;͵�Τ��뱿ž�ײ��Ω�Ƥ롣
��Ū�Ϥ����夷�ʤ���Ф����ʤʤ����֤�����Τʤ�
�������5ʬ〜10ʬ;͵�ƽ�ȯ�롣
�⤦1�Ĥ����ʤ����褫���ä���Ȥ�뽬����Ĥ��롣
�����鲿���λ��˵ޤ��ʤ��褦�ˤ��褦�ȻפäƤ�ޤ�����������ͤˤ�̵����
����ޤα�ž���㳰�ǤϤʤ������Ǥ���
���ڤʤΤ�1��1�Ĥ���ǫ�����襹�������ȤˤĤ��뤳�ȡ�
���줬������ž�δ��ܤˤʤ�ޤ���

������ɤ���ɥ饤�С��γ�����ϡֵޤ�����ž�ϴ��ʤ��ʡפȻפä��Ϥ���
�Τ��ˡֻ��פǡ��Ƥ������转�������ͤʤȤ��������ͤʥ�������ɽ���Ǥ��礦��
��������餷����ǫ���Ѥ߽ŤͤƼ�ư�֤α�ž��ȿ�Ǥ����褦�˿�����������ΤǤ���
��˷�����ꡢ�Ф���������˻��֤������ä����ī�α�ž�ϵޤ�������
�����Υ���ޤǤΤ��Ф�����֡����ޤǤ��夫�ʤ��ȡ��פȵޤ����Ȥ⤢��Ǥ��礦��
�Ǥ⡢�Ǥ뵤�����ϴ��������Τ�Ͷȯ�����ͤޤ���
����϶彣��� ��ر� �����Ǹ��̿����ؤ�����λ�Ʋ�� ��§����ˤ��ä�Ǥ�
�ֵޤ��ο�������ž��Ϳ����ƶ��פ��������ޤ�����

��ž�˸¤餺����������ǵޤ��Dz�������Ϥ���
������������夫�������ˤʤä��ꡢ�Ӥäݤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ���
��ž�Ǥ�Ʊ�����Ȼ�Ʋ�������ϸ����ޤ���
��ä���Ȥ������Ťʾ��֤Dz����˵ޤ���ʬ���������Ƥߤ��
���ޤꤤ�������ˤϤ����ʤ��������ʤȻפ��ޤ���͡�
Ƚ�Ǥ���롢��ư��ְ㤨�롢�����¿����
�����ޤα�ž�����ƤϤ��ȡ�
�ޤ��������ϥ��ԡ��ɤ�Ф����Ȥ˷Ҥ���ޤ���
����ޤ�ž���Ƥ��������������9�䤬��Ф��顣
���ԡ��ɤ�Ф��о����̤�¿���ʤꡢ�����������롢
������Ф��ƿʹ֤������Ϥˤϸ³������롣
������ü����ӤǤ�����®40km�����Ԥ���ɥ饤�С��λ������100�١�
���줬��®130km�ˤʤ����30�٤ˤޤǶ����ʤ�ޤ���
�Ĥޤꡢ�������б��Ǥ��ʤ��ɵ���ɤ������Ƥ����櫓�Ǥ���
�����ơ������Ǥ���夭�����ΤǼ����ѹ������ˤ˹Ԥ���
���椬�Ѥ�����Ȥ��Ƥ���Τ˻ߤޤ餺���ͤù���Ǥ�����
�⤦��������������ޤ���

�����ơ��ޤ��Ǥ뱿ž��¾�δ����ˤ�Ҥ����ǽ��������ޤ���
���ˤʤꡢ�Ӥ��ʤ뤿�ᡢ�����걿ž�ȼ������줫�ͤޤ���
����������¾�Υɥ饤�С��Τ����걿ž��Ͷȯ�����ǽ���⤢��ޤ���
���Τ��Ȥ�Ƭ���Ҷ����֤��Ƥ����ޤ��礦��
����ʻ��֤ˤʤ�ʤ��褦��
�����ޤ�����ž�ʤ��ݥ���Ȥϣ��Ĥ���Ȼ�Ʋ�������ϸ����ޤ���
1�Ĥ�;͵�Τ��뱿ž�ײ��Ω�Ƥ롣
��Ū�Ϥ����夷�ʤ���Ф����ʤʤ����֤�����Τʤ�
�������5ʬ〜10ʬ;͵�ƽ�ȯ�롣
�⤦1�Ĥ����ʤ����褫���ä���Ȥ�뽬����Ĥ��롣
�����鲿���λ��˵ޤ��ʤ��褦�ˤ��褦�ȻפäƤ�ޤ�����������ͤˤ�̵����
����ޤα�ž���㳰�ǤϤʤ������Ǥ���
���ڤʤΤ�1��1�Ĥ���ǫ�����襹�������ȤˤĤ��뤳�ȡ�
���줬������ž�δ��ܤˤʤ�ޤ���

������ɤ���ɥ饤�С��γ�����ϡֵޤ�����ž�ϴ��ʤ��ʡפȻפä��Ϥ���
�Τ��ˡֻ��פǡ��Ƥ������转�������ͤʤȤ��������ͤʥ�������ɽ���Ǥ��礦��
��������餷����ǫ���Ѥ߽ŤͤƼ�ư�֤α�ž��ȿ�Ǥ����褦�˿�����������ΤǤ���
��355����ޤ����
2022/01/21
���������ᵤ���紨��
1ǯ�Ǥ����Ф�������ޤ��Ƥ��ޤ���
ī���жФʤɤǥ���ޤ˾�����Ȥ�������
�ե���ȥ��饹����뤷�Ƥ��뤳�Ȥ��̹�����Ǥʤ�����Ǥ���Ǥ��礦��
������JAF ������� ���Ȳݸ��̴Ķ��������� ͪ������ˤ��ä�Ǥ�
�֥���ޤ����פ�ơ��ޤˤ����ꤷ�ޤ�����

2018ǯ�⾾����λ�ƻ���⤤�Ƥ������������˻�2�ͤ��Ф���
���������®�����Ԥ��Ƥ����ڥȥ�å������ͤ�����Τ������ޤ�����
�ڥȥ�å��ϥե���ȥ��饹���������夷�����֤�
�������ۤȤ�ɸ����������Ԥ��Ƥ��������Ǥ���
�����ʤ��Ȥ�2�ͤϷڽ��ǺѤߤޤ�����
�֥ե���ȥ��饹����뤷�Ƥ����������ˤ�����
�Ǥ⡢��Ū�Ϥ϶ᤤ���餤�����������פ���ʵ������ϴ�����
�и��������ȤΤ������Ϥ狼��Ϥ���
�ե���ȥ��饹����뤷�Ƥ�����ɹ������ʤ����ƽ�ȯ���ޤ��礦��

��������ˤ��Ȱ���JAF�Ǥϥե���ȥ��饹������
�ɤΤ褦����ˡ���Ϥ����Τ�������2�ѥ�����Ǽ¸����ޤ�����
��ɹ���ץ졼�ȥ�������Υǥե���������ǽ��ȤäƲ�����֤���Ӥ����ΤǤ���
���η�̡���������Υǥե���������ǽ���Ȼ볦�����ݤǤ���ޤ���10ʬ��
�ԤäƤ���֤ϥ����ɥ���Ƥ���ΤǴĶ��̤���٤⤫����ޤ���
�����ǻ��Τβ�ɹ���ץ졼����1ʬ���١�
�ե���ȥ��饹�˿�䤪�������ˡ�⤢��ޤ�����
���ٺ��ǥ��饹�˥ҥӤ����ä��ꡢ�Ϥ����夬���������äƤ��ޤ����Ȥ⤢��ޤ���
���դ��Ʋ�������

�ե���ȥ��饹��������������Τϴ���Ū��ī��
�ж������ޤ��ʤ���Ф����ʤ�������¿���Ȼפ��ޤ���
���Τޤ�ȯ����Τ�������
��������Υǥե���������ǽ������Ȥä��Ϥ��������
�٤�����᤹����ԡ��ɤ�Ф��Τϴ�����
�ߤλ����ϻ��Τβ�ɹ���ץ졼��������Ƥ����ޤ��礦��

�����к���ΤϤ������
�����к���֤��Ƥ����С������ɤ��뤫�⤷��ޤ���
JAF�Ͼ�郎�ۤʤ�3��Υ���ޤ��Ѱդ��Ƽ¸���Ԥʤä���������ޤ���
�����к����Ƥ��ʤ�����ޡ�
����ޤ�ե���ȥ��饹���ɤä�����ޡ�
�ե���ȥ��饹���Τ˥��С���������ޤ�3��Ǥ���
�����к����ʤ��ä�����ޤξ��ϥե���ȥ��饹����롣
ī�ˤʤäƥإ�䥹���졼�ѡ���ȤäƤ������꤭�줺
�볦����ݤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ���̤ˤʤ�ޤ�����
����ޤ�����˥ե���ȥ��饹���ɤäƤ�������ޤ�
��Ϥ���뤷�ޤ����������졼�ѡ���Ȥ����Ȥ�
ɹ�٤ƺ����Ȥ����Ȥ��Ǥ��ƻ볦����ݤǤ��ޤ�����
�ե���ȥ��饹���Τ˥��С���������ޤ���뤻��
���줬1��ͭ�����к����Ȥ������Ȥ��狼��ޤ�����
���ѥ��С��ϥ�������Ź�Ǥ����䤵��Ƥ��ޤ�����
���������ۤ�Х�������Ǥ����ѤǤ��ޤ���
��äƤ��ʤ��������С��ˤ������к���Ϥ�ƤߤƤ���������

�ޤ��������ϤǤ��㤬�ߤäƤ������ϩ�̤α��줬�Ĥ��䤹���ʤ�Τ�
������ɥ����å��㡼�դλ������٤���ޤ�ޤ�����
�����å��㡼�դ���äƤ��ޤ���ǽ�����ꡣ
�������Ѥ���Ѥ��뤫���������˹�碌��ǻ��Ĵ�ɬ�פǤ���
�ޤ����������ѱդ���뤷�Ƥ��ޤ����⤷��ޤ���
����⳰�����˹�碌��Ŭ�ڤ�ǻ�٤�Ĵ������褦�������Ʋ�������

1ǯ�Ǥ����Ф�������ޤ��Ƥ��ޤ���
ī���жФʤɤǥ���ޤ˾�����Ȥ�������
�ե���ȥ��饹����뤷�Ƥ��뤳�Ȥ��̹�����Ǥʤ�����Ǥ���Ǥ��礦��
������JAF ������� ���Ȳݸ��̴Ķ��������� ͪ������ˤ��ä�Ǥ�
�֥���ޤ����פ�ơ��ޤˤ����ꤷ�ޤ�����

2018ǯ�⾾����λ�ƻ���⤤�Ƥ������������˻�2�ͤ��Ф���
���������®�����Ԥ��Ƥ����ڥȥ�å������ͤ�����Τ������ޤ�����
�ڥȥ�å��ϥե���ȥ��饹���������夷�����֤�
�������ۤȤ�ɸ����������Ԥ��Ƥ��������Ǥ���
�����ʤ��Ȥ�2�ͤϷڽ��ǺѤߤޤ�����
�֥ե���ȥ��饹����뤷�Ƥ����������ˤ�����
�Ǥ⡢��Ū�Ϥ϶ᤤ���餤�����������פ���ʵ������ϴ�����
�и��������ȤΤ������Ϥ狼��Ϥ���
�ե���ȥ��饹����뤷�Ƥ�����ɹ������ʤ����ƽ�ȯ���ޤ��礦��

��������ˤ��Ȱ���JAF�Ǥϥե���ȥ��饹������
�ɤΤ褦����ˡ���Ϥ����Τ�������2�ѥ�����Ǽ¸����ޤ�����
��ɹ���ץ졼�ȥ�������Υǥե���������ǽ��ȤäƲ�����֤���Ӥ����ΤǤ���
���η�̡���������Υǥե���������ǽ���Ȼ볦�����ݤǤ���ޤ���10ʬ��
�ԤäƤ���֤ϥ����ɥ���Ƥ���ΤǴĶ��̤���٤⤫����ޤ���
�����ǻ��Τβ�ɹ���ץ졼����1ʬ���١�
�ե���ȥ��饹�˿�䤪�������ˡ�⤢��ޤ�����
���ٺ��ǥ��饹�˥ҥӤ����ä��ꡢ�Ϥ����夬���������äƤ��ޤ����Ȥ⤢��ޤ���
���դ��Ʋ�������

�ե���ȥ��饹��������������Τϴ���Ū��ī��
�ж������ޤ��ʤ���Ф����ʤ�������¿���Ȼפ��ޤ���
���Τޤ�ȯ����Τ�������
��������Υǥե���������ǽ������Ȥä��Ϥ��������
�٤�����᤹����ԡ��ɤ�Ф��Τϴ�����
�ߤλ����ϻ��Τβ�ɹ���ץ졼��������Ƥ����ޤ��礦��

�����к���ΤϤ������
�����к���֤��Ƥ����С������ɤ��뤫�⤷��ޤ���
JAF�Ͼ�郎�ۤʤ�3��Υ���ޤ��Ѱդ��Ƽ¸���Ԥʤä���������ޤ���
�����к����Ƥ��ʤ�����ޡ�
����ޤ�ե���ȥ��饹���ɤä�����ޡ�
�ե���ȥ��饹���Τ˥��С���������ޤ�3��Ǥ���
�����к����ʤ��ä�����ޤξ��ϥե���ȥ��饹����롣
ī�ˤʤäƥإ�䥹���졼�ѡ���ȤäƤ������꤭�줺
�볦����ݤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ���̤ˤʤ�ޤ�����
����ޤ�����˥ե���ȥ��饹���ɤäƤ�������ޤ�
��Ϥ���뤷�ޤ����������졼�ѡ���Ȥ����Ȥ�
ɹ�٤ƺ����Ȥ����Ȥ��Ǥ��ƻ볦����ݤǤ��ޤ�����
�ե���ȥ��饹���Τ˥��С���������ޤ���뤻��
���줬1��ͭ�����к����Ȥ������Ȥ��狼��ޤ�����
���ѥ��С��ϥ�������Ź�Ǥ����䤵��Ƥ��ޤ�����
���������ۤ�Х�������Ǥ����ѤǤ��ޤ���
��äƤ��ʤ��������С��ˤ������к���Ϥ�ƤߤƤ���������

�ޤ��������ϤǤ��㤬�ߤäƤ������ϩ�̤α��줬�Ĥ��䤹���ʤ�Τ�
������ɥ����å��㡼�դλ������٤���ޤ�ޤ�����
�����å��㡼�դ���äƤ��ޤ���ǽ�����ꡣ
�������Ѥ���Ѥ��뤫���������˹�碌��ǻ��Ĵ�ɬ�פǤ���
�ޤ����������ѱդ���뤷�Ƥ��ޤ����⤷��ޤ���
����⳰�����˹�碌��Ŭ�ڤ�ǻ�٤�Ĵ������褦�������Ʋ�������

��354���������ץ����饤��
2022/01/14
���ϥ��������� ����Ĺ����������ػ��رۼ�ư��ƻ��
���β��ꡢ�쾾��IC�ն��ϩ�̤��п��μ�����������Ƥ��ޤ���
�ر�ƻ��������ˡ֤����Ф����ϲ����פȻפä��и����������⤤��Ǥ��礦����
����ϡּ��������ץ����饤��פ�̾�դ���줿��Ρ�
�����NEXCO�����ܴ���ټ� ����ͽ���
�г� �����ˤ��ä�Ǥ�������������Ū���������ޤ�����

���������ץ����饤���2021ǯ 7��˽������֤���ޤ�����
���ϴرۼ�ư��ƻ���� �쾾��IC��������ή��������4km�ζ�֡�
��μ̿��������������Ф�¦�����Լ����κ����˰�����Ƥ��ޤ���
�ޤ������������Ǥʤ��쾾��IC��ή�����פˤ⤢�ꡢ���줬�ʲ��Υ��饹�ȡ�
�饤���������Ū�����ѼԤ����Ƥ�餦����
�����������פΥ�å�����ɽ���⤢�����Ű���ޤäƤ���Τ��狼��ޤ���
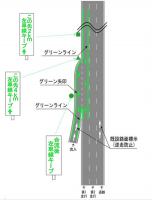
���������ץ����饤�����Ū��2�ġ�
�� �����ץ�եȤ�¥�ʤˤ�����ͽ��
�������Υɥ饤�С��Ͼ����Ǥ���ʤ⤦���ɤ��ۤ����������Ѥ�������
�Ǥ⡢�¤Ͻ��ڤ�¿�����ɤ��ۤ���������ȯ�����Ƥ��ޤ���
����ϼ֤��ɤ��ۤ������˽��椷�Ƥ��Ƥ��ޤ����顣
�ޤ�������䤫�����˸��ۤ��Ѳ�����������֥����פȸ����ޤ���
����������̵�ռ��˥���ޤ�®�٤��㲼���ƽ��ڤ�ȯ�����䤹���ʤ�ޤ���
���������ץ����饤�����֤��줿�쾾��IC���Ȥ�Ĺ�����䡣
�����ǥ����ץ�եȿ������ƽ��ڤ���¤��褦�Ȥ��������Ǥ���
�� ��������ή������֤ε����к�
�������IC�Υ��פ�����������ץ����饤��˱�ä����Ԥ��Ƥ�餦���Ȥ�
�����ؤθ�ή�⼫���������������ǹ�ή�Ǥ���Τǵ����к��˷Ҥ���Ȥ��������Ǥ���

�ּ��������ץ����饤��פ��ʤ��Ƥ�̵�Ǥ��ɱۼ��������Ԥ��ޤ��礦��
�ޤ���NEXCO�����ܤǤϾ����®���㲼���������������Ǥ��Ȥ���ɸ����
�����ϥ����ǽ��ڤ�ȯ���ݥ���ȤǤ���ȥɥ饤�С����Τ餻��ɸ���������֤��Ƥ��ޤ���
�����������ˤ�®�٤β��������ޤ��礦��
�ɥ饤�С��κ��٤ʼ�ʬ����ʱ�ž���Ѥ߽Ťʤä��礭�ʽ��ڤ�ȯ�����뤳�Ȥ⤢��ޤ���
�ҤȤ�ҤȤ꤬���դ������Ǥ��͡�
���β��ꡢ�쾾��IC�ն��ϩ�̤��п��μ�����������Ƥ��ޤ���
�ر�ƻ��������ˡ֤����Ф����ϲ����פȻפä��и����������⤤��Ǥ��礦����
����ϡּ��������ץ����饤��פ�̾�դ���줿��Ρ�
�����NEXCO�����ܴ���ټ� ����ͽ���
�г� �����ˤ��ä�Ǥ�������������Ū���������ޤ�����

���������ץ����饤���2021ǯ 7��˽������֤���ޤ�����
���ϴرۼ�ư��ƻ���� �쾾��IC��������ή��������4km�ζ�֡�
��μ̿��������������Ф�¦�����Լ����κ����˰�����Ƥ��ޤ���
�ޤ������������Ǥʤ��쾾��IC��ή�����פˤ⤢�ꡢ���줬�ʲ��Υ��饹�ȡ�
�饤���������Ū�����ѼԤ����Ƥ�餦����
�����������פΥ�å�����ɽ���⤢�����Ű���ޤäƤ���Τ��狼��ޤ���
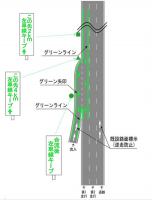
���������ץ����饤�����Ū��2�ġ�
�� �����ץ�եȤ�¥�ʤˤ�����ͽ��
�������Υɥ饤�С��Ͼ����Ǥ���ʤ⤦���ɤ��ۤ����������Ѥ�������
�Ǥ⡢�¤Ͻ��ڤ�¿�����ɤ��ۤ���������ȯ�����Ƥ��ޤ���
����ϼ֤��ɤ��ۤ������˽��椷�Ƥ��Ƥ��ޤ����顣
�ޤ�������䤫�����˸��ۤ��Ѳ�����������֥����פȸ����ޤ���
����������̵�ռ��˥���ޤ�®�٤��㲼���ƽ��ڤ�ȯ�����䤹���ʤ�ޤ���
���������ץ����饤�����֤��줿�쾾��IC���Ȥ�Ĺ�����䡣
�����ǥ����ץ�եȿ������ƽ��ڤ���¤��褦�Ȥ��������Ǥ���
�� ��������ή������֤ε����к�
�������IC�Υ��פ�����������ץ����饤��˱�ä����Ԥ��Ƥ�餦���Ȥ�
�����ؤθ�ή�⼫���������������ǹ�ή�Ǥ���Τǵ����к��˷Ҥ���Ȥ��������Ǥ���

�ּ��������ץ����饤��פ��ʤ��Ƥ�̵�Ǥ��ɱۼ��������Ԥ��ޤ��礦��
�ޤ���NEXCO�����ܤǤϾ����®���㲼���������������Ǥ��Ȥ���ɸ����
�����ϥ����ǽ��ڤ�ȯ���ݥ���ȤǤ���ȥɥ饤�С����Τ餻��ɸ���������֤��Ƥ��ޤ���
�����������ˤ�®�٤β��������ޤ��礦��
�ɥ饤�С��κ��٤ʼ�ʬ����ʱ�ž���Ѥ߽Ťʤä��礭�ʽ��ڤ�ȯ�����뤳�Ȥ⤢��ޤ���
�ҤȤ�ҤȤ꤬���դ������Ǥ��͡�
��353����������Ƥ����٤����
2022/01/07
��ǯ��ޤ���1���֤��Ф��ޤ�����
2022ǯ�������ž�ǻ��Τ����ʤ��褦�˵���Ĥ��ޤ��礦��
��ǯ�ǽ�Ρ֤ʤ�ۤɡ����̰����פϡ�
�Ȥ⤷��ɤλ��������Ƽ֤��Ѥ�Ǥ��������ƥ��
��ư�֥饤���� ��ƣ��������ˤ��ä�ʹ�����������ޤ�����

�֤˾�äƤ�������Ͽ̡��л���ʮ�С��ں����졢����ʤɤκҳ���
��������λ��Τ˴������ޤ�뤳�Ȥ�ͤ����ޤ���
��ƣ���Ƥ������ä�3�ĤΥޥ��ȥ����ƥ��
���������������ϥ�ޡ�������ɽ���ġ�
�ȥ�ͥ���Ĥ������줿���䡢
��֤�Ť��Ȥ����ǿ�ư�������ʤ��ʤä����Τ���β���������
�볦����ݤ����ꡢ����ǰ¿��������뤳�Ȥ�����ޤ���
LED��Ȥä������פ����뤵�����Ӥξ����ͤ���Ȥ������ᡣ

�籫��¿ȯ�����
�֤���æ�Ф��ʤ���Ф����ʤ����֤�ͤ����ޤ���
����ʻ���ɬ�פʤΤ�������ɥ�����ϥ�ޡ���
�����ȥ٥�ȥ��å����դ����������⤷��ޤ���

����ɽ���Ĥ��Ȥ�Ω�Ƥ�Ȱ��Ҥ�40��������餤��
�֤θ�����֤��Ƽ֤��ߤޤäƤ��뤳�Ȥ��³�֤������뤿��Τ�Ρ�
���������ͤ����Τ��ɤ�����ϥ饤�Ȥ�ȿ�ͤ��ޤ���
�֤��Ѥ�Ǥ�����̳�Ϥ���ޤ�����®ƻϩ��ϩ���˶۵���֤�����ˤ�
����ɽ���Ĥ�Ȥ�ʤ��Ȱ�ȿ�ˤʤ�ΤǼ֤˺ܤ��Ƥ����٤���ΤǤ���

�����ơ��Ǥ���м���˽������Ƥ������ۤ����ɤ���Τ�4�ġ�
���Ӽ�ȯ�������֡������������֥롦���������ס��òд�Ǥ���
ȯ�����Ϥɤμ֤ˤ��Ѥ�Ǥ���Ȼפ��ޤ�����ɸ�������Τ�Τϻ�³���֤�û����
���Ӽ����Ѱդ��Ƥ����С�Ĺ�����֡������������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
�֡������������֥�ϥХåƥ���夬�ä�����
¾�μ֤����ŵ���ʬ���Ƥ�餤�������ƤӤ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
JAF�Υ����ɥ����ӥ���ư��ͳ��4�䤬�Хåƥ���夬�ä����ȡ�
�����������ݤ�̵�̤ʽ�������ޤ���
���������פ���ƻ�ʤɤ�ư���ʤ��ʤä����˼֤Ǹ���������Τ��ᡣ
��ʬ��������¦�Ǥ⡢�����Ƥ�餦¦�Ǥ�Ȥ����Ȥ��Ǥ��ޤ���
�ä���ƻ��������ˤ��Ѱդ��Ƥ��������Ȥ�����
�ò���ϼ֤���Ф��Ф��Ȥ��˻Ȥ��ޤ���
�¤�ǯ��1500�擄�餤�μ֤βл��������Ƥ��ޤ���

�����ơ����ε������ؤ�������ͤ��ޤ��礦��
�㤨����������Ǽ֤�ư�������Ȥ�����ʤ��ʤä����Τ�����Τ�����ۡ�
�۵�̿�θ���Ǥ�Ȥ��Ƥ��륨�ޡ��������֥�åȤ���ƣ����Τ������ᡣ
������������������륢�����������ѥ��ȤǼ֤��Ѥ�Ǥ����Τ��ɤ��Ȥ������ȤǤ���
�ޤ�Ĺ���֡�������Ĥ�����餿���Τ���ΰ����塦��¸����������������Ȱ¿��Ǥ���
����Ū�ʤȤ����Ǥϡ����ۤʤΤ�Ω�����������Ȥ���dz���ڤ졣
���ߤޤ�ȥҡ�������Ȥ��ʤ��ʤ�Τ�dz���ڤ��������
�ä˹����ϰ�ˤ����ޤ������ϤǤ������dz����������ˤ��Ƥ����ޤ��礦��

�����졢����ƻϩ���®ƻϩ�ǻ��Τ������ԤˤʤäƤ��ޤä���硢
�ޤ����ͤ��ʤ���Ф����ʤ��Τ���ʬ�ΰ������ݡ�
�֤�ߤ�ƥ�����ڤꡢ�֤���ߤ����ϸ�³�֤ä������դ��뤳�ȡ�
���ξ�Ǹ��������ͤ���ʤ��褦��ɽ���Ǥ�ȯ�����ǻ��Τ���֤ԡ��뤷�ޤ���
ϩ���˻ߤޤäƤ���֤ˤϾ�˸��������ͤ������������뤳�Ȥ�ǰƬ�ˤ����Ʋ�������
���줫�����ͤ�����е߸�ȷٻ�����ɤؤ�Ϣ����
��®ƻϩ�ǽ������ԤĴ֤ϥե���ۤ���ƻϩ�γ����ԤäƤ���褦�ˤ��ޤ��礦��
��³�֤����ͤ�����ҳ����ɤ�����Ǥ���

�����ɥ���ޤ˺ܤ��Ƥ���۵ޥ��å����ǧ���Ĥġ�
��ʤ���Τ�������㤤���褦�ˤ��Ʋ�������
�����ν������դ餺���Ȥ⤷��ɤλ�������夤�ƹ�ư���ޤ��礦��
2022ǯ�Υ����饤�դ⡢�������ˡ�
2022ǯ�������ž�ǻ��Τ����ʤ��褦�˵���Ĥ��ޤ��礦��
��ǯ�ǽ�Ρ֤ʤ�ۤɡ����̰����פϡ�
�Ȥ⤷��ɤλ��������Ƽ֤��Ѥ�Ǥ��������ƥ��
��ư�֥饤���� ��ƣ��������ˤ��ä�ʹ�����������ޤ�����

�֤˾�äƤ�������Ͽ̡��л���ʮ�С��ں����졢����ʤɤκҳ���
��������λ��Τ˴������ޤ�뤳�Ȥ�ͤ����ޤ���
��ƣ���Ƥ������ä�3�ĤΥޥ��ȥ����ƥ��
���������������ϥ�ޡ�������ɽ���ġ�
�ȥ�ͥ���Ĥ������줿���䡢
��֤�Ť��Ȥ����ǿ�ư�������ʤ��ʤä����Τ���β���������
�볦����ݤ����ꡢ����ǰ¿��������뤳�Ȥ�����ޤ���
LED��Ȥä������פ����뤵�����Ӥξ����ͤ���Ȥ������ᡣ

�籫��¿ȯ�����
�֤���æ�Ф��ʤ���Ф����ʤ����֤�ͤ����ޤ���
����ʻ���ɬ�פʤΤ�������ɥ�����ϥ�ޡ���
�����ȥ٥�ȥ��å����դ����������⤷��ޤ���

����ɽ���Ĥ��Ȥ�Ω�Ƥ�Ȱ��Ҥ�40��������餤��
�֤θ�����֤��Ƽ֤��ߤޤäƤ��뤳�Ȥ��³�֤������뤿��Τ�Ρ�
���������ͤ����Τ��ɤ�����ϥ饤�Ȥ�ȿ�ͤ��ޤ���
�֤��Ѥ�Ǥ�����̳�Ϥ���ޤ�����®ƻϩ��ϩ���˶۵���֤�����ˤ�
����ɽ���Ĥ�Ȥ�ʤ��Ȱ�ȿ�ˤʤ�ΤǼ֤˺ܤ��Ƥ����٤���ΤǤ���

�����ơ��Ǥ���м���˽������Ƥ������ۤ����ɤ���Τ�4�ġ�
���Ӽ�ȯ�������֡������������֥롦���������ס��òд�Ǥ���
ȯ�����Ϥɤμ֤ˤ��Ѥ�Ǥ���Ȼפ��ޤ�����ɸ�������Τ�Τϻ�³���֤�û����
���Ӽ����Ѱդ��Ƥ����С�Ĺ�����֡������������뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
�֡������������֥�ϥХåƥ���夬�ä�����
¾�μ֤����ŵ���ʬ���Ƥ�餤�������ƤӤ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
JAF�Υ����ɥ����ӥ���ư��ͳ��4�䤬�Хåƥ���夬�ä����ȡ�
�����������ݤ�̵�̤ʽ�������ޤ���
���������פ���ƻ�ʤɤ�ư���ʤ��ʤä����˼֤Ǹ���������Τ��ᡣ
��ʬ��������¦�Ǥ⡢�����Ƥ�餦¦�Ǥ�Ȥ����Ȥ��Ǥ��ޤ���
�ä���ƻ��������ˤ��Ѱդ��Ƥ��������Ȥ�����
�ò���ϼ֤���Ф��Ф��Ȥ��˻Ȥ��ޤ���
�¤�ǯ��1500�擄�餤�μ֤βл��������Ƥ��ޤ���

�����ơ����ε������ؤ�������ͤ��ޤ��礦��
�㤨����������Ǽ֤�ư�������Ȥ�����ʤ��ʤä����Τ�����Τ�����ۡ�
�۵�̿�θ���Ǥ�Ȥ��Ƥ��륨�ޡ��������֥�åȤ���ƣ����Τ������ᡣ
������������������륢�����������ѥ��ȤǼ֤��Ѥ�Ǥ����Τ��ɤ��Ȥ������ȤǤ���
�ޤ�Ĺ���֡�������Ĥ�����餿���Τ���ΰ����塦��¸����������������Ȱ¿��Ǥ���
����Ū�ʤȤ����Ǥϡ����ۤʤΤ�Ω�����������Ȥ���dz���ڤ졣
���ߤޤ�ȥҡ�������Ȥ��ʤ��ʤ�Τ�dz���ڤ��������
�ä˹����ϰ�ˤ����ޤ������ϤǤ������dz����������ˤ��Ƥ����ޤ��礦��

�����졢����ƻϩ���®ƻϩ�ǻ��Τ������ԤˤʤäƤ��ޤä���硢
�ޤ����ͤ��ʤ���Ф����ʤ��Τ���ʬ�ΰ������ݡ�
�֤�ߤ�ƥ�����ڤꡢ�֤���ߤ����ϸ�³�֤ä������դ��뤳�ȡ�
���ξ�Ǹ��������ͤ���ʤ��褦��ɽ���Ǥ�ȯ�����ǻ��Τ���֤ԡ��뤷�ޤ���
ϩ���˻ߤޤäƤ���֤ˤϾ�˸��������ͤ������������뤳�Ȥ�ǰƬ�ˤ����Ʋ�������
���줫�����ͤ�����е߸�ȷٻ�����ɤؤ�Ϣ����
��®ƻϩ�ǽ������ԤĴ֤ϥե���ۤ���ƻϩ�γ����ԤäƤ���褦�ˤ��ޤ��礦��
��³�֤����ͤ�����ҳ����ɤ�����Ǥ���

�����ɥ���ޤ˺ܤ��Ƥ���۵ޥ��å����ǧ���Ĥġ�
��ʤ���Τ�������㤤���褦�ˤ��Ʋ�������
�����ν������դ餺���Ȥ⤷��ɤλ�������夤�ƹ�ư���ޤ��礦��
2022ǯ�Υ����饤�դ⡢�������ˡ�


