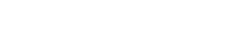第474話 継続することの大切さを知る
-【千葉県にまつわるレジェンド篇】教育家 津田梅子-
[2024.09.28]
Podcast

今年20年ぶりに発行された新紙幣、その五千円札の顔になった、日本女子教育の先駆者がいます。
津田梅子(つだ・うめこ)。
まだ女性の教育が『良妻賢母』のためだけだった時代に、留学のための「日本婦人米国奨学金」を創設したり、女子英学塾、のちの津田塾大学を設立するなど、梅子は、女性の社会進出を推進するさまざまな取り組みに一生を捧げました。
彼女の父、津田仙(つだ・せん)は、下総国佐倉藩、現在の千葉県佐倉市に生まれ、日本の近代農業の発展に尽力しました。
さらに福沢諭吉らと共に、アメリカに留学。
欧米の文化にも精通した知識人でした。
しかし、そんな先進的な津田仙であっても、姉の琴子(ことこ)に次いで梅子が生まれたとき、こう言い放ったのです。
「なんだ、また、女が生まれたのか、今度は男だと思っておったのに、後継ぎにもなりはしない。
つまらん! もう、どうでもいい!」
梅子が生まれた1864年は、明治政府ができる4年前。
封建制度は厳しく女性を縛り、どう生きるかより、どんな男性と結婚するかが重要だと、親に諭される時代でした。
梅子の父も御多分にもれず、梅子の幸せは結婚にあると思いつつ、ただ、他の父親とは違う助言をしました。
「私は20歳で留学したので、英語を習うのにとても苦労したんだ。
語学をやるのはもっともっと若いうちがいい」
そうして、梅子は若干6歳で、岩倉使節団に応募。
アメリカに留学することになったのです。
この決断が、彼女の後の人生を決定づけたのは間違いありませんが、梅子の凄さは、苦難にめげない持続力でした。
当時、英語ができるだけでは、職は限られ、なかなか就職のあてがない状況。
それでも女子教育の場を造りたいと決めた彼女は、文字通り東奔西走し、何度失敗しても意志を曲げなかったのです。
女性の地位向上に邁進したレジェンド、津田梅子が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

今年、2024年7月に発行された新紙幣。
その五千円札の肖像になった偉人・津田梅子は、1864年12月31日、江戸牛込南御徒町、現在の東京都新宿区で生まれた。
父は佐倉藩出身。農学者として近代農業に貢献。
アスパラガス、レタス、ブロッコリーなどの西洋野菜や、イチゴ、ブドウ、リンゴなどの果物を、輸入に頼らず、国内で栽培できるように尽力した。
千葉県佐倉市では、市役所の食堂で、地元の名士に敬意を払い、「津田仙 特別メニュー」を提供している。
キリスト教信者でもあり、青山学院大学の創立にも関与した梅子の父は、英語の大切さを実感していた。
梅子が生まれるおよそ10年前にペリーが来航。
日本は新政府をつくり、いよいよ海外との貿易、国交、交流が急速に栄えていくことは必至だった。
英語を話せる人間がニッポンの先頭に立つ。
父はそう信じ、娘に留学を進めた。
語学をやるなら早いほどいい、若いほど身に着く、さらに、アメリカに10年もいれば、語学だけではなく文化まで学べる。
6歳の梅子は、当初、アメリカになど行きたくなかった。
まだまだ甘えたい盛り。両親や姉と暮らしていたい。
しかし心から尊敬している父の話を聞くうちに、留学したいと思うようになっていった。
こうして幼い少女は横浜港に向かった。
見たことのない大きな船が停泊している。
岩倉具視が率いる使節団。
14歳を筆頭に、5人の女子が留学生として加わった。
もちろん、梅子は最年少。
不安を吹き飛ばすように、大きく、汽笛が鳴った。
近代女子教育の母、津田梅子は、7歳の時、ワシントンD.C.、ジョージタウンのランマン夫妻の家に預けられる。
子どものいない夫妻は、幼い梅子を我が子のように可愛がった。
留学生5人の少女のうち、年長の二人は、体調を崩し、日本に帰国。
梅子は、残った。
地元の小学校に入ったが、当然のように言葉がわからない。
同級生たちに笑われる。
着物でサンフランシスコに降り立った梅子たち。
留学生も日本人の女性も、ほとんど街にいなかった。
辞書を引いて、必死に、英語にくらいつく。
梅子の英語力は、日を追うごとに上達していった。
そんな少女の努力を、ランマン夫人は支えた。
ゆっくり話し、発音を直す。
何度も何度も、根気よく、直す。
梅子は、思った。
もしここに自分の家族がいたら、甘えてしまい、勉強をやめて、日本に帰るだろう。
甘えられない環境。そこに継続のヒントがあった。
そして環境より、もっと大切なものがあった。
それは、学びたいという意志。
「やり抜こう」と思う気持ちは、自分をひとつ上のステージに引き上げてくれる。
津田梅子は、およそ11年間の留学生活を送り、日本に帰国。17歳になっていた。
横浜港に着いて、懐かしい両親の顔を見る。
ここで、とてつもない事実を知った。
日本語が、話せない。
口をついて出てくるのは、全て英語だった。
幸い、父の津田仙は英語ができたので、集まった親戚たちに通訳する。
焦った。
日本語ができない自分が、この日本でどうやって生きていくのか。
梅子は、アメリカで、すでに思っていた。
「いつか必ず、日本に女性のための学校をつくりたい。
女性も男性と同じように知識や教養を身に着け、対等に働ける世の中にしたい」
そんな人生を賭ける夢も、どんどん遠のいていく。
日本語ができないイコール、就職ができない。
男性は、英語ができるだけでさまざまな要職についているのに、女性にはその門戸が開かれていなかった。
絶望の中、思い出した。
根気よく、自分に英語を教えてくれたランマン夫人。
「そうだ、ここで諦めてはいけない。この英語を生かせる道が、きっとあるはずだ」
日本語を学び、なんとか夢の実現のために頑張っていた梅子に出会いが待っていた。
あるパーティーでの再会。
同じ岩倉使節団にいた男性が声をかけてくれた。
「津田梅子さん、もしよかったら、我が家で英語の家庭教師をしていただけませんか?
我が家だけでなく、ニッポンには、あなたの力が必要だと思います」
その男性こそ、のちに初代総理大臣になる、伊藤博文だった。
「何かを始めることはやさしいが、それを継続することは難しい。
成功させることはなお難しい」
津田梅子


【ON AIR LIST】
◆CLOSER TO FINE / Indigo Girls
◆アルマ・マーター組曲 図書閲覧室 / リロイ・アンダーソン(作曲)、ニュートン・ウェイランド、ロチェスターポップス管弦楽団
◆EVERYDAY IS A WINDING ROAD / Sheryl Crow
◆Will / 浜崎あゆみ
津田梅子(つだ・うめこ)。
まだ女性の教育が『良妻賢母』のためだけだった時代に、留学のための「日本婦人米国奨学金」を創設したり、女子英学塾、のちの津田塾大学を設立するなど、梅子は、女性の社会進出を推進するさまざまな取り組みに一生を捧げました。
彼女の父、津田仙(つだ・せん)は、下総国佐倉藩、現在の千葉県佐倉市に生まれ、日本の近代農業の発展に尽力しました。
さらに福沢諭吉らと共に、アメリカに留学。
欧米の文化にも精通した知識人でした。
しかし、そんな先進的な津田仙であっても、姉の琴子(ことこ)に次いで梅子が生まれたとき、こう言い放ったのです。
「なんだ、また、女が生まれたのか、今度は男だと思っておったのに、後継ぎにもなりはしない。
つまらん! もう、どうでもいい!」
梅子が生まれた1864年は、明治政府ができる4年前。
封建制度は厳しく女性を縛り、どう生きるかより、どんな男性と結婚するかが重要だと、親に諭される時代でした。
梅子の父も御多分にもれず、梅子の幸せは結婚にあると思いつつ、ただ、他の父親とは違う助言をしました。
「私は20歳で留学したので、英語を習うのにとても苦労したんだ。
語学をやるのはもっともっと若いうちがいい」
そうして、梅子は若干6歳で、岩倉使節団に応募。
アメリカに留学することになったのです。
この決断が、彼女の後の人生を決定づけたのは間違いありませんが、梅子の凄さは、苦難にめげない持続力でした。
当時、英語ができるだけでは、職は限られ、なかなか就職のあてがない状況。
それでも女子教育の場を造りたいと決めた彼女は、文字通り東奔西走し、何度失敗しても意志を曲げなかったのです。
女性の地位向上に邁進したレジェンド、津田梅子が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

今年、2024年7月に発行された新紙幣。
その五千円札の肖像になった偉人・津田梅子は、1864年12月31日、江戸牛込南御徒町、現在の東京都新宿区で生まれた。
父は佐倉藩出身。農学者として近代農業に貢献。
アスパラガス、レタス、ブロッコリーなどの西洋野菜や、イチゴ、ブドウ、リンゴなどの果物を、輸入に頼らず、国内で栽培できるように尽力した。
千葉県佐倉市では、市役所の食堂で、地元の名士に敬意を払い、「津田仙 特別メニュー」を提供している。
キリスト教信者でもあり、青山学院大学の創立にも関与した梅子の父は、英語の大切さを実感していた。
梅子が生まれるおよそ10年前にペリーが来航。
日本は新政府をつくり、いよいよ海外との貿易、国交、交流が急速に栄えていくことは必至だった。
英語を話せる人間がニッポンの先頭に立つ。
父はそう信じ、娘に留学を進めた。
語学をやるなら早いほどいい、若いほど身に着く、さらに、アメリカに10年もいれば、語学だけではなく文化まで学べる。
6歳の梅子は、当初、アメリカになど行きたくなかった。
まだまだ甘えたい盛り。両親や姉と暮らしていたい。
しかし心から尊敬している父の話を聞くうちに、留学したいと思うようになっていった。
こうして幼い少女は横浜港に向かった。
見たことのない大きな船が停泊している。
岩倉具視が率いる使節団。
14歳を筆頭に、5人の女子が留学生として加わった。
もちろん、梅子は最年少。
不安を吹き飛ばすように、大きく、汽笛が鳴った。
近代女子教育の母、津田梅子は、7歳の時、ワシントンD.C.、ジョージタウンのランマン夫妻の家に預けられる。
子どものいない夫妻は、幼い梅子を我が子のように可愛がった。
留学生5人の少女のうち、年長の二人は、体調を崩し、日本に帰国。
梅子は、残った。
地元の小学校に入ったが、当然のように言葉がわからない。
同級生たちに笑われる。
着物でサンフランシスコに降り立った梅子たち。
留学生も日本人の女性も、ほとんど街にいなかった。
辞書を引いて、必死に、英語にくらいつく。
梅子の英語力は、日を追うごとに上達していった。
そんな少女の努力を、ランマン夫人は支えた。
ゆっくり話し、発音を直す。
何度も何度も、根気よく、直す。
梅子は、思った。
もしここに自分の家族がいたら、甘えてしまい、勉強をやめて、日本に帰るだろう。
甘えられない環境。そこに継続のヒントがあった。
そして環境より、もっと大切なものがあった。
それは、学びたいという意志。
「やり抜こう」と思う気持ちは、自分をひとつ上のステージに引き上げてくれる。
津田梅子は、およそ11年間の留学生活を送り、日本に帰国。17歳になっていた。
横浜港に着いて、懐かしい両親の顔を見る。
ここで、とてつもない事実を知った。
日本語が、話せない。
口をついて出てくるのは、全て英語だった。
幸い、父の津田仙は英語ができたので、集まった親戚たちに通訳する。
焦った。
日本語ができない自分が、この日本でどうやって生きていくのか。
梅子は、アメリカで、すでに思っていた。
「いつか必ず、日本に女性のための学校をつくりたい。
女性も男性と同じように知識や教養を身に着け、対等に働ける世の中にしたい」
そんな人生を賭ける夢も、どんどん遠のいていく。
日本語ができないイコール、就職ができない。
男性は、英語ができるだけでさまざまな要職についているのに、女性にはその門戸が開かれていなかった。
絶望の中、思い出した。
根気よく、自分に英語を教えてくれたランマン夫人。
「そうだ、ここで諦めてはいけない。この英語を生かせる道が、きっとあるはずだ」
日本語を学び、なんとか夢の実現のために頑張っていた梅子に出会いが待っていた。
あるパーティーでの再会。
同じ岩倉使節団にいた男性が声をかけてくれた。
「津田梅子さん、もしよかったら、我が家で英語の家庭教師をしていただけませんか?
我が家だけでなく、ニッポンには、あなたの力が必要だと思います」
その男性こそ、のちに初代総理大臣になる、伊藤博文だった。
「何かを始めることはやさしいが、それを継続することは難しい。
成功させることはなお難しい」
津田梅子


【ON AIR LIST】
◆CLOSER TO FINE / Indigo Girls
◆アルマ・マーター組曲 図書閲覧室 / リロイ・アンダーソン(作曲)、ニュートン・ウェイランド、ロチェスターポップス管弦楽団
◆EVERYDAY IS A WINDING ROAD / Sheryl Crow
◆Will / 浜崎あゆみ