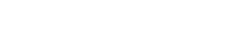第457話 信念を貫く
-【今年メモリアルなレジェンド篇】生物学者 レイチェル・カーソン-
[2024.06.01]
Podcast

©Nature and Science/Alamy/amanaimages
今年没後60年を迎えた、世界で初めて化学物質の危険性を告発した生物学者がいます。
レイチェル・カーソン。
アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身で、もともと生物学者だった彼女の名を一躍有名にしたのが、1962年に出版された『沈黙の春』という書物です。
一見、純文学ともとれるタイトル、「森の生き物が死滅し、春になっても声がしない」という観念的で、ポエジーな書き出しのこの本は、実は、世界で初めての環境問題告発本だったのです。
なぜ、こんなタイトルになったのか…。
レイチェルが訴えた最大のターゲットが、DDTという殺虫剤だったことが大きく関係しています。
第二次大戦中、アメリカ軍兵士の間で爆発的に蔓延した感染症。
戦争で命を落とすより、マラリアなどの感染症で命を落とす兵士が多いとされていましたが、DDTをふりかけることで、多くの兵士が死なずに済んだと報じられました。
その勢いを借りて、ノミなどの害虫を駆除する農薬として、アメリカ全土で大ヒット商品になったのです。
当初から人体や環境への影響が懸念されていましたが、DDTを製造する会社が大きな力を持ち、批判的な論文や報道は全て握り潰されてきたのです。
生物学者として、森を、海を、愛してやまないレイチェルは、食物連鎖の観点から、多くのデータを集め、DDT禁止を訴えることにしました。
彼女の論文は、どの出版社に持ち込んでも断られてしまいます。
化学物質を取り扱う企業の反対や訴訟を恐れてのことでした。
当時、彼女は体の不調を感じていました。
医者の診断は、手の施しようのない末期がん。
病気を隠しつつ、痛みに苦しみながら、レイチェルはこの本の出版を諦めませんでした。
しかし、思いはなかなか届かず、出版の夢は、やはりかなわないのかと絶望の淵に立ったとき、唯一、救いの手を差し伸べてくれたのが、時の大統領、ジョン・F・ケネディだったのです。
死の直前まで信念を貫いた賢人、レイチェル・カーソンが人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

©Randy Duchaine/Alamy/amanaimages
環境問題を世に訴えた最初のレジェンド、レイチェル・カーソンは1907年5月27日、アメリカ合衆国ペンシルベニア州スプリングデールで生まれた。
アメリカには、大恐慌の嵐が近づいていた。
レイチェルの父は、近くに工場が立つという噂を信じ、25万坪の森を買った。
借金までして購入したが、不景気で開発は頓挫。
一家は、農場を経営しつつ、貧しい暮らしを強いられる。
しかし、幼いレイチェルにとって森の中での生活は、楽園だった。
特に彼女が興味を持ったのが、音。
さまざまな鳥の声。ミツバチの羽音。木々のざわめき。
カエルの鳴き声、動物たちの足音。
草原に寝ころんで目を閉じると、森の香りとともに、音がやってくる。
聡明な母は、教えてくれた。
「あらゆる生き物が、お互い助け合って生きているのよ」
でも、残酷な場面を何度も見た。
虫をカエルが食べ、そのカエルを小鳥が食べ、その小鳥をハヤブサが食べ…。
「助け合う」という自然の仕組みがわからず、泣いてしまう。
母は、何も言わず、ただ、我が娘を抱きしめた。
ある夕暮れ時、幼いレイチェル・カーソンが家に帰ると、父と母が上機嫌でビールを飲んでいた。
父が言った。
「レイチェル! この森が売れるんだ、石炭会社がここを買ってくれることになったんだ!
貧乏とは、おさらばだ!」
森の木を全て伐採して、工場を造るのだという。
レイチェルは、泣きだしてしまう。
森がなくなる。
もうリスやトナカイ、鳥たちに会えなくなる。
そう思うと、涙があふれた。
それを見た父は、母に言った。
「このまま、貧しい暮らしでもいいかい?」
母は、大きくうなずいた。
父は、石炭会社の申し出を断ることにした。
レイチェルは、8歳の頃にはすでに文才を発揮した。
作文の成績は群を抜き、子ども向け雑誌に掲載されるほどだった。
彼女が特に好きだったのは、『ピーターラビットの物語』。
ウサギが友だちだった。
だから、食卓にウサギの肉が並ぶことが信じられなかった。
またしても、泣いた。
「こんなお肉、食べたくない!」
母はレイチェルに、食物連鎖について教えた。
この世の生き物は、基本、何かの命をいただかないと、生きてはいけないものだということ。
だからこそ、自然の生態系が健全でないと、口にするものが危険なものになっていくことを。
頭では、とうてい理解できない。
でも、母の教えは、彼女の心にしっかりと根付いた。
小、中、高校と優秀な成績を収め、そのほとんどを首席で通したレイチェル・カーソンだったが、彼女の足を引っ張ったのは貧しさだった。
奨学金をもらえるよう頑張り、家庭教師をしながら学校に通ったが、父が亡くなり、病弱な母を養うため、大学院は断念。
大学に残って研究職につきたかったが、お金のため、フルタイムの教職についた。
海に憧れ、海洋生物に興味を持った。
海の中の食物連鎖を学んだとき、幼い頃過ごした森を思い出した。
海も森も、同じだ。
小さな生物から大きな生き物まで、みんなが連鎖しあい、影響し合って生きている。
もし人間が、その連鎖を壊すようなものを開発してしまったら…。
環境破壊という言葉がまだ浸透していない時代に、彼女は畏れていた。
人間の驕り、傲慢を。
彼女の信念の奥底には、いつも、森が生きていた。
小さいものから大きなものまで、みんなで助け合い、生きている姿を感覚的に知っていた。
のちに、彼女が提出したデータが事実と違うという指摘もあった。
それでも、彼女が命を賭けて発言した環境問題は、今こそ、私たちの心に突き刺さる。
地球の美しさと神秘を感じることができる人は、科学者であろうがなかろうが、人生に絶望して疲れたり、孤独に悩むことは、けっしてないでしょう。
レイチェル・カーソン

©Danita Delimont/Alamy/amanaimages
【ON AIR LIST】
◆BIG YELLOW TAXI / Joni Mitchell
◆ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品61 第3楽章 / ベートーヴェン(作曲)、イツァーク・パールマン、ダニエル・バレンボイム(指揮)、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
◆WHO'S GONNA STAND UP / Neil Young
◆A SENSE OF WONDER / Van Morrison