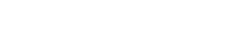第455話 今日一日を精一杯生きる
-【福井にまつわるレジェンド篇】蘭方医 杉田玄白-
[2024.05.18]
Podcast

福井県小浜市にゆかりのある、『解体新書』で有名な蘭方医がいます。
杉田玄白(すぎた・げんぱく)。
蘭方医とは、江戸時代に西洋医学を学んだ日本人医師のこと。
若狭国小浜藩の、藩専任の医者だった父の影響で、幼くして医学が身近にあった玄白にとっての最大の関心事は、人体の中身でした。
当時は、中国から伝わった漢方が主流。
人間には五臓六腑があり、それらの調子が悪くなれば、煎じ薬で治すという考えが王道でした。
あくまで人間の外、表面を診断し、処方する。
しかし、初めて、腑分け、すなわち「解剖」に立ち会った玄白は、愕然とするのです。
「書物にある五臓六腑とは、全然違うじゃないか!
そもそも人間の体の仕組みがわからなくて、どうして病と闘えるというんだ!」
中国伝来の医学書と違い、オランダ語で書かれた、『ターヘル・アナトミア』という本の解剖図は、見事に人間の内臓、骨格、筋肉までもが示されていました。
「これだ! この本だ!
これを翻訳して全国の医者や学者に読ませないと、日本の医学は、間違った方向に進んでしまう!」
玄白は、同じ漢方医の前野良沢(まえの・りょうたく)、中川淳庵(なかがわ・じゅんあん)らと共に、『ターヘル・アナトミア』の翻訳に着手するのです。
翻訳は、難航を極めます。
そもそも、オランダ語がわからない、専門用語も知らない。
すなわち、オランダ語がわかっても、日本にはその用語がない。
たとえば、「視聴、言動を司り、かつ痛痒、あるいは感熱を知る」、すなわち「見たり聞いたり、しゃべったり、痛さ 痒さ 熱さを感じるもの」というのは、従来の日本の医学にはない用語でした。
これを玄白は、まるで神様が持つ器官のようだということで「神経」と名付けました。
3年5か月をかけて完成した翻訳本、その名は『解体新書』。
この本をめぐっては、玄白と前野良沢の間で意見が分かれました。
まだ、この翻訳には不備があると言って出版を嫌がった良沢。
完全を目指すより、一刻も早くこの本を世に出すべきだと主張する玄白。
玄白には、遠くの未来より、今、今日が大切だったのです。
日本の医学に新しい道を切り開いた賢人・杉田玄白が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

『解体新書』の翻訳で知られる杉田玄白は、1733年、江戸、牛込に生まれた。
父は、若狭国小浜藩の藩医。
時に藩主や、幕府の重鎮の診察も行う名医だった。
しかし、母は、玄白を生んだ際、難産の末、亡くなる。
玄白は、母を知らずに育った。
幼い玄白は、飼っていた犬が病気にかかったのを知って、父に懇願する。
「父上、この犬をお助けください! 父上なら、きっと治してくださいますよね?」
しかし、父は、犬に触ろうともしない。
なぜかと尋ねると、父は言った。
「お殿様をおさわり申し上げるこの手を、動物に使うわけにはいくまい」
玄白は、理解できなかった。
犬もまた命を持つ生き物。手が汚れれば洗えばいいのではないか。
命を助けることに、どうして区別や差別があるのか、よくわからなかった。
大切な飼い犬は、苦しんだすえ、亡くなってしまった。
最後にゆっくり目を閉じる、愛犬。
なぜ父は、助けなかったのか。
目の前で消えていく命。
このとき感じた違和感を、玄白は、生涯忘れなかった。

杉田玄白の父は、出産の際に亡くなった妻の面影を、我が子に重ね合わせるように、玄白を大切に育てた。
物心がつくと、医術を教え、学問の大切さを叩きこむ。
玄白が8歳の時、一家は若狭国小浜に移る。
玄白は、最も多感な幼少期を小浜で過ごす。
父の名医としての評判は、またたく間に藩内に広がった。
しかし玄白は、兄を、そして義理の母を、相次いで亡くす。
名医とはいえ、はしかという流行り病になすすべもなかった。
玄白は義理の母を、最後まで「お母さま」と呼べなかった。
そのことが心残りで、後悔した。
「たった一度でいい、そう呼んであげたかった。それを母が望んでいることを、知っていたのに…」
後悔は、取り返しがつかない。
だったら後悔しないように、今を精一杯生きるしかない。
20歳のとき、父の跡を継ぎ、小浜藩の藩医になった。
江戸の小浜藩の上屋敷で、医者として勤務するよう命じられる。
玄白には、医学を学べば学ぶほど、解せない一点があった。
人体の中身を知らないひとが、なぜ、こんなにも多いのか。
中身を知らずして、なぜ、病と闘えるのか。
そんな22歳の玄白に、またとない機会が訪れる。
処刑された罪人の腑分けに立ち会わないかという誘いだった。
杉田玄白の迷いは、吹っ切れた。
『ターヘル・アナトミア』。
オランダ語で書かれたこの解剖書こそ、自分が望んでいたものだった。
蘭学に長けた医者仲間の先輩、前野良沢を誘って翻訳に着手。
しかし、良沢と玄白は、当初から意見の相違でぶつかる。
何事も完璧を目指し、後世に名が残るのであれば、間違いは犯したくないという良沢。
一方の玄白は、今このときも、適切な治療を受けずに亡くなっていく患者の存在を感じ、一刻も早い、翻訳書の完成を訴える。
3年5か月経って、おおよその翻訳を終えても、良沢は、出版を拒んだ。
「これを出しては、私たちの功績に傷がつきます」
10歳も年上の良沢に、玄白はくってかかる。
「良沢さん! 遠い未来に残る私たちの名誉など、どうでもいいのです。
大切なのは今です。今、目の前にいる患者です!
私は、幼い頃より、多くの親しいひとを亡くしてきました。
もうあんな思いは嫌です。
お願いです。今すぐ、出版させてください!!」
良沢は、『解体新書』の奥付に、自らの名前を記さないことを条件に、出版を嫌々承知した。
玄白の英断のおかげで、多くの人命が助かった。
さらに、蘭学の評価が高まり、西洋の文化芸術への扉が開く。
『昨日の非は悔恨すべからず、明日これを念慮すべし』
杉田玄白

【ON AIR LIST】
◆Human Body~I L-O-V-E U / TAKE 6
◆グレゴリオ聖歌「命の中で」 / オランダ・バロック
◆Journey Into The Body / 川井憲次
◆風は西から / 奥田民生
杉田玄白(すぎた・げんぱく)。
蘭方医とは、江戸時代に西洋医学を学んだ日本人医師のこと。
若狭国小浜藩の、藩専任の医者だった父の影響で、幼くして医学が身近にあった玄白にとっての最大の関心事は、人体の中身でした。
当時は、中国から伝わった漢方が主流。
人間には五臓六腑があり、それらの調子が悪くなれば、煎じ薬で治すという考えが王道でした。
あくまで人間の外、表面を診断し、処方する。
しかし、初めて、腑分け、すなわち「解剖」に立ち会った玄白は、愕然とするのです。
「書物にある五臓六腑とは、全然違うじゃないか!
そもそも人間の体の仕組みがわからなくて、どうして病と闘えるというんだ!」
中国伝来の医学書と違い、オランダ語で書かれた、『ターヘル・アナトミア』という本の解剖図は、見事に人間の内臓、骨格、筋肉までもが示されていました。
「これだ! この本だ!
これを翻訳して全国の医者や学者に読ませないと、日本の医学は、間違った方向に進んでしまう!」
玄白は、同じ漢方医の前野良沢(まえの・りょうたく)、中川淳庵(なかがわ・じゅんあん)らと共に、『ターヘル・アナトミア』の翻訳に着手するのです。
翻訳は、難航を極めます。
そもそも、オランダ語がわからない、専門用語も知らない。
すなわち、オランダ語がわかっても、日本にはその用語がない。
たとえば、「視聴、言動を司り、かつ痛痒、あるいは感熱を知る」、すなわち「見たり聞いたり、しゃべったり、痛さ 痒さ 熱さを感じるもの」というのは、従来の日本の医学にはない用語でした。
これを玄白は、まるで神様が持つ器官のようだということで「神経」と名付けました。
3年5か月をかけて完成した翻訳本、その名は『解体新書』。
この本をめぐっては、玄白と前野良沢の間で意見が分かれました。
まだ、この翻訳には不備があると言って出版を嫌がった良沢。
完全を目指すより、一刻も早くこの本を世に出すべきだと主張する玄白。
玄白には、遠くの未来より、今、今日が大切だったのです。
日本の医学に新しい道を切り開いた賢人・杉田玄白が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

『解体新書』の翻訳で知られる杉田玄白は、1733年、江戸、牛込に生まれた。
父は、若狭国小浜藩の藩医。
時に藩主や、幕府の重鎮の診察も行う名医だった。
しかし、母は、玄白を生んだ際、難産の末、亡くなる。
玄白は、母を知らずに育った。
幼い玄白は、飼っていた犬が病気にかかったのを知って、父に懇願する。
「父上、この犬をお助けください! 父上なら、きっと治してくださいますよね?」
しかし、父は、犬に触ろうともしない。
なぜかと尋ねると、父は言った。
「お殿様をおさわり申し上げるこの手を、動物に使うわけにはいくまい」
玄白は、理解できなかった。
犬もまた命を持つ生き物。手が汚れれば洗えばいいのではないか。
命を助けることに、どうして区別や差別があるのか、よくわからなかった。
大切な飼い犬は、苦しんだすえ、亡くなってしまった。
最後にゆっくり目を閉じる、愛犬。
なぜ父は、助けなかったのか。
目の前で消えていく命。
このとき感じた違和感を、玄白は、生涯忘れなかった。

杉田玄白の父は、出産の際に亡くなった妻の面影を、我が子に重ね合わせるように、玄白を大切に育てた。
物心がつくと、医術を教え、学問の大切さを叩きこむ。
玄白が8歳の時、一家は若狭国小浜に移る。
玄白は、最も多感な幼少期を小浜で過ごす。
父の名医としての評判は、またたく間に藩内に広がった。
しかし玄白は、兄を、そして義理の母を、相次いで亡くす。
名医とはいえ、はしかという流行り病になすすべもなかった。
玄白は義理の母を、最後まで「お母さま」と呼べなかった。
そのことが心残りで、後悔した。
「たった一度でいい、そう呼んであげたかった。それを母が望んでいることを、知っていたのに…」
後悔は、取り返しがつかない。
だったら後悔しないように、今を精一杯生きるしかない。
20歳のとき、父の跡を継ぎ、小浜藩の藩医になった。
江戸の小浜藩の上屋敷で、医者として勤務するよう命じられる。
玄白には、医学を学べば学ぶほど、解せない一点があった。
人体の中身を知らないひとが、なぜ、こんなにも多いのか。
中身を知らずして、なぜ、病と闘えるのか。
そんな22歳の玄白に、またとない機会が訪れる。
処刑された罪人の腑分けに立ち会わないかという誘いだった。
杉田玄白の迷いは、吹っ切れた。
『ターヘル・アナトミア』。
オランダ語で書かれたこの解剖書こそ、自分が望んでいたものだった。
蘭学に長けた医者仲間の先輩、前野良沢を誘って翻訳に着手。
しかし、良沢と玄白は、当初から意見の相違でぶつかる。
何事も完璧を目指し、後世に名が残るのであれば、間違いは犯したくないという良沢。
一方の玄白は、今このときも、適切な治療を受けずに亡くなっていく患者の存在を感じ、一刻も早い、翻訳書の完成を訴える。
3年5か月経って、おおよその翻訳を終えても、良沢は、出版を拒んだ。
「これを出しては、私たちの功績に傷がつきます」
10歳も年上の良沢に、玄白はくってかかる。
「良沢さん! 遠い未来に残る私たちの名誉など、どうでもいいのです。
大切なのは今です。今、目の前にいる患者です!
私は、幼い頃より、多くの親しいひとを亡くしてきました。
もうあんな思いは嫌です。
お願いです。今すぐ、出版させてください!!」
良沢は、『解体新書』の奥付に、自らの名前を記さないことを条件に、出版を嫌々承知した。
玄白の英断のおかげで、多くの人命が助かった。
さらに、蘭学の評価が高まり、西洋の文化芸術への扉が開く。
『昨日の非は悔恨すべからず、明日これを念慮すべし』
杉田玄白

【ON AIR LIST】
◆Human Body~I L-O-V-E U / TAKE 6
◆グレゴリオ聖歌「命の中で」 / オランダ・バロック
◆Journey Into The Body / 川井憲次
◆風は西から / 奥田民生