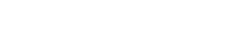第454話 周りのひとを幸せにする
-【福井にまつわるレジェンド篇】慈善活動家 林歌子-
[2024.05.11]
Podcast

福井県出身の、児童福祉の先駆者がいます。
林歌子(はやし・うたこ)。
明治時代から、大正、昭和と、社会事業活動に生涯を捧げた歌子の功績は、大きく3つあります。
ひとつは、アルコール依存症で悩むひとのための禁酒に関する活動。
2つ目は、女性の人権尊重のもとに遊郭廃止を訴え続けたこと。
そして3つ目が、孤児院を設立し、恵まれない子どもたちの生活や心のケアのために尽力したこと。
当時は、男性の慈善活動でさえ、思うように世間に受け入れられなかった時代。
女性の歌子に至っては、疎んじられるどころか、狂人というレッテルを貼られ、ひどい仕打ちを受けたのです。
それでも、歌子は、活動を止めませんでした。
稼いだ金、集めた寄付金は、惜しげもなく、全部、困っているひとのため、慈善活動のために差し出したのです。
彼女は、特別、強く、清い心を持ったひとだったのでしょうか。
評論家・小林秀雄の妹で劇作家の、高見澤潤子(たかみざわ・じゅんこ)は、小説『林歌子の生涯 涙とともに蒔くものは』の中で、歌子も、迷い、惑い、葛藤を繰り返す、ひとりの人間に過ぎなかったことを描いています。
さらに、小橋勝之助(こばし・かつのすけ)、小橋実之助(こばし・じつのすけ)という兄弟との出会いがなければ、歌子の偉業はなかったかもしれません。
大阪にある彼女の墓石には、こんな言葉が刻まれています。
「暁の ねざめ静かに祈るなり おのがなすべき 今日のつとめを」
歌子にとって、なすべきつとめとは「周りのひとを幸せにすること」でした。
なぜ、彼女はそう考えるようになったのでしょうか。
幾多の試練を乗り越えたレジェンド・林歌子が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

日本の女性慈善活動家の草分け、林歌子は、1865年1月11日、越前国大野郡、現在の福井県大野市で生まれた。
父は藩に仕える下級武士。
向学心に燃え、いずれ長崎に留学したいと勉学に励んでいた。
しかし、歌子が生まれて3年後。
大きな出来事が二つ起きた。
ひとつは、明治維新。
藩士は全ての権利を奪われ、父はわずかな貯金で金融業を始める。
そして、もうひとつの出来事が、妻、すなわち歌子の母の死。
長崎への留学どころか、日々の暮らしや子育ての重圧が、一気に父を追いつめる。
父は、自らの夢を諦めると同時に、その思いを、歌子に託すことにした。
歌子は、物心ついたときから、優秀だった。
それを悟った父は、一日中、読み書き、そろばんを教えた。
近所の友だちと遊ぶことはない。
ひたすら家にこもり、勉強、勉強。
4歳のときには、『論語』を精読し、暗記していた。
歌子は、母のいない寂しさを埋めるかのように、孔子の教えに没入していく。
孔子の「忠恕(ちゅうじょ)」という考え方が彼女にしみこむ。
「忠」は、偽らざる心。「恕」は、他人を思いやる心。
のちにキリスト教の洗礼を受ける歌子が、このとき、儒学の教えに学んだことは、一生を左右する大切な出会いだった。
林歌子は、幼くして、勉学の楽しさを知った。
一方で、他の子どもたちと遊ぶことのない孤独も感じていた。
父が、再婚。
継母は、歌子に、掃除や服の繕いを命じる。
歌子は、嫌ではなかった。
むしろ、他の女の子たちと同じようなことができて、うれしかった。
喜々として、廊下の雑巾がけをしているときだった。
それを見た父は、烈火のごとく、継母を叱責した。
「何をさせているんだ! 歌子に、他の女の子がやるようなことをやらせるな!
歌子は、勉強だ! 勉強だけしていればいいんだ!」
自分のせいで、継母が怒られる。
申し訳なくて、顔が真っ赤になった。
ただ、雑巾がけが楽しい、やらせてほしいとは、言えなかった。
他の子と一緒でいたい、でも、父を喜ばす特別な自分でいたい、二つの思いで歌子は揺れた。
父の考え方はこうだった。
「女子に学問がいらぬなどと言う輩がいるが、とんでもない。
子どもを教育するのは、母だ。母に学問がない国は、滅びる!」
先鋭的なようで、保守的。
さらに自分の夢をひたすら娘に託す。
12歳で福井県立女子師範学校に入学した歌子に、父を喜ばす最大の機会が訪れた。
明治天皇の北陸巡幸。
それに合わせて教育振興のため、学校に政府の重鎮・大隈重信がやってくることになった。
大隈重信の前で、講義をする生徒が二人選ばれる。
そのひとりが、林歌子だった。
林歌子は、明治時代の歴史書の大ベストセラー『日本外史』について、講義した。
緊張はしたが、その場に立てた自分が誇らしかった。
客席に、涙ぐみながら聞く、父の姿が見えた。
講義が終わると、拍手が起きた。
大隈重信は、壇上に立ち、歌子の講義をこう評した。
「栴檀(せんだん)は、双葉より芳し、ですな。
林歌子さんは、立派な女性になるでしょう」
栴檀とは、白檀(びゃくだん)のこと。
白檀は、まだ双葉の頃から、かぐわしい香りを放つので、賢人は幼き時よりその片鱗を感じる、という例えに使われる。
父が喜ぶ姿を見て、歌子は思った。
「そうか、私はどうやら、身近な周りのひとが喜んだり、嬉しそうな顔をしているのが好きなんだ。
自分の幸せは、自分だけではつくれない。
周りが幸せでないと、私はちっとも幸せではないんだ」
それは、師範学校を出て、小学校の教師になったときも同じだった。
目の前の子どもたちが嬉しそうな顔をしていないと、毎日が楽しくなかった。
恵まれない子どもたちのために孤児院をつくりたいという、小橋兄弟に出会ったときも、高邁な思想より、まず、目の前にいる兄弟の役に立ちたいと願った。
林歌子は知っていた。
壮大な思想も、抽象的な理想も、ひとを動かさない。
大切なのは、目の前のひとを幸せにするために、行動すること。

【ON AIR LIST】
◆星の流れに / ちあきなおみ
◆BELIEVE IN HUMANITY / Carole King
◆WHAT ABOUT THE CHILDREN / Gary Clark Jr. & Stevie Wonder
林歌子(はやし・うたこ)。
明治時代から、大正、昭和と、社会事業活動に生涯を捧げた歌子の功績は、大きく3つあります。
ひとつは、アルコール依存症で悩むひとのための禁酒に関する活動。
2つ目は、女性の人権尊重のもとに遊郭廃止を訴え続けたこと。
そして3つ目が、孤児院を設立し、恵まれない子どもたちの生活や心のケアのために尽力したこと。
当時は、男性の慈善活動でさえ、思うように世間に受け入れられなかった時代。
女性の歌子に至っては、疎んじられるどころか、狂人というレッテルを貼られ、ひどい仕打ちを受けたのです。
それでも、歌子は、活動を止めませんでした。
稼いだ金、集めた寄付金は、惜しげもなく、全部、困っているひとのため、慈善活動のために差し出したのです。
彼女は、特別、強く、清い心を持ったひとだったのでしょうか。
評論家・小林秀雄の妹で劇作家の、高見澤潤子(たかみざわ・じゅんこ)は、小説『林歌子の生涯 涙とともに蒔くものは』の中で、歌子も、迷い、惑い、葛藤を繰り返す、ひとりの人間に過ぎなかったことを描いています。
さらに、小橋勝之助(こばし・かつのすけ)、小橋実之助(こばし・じつのすけ)という兄弟との出会いがなければ、歌子の偉業はなかったかもしれません。
大阪にある彼女の墓石には、こんな言葉が刻まれています。
「暁の ねざめ静かに祈るなり おのがなすべき 今日のつとめを」
歌子にとって、なすべきつとめとは「周りのひとを幸せにすること」でした。
なぜ、彼女はそう考えるようになったのでしょうか。
幾多の試練を乗り越えたレジェンド・林歌子が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

日本の女性慈善活動家の草分け、林歌子は、1865年1月11日、越前国大野郡、現在の福井県大野市で生まれた。
父は藩に仕える下級武士。
向学心に燃え、いずれ長崎に留学したいと勉学に励んでいた。
しかし、歌子が生まれて3年後。
大きな出来事が二つ起きた。
ひとつは、明治維新。
藩士は全ての権利を奪われ、父はわずかな貯金で金融業を始める。
そして、もうひとつの出来事が、妻、すなわち歌子の母の死。
長崎への留学どころか、日々の暮らしや子育ての重圧が、一気に父を追いつめる。
父は、自らの夢を諦めると同時に、その思いを、歌子に託すことにした。
歌子は、物心ついたときから、優秀だった。
それを悟った父は、一日中、読み書き、そろばんを教えた。
近所の友だちと遊ぶことはない。
ひたすら家にこもり、勉強、勉強。
4歳のときには、『論語』を精読し、暗記していた。
歌子は、母のいない寂しさを埋めるかのように、孔子の教えに没入していく。
孔子の「忠恕(ちゅうじょ)」という考え方が彼女にしみこむ。
「忠」は、偽らざる心。「恕」は、他人を思いやる心。
のちにキリスト教の洗礼を受ける歌子が、このとき、儒学の教えに学んだことは、一生を左右する大切な出会いだった。
林歌子は、幼くして、勉学の楽しさを知った。
一方で、他の子どもたちと遊ぶことのない孤独も感じていた。
父が、再婚。
継母は、歌子に、掃除や服の繕いを命じる。
歌子は、嫌ではなかった。
むしろ、他の女の子たちと同じようなことができて、うれしかった。
喜々として、廊下の雑巾がけをしているときだった。
それを見た父は、烈火のごとく、継母を叱責した。
「何をさせているんだ! 歌子に、他の女の子がやるようなことをやらせるな!
歌子は、勉強だ! 勉強だけしていればいいんだ!」
自分のせいで、継母が怒られる。
申し訳なくて、顔が真っ赤になった。
ただ、雑巾がけが楽しい、やらせてほしいとは、言えなかった。
他の子と一緒でいたい、でも、父を喜ばす特別な自分でいたい、二つの思いで歌子は揺れた。
父の考え方はこうだった。
「女子に学問がいらぬなどと言う輩がいるが、とんでもない。
子どもを教育するのは、母だ。母に学問がない国は、滅びる!」
先鋭的なようで、保守的。
さらに自分の夢をひたすら娘に託す。
12歳で福井県立女子師範学校に入学した歌子に、父を喜ばす最大の機会が訪れた。
明治天皇の北陸巡幸。
それに合わせて教育振興のため、学校に政府の重鎮・大隈重信がやってくることになった。
大隈重信の前で、講義をする生徒が二人選ばれる。
そのひとりが、林歌子だった。
林歌子は、明治時代の歴史書の大ベストセラー『日本外史』について、講義した。
緊張はしたが、その場に立てた自分が誇らしかった。
客席に、涙ぐみながら聞く、父の姿が見えた。
講義が終わると、拍手が起きた。
大隈重信は、壇上に立ち、歌子の講義をこう評した。
「栴檀(せんだん)は、双葉より芳し、ですな。
林歌子さんは、立派な女性になるでしょう」
栴檀とは、白檀(びゃくだん)のこと。
白檀は、まだ双葉の頃から、かぐわしい香りを放つので、賢人は幼き時よりその片鱗を感じる、という例えに使われる。
父が喜ぶ姿を見て、歌子は思った。
「そうか、私はどうやら、身近な周りのひとが喜んだり、嬉しそうな顔をしているのが好きなんだ。
自分の幸せは、自分だけではつくれない。
周りが幸せでないと、私はちっとも幸せではないんだ」
それは、師範学校を出て、小学校の教師になったときも同じだった。
目の前の子どもたちが嬉しそうな顔をしていないと、毎日が楽しくなかった。
恵まれない子どもたちのために孤児院をつくりたいという、小橋兄弟に出会ったときも、高邁な思想より、まず、目の前にいる兄弟の役に立ちたいと願った。
林歌子は知っていた。
壮大な思想も、抽象的な理想も、ひとを動かさない。
大切なのは、目の前のひとを幸せにするために、行動すること。

【ON AIR LIST】
◆星の流れに / ちあきなおみ
◆BELIEVE IN HUMANITY / Carole King
◆WHAT ABOUT THE CHILDREN / Gary Clark Jr. & Stevie Wonder