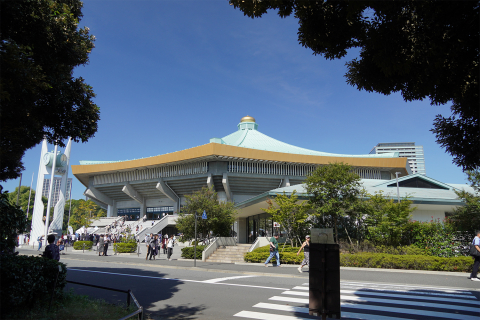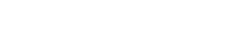第442話 責任感を持つことで成長する
-【京都にまつわるレジェンド篇】女優 高峰秀子-
[2024.02.17]
Podcast

今年、生誕100年を迎える、伝説の大女優がいます。
高峰秀子(たかみね・ひでこ)。
1924年3月27日生まれの彼女の「高峰秀子生誕100年プロジェクト」は、昨年10月から始まり、今年もさまざまな企画が目白押しです。
彼女が愛した「きもの展」、エッセイでも綴られた、美学をひもとく展示や写真展。
もちろん、出演した映画の上映会も多数予定されています。
戦前の無声映画の時代、5歳で銀幕デビューを果たしてから、およそ50年間、300本以上の作品に出た高峰は、今も多くのファンを魅了してやみません。
また、エッセイストとして、多くの本を執筆。
軽妙で含羞と含蓄があふれる筆運びは、時代に色あせることなく、健在です。
4歳のとき、結核で母を亡くし、父の妹に養子に出された高峰。
5歳で、いきなり映画の世界に放り込まれ、以来、自分が役者としての素養があるやなしやの自省するいとまもなく、ひたすら走り続けてきたのです。
5歳のとき、いきなり参加した映画のオーディションに合格。
お金を出してでも我が子を映画に出したいというお金持ちが多い中、高峰の出演作は絶えません。
男の子の役までも、頭を丸刈りにされて依頼がきてしまう。
養母は、まわりからずいぶん嫌味を言われ、いじめられたといいます。
子役の役者に多額の出演料がもらえることはなく、暮らしは、貧しく、質素。
養父は全国を飛び歩く興行師、養母は内職をしていました。
そんな中、京都の賀茂川のほとりから撮影所に通うのは楽しかったと、エッセイに書いています。
撮影所では、駄々をこね、お菓子をもらったり、多くの大人たちと遊び、誰にでも可愛がられました。
ほとんど学校にも行けず、眠い目をこすりながら撮影所に通う日々。
そんな幼い高峰の心には、自分を育ててくれている母に、何か役に立つことをしたいという思いが、ささやかに、でも確実に芽生えていったのです。
戦前戦後を駆け抜けたレジェンド・高峰秀子が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

日本初の総天然色映画『カルメン故郷に帰る』に主演した、伝説の女優・高峰秀子は、1924年に北海道函館市に生まれた。
家は、祖父の代から続く料亭。
祖父は町の重鎮。いくつものお店を持っていた。
何不自由のない暮らしの中、明るく育つ。
しかし、4歳で母を亡くし、父の妹夫婦の養子になったことで、高峰の運命が大きく変わる。
いきなりの東京。
甘えたい盛りに、突然の孤独。
ただ、ここで生きていかなくてはいけないという覚悟だけはあった。
養父に手をひかれていった蒲田撮影所。
同じアパートの住人に俳優がいた。
そのつてで、訪れた見学。
着飾った子どもたちが、50人ほど集まっていた。
彼らは、やはり着飾り、派手な化粧をほどこした母親に連れられていた。
秀子は、メリンス生地のブドウ柄の粗末な着物に、白いエプロン。
風采のあがらない養父と一緒に、場違いな感じで立っている。
なぜか、秀子は列に並ばされた。
それは『母』という映画のオーディションだった。
怖そうな大人たちが、ジロジロと子どもたちを見ながら、二度三度、往復する。
ゴルフズボンをはいた太鼓腹の男が、秀子の前で立ち止まった。
彼こそ、巨匠・野村芳太郎(のむら・よしたろう)の父で、日本映画の基礎を築いた名匠、野村芳亭(のむら・ほうてい)だった。
5歳の高峰秀子が、わけもわからず並んだオーディションの列。
映画監督・野村芳亭は、一瞬で「この子しかいない!」と思った。
他の子どもと違い、しょんぼりとしていて、哀しい。
でも、笑顔が愛くるしい。
『母』という映画は、銀行家の夫を亡くし、幼い子どもを育てるために、家政婦として自立していく母親の姿を描く人情ばなし。
高峰は、いきなり綺麗な着物を着せられたり、突然、顔をおしろいで真っ白にされたり、意味もわからず、ただ、カメラの前に立った。
愛嬌と度胸の良さは、かつて祖父が経営する料亭のお座敷で、芸子さんたちに交じり、遊んでいたからだろうか。
監督に「哀しい顔!」と言われれば、亡くなった実の母を思い浮かべた。
高峰には、天性の明るさがあった。
誰にでも愛される笑顔を持っていた。
主演の人気女優・川田芳子(かわだ・よしこ)は、幼い高峰を可愛がった。
家族に恵まれなかった分、撮影所で大切にされた。
その後、役は絶えない。ただ、半分以上が男の子の役だった。
撮影が忙しく、ほとんど学校に行けない。
毎日会うひとのほとんどが大人。
いくつも役を演じているうちに、「なぜ、自分はここにいるのか」「なぜ、自分は演じなくてはならないのか」、漠然と考えるようになった。
高峰秀子が、なぜ演じるのか、と考えたとき、浮かぶのは、自分を育ててくれる養母の顔だった。
貧しいながら、大切にしてくれた。
みぞれまじりの寒い日のロケ。
母は、高峰の手を、自らのあたたかいふところに入れて、必死にあたためてくれた。
うれしかった。母のために頑張ろうと思った。
7歳のときには、母は自分の着物や指輪を全部売って、高峰を綺麗に着飾った。有難かった。
誰かのために生きるということ。
ひとりでは生きていけない時代を支えてくれた母に、感謝の気持ちがあふれ出る。
「今度は、私が母を助ける」
責任感が芽生えたとき、高峰は初めて、ほんとうの女優になった。
目の前のひとを幸せにする。
それが、やがてぐるりと回りまわって、自分に返ってくる。
撮影で長く家を空ければ空けるほど、早く母に会いたくなった。
母の喜ぶ顔が見たいと願った。
漠然とした理想や夢のために、ひとは戦えない。
高峰秀子が、50年間、女優を続けられたわけが、そこにある。
彼女は、ただ、身近なひと、目の前のひとを幸せにしたいと願った。

【ON AIR LIST】
◆燦めく星座(映画『秀子の応援団長』挿入歌) / 灰田勝彦
◆とっても綺麗 / イヴ・モンタン
◆WHAT WAS I MADE FOR? / Billie Eilish
◆銀座カンカン娘 / 高峰秀子
高峰秀子(たかみね・ひでこ)。
1924年3月27日生まれの彼女の「高峰秀子生誕100年プロジェクト」は、昨年10月から始まり、今年もさまざまな企画が目白押しです。
彼女が愛した「きもの展」、エッセイでも綴られた、美学をひもとく展示や写真展。
もちろん、出演した映画の上映会も多数予定されています。
戦前の無声映画の時代、5歳で銀幕デビューを果たしてから、およそ50年間、300本以上の作品に出た高峰は、今も多くのファンを魅了してやみません。
また、エッセイストとして、多くの本を執筆。
軽妙で含羞と含蓄があふれる筆運びは、時代に色あせることなく、健在です。
4歳のとき、結核で母を亡くし、父の妹に養子に出された高峰。
5歳で、いきなり映画の世界に放り込まれ、以来、自分が役者としての素養があるやなしやの自省するいとまもなく、ひたすら走り続けてきたのです。
5歳のとき、いきなり参加した映画のオーディションに合格。
お金を出してでも我が子を映画に出したいというお金持ちが多い中、高峰の出演作は絶えません。
男の子の役までも、頭を丸刈りにされて依頼がきてしまう。
養母は、まわりからずいぶん嫌味を言われ、いじめられたといいます。
子役の役者に多額の出演料がもらえることはなく、暮らしは、貧しく、質素。
養父は全国を飛び歩く興行師、養母は内職をしていました。
そんな中、京都の賀茂川のほとりから撮影所に通うのは楽しかったと、エッセイに書いています。
撮影所では、駄々をこね、お菓子をもらったり、多くの大人たちと遊び、誰にでも可愛がられました。
ほとんど学校にも行けず、眠い目をこすりながら撮影所に通う日々。
そんな幼い高峰の心には、自分を育ててくれている母に、何か役に立つことをしたいという思いが、ささやかに、でも確実に芽生えていったのです。
戦前戦後を駆け抜けたレジェンド・高峰秀子が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

日本初の総天然色映画『カルメン故郷に帰る』に主演した、伝説の女優・高峰秀子は、1924年に北海道函館市に生まれた。
家は、祖父の代から続く料亭。
祖父は町の重鎮。いくつものお店を持っていた。
何不自由のない暮らしの中、明るく育つ。
しかし、4歳で母を亡くし、父の妹夫婦の養子になったことで、高峰の運命が大きく変わる。
いきなりの東京。
甘えたい盛りに、突然の孤独。
ただ、ここで生きていかなくてはいけないという覚悟だけはあった。
養父に手をひかれていった蒲田撮影所。
同じアパートの住人に俳優がいた。
そのつてで、訪れた見学。
着飾った子どもたちが、50人ほど集まっていた。
彼らは、やはり着飾り、派手な化粧をほどこした母親に連れられていた。
秀子は、メリンス生地のブドウ柄の粗末な着物に、白いエプロン。
風采のあがらない養父と一緒に、場違いな感じで立っている。
なぜか、秀子は列に並ばされた。
それは『母』という映画のオーディションだった。
怖そうな大人たちが、ジロジロと子どもたちを見ながら、二度三度、往復する。
ゴルフズボンをはいた太鼓腹の男が、秀子の前で立ち止まった。
彼こそ、巨匠・野村芳太郎(のむら・よしたろう)の父で、日本映画の基礎を築いた名匠、野村芳亭(のむら・ほうてい)だった。
5歳の高峰秀子が、わけもわからず並んだオーディションの列。
映画監督・野村芳亭は、一瞬で「この子しかいない!」と思った。
他の子どもと違い、しょんぼりとしていて、哀しい。
でも、笑顔が愛くるしい。
『母』という映画は、銀行家の夫を亡くし、幼い子どもを育てるために、家政婦として自立していく母親の姿を描く人情ばなし。
高峰は、いきなり綺麗な着物を着せられたり、突然、顔をおしろいで真っ白にされたり、意味もわからず、ただ、カメラの前に立った。
愛嬌と度胸の良さは、かつて祖父が経営する料亭のお座敷で、芸子さんたちに交じり、遊んでいたからだろうか。
監督に「哀しい顔!」と言われれば、亡くなった実の母を思い浮かべた。
高峰には、天性の明るさがあった。
誰にでも愛される笑顔を持っていた。
主演の人気女優・川田芳子(かわだ・よしこ)は、幼い高峰を可愛がった。
家族に恵まれなかった分、撮影所で大切にされた。
その後、役は絶えない。ただ、半分以上が男の子の役だった。
撮影が忙しく、ほとんど学校に行けない。
毎日会うひとのほとんどが大人。
いくつも役を演じているうちに、「なぜ、自分はここにいるのか」「なぜ、自分は演じなくてはならないのか」、漠然と考えるようになった。
高峰秀子が、なぜ演じるのか、と考えたとき、浮かぶのは、自分を育ててくれる養母の顔だった。
貧しいながら、大切にしてくれた。
みぞれまじりの寒い日のロケ。
母は、高峰の手を、自らのあたたかいふところに入れて、必死にあたためてくれた。
うれしかった。母のために頑張ろうと思った。
7歳のときには、母は自分の着物や指輪を全部売って、高峰を綺麗に着飾った。有難かった。
誰かのために生きるということ。
ひとりでは生きていけない時代を支えてくれた母に、感謝の気持ちがあふれ出る。
「今度は、私が母を助ける」
責任感が芽生えたとき、高峰は初めて、ほんとうの女優になった。
目の前のひとを幸せにする。
それが、やがてぐるりと回りまわって、自分に返ってくる。
撮影で長く家を空ければ空けるほど、早く母に会いたくなった。
母の喜ぶ顔が見たいと願った。
漠然とした理想や夢のために、ひとは戦えない。
高峰秀子が、50年間、女優を続けられたわけが、そこにある。
彼女は、ただ、身近なひと、目の前のひとを幸せにしたいと願った。

【ON AIR LIST】
◆燦めく星座(映画『秀子の応援団長』挿入歌) / 灰田勝彦
◆とっても綺麗 / イヴ・モンタン
◆WHAT WAS I MADE FOR? / Billie Eilish
◆銀座カンカン娘 / 高峰秀子