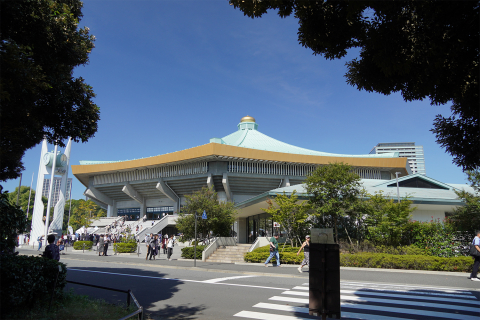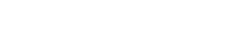第441話 自分の好奇心を信じる
-【京都にまつわるレジェンド篇】映画監督 伊丹十三-
[2024.02.10]
Podcast

2022年の『朝日新聞 be on Saturday』5月14日号の「今こそ!見たい日本映画の巨匠」読者ランキングで、黒澤明、小津安二郎を抑え、1位に輝いたレジェンドがいます。
伊丹十三(いたみ・じゅうぞう)。
『お葬式』『タンポポ』『マルサの女』など、独特のユーモアやペーソスで社会問題をくるんだ傑作を、世に送り出しました。
伊丹が映画で大切にしたこと、それは、次の3つでした。
「びっくりした」「面白い」「誰にでもわかる」。
世の中で何が流行っているかには、全く関心を持たず、常に「自分の好奇心」というアンテナだけを信じて企画を考え、細部にこだわり抜き、普遍的なエンターテインメントに仕上げたのです。
51歳にして、初の監督デビュー作となった映画『お葬式』。
妻・宮本信子の父親の葬儀を伊丹が仕切ることになった体験を反映しています。
突然の肉親の死に翻弄される夫婦の3日間を描いたこの作品で、いきなり日本アカデミー賞最優秀作品賞など、多くの賞を獲得しました。
偉大な映画監督・伊丹万作(いたみ・まんさく)を父に持つ十三は、自分は映画監督になることはないと思っていましたが、お葬式の火葬場で、立ち昇る煙を見たとき、ふと自分が小津安二郎の映画の中にいるような錯覚に陥りました。
そのとき「あ、これ、映画になるかもしれない…」、そう思ったと後に語っています。
伊丹の監督ぶりは、決して声を荒げたり、上から圧をかけるようなものではなく、ただひたすら「はい、もう一回」「うん、そうだな、もう一回やってみましょう」とダメ出しを続けたのだといいます。
自分のイメージが明確にあり、揺るぎないビジョンが存在する。
それを支えているものが、好奇心というアンテナにひっかかった、日々の何気ない日常の中にある、人間のささいな行動やしぐさ。
伊丹は、常に自分の好奇心を羅針盤にして、創作に向き合ってきたのです。
映画監督のみならず、俳優、作家、イラストレーターなど、マルチな才能で時代を駆け抜けた賢人・伊丹十三が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?
映画監督として今も人気を誇るレジェンド、伊丹十三は、1933年5月15日、京都に生まれた。
父は、巨匠・伊丹万作。
万作は、映画監督になる前は、挿絵画家として活躍。
洋画家としては、あの岸田劉生(きしだ・りゅうせい)から将来を期待されていた。
しかし画家は断念し、撮影所に入った。
十三にとって父の記憶とは、ほとんど怒っている姿だった。
常に不機嫌で怖い存在。
ただ、ときおり、手作りのいろはかるたで遊んでくれた。
2歳のとき、父の映画で俳優デビュー。
殿様の赤ちゃん役だった。
愛媛県松山市にある「伊丹十三記念館」には、十三が小学一年生のときに描いた「野菜の絵」が展示してある。
物心ついた頃から絵の才能を発揮していた我が子の作品を見て、父は感心した。
俳人・中村草田男(なかむら・くさたお)が、家に遊びに来たとき、珍しく父は自慢する。
「まあ、見てくれたまえ。小学一年生が画いた絵に、見えるか。
構図、色使い、斬新で、素晴らしいとは思わんか」
十三が13歳の時、父は結核でこの世を去る。
8年もの闘病生活の果てだった。
父がいったいどんなひとで、どんなことをやっていたのか、よくわからないまま、いなくなってしまった。
ただ、自分の絵をほめてくれたときの、あの優しい声だけは、ずっと覚えていた。

京都の中学に入学してすぐ、父を亡くした伊丹十三は、その後転校を繰り返し、17歳のとき、愛媛県松山市に転居。
松山東高等学校に編入する。
当時の集合写真。伊丹だけが学帽を被らず、髪は長い。
明らかに浮いた存在だった。
幼少期から、世の中との齟齬、ズレを感じていた。
まわりに合わせようと思っても、うまくできない。
ひとりで絵を画いているときだけが、幸せだった。
やがて高校の文芸誌に作品を発表。
その作品を読んで、「キミは、素敵な文章を書くじゃないか」と言ってきた生徒がいた。
大江健三郎だった。
演劇部の裏方として美術を担当。
フツウに生きられない窮屈さを救ってくれたのが、フィクション、創作の世界だった。
やがて松山南高等学校に転入。
卒業したのは、20歳になってからだった。
大学には行かず、上京し、新東宝編集部に入社。
その後、商業デザイナーとして、広告のデザインに従事した。
デザイン力、特にレタリングでは一目置かれ、明朝体を書かせたら日本一、とまで言われたという。
26歳のとき、俳優に挑戦。
偉大な父の近くには行かないようにしていたが、どんどん、近づいていく。
俳優としてさまざまな人間を演じるうちに、伊丹十三は気づいていった。
「われわれは、われわれの一生を通じてわれわれ自身になっていく」ということ。
自我が、蓋をしてしまったエス。
どろどろした欲望や衝動を認識し、「ないもの」にはしない。
伊丹は、精神分析に興味を持っていく。
自らの蓋を開ければ、幼い頃、世の中とうまく折り合いがつかず、孤独を感じた自分がいた。
世の中なんて、信じない。自分は自分でやっていく。
俳優として外国映画にも出演。好評を得た。
撮影で訪れたヨーロッパでの体験をエッセイにまとめる。
『ヨーロッパ退屈日記』は、ベストセラーになった。
本のデザインや装丁。文筆業。
全て順風の中にある。
それでも彼の好奇心は、最後の扉をこじ開けた。
映画監督。
気づけば、父の傍らにいた。
そして、父・伊丹万作の「ユーモアをまぶしながらも、鋭い社会批判を提示する」という映画のスタイルは、どこか後の十三の作品に似ていた。
「みんなが信じこんでるものは、とりあえず、俺はやめとこう、あれは絶対ついていってろくなもんじゃない、と思っちゃう」
伊丹十三
【ON AIR LIST】
◆YOUR SONG / Elton John
◆THE WEIGHT / The Band
◆マルサの女 / 本多俊之
伊丹十三(いたみ・じゅうぞう)。
『お葬式』『タンポポ』『マルサの女』など、独特のユーモアやペーソスで社会問題をくるんだ傑作を、世に送り出しました。
伊丹が映画で大切にしたこと、それは、次の3つでした。
「びっくりした」「面白い」「誰にでもわかる」。
世の中で何が流行っているかには、全く関心を持たず、常に「自分の好奇心」というアンテナだけを信じて企画を考え、細部にこだわり抜き、普遍的なエンターテインメントに仕上げたのです。
51歳にして、初の監督デビュー作となった映画『お葬式』。
妻・宮本信子の父親の葬儀を伊丹が仕切ることになった体験を反映しています。
突然の肉親の死に翻弄される夫婦の3日間を描いたこの作品で、いきなり日本アカデミー賞最優秀作品賞など、多くの賞を獲得しました。
偉大な映画監督・伊丹万作(いたみ・まんさく)を父に持つ十三は、自分は映画監督になることはないと思っていましたが、お葬式の火葬場で、立ち昇る煙を見たとき、ふと自分が小津安二郎の映画の中にいるような錯覚に陥りました。
そのとき「あ、これ、映画になるかもしれない…」、そう思ったと後に語っています。
伊丹の監督ぶりは、決して声を荒げたり、上から圧をかけるようなものではなく、ただひたすら「はい、もう一回」「うん、そうだな、もう一回やってみましょう」とダメ出しを続けたのだといいます。
自分のイメージが明確にあり、揺るぎないビジョンが存在する。
それを支えているものが、好奇心というアンテナにひっかかった、日々の何気ない日常の中にある、人間のささいな行動やしぐさ。
伊丹は、常に自分の好奇心を羅針盤にして、創作に向き合ってきたのです。
映画監督のみならず、俳優、作家、イラストレーターなど、マルチな才能で時代を駆け抜けた賢人・伊丹十三が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?
映画監督として今も人気を誇るレジェンド、伊丹十三は、1933年5月15日、京都に生まれた。
父は、巨匠・伊丹万作。
万作は、映画監督になる前は、挿絵画家として活躍。
洋画家としては、あの岸田劉生(きしだ・りゅうせい)から将来を期待されていた。
しかし画家は断念し、撮影所に入った。
十三にとって父の記憶とは、ほとんど怒っている姿だった。
常に不機嫌で怖い存在。
ただ、ときおり、手作りのいろはかるたで遊んでくれた。
2歳のとき、父の映画で俳優デビュー。
殿様の赤ちゃん役だった。
愛媛県松山市にある「伊丹十三記念館」には、十三が小学一年生のときに描いた「野菜の絵」が展示してある。
物心ついた頃から絵の才能を発揮していた我が子の作品を見て、父は感心した。
俳人・中村草田男(なかむら・くさたお)が、家に遊びに来たとき、珍しく父は自慢する。
「まあ、見てくれたまえ。小学一年生が画いた絵に、見えるか。
構図、色使い、斬新で、素晴らしいとは思わんか」
十三が13歳の時、父は結核でこの世を去る。
8年もの闘病生活の果てだった。
父がいったいどんなひとで、どんなことをやっていたのか、よくわからないまま、いなくなってしまった。
ただ、自分の絵をほめてくれたときの、あの優しい声だけは、ずっと覚えていた。

京都の中学に入学してすぐ、父を亡くした伊丹十三は、その後転校を繰り返し、17歳のとき、愛媛県松山市に転居。
松山東高等学校に編入する。
当時の集合写真。伊丹だけが学帽を被らず、髪は長い。
明らかに浮いた存在だった。
幼少期から、世の中との齟齬、ズレを感じていた。
まわりに合わせようと思っても、うまくできない。
ひとりで絵を画いているときだけが、幸せだった。
やがて高校の文芸誌に作品を発表。
その作品を読んで、「キミは、素敵な文章を書くじゃないか」と言ってきた生徒がいた。
大江健三郎だった。
演劇部の裏方として美術を担当。
フツウに生きられない窮屈さを救ってくれたのが、フィクション、創作の世界だった。
やがて松山南高等学校に転入。
卒業したのは、20歳になってからだった。
大学には行かず、上京し、新東宝編集部に入社。
その後、商業デザイナーとして、広告のデザインに従事した。
デザイン力、特にレタリングでは一目置かれ、明朝体を書かせたら日本一、とまで言われたという。
26歳のとき、俳優に挑戦。
偉大な父の近くには行かないようにしていたが、どんどん、近づいていく。
俳優としてさまざまな人間を演じるうちに、伊丹十三は気づいていった。
「われわれは、われわれの一生を通じてわれわれ自身になっていく」ということ。
自我が、蓋をしてしまったエス。
どろどろした欲望や衝動を認識し、「ないもの」にはしない。
伊丹は、精神分析に興味を持っていく。
自らの蓋を開ければ、幼い頃、世の中とうまく折り合いがつかず、孤独を感じた自分がいた。
世の中なんて、信じない。自分は自分でやっていく。
俳優として外国映画にも出演。好評を得た。
撮影で訪れたヨーロッパでの体験をエッセイにまとめる。
『ヨーロッパ退屈日記』は、ベストセラーになった。
本のデザインや装丁。文筆業。
全て順風の中にある。
それでも彼の好奇心は、最後の扉をこじ開けた。
映画監督。
気づけば、父の傍らにいた。
そして、父・伊丹万作の「ユーモアをまぶしながらも、鋭い社会批判を提示する」という映画のスタイルは、どこか後の十三の作品に似ていた。
「みんなが信じこんでるものは、とりあえず、俺はやめとこう、あれは絶対ついていってろくなもんじゃない、と思っちゃう」
伊丹十三
【ON AIR LIST】
◆YOUR SONG / Elton John
◆THE WEIGHT / The Band
◆マルサの女 / 本多俊之