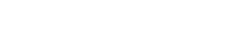第436話 歩みをとめない
-【長野にまつわるレジェンド篇】永六輔-
[2024.01.06]
Podcast
坂本九が歌い、一世を風靡した名曲『上を向いて歩こう』を作詞したレジェンドがいます。
永六輔(えい・ろくすけ)。
『上を向いて歩こう』は、1961年、NHKの音楽バラエティ番組『夢であいましょう』の今月の歌で初披露するや、またたく間に大ヒット。
3か月連続ヒットチャート1位を記録。
さらに『SUKIYAKI(スキヤキ)』とタイトルを変え、アメリカ、ビルボードのヒットチャートで3週連続1位の快挙に輝きました。
時は安保闘争真っただ中。
永は、放送作家の激務の合間をかいくぐって、デモに参加します。
あまりに熱心にデモに参加するので、テレビ局のディレクターから、「キミは、仕事とデモ、どっちが大事なんだ?」と責められます。
永は、「デモです」と即答。
そのまま番組を降りたという逸話が残されています。
終戦後、目覚ましい復興を遂げた日本でしたが、再び、戦争の影が忍び寄っているのではないか、永は、繊細な感性で怖れを感じたのです。
終生、反戦、反権力を訴えた彼は、「本当に戦争に関わるのはよそう。戦争を手伝うのもよそう。どっかの戦争を支持するのもよそう。それだけを言い続けていきたい」と話しました。
『上を向いて歩こう』の歌詞には、彼の二つの強い思いが込められているように感じられます。
ひとつは、安保闘争に敗れた悔しさ、怒り、それでも生きていこうとする決意。
もうひとつは、戦時中の幼少期、疎開先の長野県で感じた思いです。
親元を離れ、ひとりで通学する夜道。
ひとりぼっちが身に沁みます。
さびしい、つらい。
こらえても、後から後から涙がこぼれてくる。
涙を止めることができないのなら、せめて、上を向いて歩こう。
それはどこか、永の人生観にも通じます。
彼の優しさは、涙を流すなとは言いません。
人生は理不尽で、思うようにならない苦難の連続。
唯一、それに打ち勝つには、歩くのをやめないこと。
涙がこぼれないように、上を向いて。
軽妙な語り口と鋭い視点で多くのひとを魅了した、唯一無二の賢人、永六輔が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

放送作家、タレントで作詞家の永六輔は、1933年4月10日、東京神田の順天堂産院で生まれ、浅草で育つ。
父は、浄土真宗・最尊寺の住職。
生まれて最初の記憶は、ベルリンオリンピックのラジオ中継に熱中する大人たちだった。
町には、芸人や役者たちが多く、夏には祭りで盛り上がる。
活気あふれる下町の雰囲気が好きだった。
ラジオが大好きで、落語や漫談に夢中になる。
いつも着物姿だった父が、いつしかカーキ色の洋服を着るようになり、子ども心に戦争の影を感じた。
体が弱く、病気がち。
入院先で『キュリー夫人』を読んで感銘を受ける。
8歳の時、太平洋戦争が始まった。
近所で出征兵士を見送る行列を見かけるようになる。
寺の鐘は没収となり、仏具は陶器に変った。
母と子どもで、信州に疎開。
子どもの中で最も年長だったので、母を守らなくてはいけないと思う。
1945年3月10日。12歳の永は、浅間山の麓から、東京の空が真っ赤になるのを見た。
東京大空襲。
のちに永少年は、一面焼け野原になった愛する下町を目にすることになる。
永六輔は、信州の旧制上田中学に入ったが、14歳のとき、東京に戻り、早稲田中学に転校した。
以前は病気がちだった体も、長野で鍛えられ、たくましくなっていた。
自宅は焼失。
知り合いの寺に家族で身を寄せる。
町はすっかり、変わってしまった。
このときの東京の悲惨な風景を、永は生涯忘れなかった。
「戦争はダメだ。戦争はゼッタイよくない」
そう、心に刻む。
焼け跡を歩き回り、銅や鉛を見つけては、売った。
儲けたお金で、家計を助ける。
近所の子どもたちも、似たようなことをして稼いでいた。
そんな少年たちにボスがいた。
彼は「車坂の田所」と呼ばれていた。
のちの、渥美清だった。
永は、部品を買って、鉱石ラジオを作った。
ラジオを聴いている時間は、平和だった。
戦争前と変わらない。
特にNHKの人気ラジオ番組、三木鶏郎(みき・とりろう)の『日曜娯楽版』が好きだった。
思い切って、ネタを投稿する。
やがて、そのネタが採用された。
それは、ささやかだけれど、まぎれもなく、放送作家への扉が開いた瞬間だった。
永六輔は、せっせとラジオ番組に投稿を続ける。
学校の成績は落ちていく一方だったが、少しでも時間があると、映画や芝居を観てまわる。
その一方で、アイスクリームや宝くじを売ったり、履物屋の下駄の配達を請け負ったりして稼ぐ。
その全ての体験が、のちの人生の養分になるとは、そのとき、知る由もなかった。
ただ、何かに背中を押される。
何かが急き立てる。
戦争をくぐりぬけ、生き延びた命。
休んでいてはもったいない。

やがて、永にとってヒーロー的な存在の、三木鶏郎から声をかけられる。
「キミ、放送作家をやってみないか」
うれしかった。どんなにつらいときも、さみしいときも、ラジオがあれば生きていけた。
そのラジオの番組に、かかわることができるなんて…。
ちょうど18歳の時に、民放が開局。
早稲田大学に入学したが、大学に行くより仕事が忙しくなった。
放送という世界は、魅惑的で夢中になる。
ただ、敬愛する民俗学者、宮本常一のこの言葉だけは忘れなかった。
「放送というのは、電波がどこまでも飛んでいく。
その飛んでいく手前にいてはいけません。
必ず、飛んでいく先に行きなさい。
そして、そこでどんなふうに受け止められているか、どういうふうにみなさんが話しているか、それを聞いて、スタジオに持ち帰りなさい」
永は、現場に行く。
永は、ひとに会いに行くことをやめない。
前に、前に、歩き続ける。
「私が私になるのに、無駄なことは何一つありませんでした」
永六輔
【ON AIR LIST】
◆上を向いて歩こう / 坂本九
◆遠くへ行きたい / ジェリー藤尾
◆こんにちは赤ちゃん / 梓みちよ
◆見上げてごらん夜の星を / 坂本九
永六輔(えい・ろくすけ)。
『上を向いて歩こう』は、1961年、NHKの音楽バラエティ番組『夢であいましょう』の今月の歌で初披露するや、またたく間に大ヒット。
3か月連続ヒットチャート1位を記録。
さらに『SUKIYAKI(スキヤキ)』とタイトルを変え、アメリカ、ビルボードのヒットチャートで3週連続1位の快挙に輝きました。
時は安保闘争真っただ中。
永は、放送作家の激務の合間をかいくぐって、デモに参加します。
あまりに熱心にデモに参加するので、テレビ局のディレクターから、「キミは、仕事とデモ、どっちが大事なんだ?」と責められます。
永は、「デモです」と即答。
そのまま番組を降りたという逸話が残されています。
終戦後、目覚ましい復興を遂げた日本でしたが、再び、戦争の影が忍び寄っているのではないか、永は、繊細な感性で怖れを感じたのです。
終生、反戦、反権力を訴えた彼は、「本当に戦争に関わるのはよそう。戦争を手伝うのもよそう。どっかの戦争を支持するのもよそう。それだけを言い続けていきたい」と話しました。
『上を向いて歩こう』の歌詞には、彼の二つの強い思いが込められているように感じられます。
ひとつは、安保闘争に敗れた悔しさ、怒り、それでも生きていこうとする決意。
もうひとつは、戦時中の幼少期、疎開先の長野県で感じた思いです。
親元を離れ、ひとりで通学する夜道。
ひとりぼっちが身に沁みます。
さびしい、つらい。
こらえても、後から後から涙がこぼれてくる。
涙を止めることができないのなら、せめて、上を向いて歩こう。
それはどこか、永の人生観にも通じます。
彼の優しさは、涙を流すなとは言いません。
人生は理不尽で、思うようにならない苦難の連続。
唯一、それに打ち勝つには、歩くのをやめないこと。
涙がこぼれないように、上を向いて。
軽妙な語り口と鋭い視点で多くのひとを魅了した、唯一無二の賢人、永六輔が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?
放送作家、タレントで作詞家の永六輔は、1933年4月10日、東京神田の順天堂産院で生まれ、浅草で育つ。
父は、浄土真宗・最尊寺の住職。
生まれて最初の記憶は、ベルリンオリンピックのラジオ中継に熱中する大人たちだった。
町には、芸人や役者たちが多く、夏には祭りで盛り上がる。
活気あふれる下町の雰囲気が好きだった。
ラジオが大好きで、落語や漫談に夢中になる。
いつも着物姿だった父が、いつしかカーキ色の洋服を着るようになり、子ども心に戦争の影を感じた。
体が弱く、病気がち。
入院先で『キュリー夫人』を読んで感銘を受ける。
8歳の時、太平洋戦争が始まった。
近所で出征兵士を見送る行列を見かけるようになる。
寺の鐘は没収となり、仏具は陶器に変った。
母と子どもで、信州に疎開。
子どもの中で最も年長だったので、母を守らなくてはいけないと思う。
1945年3月10日。12歳の永は、浅間山の麓から、東京の空が真っ赤になるのを見た。
東京大空襲。
のちに永少年は、一面焼け野原になった愛する下町を目にすることになる。
永六輔は、信州の旧制上田中学に入ったが、14歳のとき、東京に戻り、早稲田中学に転校した。
以前は病気がちだった体も、長野で鍛えられ、たくましくなっていた。
自宅は焼失。
知り合いの寺に家族で身を寄せる。
町はすっかり、変わってしまった。
このときの東京の悲惨な風景を、永は生涯忘れなかった。
「戦争はダメだ。戦争はゼッタイよくない」
そう、心に刻む。
焼け跡を歩き回り、銅や鉛を見つけては、売った。
儲けたお金で、家計を助ける。
近所の子どもたちも、似たようなことをして稼いでいた。
そんな少年たちにボスがいた。
彼は「車坂の田所」と呼ばれていた。
のちの、渥美清だった。
永は、部品を買って、鉱石ラジオを作った。
ラジオを聴いている時間は、平和だった。
戦争前と変わらない。
特にNHKの人気ラジオ番組、三木鶏郎(みき・とりろう)の『日曜娯楽版』が好きだった。
思い切って、ネタを投稿する。
やがて、そのネタが採用された。
それは、ささやかだけれど、まぎれもなく、放送作家への扉が開いた瞬間だった。
永六輔は、せっせとラジオ番組に投稿を続ける。
学校の成績は落ちていく一方だったが、少しでも時間があると、映画や芝居を観てまわる。
その一方で、アイスクリームや宝くじを売ったり、履物屋の下駄の配達を請け負ったりして稼ぐ。
その全ての体験が、のちの人生の養分になるとは、そのとき、知る由もなかった。
ただ、何かに背中を押される。
何かが急き立てる。
戦争をくぐりぬけ、生き延びた命。
休んでいてはもったいない。
やがて、永にとってヒーロー的な存在の、三木鶏郎から声をかけられる。
「キミ、放送作家をやってみないか」
うれしかった。どんなにつらいときも、さみしいときも、ラジオがあれば生きていけた。
そのラジオの番組に、かかわることができるなんて…。
ちょうど18歳の時に、民放が開局。
早稲田大学に入学したが、大学に行くより仕事が忙しくなった。
放送という世界は、魅惑的で夢中になる。
ただ、敬愛する民俗学者、宮本常一のこの言葉だけは忘れなかった。
「放送というのは、電波がどこまでも飛んでいく。
その飛んでいく手前にいてはいけません。
必ず、飛んでいく先に行きなさい。
そして、そこでどんなふうに受け止められているか、どういうふうにみなさんが話しているか、それを聞いて、スタジオに持ち帰りなさい」
永は、現場に行く。
永は、ひとに会いに行くことをやめない。
前に、前に、歩き続ける。
「私が私になるのに、無駄なことは何一つありませんでした」
永六輔
【ON AIR LIST】
◆上を向いて歩こう / 坂本九
◆遠くへ行きたい / ジェリー藤尾
◆こんにちは赤ちゃん / 梓みちよ
◆見上げてごらん夜の星を / 坂本九