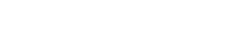第432話 絶望は気づきの時間
-【音楽家のレジェンド篇】フレデリック・ショパン-
[2023.12.09]
Podcast
00:00/00:00

©Rafal Jablonski/Alamy/amanaimages
ピアノ音楽に革命をもたらした、ポーランドの天才作曲家がいます。
フレデリック・ショパン。
自身も優れたピアニストとしてその名をとどろかせたショパン。
彼が創る楽曲は、そのほとんどがピアノ曲で、これまでになかった美しく哀しい旋律や新しい表現形式にふちどられ、彼は、『ピアノの詩人』と呼ばれています。
華々しい功績の影で、そのわずか39年の生涯は、孤独と病魔との闘いでした。
さらに財力のない自分に不安を覚え、常にお金を稼がねばならないという強迫観念に追われていたと言われています。
1810年、ポーランドのワルシャワに生まれたショパンの、最初の大きな挫折は、20歳の時。
音楽の都、ウィーンでの生活が始まり、本格的な音楽家の道を歩もうとした矢先でした。
1830年11月。故郷ワルシャワで起こった、武装蜂起。
当時、ワルシャワ公国は、ロシア帝国の支配下にありました。
しかし、7月のパリ革命を契機に独立の機運が高まり、ついにふるさとは、戦場と化したのです。
愛するポーランドが、心配でならないショパン。
一緒にウィーンにやってきた親友のティトゥスは、兵士になる決意を胸に、すぐに帰国しますが、体の弱いショパンは、父から、こう告げられます。
「おまえは体が弱い、こっちに帰ってきてはダメだ。
おまえには一流の音楽家になる使命があるんだ。
神様からのギフトを持っている者は、それを使い、ひとびとを幸せにする責任がある。
こっちは、大丈夫だ。
ただ、ポーランドはいつだって、おまえの味方だ。
安心して、がんばりなさい」
ショパンは、悩み、自分を責めます。
故郷の愛する家族、大切な人々が苦しんでいるときに、自分は、ここにいていいのか。
さらに、誰も後ろ盾がいないウィーンでの孤独。
ウィーンの人々は、ワルシャワ蜂起をよく思っておらず、ポーランド出身のショパンへの態度は、冷たいものでした。
やがて、ショパンは心を病んでいきます。
それでも彼は、ピアノに向かいました。
ピアノだけが、彼にとって唯一のよりどころであり、生きる意味だったからです。
ピアノに一生を捧げたレジェンド、フレデリック・ショパンが人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

©Marzena Hmielewicz/Alamy/amanaimages
『ピアノの詩人』、フレデリック・ショパンは、20歳の時、大いなる希望を抱いて、ウィーンにやってきた。
幼い頃から神童と呼ばれ、7歳の時には、『ポロネーズ ト短調』を作曲。
8歳で演奏会を開催し、ワルシャワ音楽院を首席で卒業した。
卒業旅行で行ったときのウィーンでは、大歓迎された。
音楽の中心地での演奏会は大成功。
彼の自信につながった。
決して経済的に豊かではないのに、父はワルシャワを出て、ウィーンで暮らすことを後押ししてくれた。
しかし…満を持して乗り込んだ音楽の都は、冷ややかだった。
卒業旅行の時に後ろ盾になってくれたひとは皆、病に倒れたり、他に移り住んでいたりして、頼りにならない。
しかも、ワルシャワ蜂起の火種がウィーンに来ることを恐れていた市民は、ポーランド人に冷ややかだった。
あてにしていた演奏会は、いつまでたっても実現しない。
楽譜の出版も中止。
何のためにここに来たのか、わからない。
父からもらった大切なお金が、ただただ減っていくのを待つばかりだった。
誰も自分の存在を認めてくれない。
むしろ忌み嫌われる厄介者。
生まれて初めての孤独なクリスマスだった。
広場のツリーを眺めていると、涙がこぼれる。
「ああ、帰りたい…ふるさとに帰りたい」
ショパンの心に、冷たい風が吹き荒れた。
フレデリック・ショパンのウィーンでの失意の日々。
この哀しみの時間で、彼は二つのことをあらためて感じた。
ひとつは、ウィーンの人たちが冷たければ冷たいほど、出自、自分のルーツに目が向いた。
すなわち、故郷ポーランド。
この時期、彼はマズルカを多く作曲しているが、マズルカとは、ポロネーズと共に、ポーランドで有名な民族舞踏のリズムと形式のこと。
彼の郷土愛は、どんどん強くなっていく。
さらに彼を励ましたのは、ワルシャワから来た、たくさんの手紙だった。
愛国詩人ヴィトフィッキは、こう書いた。
「ショパン君、君はいつか、ポーランド・オペラを書くべきひとだ。
負けないでくれたまえ。
君の後ろには、我々、ポーランド国民がついている」
もうひとつ、彼が強く自覚したこと。
それは、言うまでもなく、ピアノだった。
演奏できないとなると、無性に演奏したくなる。
これまで、聴衆の前で演奏するのは苦手だと思っていた。
どこかで、お金のために演奏会を開催している、そんな気持ちになっていた。
でも、違う。
自分は作曲し、それを誰かに聴いてもらうのが、好きなのだ。
誰かが自分の楽曲で少しでも安らかな気持ちになってくれたら、それこそ、自分の幸せなのだ。
そのことに気づいたとき、彼に、困難に立ち向かう力が湧いてきた。

©Karol Kozlowski/Alamy/amanaimages
フレデリック・ショパンは、いつまで経っても演奏会ができないウィーンをあとにした。
パリに向かう、その道中で、絶望的なニュースを知る。
ロシア軍の侵攻により、ワルシャワ陥落。
怒り、哀しみ、後悔、無力感。
家族は、友人たちは、どうなっただろう…。
自分は武器も持たずに、ただ遠く離れた地で空を眺めているばかり。
そのとき作曲したのが『エチュード12番「革命」』だと言われている。
パリに着いたショパンは、そこで、戦禍を逃れてきた、多くのポーランド人に出会う。
家族や友人が無事であることもわかり、彼は久しぶりに祖国の人間と交流を持つことができた。
さらに知人・友人たちが手配してくれた紹介状のおかげで、パリ音楽界の重鎮、フェルディナンド・パエルに会えた。
パエルに紹介してもらったのが、当時、パリで一世を風靡していた天才ピアニスト、フランツ・リストだった。
リストとショパンは、すぐにお互いの芸術性の高さを知り、親友になる。
ショパンに、つかの間の安らぎの日々が訪れた。
彼は、自分を本当に思ってくれるひとの存在と、一生を賭けて打ち込めるものを確認することで、絶望のどん底から抜け出すことができた。
【ON AIR LIST】
◆ピアノ協奏曲第1番 第一楽章 / ショパン(作曲)、ホルヘ・ボレット(ピアノ)、モントリオール交響楽団、シャルル・デュトワ(指揮)
◆華麗なる大円舞曲 / ショパン(作曲)、横山幸雄(ピアノ)
◆革命のエチュード / ショパン(作曲)、横山幸雄(ピアノ)