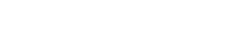第387話 人生に勝ち負けはない
-【長野篇】映画監督 降旗康男-
[2023.01.28]
Podcast
長野県松本市に生まれた、映画監督のレジェンドがいます。
降旗康男(ふるはた・やすお)。
高倉健主演の映画を数多く監督し、1999年公開の『鉄道員(ぽっぽや)』で、日本アカデミー賞 最優秀監督賞を受賞しました。
80歳になってもメガフォンをとり続け、岡田准一主演のヒューマンサスペンス『追憶』が、最後の作品になりました。
降旗のテーマは、常に、人生をうまく生きられないひとを描くこと。
東映に入社し、監督デビューをしたばかりの頃、ある企業の創業者を主人公にした映画を撮らないか、という話がきました。
会議室に呼ばれた降旗は、上司にこう言います。
「せっかくのお話ですが、僕は、成功したひとの映画は撮りたくありません。
映画は、不幸なひと、幸せや運を捨ててしまう、人間の哀しさを描くものだと思っています。
失敗したひと、負けたひとを撮りたいんです」
ジャン・リュック・ゴダールなど、フランス映画の影響を受けた彼にとって、芸術や芸能は、立身出世を謳うものでも、強いヒーローが悪者をこらしめるものでもなく、日々の営みに翻弄され、うまく生きることができずにもがく人間たちを、負けた者の立場で描くものだ、という考えがあったのです。
現場では大声を出さず、口数も少なく、淡々と撮影を進めていきますが、高倉健は、こんな感想を周囲のひとに話したそうです。
「映画が完成すると、不思議なことに、全部、降旗さんにしか撮れない、降旗さんの作品になっているんです」
降旗康男の目線が、光と影の、影のほうに向いているもうひとつの大きな理由に、戦争の体験、特攻隊の隊員とのふれあいがあります。
彼が幼い頃、ふるさと松本市の浅間温泉には、特攻隊の若き隊員たちが待機していました。
降旗たちが遊んでいると、隊員たちはお菓子や果物を分けてくれたそうです。
そうして、ある隊員は言いました。
「いいかい、キミたちは兵隊になんかなるんじゃないよ。
お国のためになるのは、何も兵隊じゃなくてもできるんだ。
僕たちが死んだあとのお国を、頼んだよ」
降旗は、『ホタル』という映画で特攻を描き、若くして散っていった彼らの無念をフィルムに刻みました。
常に弱者の心に寄り添った映画監督・降旗康男が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

高倉健とのコンビで数々の名作を残した映画監督・降旗康男は、1934年8月19日、長野県松本市に生まれた。
祖父も父も国会議員。地元の名家だった。
成績は優秀。物静かな子どもだったが、一度言い出したらきかない、頑固なところがあった。
国民学校4年生のとき、担任の先生が、夕陽が差し込む誰もいない教室で、こう言った。
「サイパン島が玉砕したらしい。日本は負けるよ。くれぐれも、少年飛行兵に志願しちゃダメだぞ、いいな」
当時、そんなことを言ったのがバレたら大変なことになるのを承知で、先生は話してくれた。
でも、そのときは、「先生は、なんだって変なことを言うんだろう」と思っていた。
翌年、敗戦。
先生の高等科のクラスで、何人かの生徒が帰らぬひとになったと、後で聞いた。
一夜にして、何もかもがガラリと変わる。
大人たちの豹変ぶりに、いったい何が正しいのか、わからなくなる。
どんなに世の中が変化しても、日常はやってきた。
生きるというのは、綺麗にはいかない。
カッコ悪く、ぶざま。
子ども心に、人間の奥深い欲や弱さを知る。
勉強は頑張ったが、どこかに満たされない思いが宿った。
やがて、その虚無感を忘れさせてくれるものに出会う。
それが、映画だった。

降旗康男は、県内でも有数の進学校、松本深志高等学校に入学した。
しかし、授業などそっちのけで、映画館に通う。
父の顔ききで、松本市に7つあった映画館は全てフリーパスだった。
午前中の授業は、出席。
運動部のクラスメートの代返をする。
反対に午後は、運動部の連中が、自分の代返をしてくれた。
昼間、暗闇に身を置く快楽。
1937年のフランス映画、ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の『舞踏会の手帖』に、人生とは何かを教わる。
美しい未亡人が、かつて舞踏会で一緒に踊った男性たちを訪ねるオムニバス形式の映画。
政治家志望、医者、作家や作曲家を夢見た前途有望な男たちも、数十年ぶりに会うと、挫折や失敗、堕落の沼にはまっていた。
その映画には、教訓も救いもない。
ただ、淡々と負けていく男たちが描かれていた。
感動した。
「これが人生だよ」と教えてくれているように感じた。
まわりの大人たちは、上っ面の目標や道徳ばかりを語る。
でも、そんなもので一生を生き抜くことができないのは、なんとなくわかっていた。
『舞踏会の手帖』を、何度も何度も観た。
なぜか、エンドロールで涙が出る。
「そうか、人生に勝つ必要はないんだ。負ける姿が、最も人間らしくて、美しい」

降旗康男は、東映に入社。
だが、最初から、上司には扱いづらい社員だった。
当時、主流だった時代劇は、やりたくないと断る。
やりたいこと、やりたくないことがハッキリしていた。
3年目を迎え、会社を辞めようかと考える。
「ここにいても、自分が撮りたい映画なんて撮れっこない」。
そんな、はねっかえりの青年がサード助監督でついたのが、家城巳代治(いえき・みよじ)監督、宮島義勇(みやじま・よしお)カメラマンの映画だった。
二人とも、超ベテラン。あまりにも雲の上の存在だった。
ある日の撮影で、宮島が声をかけた。
「おい! 降旗、こっちに来い!」
宮島が、レンズをのぞけと合図する。
サード監督がカメラのレンズをのぞくことなど、恐れ多くてありえない。
「いいから、観てみろ!」
レンズに右目を近づける。
切り取られた四角い画面があった。
「そうか…この四角いフレームが、映画なんだ」
何を切り取り、何を捨てるか、全部、監督が決めていい。
降旗は、思った。
「自分は不幸なひと、負けたひとを、この四角の中に描いていこう」
人生に勝ち負けなどない。
あるのは、じたばた生きた哀しみだけだ。

【ON AIR LIST】
鉄道員(映画『鉄道員(ぽっぽや)』) / 坂本美雨
故郷の空~愛~(映画『ホタル』) / 国吉良一
舞踏会の手帖 / マルセル・キャリバン・オーケストラ
赤い運命 / 山口百恵
【参考文献】
『人生の流儀』(新日本出版社)
降旗康男(ふるはた・やすお)。
高倉健主演の映画を数多く監督し、1999年公開の『鉄道員(ぽっぽや)』で、日本アカデミー賞 最優秀監督賞を受賞しました。
80歳になってもメガフォンをとり続け、岡田准一主演のヒューマンサスペンス『追憶』が、最後の作品になりました。
降旗のテーマは、常に、人生をうまく生きられないひとを描くこと。
東映に入社し、監督デビューをしたばかりの頃、ある企業の創業者を主人公にした映画を撮らないか、という話がきました。
会議室に呼ばれた降旗は、上司にこう言います。
「せっかくのお話ですが、僕は、成功したひとの映画は撮りたくありません。
映画は、不幸なひと、幸せや運を捨ててしまう、人間の哀しさを描くものだと思っています。
失敗したひと、負けたひとを撮りたいんです」
ジャン・リュック・ゴダールなど、フランス映画の影響を受けた彼にとって、芸術や芸能は、立身出世を謳うものでも、強いヒーローが悪者をこらしめるものでもなく、日々の営みに翻弄され、うまく生きることができずにもがく人間たちを、負けた者の立場で描くものだ、という考えがあったのです。
現場では大声を出さず、口数も少なく、淡々と撮影を進めていきますが、高倉健は、こんな感想を周囲のひとに話したそうです。
「映画が完成すると、不思議なことに、全部、降旗さんにしか撮れない、降旗さんの作品になっているんです」
降旗康男の目線が、光と影の、影のほうに向いているもうひとつの大きな理由に、戦争の体験、特攻隊の隊員とのふれあいがあります。
彼が幼い頃、ふるさと松本市の浅間温泉には、特攻隊の若き隊員たちが待機していました。
降旗たちが遊んでいると、隊員たちはお菓子や果物を分けてくれたそうです。
そうして、ある隊員は言いました。
「いいかい、キミたちは兵隊になんかなるんじゃないよ。
お国のためになるのは、何も兵隊じゃなくてもできるんだ。
僕たちが死んだあとのお国を、頼んだよ」
降旗は、『ホタル』という映画で特攻を描き、若くして散っていった彼らの無念をフィルムに刻みました。
常に弱者の心に寄り添った映画監督・降旗康男が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?
高倉健とのコンビで数々の名作を残した映画監督・降旗康男は、1934年8月19日、長野県松本市に生まれた。
祖父も父も国会議員。地元の名家だった。
成績は優秀。物静かな子どもだったが、一度言い出したらきかない、頑固なところがあった。
国民学校4年生のとき、担任の先生が、夕陽が差し込む誰もいない教室で、こう言った。
「サイパン島が玉砕したらしい。日本は負けるよ。くれぐれも、少年飛行兵に志願しちゃダメだぞ、いいな」
当時、そんなことを言ったのがバレたら大変なことになるのを承知で、先生は話してくれた。
でも、そのときは、「先生は、なんだって変なことを言うんだろう」と思っていた。
翌年、敗戦。
先生の高等科のクラスで、何人かの生徒が帰らぬひとになったと、後で聞いた。
一夜にして、何もかもがガラリと変わる。
大人たちの豹変ぶりに、いったい何が正しいのか、わからなくなる。
どんなに世の中が変化しても、日常はやってきた。
生きるというのは、綺麗にはいかない。
カッコ悪く、ぶざま。
子ども心に、人間の奥深い欲や弱さを知る。
勉強は頑張ったが、どこかに満たされない思いが宿った。
やがて、その虚無感を忘れさせてくれるものに出会う。
それが、映画だった。
降旗康男は、県内でも有数の進学校、松本深志高等学校に入学した。
しかし、授業などそっちのけで、映画館に通う。
父の顔ききで、松本市に7つあった映画館は全てフリーパスだった。
午前中の授業は、出席。
運動部のクラスメートの代返をする。
反対に午後は、運動部の連中が、自分の代返をしてくれた。
昼間、暗闇に身を置く快楽。
1937年のフランス映画、ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の『舞踏会の手帖』に、人生とは何かを教わる。
美しい未亡人が、かつて舞踏会で一緒に踊った男性たちを訪ねるオムニバス形式の映画。
政治家志望、医者、作家や作曲家を夢見た前途有望な男たちも、数十年ぶりに会うと、挫折や失敗、堕落の沼にはまっていた。
その映画には、教訓も救いもない。
ただ、淡々と負けていく男たちが描かれていた。
感動した。
「これが人生だよ」と教えてくれているように感じた。
まわりの大人たちは、上っ面の目標や道徳ばかりを語る。
でも、そんなもので一生を生き抜くことができないのは、なんとなくわかっていた。
『舞踏会の手帖』を、何度も何度も観た。
なぜか、エンドロールで涙が出る。
「そうか、人生に勝つ必要はないんだ。負ける姿が、最も人間らしくて、美しい」
降旗康男は、東映に入社。
だが、最初から、上司には扱いづらい社員だった。
当時、主流だった時代劇は、やりたくないと断る。
やりたいこと、やりたくないことがハッキリしていた。
3年目を迎え、会社を辞めようかと考える。
「ここにいても、自分が撮りたい映画なんて撮れっこない」。
そんな、はねっかえりの青年がサード助監督でついたのが、家城巳代治(いえき・みよじ)監督、宮島義勇(みやじま・よしお)カメラマンの映画だった。
二人とも、超ベテラン。あまりにも雲の上の存在だった。
ある日の撮影で、宮島が声をかけた。
「おい! 降旗、こっちに来い!」
宮島が、レンズをのぞけと合図する。
サード監督がカメラのレンズをのぞくことなど、恐れ多くてありえない。
「いいから、観てみろ!」
レンズに右目を近づける。
切り取られた四角い画面があった。
「そうか…この四角いフレームが、映画なんだ」
何を切り取り、何を捨てるか、全部、監督が決めていい。
降旗は、思った。
「自分は不幸なひと、負けたひとを、この四角の中に描いていこう」
人生に勝ち負けなどない。
あるのは、じたばた生きた哀しみだけだ。
【ON AIR LIST】
鉄道員(映画『鉄道員(ぽっぽや)』) / 坂本美雨
故郷の空~愛~(映画『ホタル』) / 国吉良一
舞踏会の手帖 / マルセル・キャリバン・オーケストラ
赤い運命 / 山口百恵
【参考文献】
『人生の流儀』(新日本出版社)