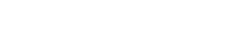第424話 哀しみから逃げない
-【絵画の世界に革命をもたらしたレジェンド篇】棟方志功-
[2023.10.14]
Podcast
00:00/00:00
青森県出身の、20世紀の日本を代表する板画家がいます。
棟方志功(むなかた・しこう)。
今年、生誕120年を迎える彼の展覧会が、現在、東京国立近代美術館で開催されています。
『棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ』。
この展覧会の特徴のひとつは、青森、東京、富山と、棟方が暮らした三つの土地をたどる、初の大回顧展であるということです。
ヴェネチア・ビエンナーレでの受賞を始め、版画絵の世界に革命を起こした彼は、「世界のムナカタ」として国際的に多大なる評価を得ました。
その創作の秘密を、彼が暮らした三つの場所からひもとく試みは、必見です。
特に注目は、久しぶりの公開となる、棟方が疎開した富山県福光町の光徳寺から依頼を受けて画いた『華厳松』。
墨がはじけ飛ぶダイナミックな筆致が堪能できます。
今もなお、世界中のファンを魅了してやまない棟方ですが、その人生は、苦難の連続でした。
そのひとつに、視力があります。
幼い頃から、右目がよく見えない。
歳とともに視力は低下し、やがて、右目は全く見えず、左目も半分は闇の中だったのです。
木版に顔をくっつけるようにして対峙する姿は、彼にとって、止むに止まれぬもの。
ただ、棟方は、日本図書センターが発刊した『人間の記録』でこう語っています。
「ただまことにおかしなもので、わたくしの右眼は、板画の刃物を持つと見えてきます」
彼は、うまくいかないこと、不器用にしか生きられない哀しみを大切にしました。
あるインタビューで、こう答えています。
「哀しむことを裏に持っていて、驚くことと喜ぶこと。
哀しみは、人間の感動の中で、いちばん大切なのであります」
絶えず笑顔でひとに接し、生きることの素晴らしさを説いた賢人、棟方志功が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?



板画家・棟方志功は、1903年9月5日、青森市に生まれた。
幼少期の棟方にとって鮮烈で、決して忘れることのできない、ある出来事があった。
それは、彼が7歳のときに経験した、大火事。
1910年5月3日の、青森大火。
青森市中心部の菓子製造工場から出火した炎は、風にあおられ、街中を焼き尽くした。
その日、遠足にいくはずだった棟方は、なぜか自宅にいて、兄と凧あげに夢中になっていた。
突然、黒い雲がやってきて、あっという間に視界をさえぎる。
兄と一緒に逃げるが、炎が河のように流れ込み、棟方は恐怖で泣き叫ぶ。
「青森じゅうの神様、仏様! どうか、お助けください!!」
涙の向こうの、火の流れが一瞬、スローモーションのように見えた。
鮮やかな赤が中心にあり、その下は真っ青。
赤の上は黄色、さらに紫。
もっと上は、青だった。
激しくほとばしる炎の色、絶えず変わる形は、棟方少年の心にしっかり刻まれた。
特にそのとき見た「赤」は、ひときわ強く彼の心をとらえた。
世界的な板画家、棟方志功の父は、鍛冶職人。
優秀な職人だったが、好き嫌いがハッキリしていて、ひとにこびることを嫌う。
大酒飲みで、一度怒ると手がつけられない。
近くの川で釣りをするのが好きだった。
たったひとり、釣り糸を垂れる。
釣れても釣れなくても、何時間でも川べりから離れない。
夜になり、追加の酒と握り飯を子どもたちが届けると、草むらでひとりニコニコ笑っていたという。
母は、苦労した。
ひとりで家計を切り盛り。
吹雪く中、行商に出かける。
お腹をすかせた子どもたち。
木の引き戸が開くと、雪まみれの母がフカシイモを手に帰ってくる。
母は、42歳の若さで亡くなった。
幼い棟方少年の目には、父も母も、なぜか哀しく見えた。
一生懸命生きているひとは、みんな、哀しく見える。
それはなぜだろう。
言いようもない思いに押しつぶされそうになるとき、祖母のお経を聞くと安心した。
祖母は信心深く、いつもお経を詠んでいた。
背中におんぶされて聞くと、スヤスヤと眠ることができた。
彼の心に、仏様の存在が静かにしみわたっていった。

棟方志功は、幼い頃から、絵を画くのが好きだった。
右目はよく見えないが、絵を画いているときは気にならなかった。
学校を出ると、兄たちと鍛冶屋の仕事をしていたが、17歳のとき、裁判所の給仕の職につく。
弁護士たちは、彼を名前ではなく、「キュー」と呼んだ。
どんなときも、「キュー」と呼ばれれば、「はい!」と答える。
目がよく見えないので、掃除には苦労した。
ゴミが見えず、何度も怒られた。
朝4時半の出社。
まだ暗い中、事務室を綺麗にして、部屋を整え、絵の道具を持って4キロほど先の公園まで歩く。
一枚か二枚、絵を画いて戻ると、みんなが出社する7時だった。
ただひたすら、目の前の仕事に懸命だった。
言われたことをやり、自分ができることを探す。
絵が画ければ、たいていのことは乗り切れた。
あるとき、雑誌『白樺』に掲載されているゴッホの『ひまわり』を見たとき、なぜか、幼い頃経験した大火事を思い出した。
そして、哀しみを感じた。
根拠のない、果てしない、哀しみ。
「そうか、芸術の真ん中には、哀しみがあるんだ」
棟方は、ゴッホになりたいと思った。
ゴッホのように、哀しみを画ける画家になりたいと願った。
ひとり草むらで笑う父。
雪まみれで帰ってくる母。
一日中、お経を詠み続ける祖母。
みんな優しくて、みんな哀しい。
彼は、自分が画家になるために必要なものを、十分持っていると思った。
「みんな楽しませ、もっと大きくなれば、神とか仏とかを遊ばせる仕事、これこそほんとの板画じゃないかと思いました」
棟方志功


よろこびの歌 / ベートーヴェン(作曲)、田中拓人
絵の具 / 空気公団
ふなまち唄 Part II / 矢野顕子
★撮影は、富山県南砺市「南砺市立 福光美術館 分館 棟方志功記念館『愛染苑』」様、「躅飛山 光徳寺」様にご協力いただきました。ありがとうございました。
棟方志功(むなかた・しこう)。
今年、生誕120年を迎える彼の展覧会が、現在、東京国立近代美術館で開催されています。
『棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ』。
この展覧会の特徴のひとつは、青森、東京、富山と、棟方が暮らした三つの土地をたどる、初の大回顧展であるということです。
ヴェネチア・ビエンナーレでの受賞を始め、版画絵の世界に革命を起こした彼は、「世界のムナカタ」として国際的に多大なる評価を得ました。
その創作の秘密を、彼が暮らした三つの場所からひもとく試みは、必見です。
特に注目は、久しぶりの公開となる、棟方が疎開した富山県福光町の光徳寺から依頼を受けて画いた『華厳松』。
墨がはじけ飛ぶダイナミックな筆致が堪能できます。
今もなお、世界中のファンを魅了してやまない棟方ですが、その人生は、苦難の連続でした。
そのひとつに、視力があります。
幼い頃から、右目がよく見えない。
歳とともに視力は低下し、やがて、右目は全く見えず、左目も半分は闇の中だったのです。
木版に顔をくっつけるようにして対峙する姿は、彼にとって、止むに止まれぬもの。
ただ、棟方は、日本図書センターが発刊した『人間の記録』でこう語っています。
「ただまことにおかしなもので、わたくしの右眼は、板画の刃物を持つと見えてきます」
彼は、うまくいかないこと、不器用にしか生きられない哀しみを大切にしました。
あるインタビューで、こう答えています。
「哀しむことを裏に持っていて、驚くことと喜ぶこと。
哀しみは、人間の感動の中で、いちばん大切なのであります」
絶えず笑顔でひとに接し、生きることの素晴らしさを説いた賢人、棟方志功が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?


躅飛山 光徳寺(富山県南砺市)

光徳寺の裏山(富山県南砺市)
板画家・棟方志功は、1903年9月5日、青森市に生まれた。
幼少期の棟方にとって鮮烈で、決して忘れることのできない、ある出来事があった。
それは、彼が7歳のときに経験した、大火事。
1910年5月3日の、青森大火。
青森市中心部の菓子製造工場から出火した炎は、風にあおられ、街中を焼き尽くした。
その日、遠足にいくはずだった棟方は、なぜか自宅にいて、兄と凧あげに夢中になっていた。
突然、黒い雲がやってきて、あっという間に視界をさえぎる。
兄と一緒に逃げるが、炎が河のように流れ込み、棟方は恐怖で泣き叫ぶ。
「青森じゅうの神様、仏様! どうか、お助けください!!」
涙の向こうの、火の流れが一瞬、スローモーションのように見えた。
鮮やかな赤が中心にあり、その下は真っ青。
赤の上は黄色、さらに紫。
もっと上は、青だった。
激しくほとばしる炎の色、絶えず変わる形は、棟方少年の心にしっかり刻まれた。
特にそのとき見た「赤」は、ひときわ強く彼の心をとらえた。
世界的な板画家、棟方志功の父は、鍛冶職人。
優秀な職人だったが、好き嫌いがハッキリしていて、ひとにこびることを嫌う。
大酒飲みで、一度怒ると手がつけられない。
近くの川で釣りをするのが好きだった。
たったひとり、釣り糸を垂れる。
釣れても釣れなくても、何時間でも川べりから離れない。
夜になり、追加の酒と握り飯を子どもたちが届けると、草むらでひとりニコニコ笑っていたという。
母は、苦労した。
ひとりで家計を切り盛り。
吹雪く中、行商に出かける。
お腹をすかせた子どもたち。
木の引き戸が開くと、雪まみれの母がフカシイモを手に帰ってくる。
母は、42歳の若さで亡くなった。
幼い棟方少年の目には、父も母も、なぜか哀しく見えた。
一生懸命生きているひとは、みんな、哀しく見える。
それはなぜだろう。
言いようもない思いに押しつぶされそうになるとき、祖母のお経を聞くと安心した。
祖母は信心深く、いつもお経を詠んでいた。
背中におんぶされて聞くと、スヤスヤと眠ることができた。
彼の心に、仏様の存在が静かにしみわたっていった。

南砺市立 福光美術館 分館 棟方志功記念館「愛染苑」(富山県南砺市)
棟方志功は、幼い頃から、絵を画くのが好きだった。
右目はよく見えないが、絵を画いているときは気にならなかった。
学校を出ると、兄たちと鍛冶屋の仕事をしていたが、17歳のとき、裁判所の給仕の職につく。
弁護士たちは、彼を名前ではなく、「キュー」と呼んだ。
どんなときも、「キュー」と呼ばれれば、「はい!」と答える。
目がよく見えないので、掃除には苦労した。
ゴミが見えず、何度も怒られた。
朝4時半の出社。
まだ暗い中、事務室を綺麗にして、部屋を整え、絵の道具を持って4キロほど先の公園まで歩く。
一枚か二枚、絵を画いて戻ると、みんなが出社する7時だった。
ただひたすら、目の前の仕事に懸命だった。
言われたことをやり、自分ができることを探す。
絵が画ければ、たいていのことは乗り切れた。
あるとき、雑誌『白樺』に掲載されているゴッホの『ひまわり』を見たとき、なぜか、幼い頃経験した大火事を思い出した。
そして、哀しみを感じた。
根拠のない、果てしない、哀しみ。
「そうか、芸術の真ん中には、哀しみがあるんだ」
棟方は、ゴッホになりたいと思った。
ゴッホのように、哀しみを画ける画家になりたいと願った。
ひとり草むらで笑う父。
雪まみれで帰ってくる母。
一日中、お経を詠み続ける祖母。
みんな優しくて、みんな哀しい。
彼は、自分が画家になるために必要なものを、十分持っていると思った。
「みんな楽しませ、もっと大きくなれば、神とか仏とかを遊ばせる仕事、これこそほんとの板画じゃないかと思いました」
棟方志功


旧棟方志功住居「鯉雨画斎」(富山県南砺市)
【ON AIR LIST】よろこびの歌 / ベートーヴェン(作曲)、田中拓人
絵の具 / 空気公団
ふなまち唄 Part II / 矢野顕子
★撮影は、富山県南砺市「南砺市立 福光美術館 分館 棟方志功記念館『愛染苑』」様、「躅飛山 光徳寺」様にご協力いただきました。ありがとうございました。