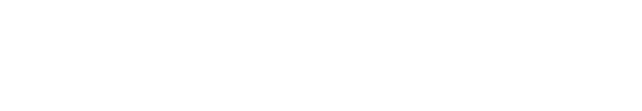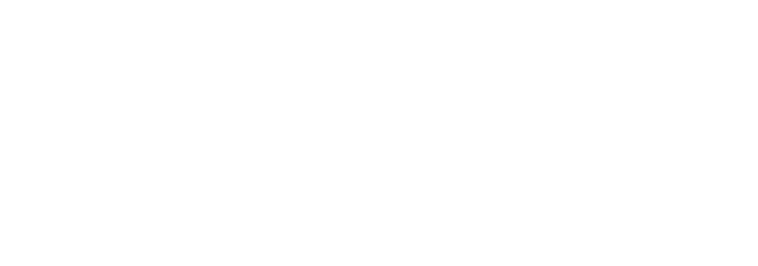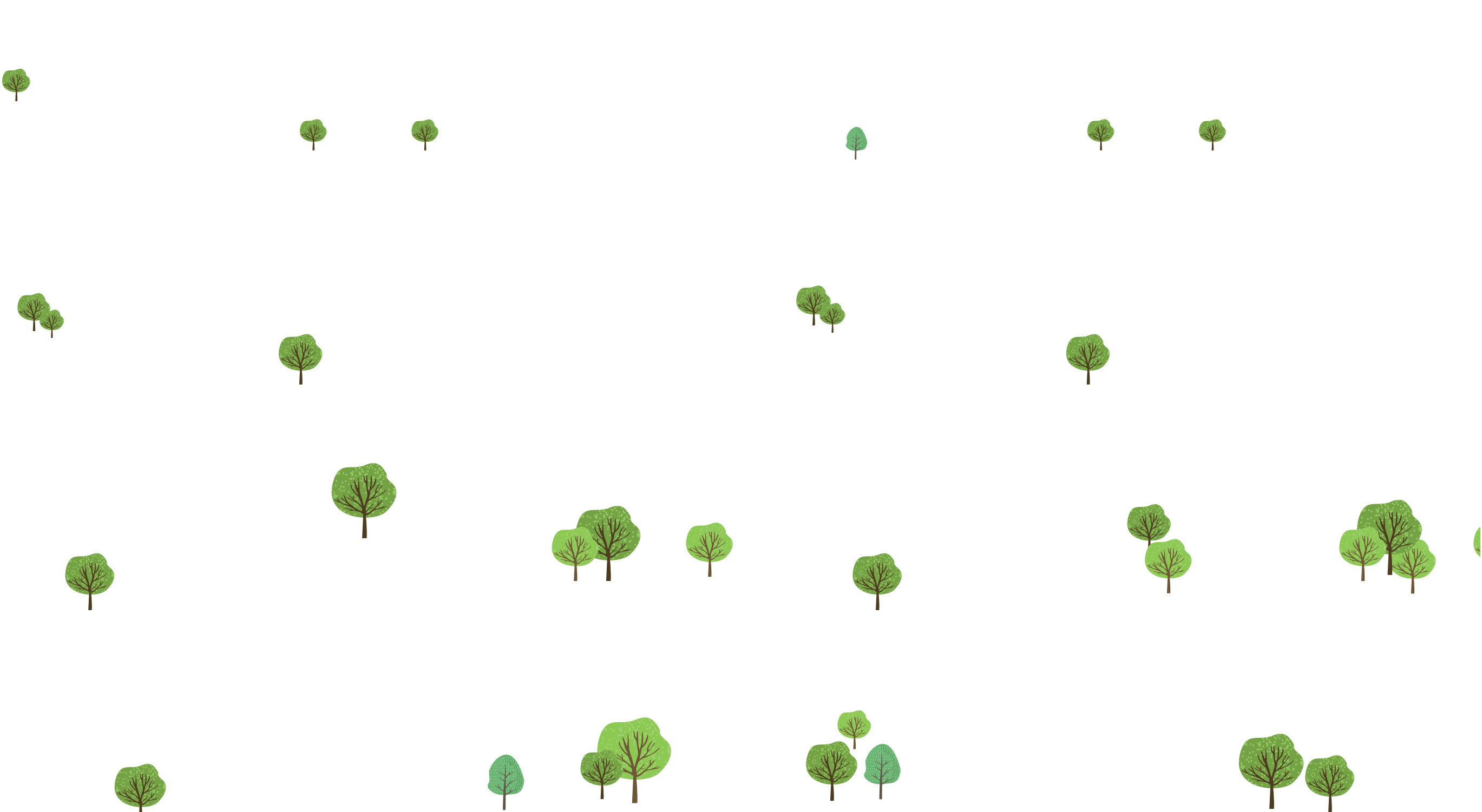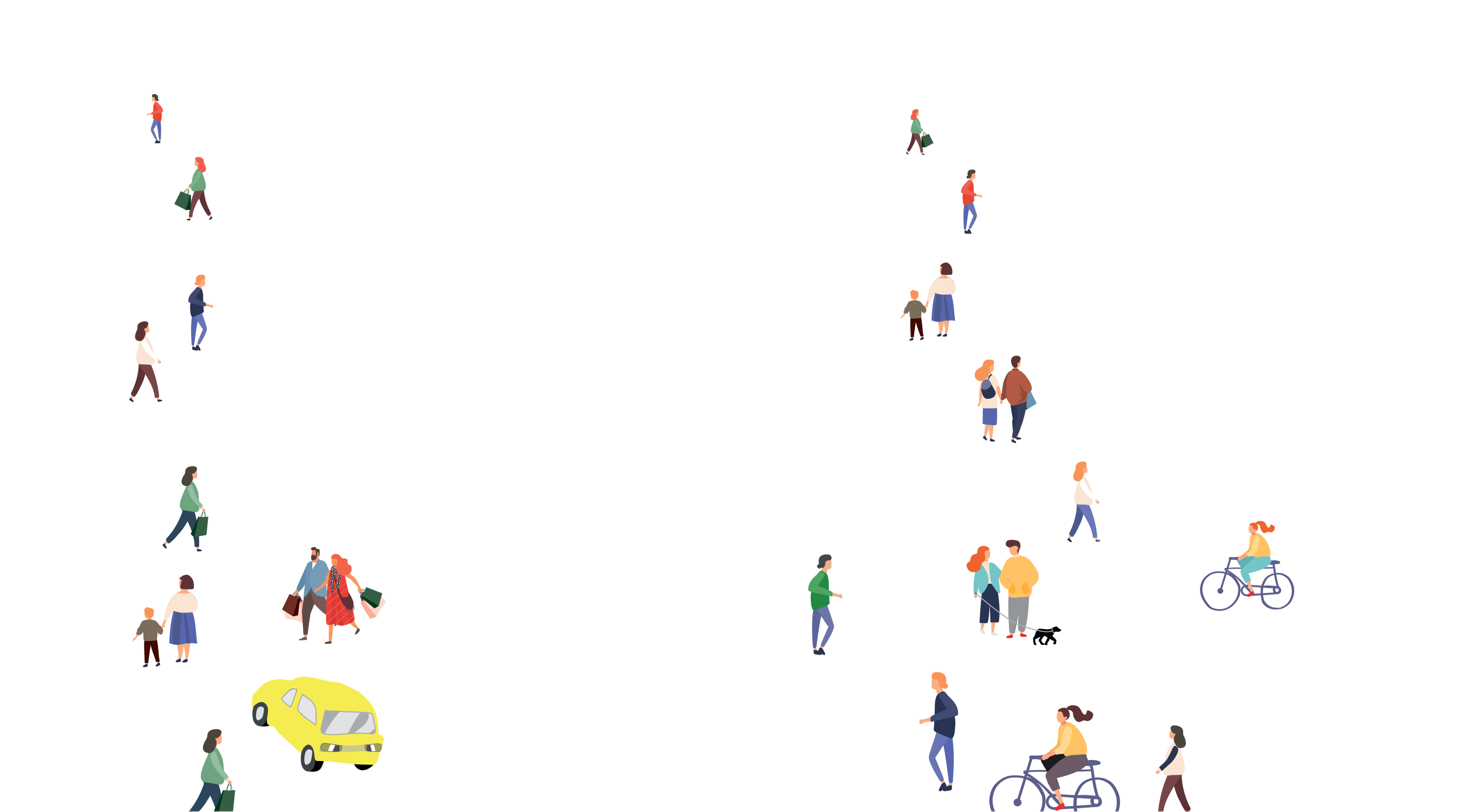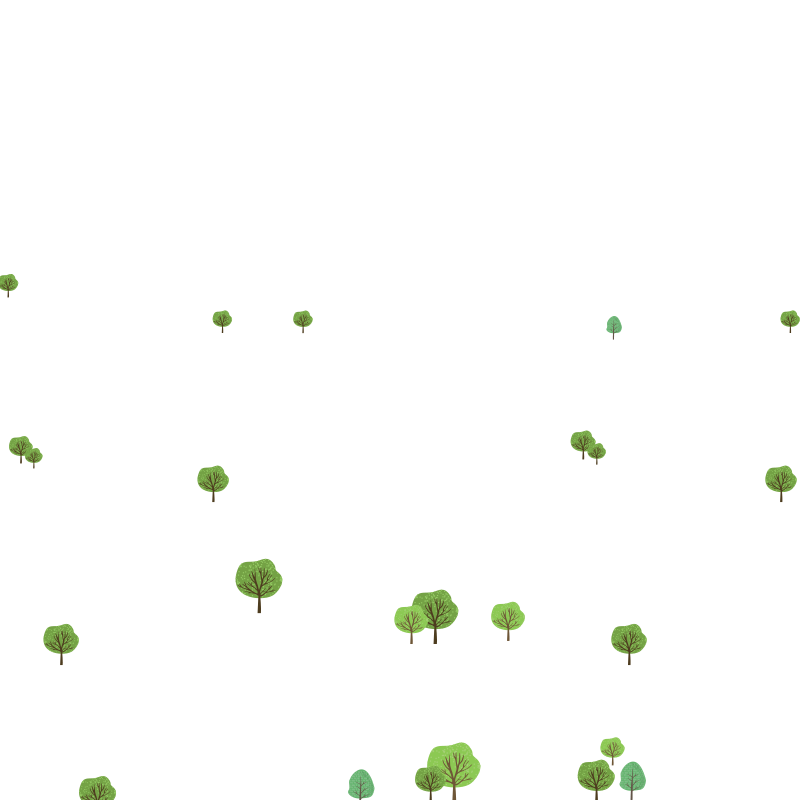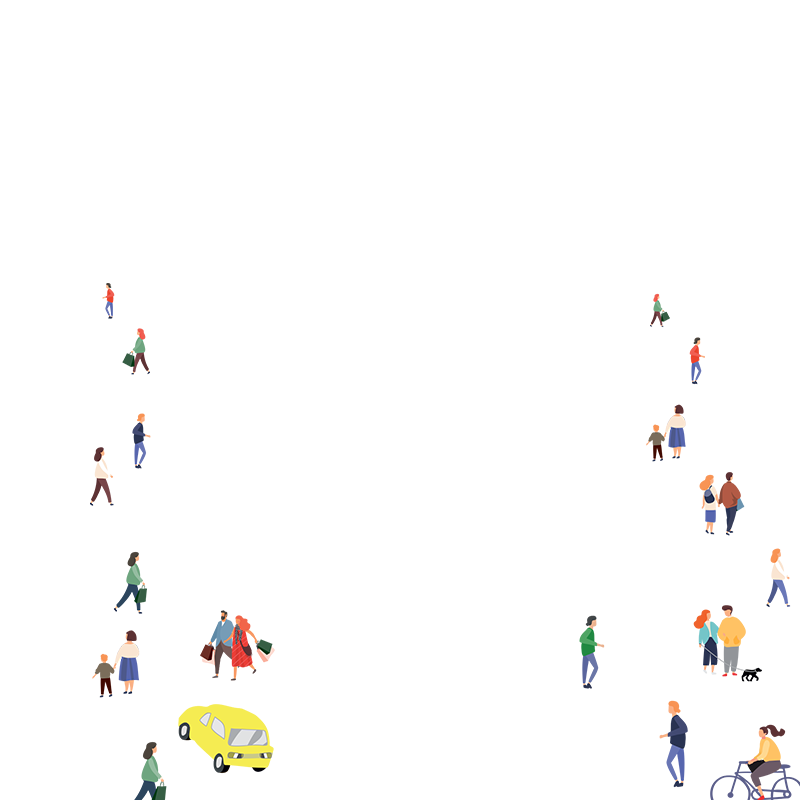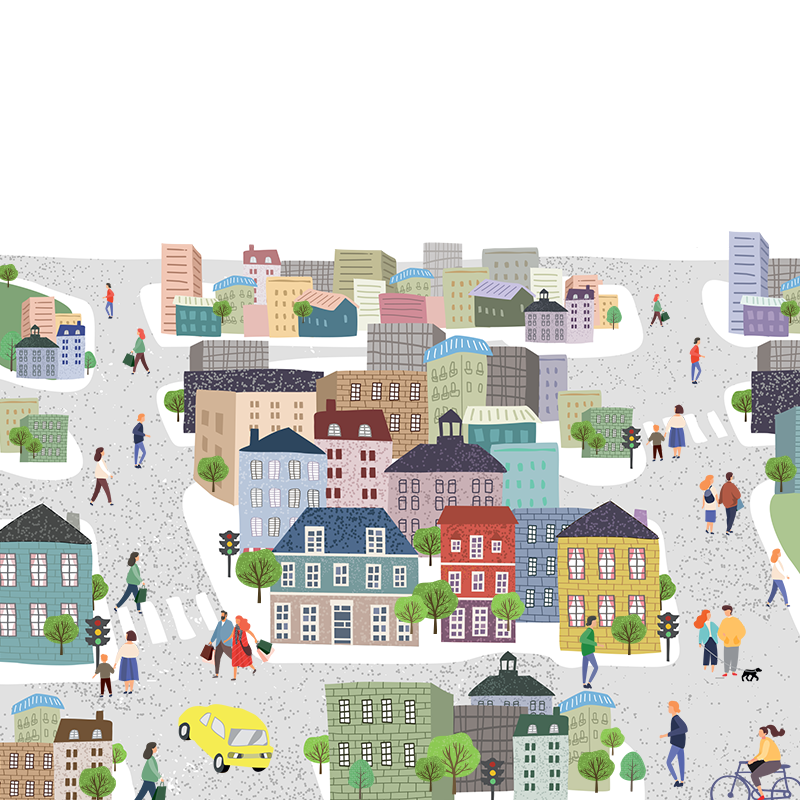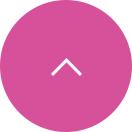第7回 12月3日「紙」前編
2023.12.03

今週と来週のテーマは世界の生産量 年間4.2億トン
日本はアメリカ、中国に次いで2,400万トンで世界3位
消費量でいうと国民ひとり当たり約250キログラム・・・ なんだか分かりますか?
正解は「紙」。
周囲を見まわせば、ノート、新聞、カレンダー、本 etc・・・
何らかのカタチでそこにありませんか? 紙。
いつ頃、どこで生まれたのか? ご存知でしょうか。
歴史の授業で習った古代エジプトの「パピルス」。
英語の「paper」という言葉の由来にもなっていて
日本語では「パピルス紙」とも呼ばれますが
植物の茎を並べて作ったものなので、厳密には「紙」ではありません。
他にも羊の皮や粘土板、木簡などが記述道具として用いられましたが、
もちろんこれらも「紙」ではありません。
紙の発祥と考えられているのは、紀元前2世紀頃の中国。
「紙」とは水中でばらばらにした植物などの繊維を薄く平らにのばして乾かしたもの。
中国で製紙法が発明されると、後漢時代の役人だった蔡倫という人物が、これを改良。
使いやすい実用的な紙が作られるようになったと言われています。
ちなみに蔡倫が紙作りに使った材料は麻のボロきれや樹皮だったそうです。
日本に紙が伝わったのは推古天皇の時代の610年。
曇徴という高句麗の僧侶が墨とともに伝えたと言われています。
伝播当初、使われていた材料は「麻」。
その後「コウゾ」や「ガンピ」などの植物も原料として使われるようになり、
紙を抄く方法にも改良が加えられ、日本独自の“和紙”が発展しました。
国内で現存する最古の紙は、702年の大宝律令の際に使われた戸籍用紙。
中国で生まれた紙は長い時間をかけて世界に広がっていきました。
発明から1千年後の8世紀には西アジアへ。その後、エジプトを経由して地中海沿岸へ。
そして、ヨーロッパに伝わったのは1,400年後の12世紀と考えられています。
そんな紙が、どうやって今のように大量生産されるようになったのか?
それは、また来週のお話。
日本はアメリカ、中国に次いで2,400万トンで世界3位
消費量でいうと国民ひとり当たり約250キログラム・・・ なんだか分かりますか?
正解は「紙」。
周囲を見まわせば、ノート、新聞、カレンダー、本 etc・・・
何らかのカタチでそこにありませんか? 紙。
いつ頃、どこで生まれたのか? ご存知でしょうか。
歴史の授業で習った古代エジプトの「パピルス」。
英語の「paper」という言葉の由来にもなっていて
日本語では「パピルス紙」とも呼ばれますが
植物の茎を並べて作ったものなので、厳密には「紙」ではありません。
他にも羊の皮や粘土板、木簡などが記述道具として用いられましたが、
もちろんこれらも「紙」ではありません。
紙の発祥と考えられているのは、紀元前2世紀頃の中国。
「紙」とは水中でばらばらにした植物などの繊維を薄く平らにのばして乾かしたもの。
中国で製紙法が発明されると、後漢時代の役人だった蔡倫という人物が、これを改良。
使いやすい実用的な紙が作られるようになったと言われています。
ちなみに蔡倫が紙作りに使った材料は麻のボロきれや樹皮だったそうです。
日本に紙が伝わったのは推古天皇の時代の610年。
曇徴という高句麗の僧侶が墨とともに伝えたと言われています。
伝播当初、使われていた材料は「麻」。
その後「コウゾ」や「ガンピ」などの植物も原料として使われるようになり、
紙を抄く方法にも改良が加えられ、日本独自の“和紙”が発展しました。
国内で現存する最古の紙は、702年の大宝律令の際に使われた戸籍用紙。
中国で生まれた紙は長い時間をかけて世界に広がっていきました。
発明から1千年後の8世紀には西アジアへ。その後、エジプトを経由して地中海沿岸へ。
そして、ヨーロッパに伝わったのは1,400年後の12世紀と考えられています。
そんな紙が、どうやって今のように大量生産されるようになったのか?
それは、また来週のお話。