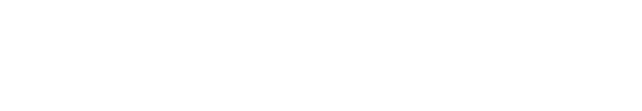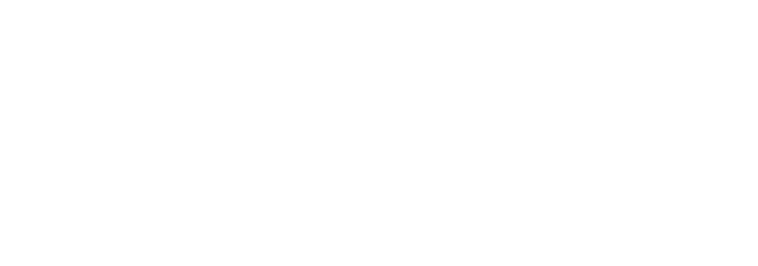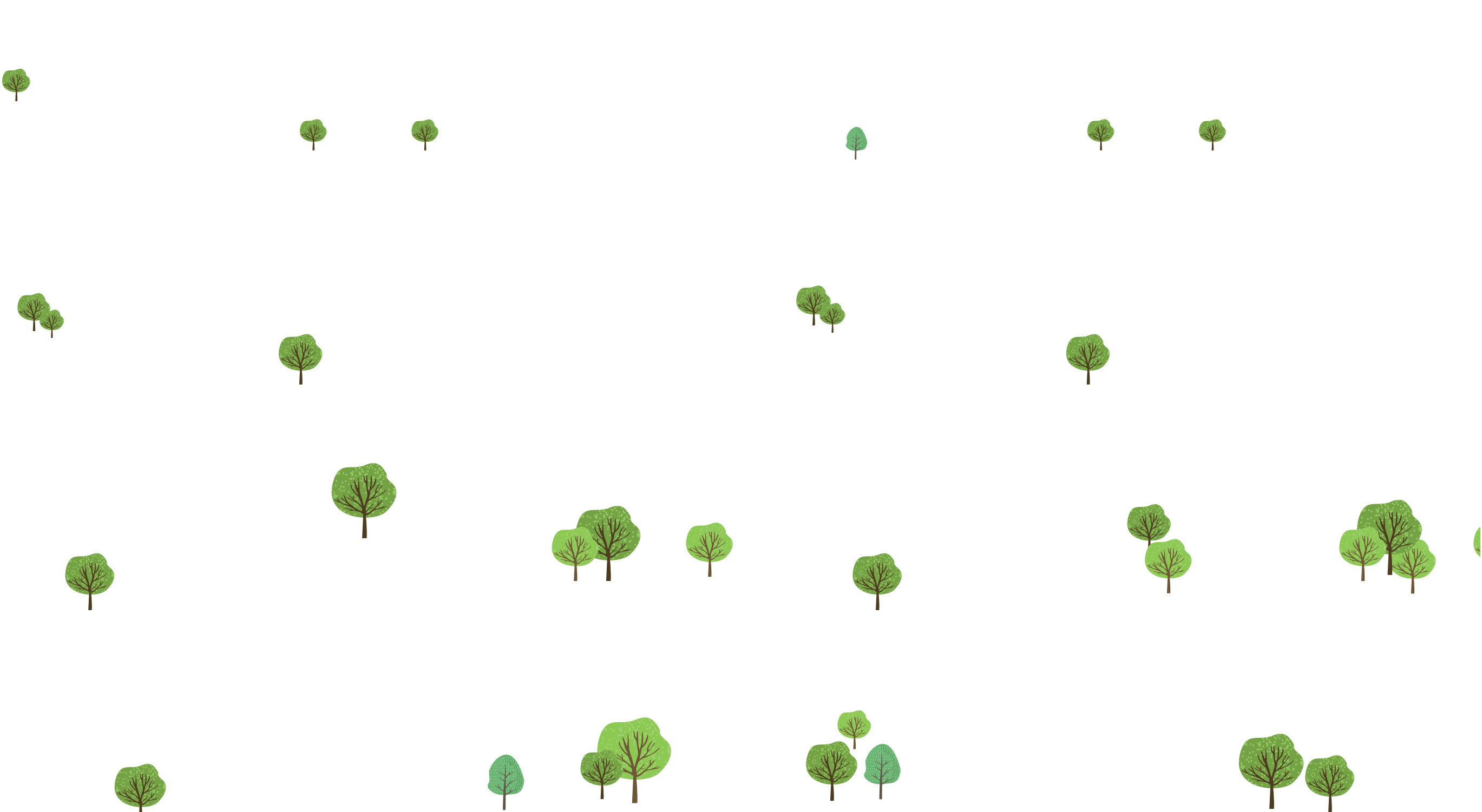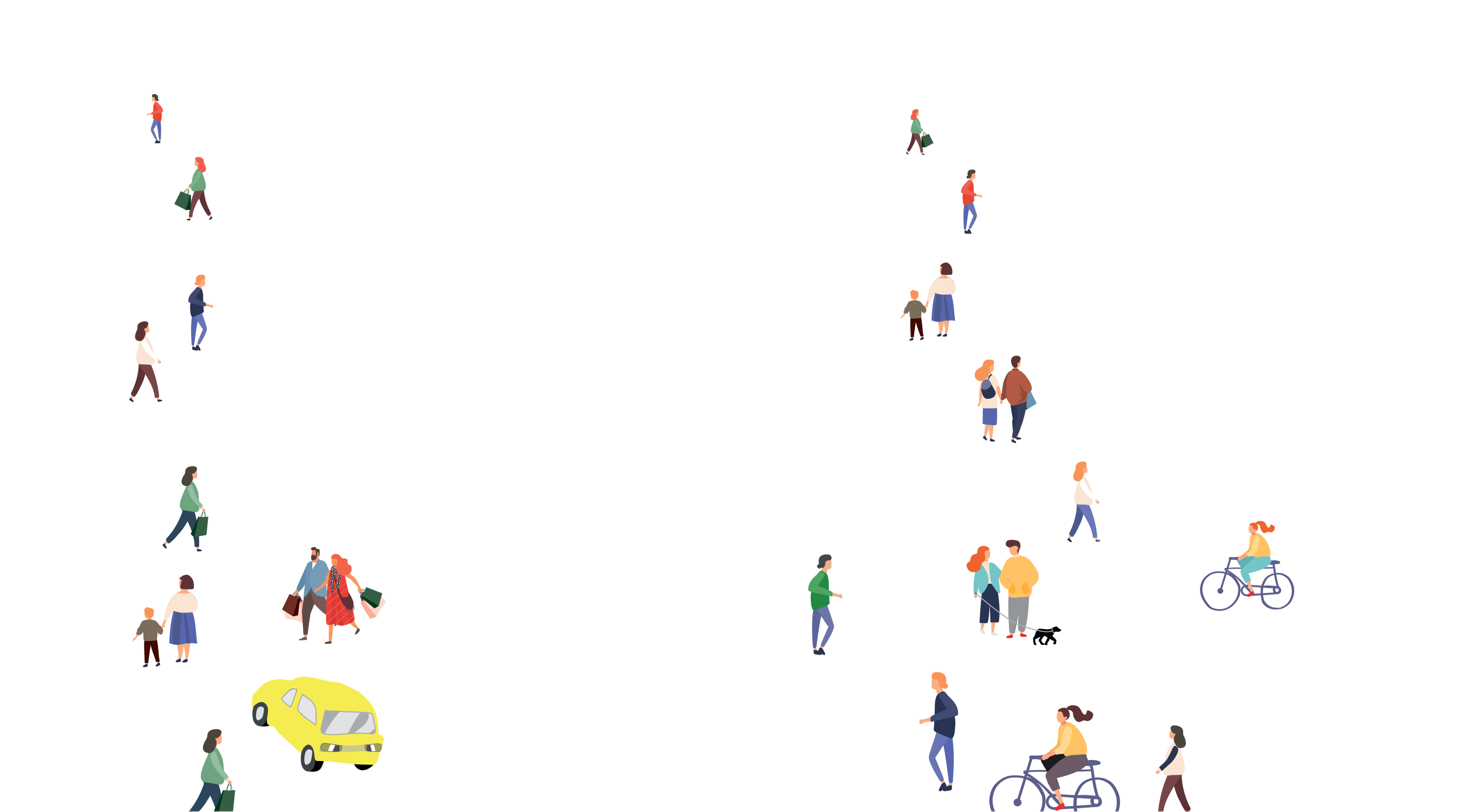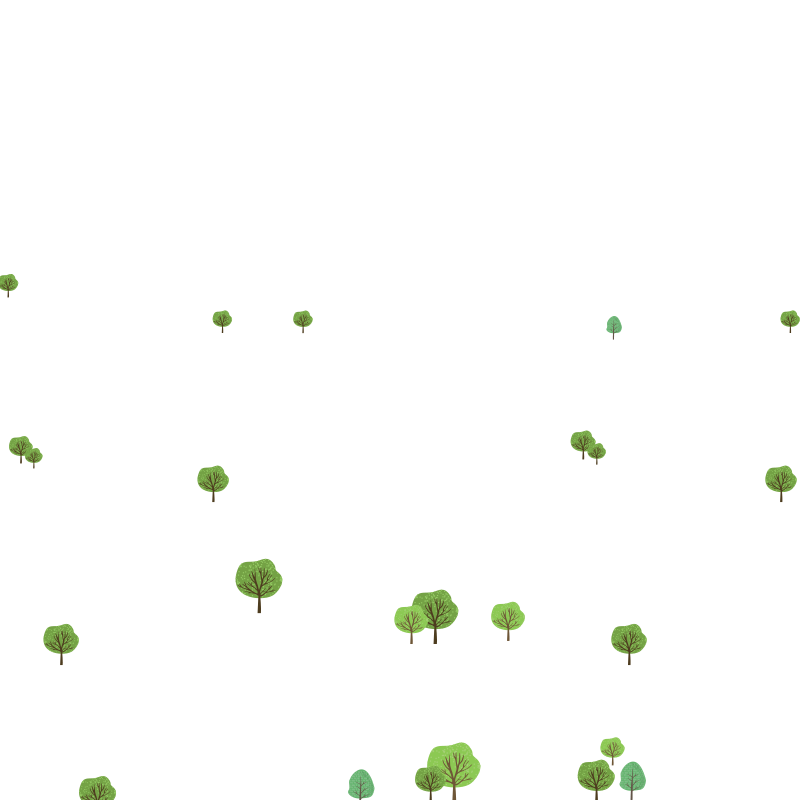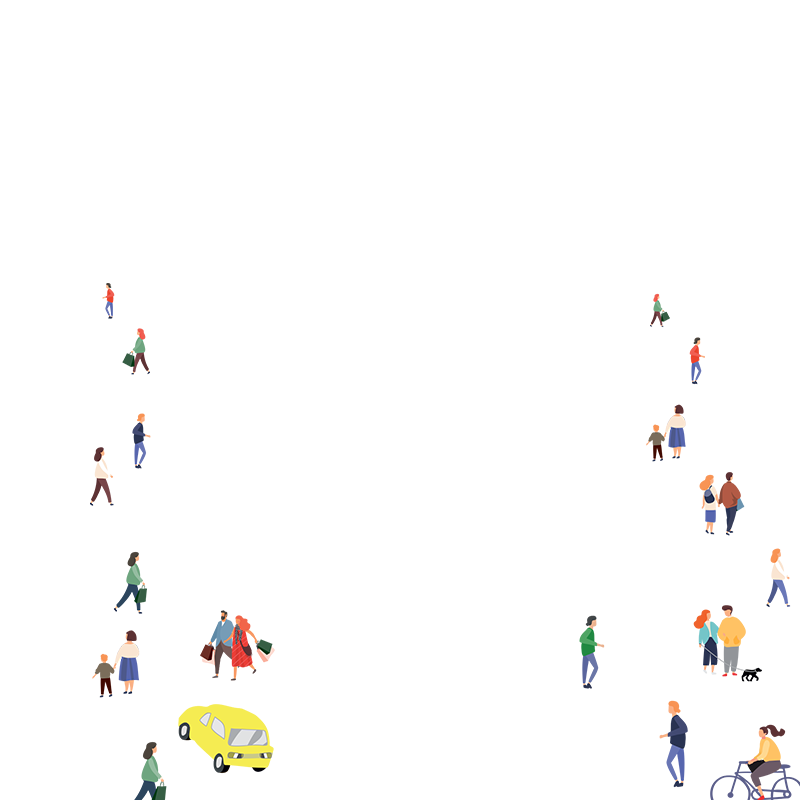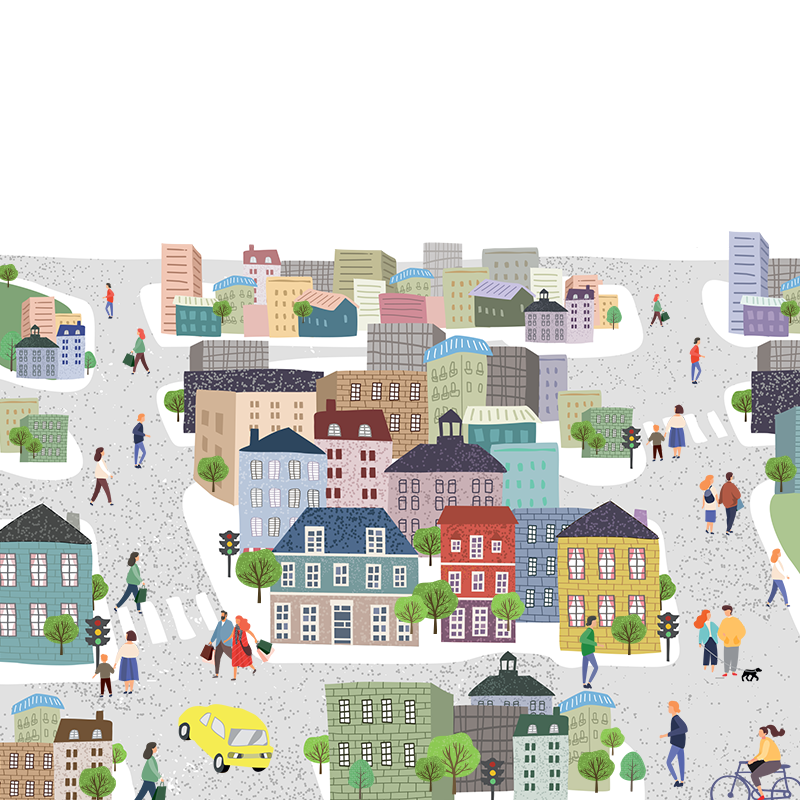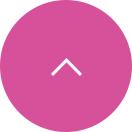第74回 3月16日「チーズ」前編
2025.03.16

人類最古の食品の1つと言われるチーズは、
メソポタミア文明で生まれて世界に広がったと考えられています。
砂漠を旅する商人が、羊の胃袋でできた水筒にミルクを入れて持ち運んでいたところ
ある時、気がつくとミルクが白い塊と液体に分離していて白い塊を食べてみると美味しく、
それがチーズになった・・・
アラビアには、そんな民話があります。
この羊や牛の胃にあるレンネットという酵素でミルクを固める方法は、現在もあるチーズの作り方。
そんなチーズが日本に入ってきたのは飛鳥時代。
この頃は「蘇」と呼ばれていました。
当時の書物に「西暦700年に文武天皇が蘇を造らせた」という記述がりますが、
蘇がどんなものだったのかは、詳しく分かっていません。
チーズやヨーグルトのようなものだという人もいれば、バターや練乳だという人もいて、
また、今と違って牛乳を煮詰めて固めて作っていたという説もあります。
いずれにしろ、蘇は栄養価の高さから貴族が口にする高級品だったようですが、
武家社会になると廃れていきました。
日本史上にチーズが復活するのは江戸時代のこと。
8代将軍 徳川吉宗公は、白牛を輸入して、今の千葉県南房総市に日本初の牧場を開き、
牛乳を煮詰めた「白牛酪」を製造しました。
団子状に丸めたこの「白牛酪」は、滋養強壮や解熱のため、
削って食べたり、お湯に溶かして飲んだとされています。
日本で現在の西洋的なチーズの製造が始まったのは、それから150年ほど経った明治時代。
庶民になじみのなかったその香りや味の特徴から、根づくまでに時間がかかることになります。
メソポタミア文明で生まれて世界に広がったと考えられています。
砂漠を旅する商人が、羊の胃袋でできた水筒にミルクを入れて持ち運んでいたところ
ある時、気がつくとミルクが白い塊と液体に分離していて白い塊を食べてみると美味しく、
それがチーズになった・・・
アラビアには、そんな民話があります。
この羊や牛の胃にあるレンネットという酵素でミルクを固める方法は、現在もあるチーズの作り方。
そんなチーズが日本に入ってきたのは飛鳥時代。
この頃は「蘇」と呼ばれていました。
当時の書物に「西暦700年に文武天皇が蘇を造らせた」という記述がりますが、
蘇がどんなものだったのかは、詳しく分かっていません。
チーズやヨーグルトのようなものだという人もいれば、バターや練乳だという人もいて、
また、今と違って牛乳を煮詰めて固めて作っていたという説もあります。
いずれにしろ、蘇は栄養価の高さから貴族が口にする高級品だったようですが、
武家社会になると廃れていきました。
日本史上にチーズが復活するのは江戸時代のこと。
8代将軍 徳川吉宗公は、白牛を輸入して、今の千葉県南房総市に日本初の牧場を開き、
牛乳を煮詰めた「白牛酪」を製造しました。
団子状に丸めたこの「白牛酪」は、滋養強壮や解熱のため、
削って食べたり、お湯に溶かして飲んだとされています。
日本で現在の西洋的なチーズの製造が始まったのは、それから150年ほど経った明治時代。
庶民になじみのなかったその香りや味の特徴から、根づくまでに時間がかかることになります。