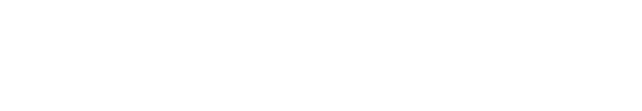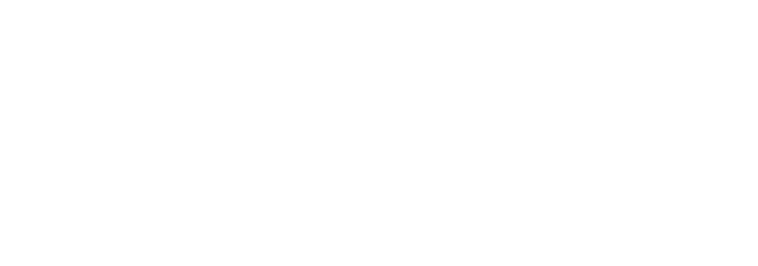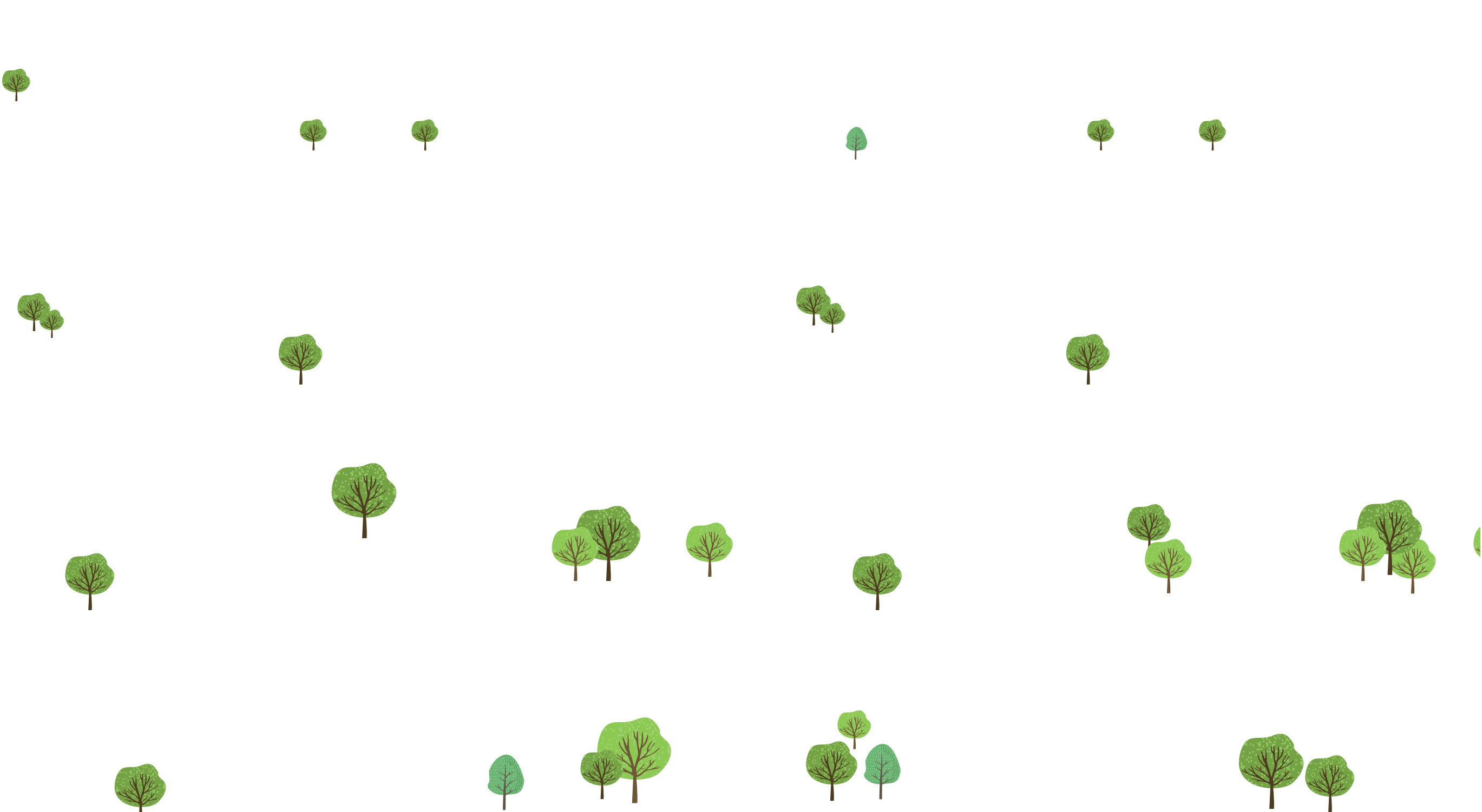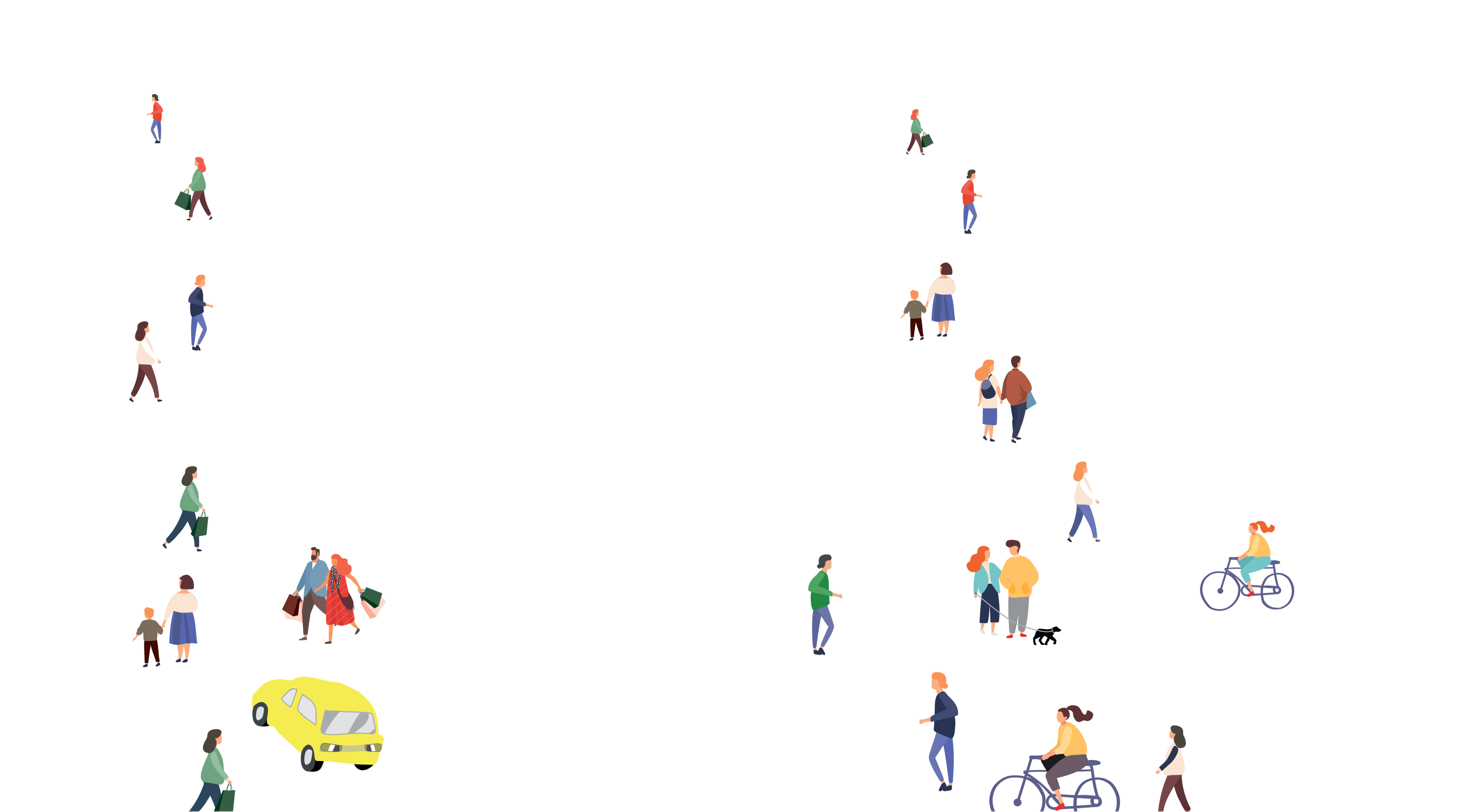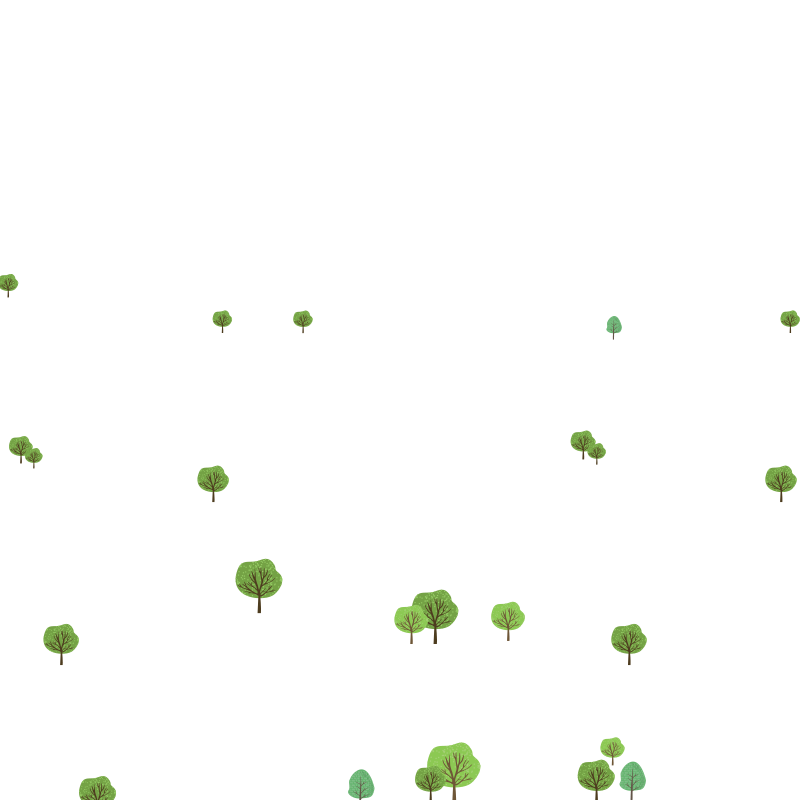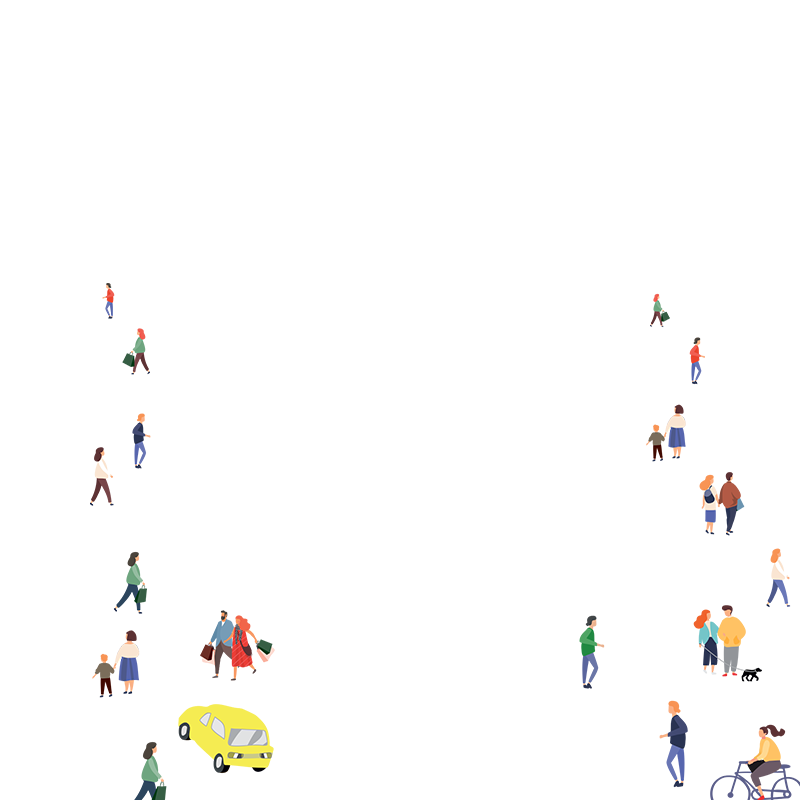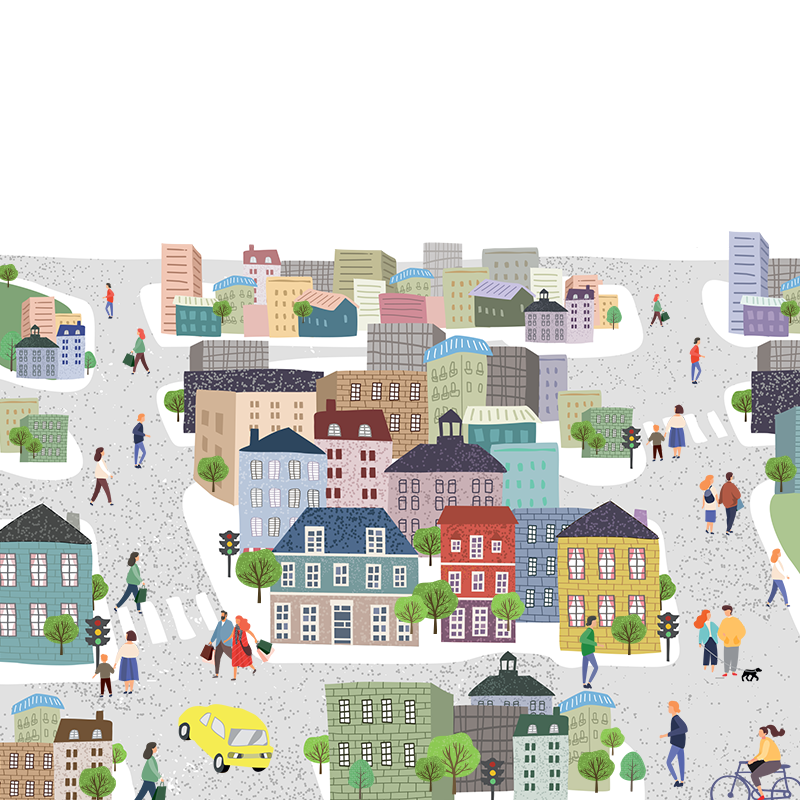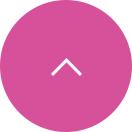第73回 3月9日「塩」後編
2025.03.09
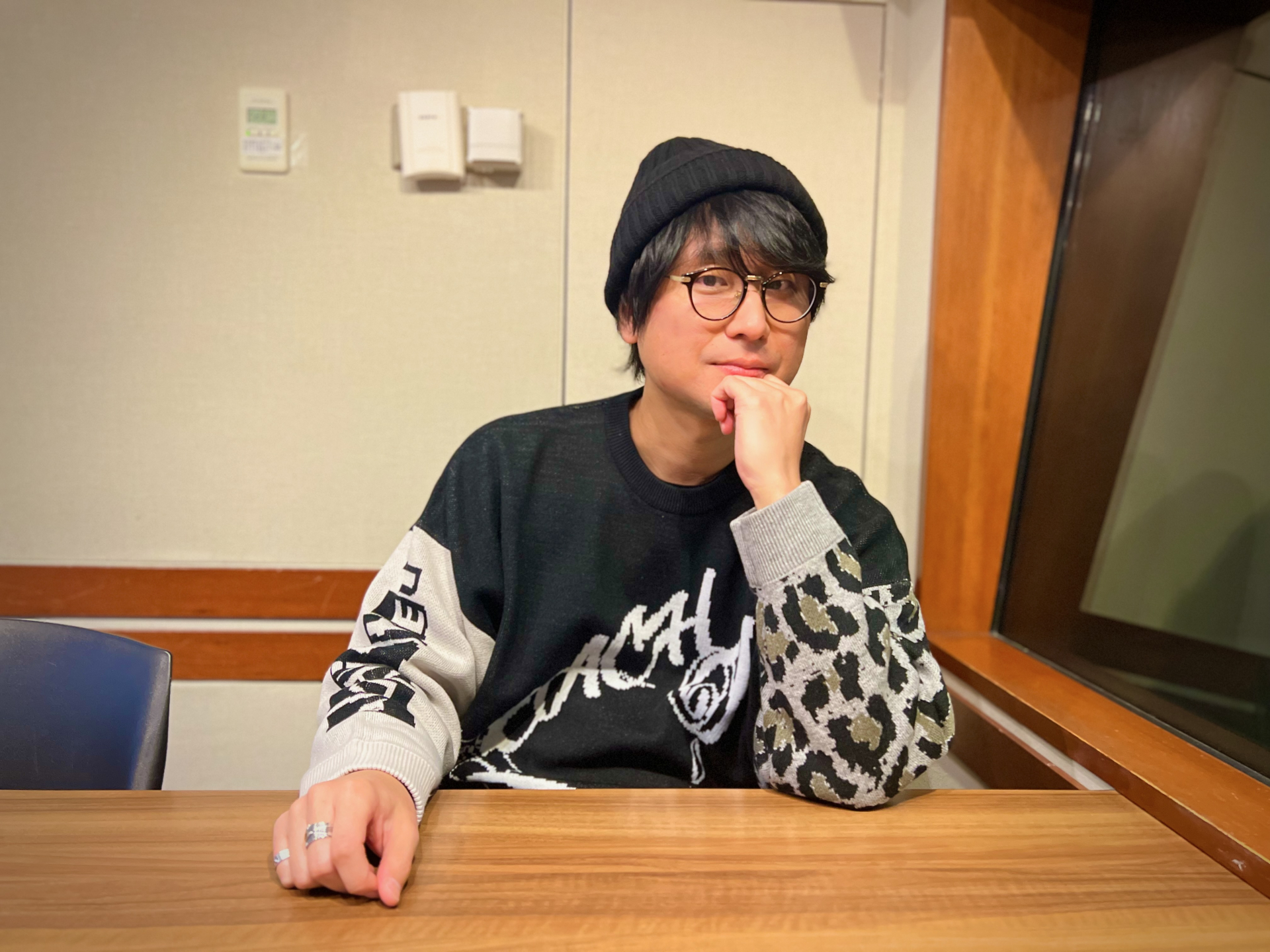
世界の塩生産量のおよそ3分の2は岩塩由来です。
遥か昔の地殻変動で海の一部が陸地となって塩分が結晶化したのが岩塩。
しかし、岩塩がない日本では、海水を利用して塩を使ってきました。
最も古くは、焼いた海藻の灰「灰」。
次に灰塩に海水を混ぜて濃い塩水、かん水をつくって煮詰めるようになります。
それが、干した海藻に付いた塩分を海水で洗い出し、
かん水をつくって煮詰める「藻塩焼き」と呼ばれる製塩法へ発展。
その後、砂を利用して濃い塩水をつくり、煮詰める方法に変わり「塩田」が生まれました。
長らく続いた塩田による製塩は
① 人が海水を汲んで撒くか、干潮と満潮の差を利用して、砂を海水で湿らせる
② 太陽熱と風で砂を乾燥させて沼井(ぬい)という装置に入れる
③ 沼井に海水を注ぎ、砂についた塩分を溶かす
④ 沼井の下から かん水が出てくる
⑤ かん水を煮詰めて結晶化させ、塩が完成
急激な変化が訪れたのは昭和40年代。
電気とイオンの特性を利用して海水中に塩分濃度が濃い部分を作り
それを採取して真空式の蒸発缶で煮つめる方法が実現したのです。
これならば、塩田のように天候に左右されず、効率的に生産できます。
ただ、日本の塩自給率は現在およそ13%。
海に囲まれた国なのに少し意外ですね。
意外と言えば、塩の消費量の約9割は食用以外の用途。
食用になるのは、わずか1割程度なのです。
最後に、私たちに欠かせない塩ですが、摂りすぎはよくありません。
日本の成人の1日あたりの平均摂取量は、男性が約11g、女性約9g。
しかし、適量とされているのは、男性7.5g、女性6.5g。
お気をつけ下さい。
遥か昔の地殻変動で海の一部が陸地となって塩分が結晶化したのが岩塩。
しかし、岩塩がない日本では、海水を利用して塩を使ってきました。
最も古くは、焼いた海藻の灰「灰」。
次に灰塩に海水を混ぜて濃い塩水、かん水をつくって煮詰めるようになります。
それが、干した海藻に付いた塩分を海水で洗い出し、
かん水をつくって煮詰める「藻塩焼き」と呼ばれる製塩法へ発展。
その後、砂を利用して濃い塩水をつくり、煮詰める方法に変わり「塩田」が生まれました。
長らく続いた塩田による製塩は
① 人が海水を汲んで撒くか、干潮と満潮の差を利用して、砂を海水で湿らせる
② 太陽熱と風で砂を乾燥させて沼井(ぬい)という装置に入れる
③ 沼井に海水を注ぎ、砂についた塩分を溶かす
④ 沼井の下から かん水が出てくる
⑤ かん水を煮詰めて結晶化させ、塩が完成
急激な変化が訪れたのは昭和40年代。
電気とイオンの特性を利用して海水中に塩分濃度が濃い部分を作り
それを採取して真空式の蒸発缶で煮つめる方法が実現したのです。
これならば、塩田のように天候に左右されず、効率的に生産できます。
ただ、日本の塩自給率は現在およそ13%。
海に囲まれた国なのに少し意外ですね。
意外と言えば、塩の消費量の約9割は食用以外の用途。
食用になるのは、わずか1割程度なのです。
最後に、私たちに欠かせない塩ですが、摂りすぎはよくありません。
日本の成人の1日あたりの平均摂取量は、男性が約11g、女性約9g。
しかし、適量とされているのは、男性7.5g、女性6.5g。
お気をつけ下さい。