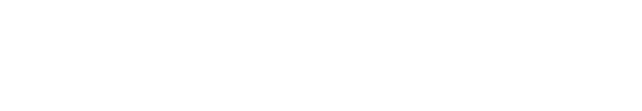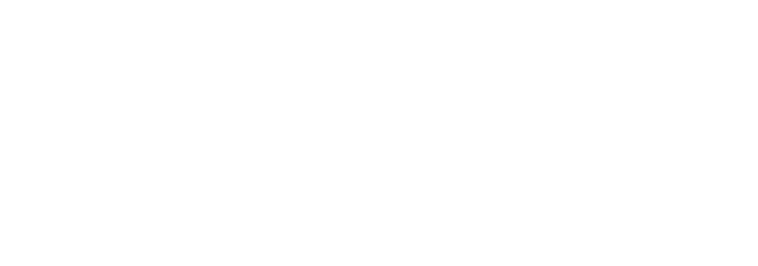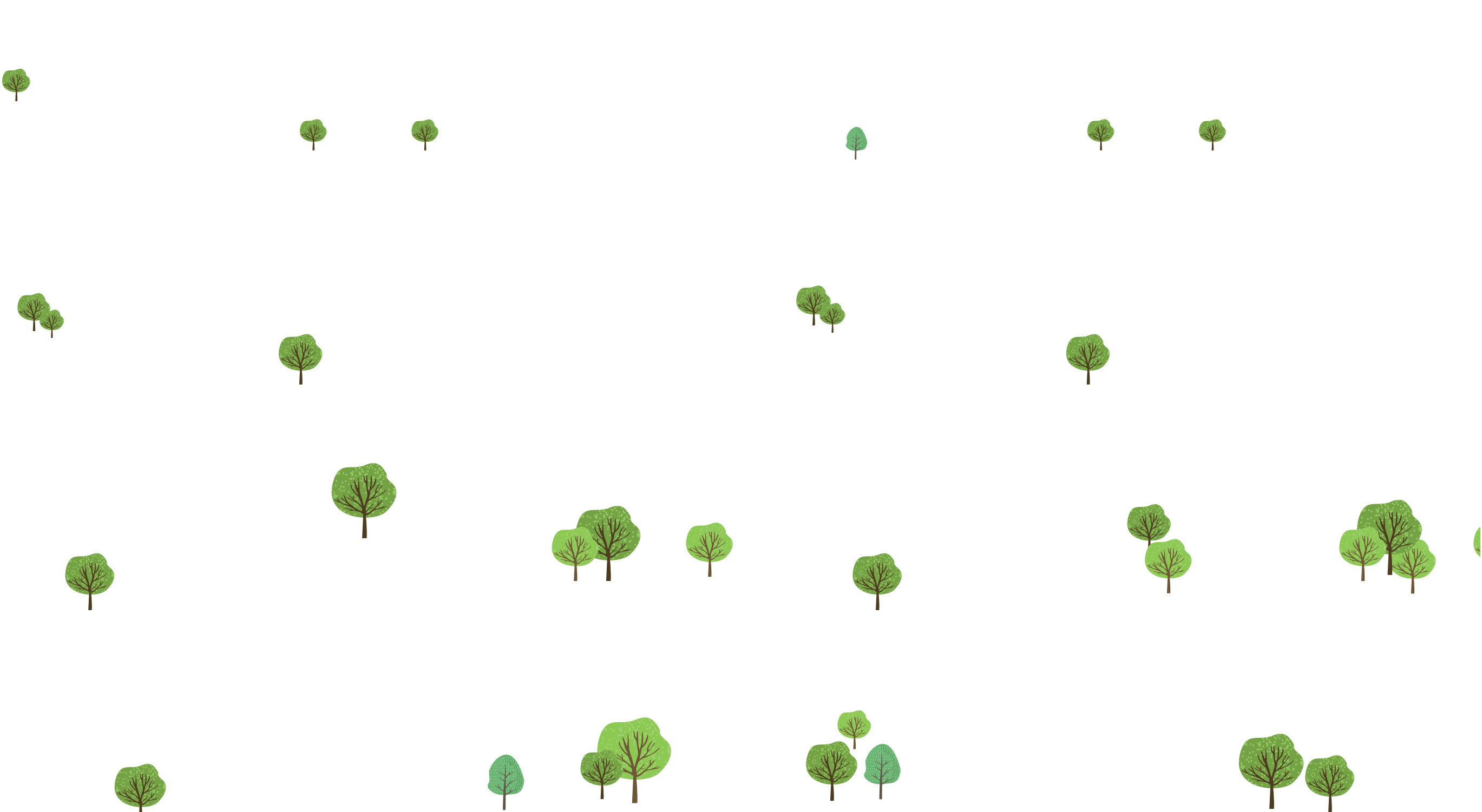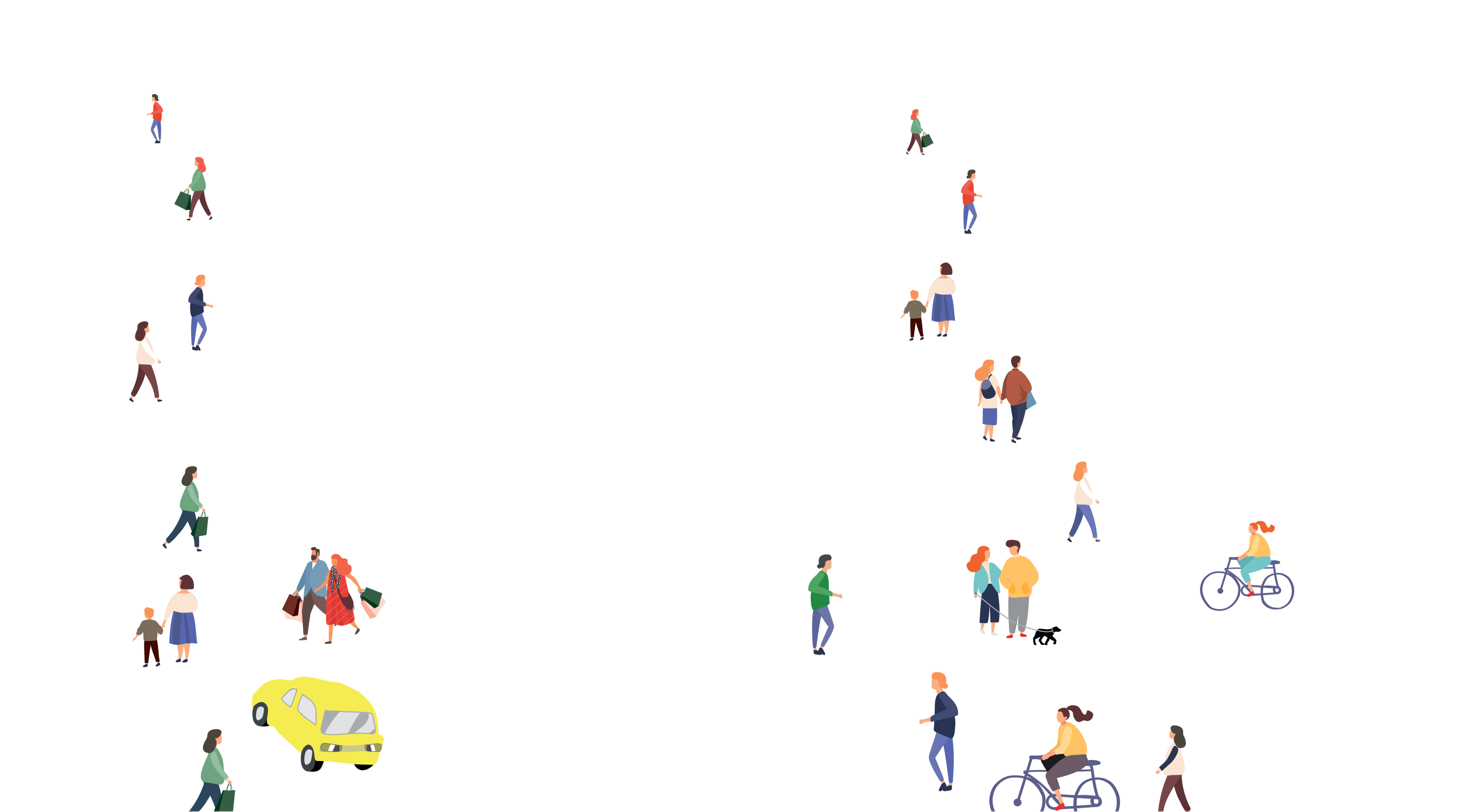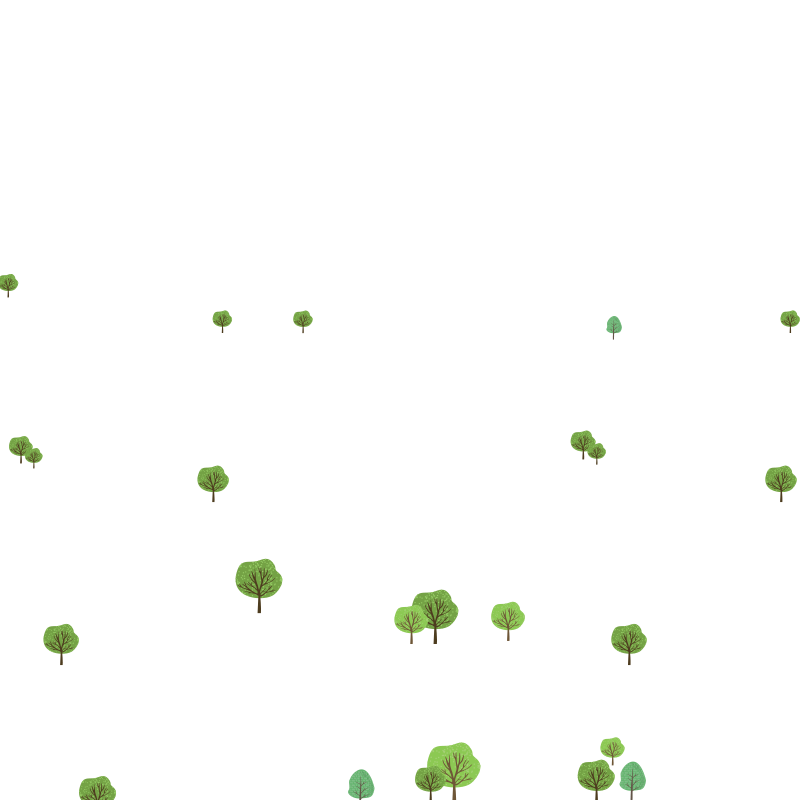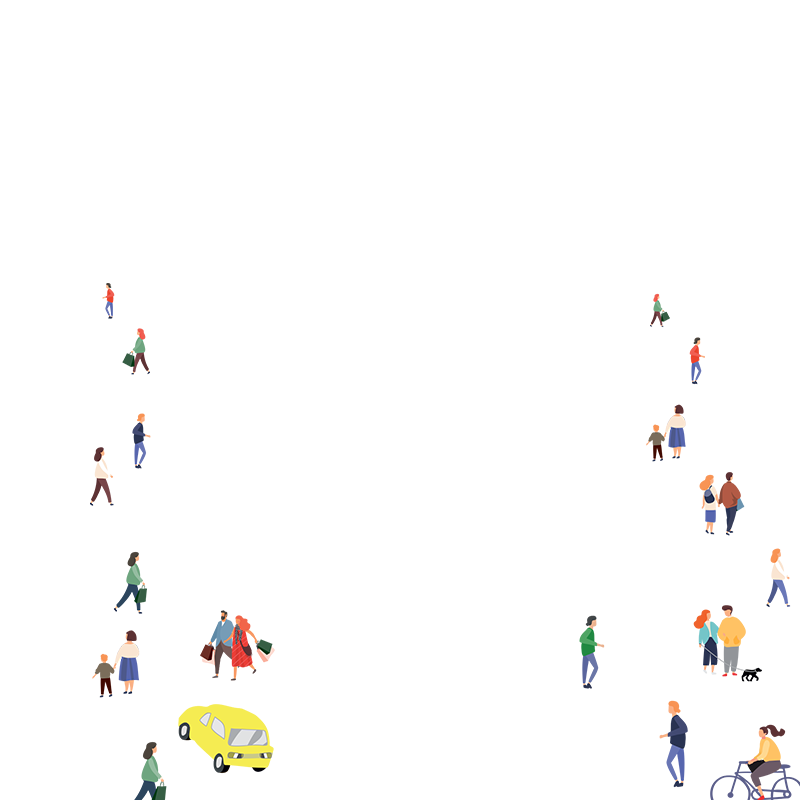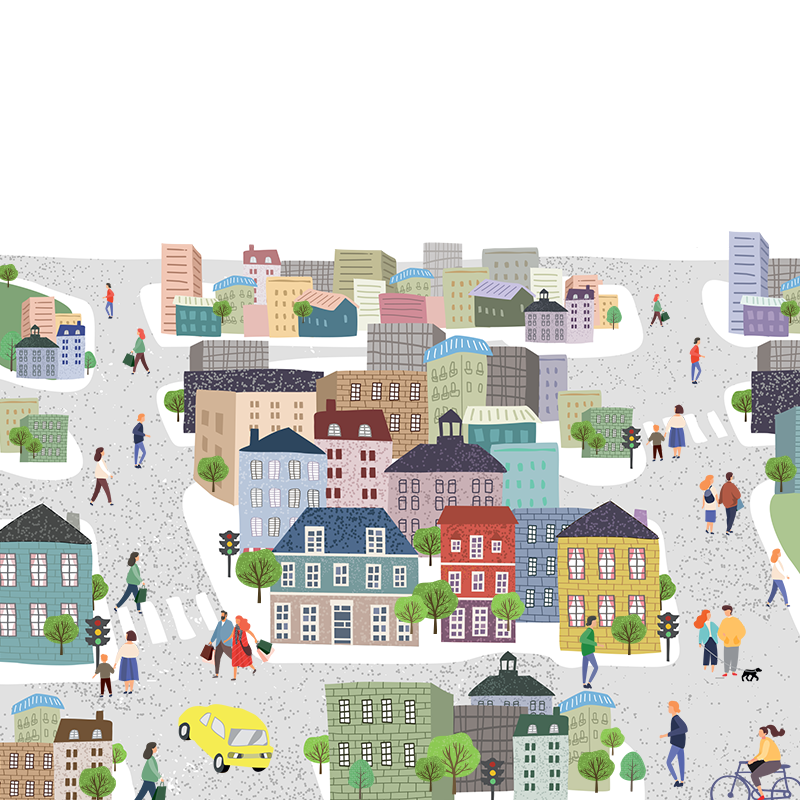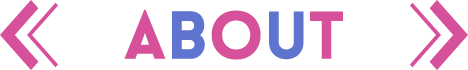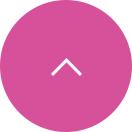毎週日曜日14:55-15:00(FM FUKUOKAのみ10:55-11:00)オンエア!毎回、世の中の”モノ”を取り上げ、そのモノの 歴史からイマ、未来をショートストーリー仕立てでお送りする番組です。身近なモノが少し、へえ~となるお話をお届けします。
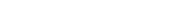
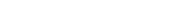
笠間 淳
声優。4月10日生まれ、広島県出身。
主な出演作品は、ナレーション「すくすく子育て」(NHK Eテレ)、劇場アニメ「THE FIRST SLAM DUNK」(三井寿)、アニメ「ガンダムビルドダイバーズ」(クジョウ・キョウヤ)、アニメ「お前はまだグンマを知らない」(轟二矢)、アニメ「タブー・タトゥー」(カーター)、ゲーム「アイドルマスター SideM」(葛之葉雨彦)など。
>>もっと読む

 2025.07.06
2025.07.06
第90回 7月6日「自動販売機」前編
自動販売機。
普通に考えると、最近の発明のように思うかもしれません。
ところが、世界最古のものは古代エジプトにあったとされています。
アレクサンドリアの学者ヘロンの著書「気体装置」によると、
紀元前215年頃、エジプトの神殿に聖水を売る装置があったそうです。
その仕組みは、投入口に硬貨を入れると、重みで受け皿が沈み、
出口を塞ぐ蓋がテコの原理で開いて受け皿が元に戻るまでの時間、水が出るというもの。
テコの原理を生かしたので、電気がない時代でも可能だったのです。
そして、現存する最古の自動販売機は、1615年のイギリスにあったタバコの自動販売機。
これは、投入口にコインを入れると、衝撃で留め金が外れ、
上部半分を覆っている蓋が開いて、煙草を自由に取り出せるというもの。
いくつ取るかは利用する人の良心に委ねられているので「正直箱」という名称だったそうです。
時は流れて1857年。
イギリス人のセミアン・デンハムさんが、切手の自動販売機を発明し、特許を取得しました。
これが特許を取った最初の自動販売機とされています。
その後のイギリスには、飲料、お菓子、食品などの販売機も誕生。
基本的な技術が確立しました。
現存する日本最古の自動販売機は、木製のハガキと切手の自動販売機。
俵谷高七さんという発明家が作り、ポストの機能も合わせ持ったアイデア製品でした。
普通に考えると、最近の発明のように思うかもしれません。
ところが、世界最古のものは古代エジプトにあったとされています。
アレクサンドリアの学者ヘロンの著書「気体装置」によると、
紀元前215年頃、エジプトの神殿に聖水を売る装置があったそうです。
その仕組みは、投入口に硬貨を入れると、重みで受け皿が沈み、
出口を塞ぐ蓋がテコの原理で開いて受け皿が元に戻るまでの時間、水が出るというもの。
テコの原理を生かしたので、電気がない時代でも可能だったのです。
そして、現存する最古の自動販売機は、1615年のイギリスにあったタバコの自動販売機。
これは、投入口にコインを入れると、衝撃で留め金が外れ、
上部半分を覆っている蓋が開いて、煙草を自由に取り出せるというもの。
いくつ取るかは利用する人の良心に委ねられているので「正直箱」という名称だったそうです。
時は流れて1857年。
イギリス人のセミアン・デンハムさんが、切手の自動販売機を発明し、特許を取得しました。
これが特許を取った最初の自動販売機とされています。
その後のイギリスには、飲料、お菓子、食品などの販売機も誕生。
基本的な技術が確立しました。
現存する日本最古の自動販売機は、木製のハガキと切手の自動販売機。
俵谷高七さんという発明家が作り、ポストの機能も合わせ持ったアイデア製品でした。
>>続きを読む
 2025.06.29
2025.06.29
第89回 6月29日「フリートーク 〜 笠間淳の音楽的ルーツ」
3ヶ月に1度の番組ナビゲーター 笠間淳さんのフリートーク。
今回のテーマは「音楽的ルーツ」でした。
現在、仕事として歌うこともある笠間さん。
そのルーツは・・・「ゆず」。
青春時代はストリートから登場したフォーク系ミュージシャンがブームで
笠間さんもゆずに出会ってギターを弾き、ハーモニカを吹き、
作詞・作曲した歌を路上で演奏していたそうです。
それが今でも歌うことが好きなところに繋がっていると感じているとか。
そして、最近は音楽はジャンルを問わず、昔の曲を聴いているそうです。
特に大学時代に好きだったジャーマンメタルのバンド Helloween!
ちょっと意外ですね(笑)
ボーカルのマイケル・キスクがカッコよくて大好きだったということで
Helloweenを聴いたことがない方、ぜひ聴いてみて下さい。
この「三井倉庫グループ presents 未来に“つなぐ”物語」では感想やメッセージ、
それからテーマにしてほしいモノや発明を募集しています。
こちらのメッセージフォームからどうぞ!
今回のテーマは「音楽的ルーツ」でした。
現在、仕事として歌うこともある笠間さん。
そのルーツは・・・「ゆず」。
青春時代はストリートから登場したフォーク系ミュージシャンがブームで
笠間さんもゆずに出会ってギターを弾き、ハーモニカを吹き、
作詞・作曲した歌を路上で演奏していたそうです。
それが今でも歌うことが好きなところに繋がっていると感じているとか。
そして、最近は音楽はジャンルを問わず、昔の曲を聴いているそうです。
特に大学時代に好きだったジャーマンメタルのバンド Helloween!
ちょっと意外ですね(笑)
ボーカルのマイケル・キスクがカッコよくて大好きだったということで
Helloweenを聴いたことがない方、ぜひ聴いてみて下さい。
この「三井倉庫グループ presents 未来に“つなぐ”物語」では感想やメッセージ、
それからテーマにしてほしいモノや発明を募集しています。
こちらのメッセージフォームからどうぞ!
>>続きを読む
 2025.06.22
2025.06.22
第88回 6月22日「冷蔵庫」後編
電気冷蔵庫のルーツとされているのは、
アメリカの発明家 ジェイコブ・パーキンスさんが、1834年に開発した機械式の製氷機です。
これは、容易に蒸発する揮発性の液体を冷媒=冷却剤として
人が手押しの空気ポンプで減圧=気圧を下げると
冷媒が蒸発する時に周囲から気加熱を奪い、それによって冷却するという原理。
気化した冷媒はその後、今度は加圧されて再び液化するといったように循環しています。
この仕組みは現在の電気冷蔵庫も同じで、電気の力で減圧と加圧が繰り返されているのです。
家庭用の電気冷蔵庫が初めて作られたのは1918年のアメリカ。
その5年後には、日本に輸入され、初の国産製品が発売されたのは1930年。
しかし、しばらくの間は「超」がつくほどの高級品で
普及し始めるのは昭和30年代以降、高度経済成長期に入ってからのことでした。
電気冷蔵庫が、電気洗濯機・白黒テレビとともに「三種の神器」と呼ばれる
憧れと豊かさの象徴だった話は聞いたことがあるでしょう。
普及率は昭和40年に90%、昭和50年に96%へと達して
時代とともに大型化と多機能化が進んできました。
AI時代の今、電気製品の技術進化には目覚ましいものがあります。
電気冷蔵庫で言うと・・・
ドアを開けると、カメラが自動で冷蔵室を撮影したり
買い物中に写真をスマホでチェックすると買い忘れや二重買いが防げたり
スマホで使い忘れを知らせてほしい食材・日付を登録しておけば、
登録した日に音声などで知らせてくれたりと・・・なんてお利口さん(笑)
さらに節電機能もかなり向上しています。
電気代を節約するポイントは
☆ 大量にモノを入れておかない
☆ 開け閉めは少なく 開けっぱなしにしない
☆ 室温によって設定温度を調整
☆ 温かいものは冷めてから入れる
といったことが挙げられています。
無駄な電力消費は避けて便利な冷蔵庫を使いましょう。
アメリカの発明家 ジェイコブ・パーキンスさんが、1834年に開発した機械式の製氷機です。
これは、容易に蒸発する揮発性の液体を冷媒=冷却剤として
人が手押しの空気ポンプで減圧=気圧を下げると
冷媒が蒸発する時に周囲から気加熱を奪い、それによって冷却するという原理。
気化した冷媒はその後、今度は加圧されて再び液化するといったように循環しています。
この仕組みは現在の電気冷蔵庫も同じで、電気の力で減圧と加圧が繰り返されているのです。
家庭用の電気冷蔵庫が初めて作られたのは1918年のアメリカ。
その5年後には、日本に輸入され、初の国産製品が発売されたのは1930年。
しかし、しばらくの間は「超」がつくほどの高級品で
普及し始めるのは昭和30年代以降、高度経済成長期に入ってからのことでした。
電気冷蔵庫が、電気洗濯機・白黒テレビとともに「三種の神器」と呼ばれる
憧れと豊かさの象徴だった話は聞いたことがあるでしょう。
普及率は昭和40年に90%、昭和50年に96%へと達して
時代とともに大型化と多機能化が進んできました。
AI時代の今、電気製品の技術進化には目覚ましいものがあります。
電気冷蔵庫で言うと・・・
ドアを開けると、カメラが自動で冷蔵室を撮影したり
買い物中に写真をスマホでチェックすると買い忘れや二重買いが防げたり
スマホで使い忘れを知らせてほしい食材・日付を登録しておけば、
登録した日に音声などで知らせてくれたりと・・・なんてお利口さん(笑)
さらに節電機能もかなり向上しています。
電気代を節約するポイントは
☆ 大量にモノを入れておかない
☆ 開け閉めは少なく 開けっぱなしにしない
☆ 室温によって設定温度を調整
☆ 温かいものは冷めてから入れる
といったことが挙げられています。
無駄な電力消費は避けて便利な冷蔵庫を使いましょう。
>>続きを読む
 2025.06.15
2025.06.15
第87回 6月15日「冷蔵庫」前編
家電製品の1つ、冷蔵庫。
日本で初めて電灯が灯ったのは文明開化の時代、1882年(明治15年)の銀座。
それ以前に現在のような冷蔵庫はありませんでした。
ただ、かつての人々も食糧の保存のため
飲み物や食べ物を冷やして美味しく口にするため
自然や環境を冷蔵庫のような役割で上手に利用していました。
日本では日本書紀などの書物に氷や雪を使って物を冷やした記録があります。
洞窟の中や地下に貯蔵庫を作ったりもしていたようです。
もちろん井戸水や川の水も使っていたことでしょう。
海外を見ると、16世紀のイタリアで硝石(硝酸カリウム)を水に溶かすと
水の温度が下がることが発見され、ワインなどを冷やす目的で利用されています。
そんな時代を経て、元祖・冷蔵庫が登場したのは1803年。
アメリカのトマス・ムーアさんが、氷で物を冷やす箱を開発。
これを「refrigerator」と名付けました。
その後、人工的に氷を作る技術が確立されたこともあり
当初の冷蔵庫は電気を使わない人工的な氷で物を冷却する箱。
ちなみにrefrigeratorはラテン語で「再び」「冷やす」という意味で
現在の「冷蔵庫」を指す英単語にもなっています。
氷を使う冷蔵庫は、明治時代になると日本にも伝わり
大正時代から昭和初期に「氷箱」という名称で一部の上流家庭に広まりました。
しかし、今のような家庭用電気冷蔵庫が普及するのは、まだ先の、それから40年近く後のこと。
家電製品や自動車など耐久消費財の統計が取られるようになった1957年(昭和32年)時点では、
冷蔵庫の一般家庭への普及率は、わずかに2.8%でした。
日本で初めて電灯が灯ったのは文明開化の時代、1882年(明治15年)の銀座。
それ以前に現在のような冷蔵庫はありませんでした。
ただ、かつての人々も食糧の保存のため
飲み物や食べ物を冷やして美味しく口にするため
自然や環境を冷蔵庫のような役割で上手に利用していました。
日本では日本書紀などの書物に氷や雪を使って物を冷やした記録があります。
洞窟の中や地下に貯蔵庫を作ったりもしていたようです。
もちろん井戸水や川の水も使っていたことでしょう。
海外を見ると、16世紀のイタリアで硝石(硝酸カリウム)を水に溶かすと
水の温度が下がることが発見され、ワインなどを冷やす目的で利用されています。
そんな時代を経て、元祖・冷蔵庫が登場したのは1803年。
アメリカのトマス・ムーアさんが、氷で物を冷やす箱を開発。
これを「refrigerator」と名付けました。
その後、人工的に氷を作る技術が確立されたこともあり
当初の冷蔵庫は電気を使わない人工的な氷で物を冷却する箱。
ちなみにrefrigeratorはラテン語で「再び」「冷やす」という意味で
現在の「冷蔵庫」を指す英単語にもなっています。
氷を使う冷蔵庫は、明治時代になると日本にも伝わり
大正時代から昭和初期に「氷箱」という名称で一部の上流家庭に広まりました。
しかし、今のような家庭用電気冷蔵庫が普及するのは、まだ先の、それから40年近く後のこと。
家電製品や自動車など耐久消費財の統計が取られるようになった1957年(昭和32年)時点では、
冷蔵庫の一般家庭への普及率は、わずかに2.8%でした。
>>続きを読む
 2025.06.08
2025.06.08
第86回 6月8日「水筒」後編
近代以降、水筒は飛躍的に進化してきました。
19世紀から広く普及したのがアルミニウム製の水筒。
戦後になるとプラスチック製やステンレス製など、素材も多様になっていきます。
一方で19世紀終わりには、後の水筒に大きな影響を与える開発がありました。
それは、魔法瓶。発明したのは、液体を長時間、温かく、または冷たく保つ方法を研究した
イギリスの化学者・物理学者 ジェームス・デュワーさん。
1873年、デュワーさんは金属容器を2重にして
間を真空にすると断熱効果があることを発見します。
その後、他の研究者によるガラス容器を使った実験などを経て
1892年、デュワーさんは、ガラスを2重に、その間を真空にしました。
そして、内壁部分のガラスに銀メッキを施し、鏡のような状態にすることで
熱を閉じ込めることをかのうにしました。これが、魔法瓶の基本的な原理です。
戦後、魔法瓶の技術は水筒にも応用されるようになりました。
昭和50年代になると、ステンレス製魔法瓶が日本で開発され
保温性があるだけでなく、割れない携帯水筒が広まります。
そして、令和7年の現在、水筒はマイボトルと言われるようになって大人気!
素材・機能・デザイン・サイズ、本当にさまざまな商品が出ています。
飲み物によって使うものを変える複数持ちの人も多いとか。
ちなみに最近は洗いやすさがポイントの1つ。
底まで洗えるタイプが注目されているようです。
職場へ、学校へ。
お気に入りのマイボトルで好きな飲み物を持っていくと
気分がよくてパフォーマンスも上がりそう。
お財布にも環境にも優しいマイボトル、マイ水筒、楽しんではどうでしょうか?
19世紀から広く普及したのがアルミニウム製の水筒。
戦後になるとプラスチック製やステンレス製など、素材も多様になっていきます。
一方で19世紀終わりには、後の水筒に大きな影響を与える開発がありました。
それは、魔法瓶。発明したのは、液体を長時間、温かく、または冷たく保つ方法を研究した
イギリスの化学者・物理学者 ジェームス・デュワーさん。
1873年、デュワーさんは金属容器を2重にして
間を真空にすると断熱効果があることを発見します。
その後、他の研究者によるガラス容器を使った実験などを経て
1892年、デュワーさんは、ガラスを2重に、その間を真空にしました。
そして、内壁部分のガラスに銀メッキを施し、鏡のような状態にすることで
熱を閉じ込めることをかのうにしました。これが、魔法瓶の基本的な原理です。
戦後、魔法瓶の技術は水筒にも応用されるようになりました。
昭和50年代になると、ステンレス製魔法瓶が日本で開発され
保温性があるだけでなく、割れない携帯水筒が広まります。
そして、令和7年の現在、水筒はマイボトルと言われるようになって大人気!
素材・機能・デザイン・サイズ、本当にさまざまな商品が出ています。
飲み物によって使うものを変える複数持ちの人も多いとか。
ちなみに最近は洗いやすさがポイントの1つ。
底まで洗えるタイプが注目されているようです。
職場へ、学校へ。
お気に入りのマイボトルで好きな飲み物を持っていくと
気分がよくてパフォーマンスも上がりそう。
お財布にも環境にも優しいマイボトル、マイ水筒、楽しんではどうでしょうか?
>>続きを読む
 2025.06.01
2025.06.01
第85回 6月1日「水筒」前編
古の生活には、今のような飲料用の缶やペットボトルはありません。
人類は何千年もの昔から飲み物を持ち運ぶ容器を見出して「水筒」として使ってきました。
素材にしたのは、それぞれの地域の暮らしや特性に合ったもの。
例えば、以前「チーズの物語」でふれたように、
古代アラビア商人が、ミルクを携帯していたのはヤギの胃袋の「水筒」。
また、紀元前3千年頃には既に皮をなめす技術が確立していたと言われていて
ヨーロッパや中国で使われていたのは、動物の皮を縫い合わせた「水筒」。
天然素材としては、北アフリカ原産とされる瓢箪が世界で栽培され「水筒」が作られます。
東アジアでは、竹を「水筒」として利用しました。
長らく日本で使われてきたのは、縄文時代に伝わったとされる瓢箪と主には竹の「水筒」。
竹は軽くて持ち運びやすいことと、おにぎりを包むのも竹の皮だったように
その抗菌作用や腐敗防止効果に気づいていたからだと考えられます。
そんな水筒は、時代とともに装飾品としての要素を持つものも作られるようになりました。
日本では幕府が安定期に入り、産業が発達して町民文化が花開いた江戸時代中期、
庶民も家紋を身につけるようになると、行楽や芝居見物に持っていくための
漆塗りで家紋が入った木製の水筒も登場しています。
そして、明治時代に入った頃には、軽くて丈夫なアルミニウム製の水筒が誕生。
そこからプラスチック製、ステンレス製と水筒の素材は増えるともに機能性も上がっていきます。
戦後の高度経済成長期の頃には、保温タイプの水筒も登場しますが・・・
この続きは後編で。
人類は何千年もの昔から飲み物を持ち運ぶ容器を見出して「水筒」として使ってきました。
素材にしたのは、それぞれの地域の暮らしや特性に合ったもの。
例えば、以前「チーズの物語」でふれたように、
古代アラビア商人が、ミルクを携帯していたのはヤギの胃袋の「水筒」。
また、紀元前3千年頃には既に皮をなめす技術が確立していたと言われていて
ヨーロッパや中国で使われていたのは、動物の皮を縫い合わせた「水筒」。
天然素材としては、北アフリカ原産とされる瓢箪が世界で栽培され「水筒」が作られます。
東アジアでは、竹を「水筒」として利用しました。
長らく日本で使われてきたのは、縄文時代に伝わったとされる瓢箪と主には竹の「水筒」。
竹は軽くて持ち運びやすいことと、おにぎりを包むのも竹の皮だったように
その抗菌作用や腐敗防止効果に気づいていたからだと考えられます。
そんな水筒は、時代とともに装飾品としての要素を持つものも作られるようになりました。
日本では幕府が安定期に入り、産業が発達して町民文化が花開いた江戸時代中期、
庶民も家紋を身につけるようになると、行楽や芝居見物に持っていくための
漆塗りで家紋が入った木製の水筒も登場しています。
そして、明治時代に入った頃には、軽くて丈夫なアルミニウム製の水筒が誕生。
そこからプラスチック製、ステンレス製と水筒の素材は増えるともに機能性も上がっていきます。
戦後の高度経済成長期の頃には、保温タイプの水筒も登場しますが・・・
この続きは後編で。
>>続きを読む
放送時間
- TOKYO FM 14:55‐15:00
- FM大阪 14:55‐15:00
- FM AICHI 14:55‐15:00
- FM FUKUOKA 10:55-11:00