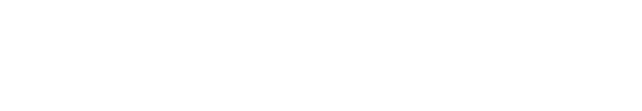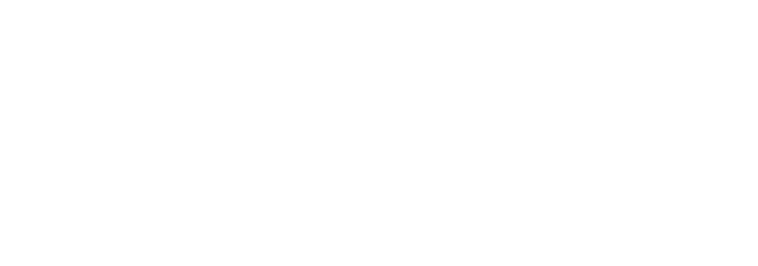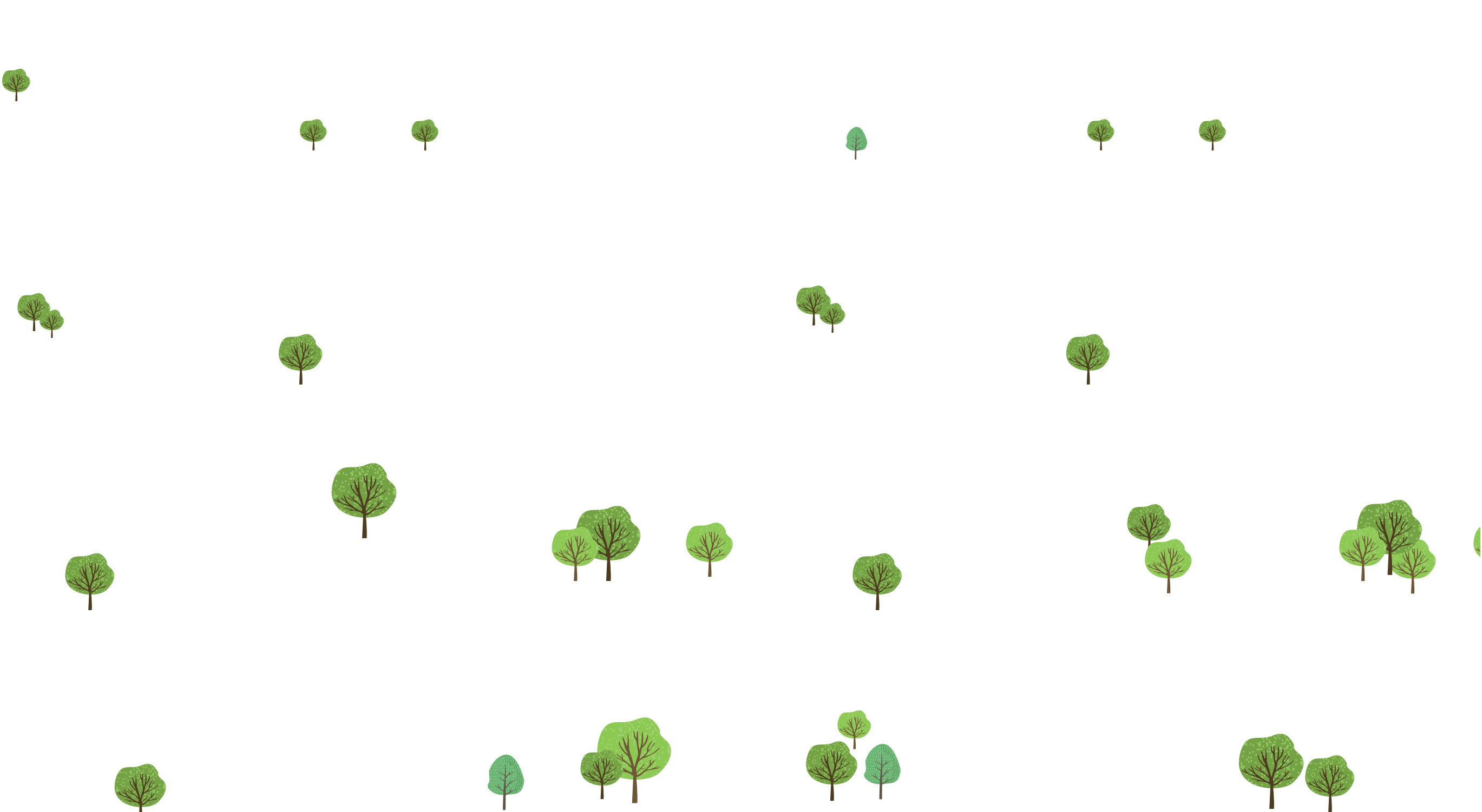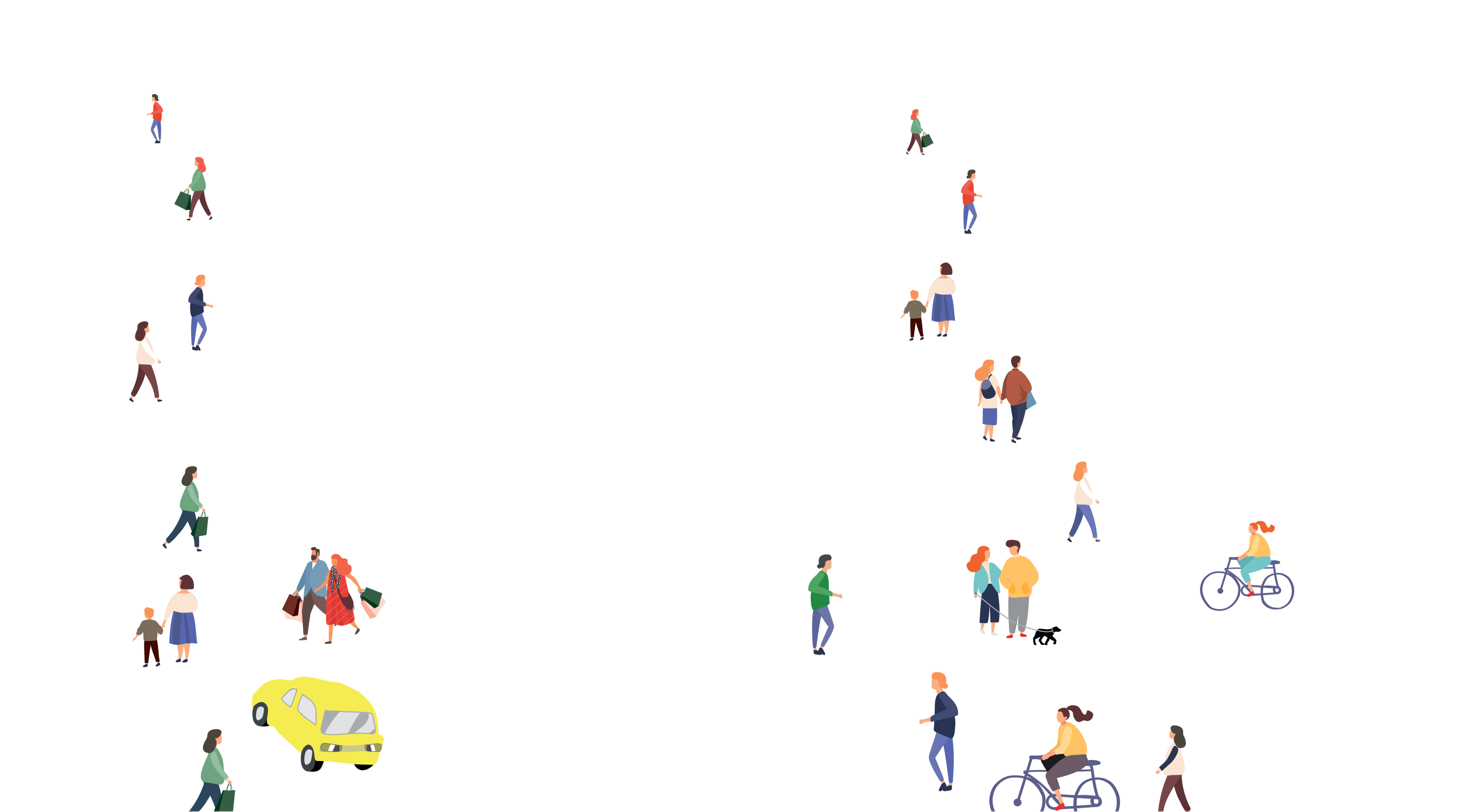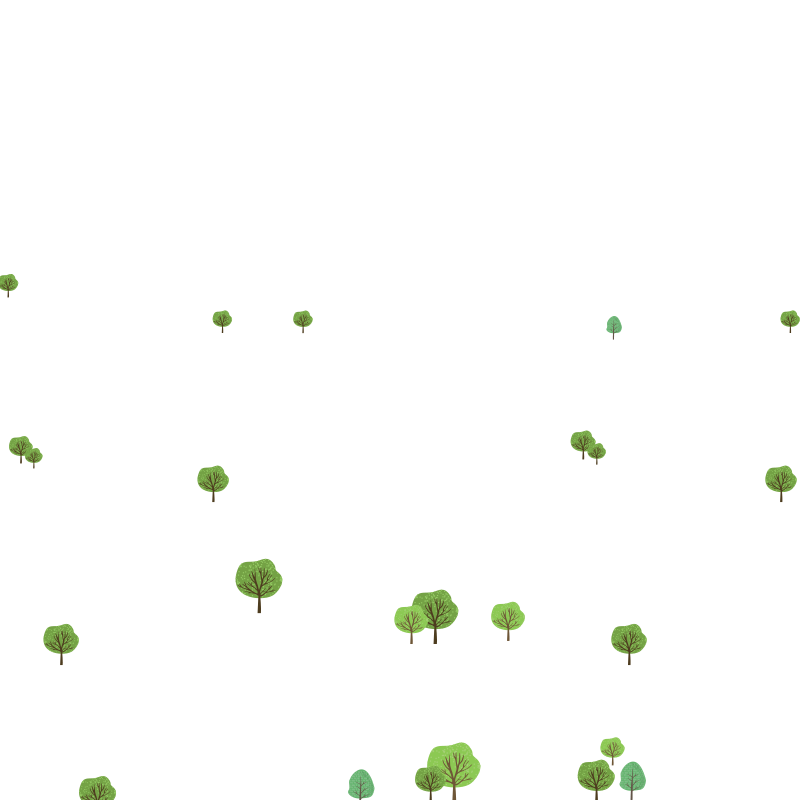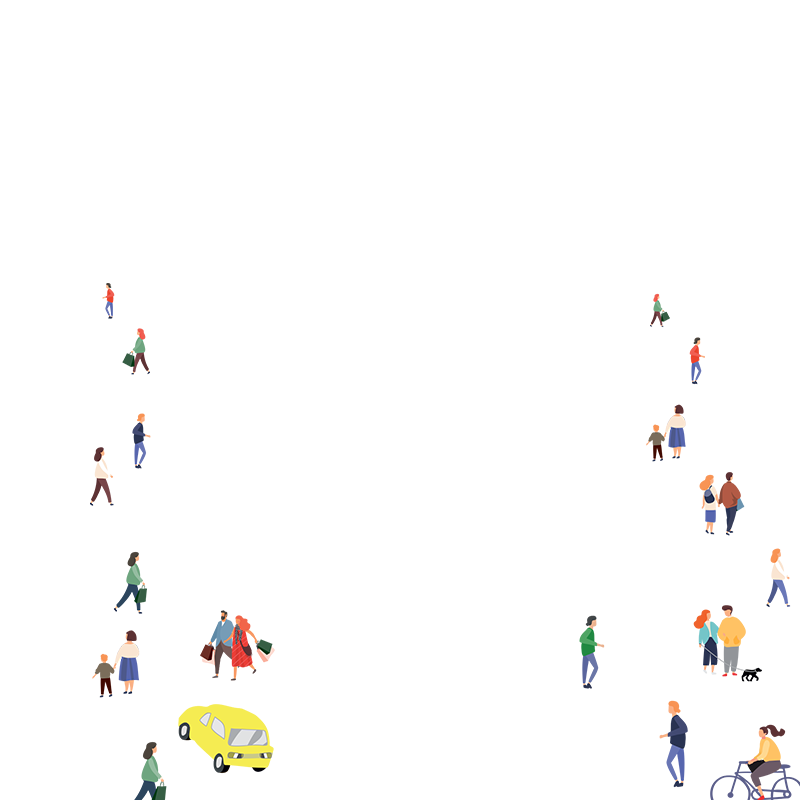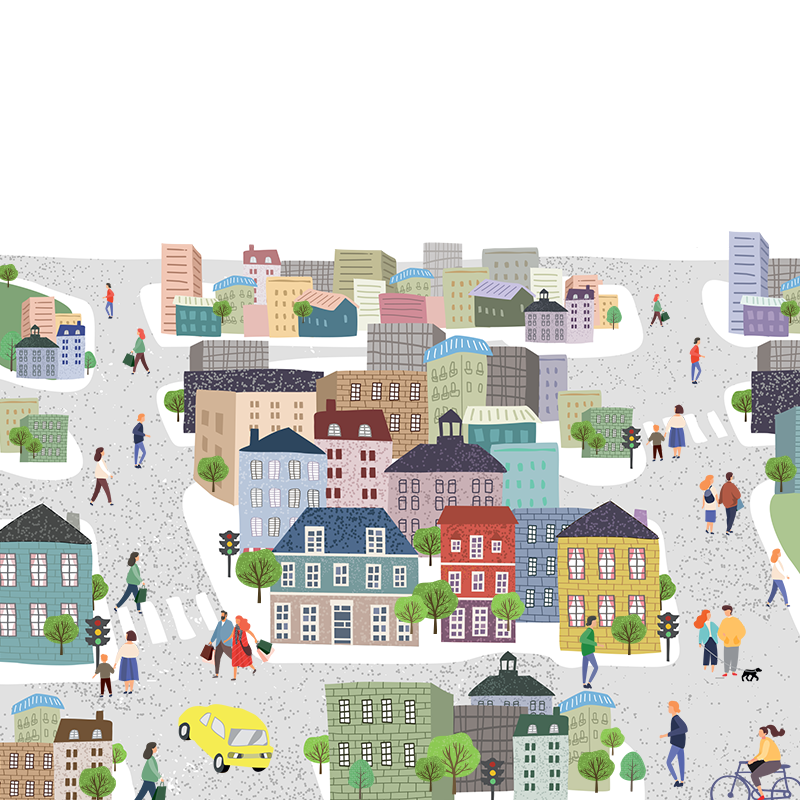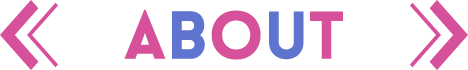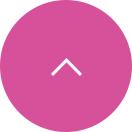毎週日曜日14:55-15:00(FM FUKUOKAのみ10:55-11:00)オンエア!毎回、世の中の”モノ”を取り上げ、そのモノの 歴史からイマ、未来をショートストーリー仕立てでお送りする番組です。身近なモノが少し、へえ~となるお話をお届けします。
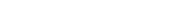
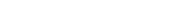
笠間 淳
声優。4月10日生まれ、広島県出身。
主な出演作品は、ナレーション「すくすく子育て」(NHK Eテレ)、劇場アニメ「THE FIRST SLAM DUNK」(三井寿)、アニメ「ガンダムビルドダイバーズ」(クジョウ・キョウヤ)、アニメ「お前はまだグンマを知らない」(轟二矢)、アニメ「タブー・タトゥー」(カーター)、ゲーム「アイドルマスター SideM」(葛之葉雨彦)など。
>>もっと読む

 2025.01.12
2025.01.12
第65回 1月12日「電子レンジ」後編
今でこそ「一家に一台」の電子レンジ。
ただ、どんな家電製品も当初は「そんな …
>>続きを読む
 2025.01.05
2025.01.05
第64回 1月5日「電子レンジ」前編
スイッチを入れるだけで冷凍食品を解凍できて、お弁当を温められて、
ちょっと …
>>続きを読む
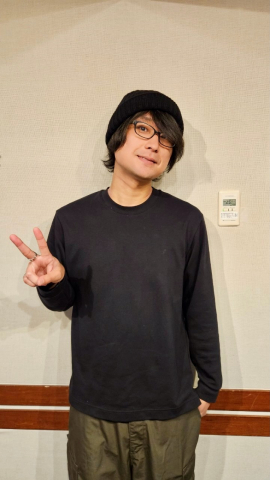 2024.12.29
2024.12.29
第63回 12月29日「2024年お世話 …
今日のオンエアは『未来に「つなぐ」物語』2024年最後の回。
3ヶ月に1度 …
>>続きを読む
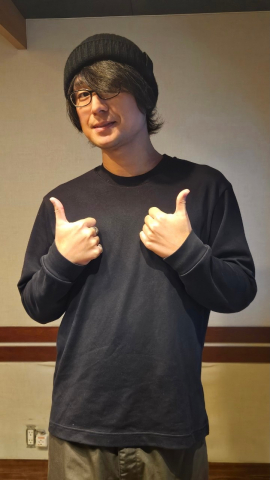 2024.12.22
2024.12.22
第62回 12月22日「段ボール」後編
断面が階段のように段々の波なので段ボールだと先週お伝えしました。
この波を …
>>続きを読む
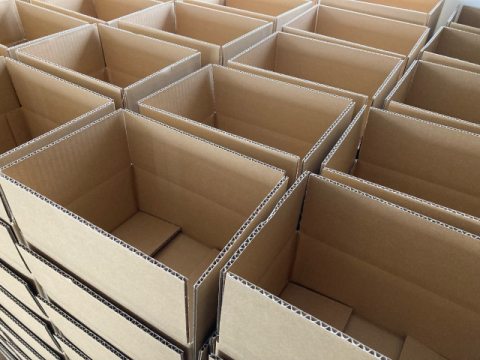 2024.12.15
2024.12.15
第61回 12月15日「段ボール」前編
「だん」を片仮名にして「ダンボール」と表記する時もありますが、本来は「段ボ …
>>続きを読む
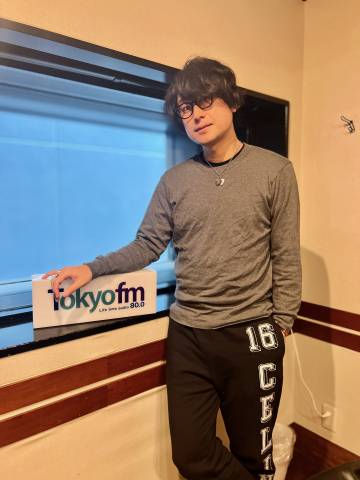 2024.12.08
2024.12.08
第60回 12月8日「ボールペン」後編
戦後、アメリカから日本に持ち込まれたボールペン。
1947年にはアメリカの …
>>続きを読む
放送時間
- TOKYO FM 14:55‐15:00
- FM大阪 14:55‐15:00
- FM AICHI 14:55‐15:00
- FM FUKUOKA 10:55-11:00