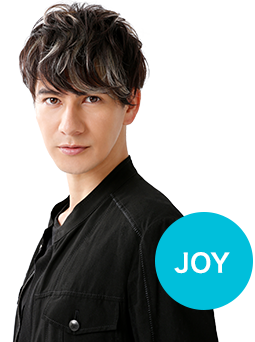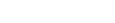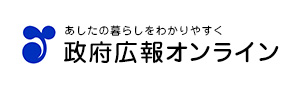順次、変わっていきます 相続に関するルール
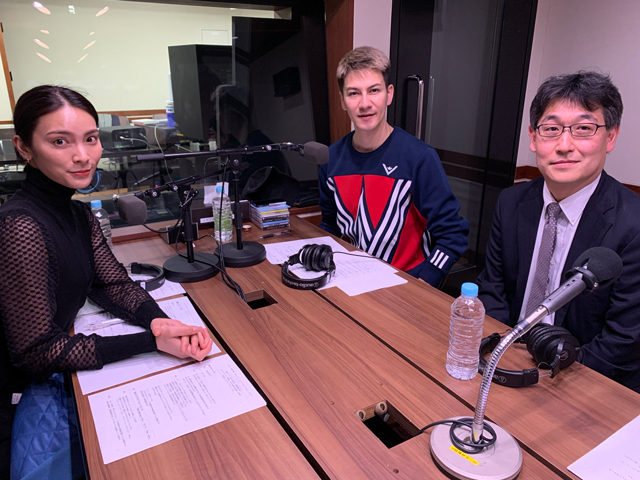
高齢化が進む中、日本では社会環境が大きく変化してきています。
そんな時代の変化に対応するため「相続法」も改正されました。
今回は「順次、変わっていきます 相続に関するルール」というテーマでお話しました。
秋元 さぁ、今日は、「相続」についてお話をしていきます。
JOYくんは相続と聞くと、どんなイメージを持っていますか。
JOY ドラマの影響かもしれないけど、なにかと揉めたりするイメージがあるな。あと、遺言書の書き方かな。書き方によっては、無効になることもあると聞いたことがあるよ。
秋元 改めて相続についてですが、相続とは、人が亡くなった時に、残された預貯金や不動産などの財産を、特定の人が引き継ぐことです。
民法には、人が亡くなった時の財産の相続などに関する基本的なルールが定められていて、この部分は相続法と呼ばれているそうです。
JOY 財産を引き継ぐのもそうなんだけど、亡くなった方の貯金をおろすには、手続がすごく複雑で大変という話を聞いたことがあるな。
あと、亡くなった方の財産だけでなく、借金も相続しないといけないんでしょ。
秋元 実は、この相続法が、40年ぶりに改正されて昨年の1月から順次、施行されているんですって。
早速、スペシャリストをお招きしましょう。
法務省 民事局 民事法制管理官 堂薗幹一郎さんです。
堂薗さん。40年ぶりに相続法が改正されたんですね。
堂薗 はい。日本は40年前と比べて高齢化が進むなど社会環境が変化しており、こうした変化に対応するために改正が行われました。
改正法は、すでにその大部分が施行されています。
秋元 そうなんですね。
堂薗 はい。例えば、先ほども話題にのぼっていましたが遺言書に関わるルールも一部、変更になりました。
例えば、遺言をする人が自分で遺言書を作成する場合には、これまでその全てを手書きで書かなければならないと、決められていました。
そのため、預貯金ならば、銀行名や支店名、口座の種類や口座番号、土地ならば、その土地の所在地や広さなど、遺言の対象になる財産の情報を記載した財産目録も財産を残すご本人が手書きで書かなければなりませんでした。
JOY これは、財産が多い人は書くのが大変ですね。
堂薗 はい。でも昨年1月13日から、遺言書に添付する財産目録はパソコンで作成したものも、認められるようになりました。
また、通帳のコピーを財産目録として添付することも認められるようになりました。
秋元 通帳のコピーもOKなんですね。
一つずつ間違えないように書いていくのは大変な作業だし、パソコンが使えるのは助かりますね。
堂薗 そうですね。ただし、遺言書の本文は全文、自分で書かなければならない点は変わりません。またパソコンで作成した財産目録には、偽造を防止するためご本人による署名と押印も必要です。
目録が2ページ以上に渡る場合は各ページに、署名と押印が必要です。
秋元 他にもすでに施行されている、新しい相続に関するルールはありますか。
堂薗 はい。新しく預貯金の払戻し制度が創設され昨年7月1日から施行されています。
これまでは、相続する人が複数いる場合、遺産分割終了前の遺産である預貯金の払戻しは、相続人全員が同意しないとできませんでした。
でもそれでは葬儀費用の支払や当面の生活費が賄えない場合もでてしまいます。
秋元 亡くなった方が家計を支えていた場合、そういうことも十分にありえますよね。
堂薗 そうなんです。でも新しく預貯金の払戻し制度が創設されたことにより、金額の上限はあるものの、預貯金の一定の割合については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で払戻しが受けられるようになりました。
秋元 相続する方は、ひとまず安心ですね。新しい相続に関するルールで、これから施行されるものもあるんですか。
堂薗 来月4月1日から「配偶者居住権」の制度が始まります。
これは、残された配偶者が安心できるように設けられたものなんです。
秋元 これはどういったものなんでしょうか。
堂薗 はい。来月4月1日に施行される「配偶者居住権」の制度は、遺産の分け方の選択肢を増やすことを目的に創設されました。
「配偶者居住権」とは、亡くなった方の配偶者が、亡くなった方の所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用できるという権利です。
秋元 イメージがわくよう、少し具体的に説明いただけますか。
堂薗 この制度ができる前は、例えば、夫が亡くなり、相続する人が複数いた場合、妻が自宅の所有権を取得してそこに住み続けようとすると、その分、預貯金などの取り分が減ってしまい、老後の生活資金が不足するという問題が生じていました。
これからは、相続の際、配偶者居住権を取得することで、妻は、住み慣れた自宅に住み続けることができ、しかも預貯金などの取り分をこれまでより増やすことができるようになります。
秋元 老後の生活は心配でしょうから、残された配偶者の方にとっては助かりますね。
堂薗 そうですね。ただし、この「配偶者居住権」は、先ほどの具体例でいうと、夫が亡くなることで妻に自然に発生するものではありません。
遺産の分割協議によって、配偶者はこの権利を取得できるようになるので、子供など他の相続人と十分に話し合ってください。
JOY この権利を取得する際、気をつけるべきことはありますか。
堂薗 配偶者居住権が設定された家の所有権は、通常、別の人が取得します。
従って、家の所有権を取得した人は、その家を他の人に売り渡すこともあり得ます。そうしたときにトラブルにならないよう、配偶者居住権を取得することが決まったら、各地の法務局で、速やかに配偶者居住権の登記をしてください。
JOY この登記は大切な手続なんですね。「配偶者居住権の取得が決まったら、速やかに登記」、このことをしっかり覚えておいてほしいですね。
堂薗 はい。また生前に、遺言で配偶者に配偶者居住権を取得させることもできますので、遺産の分配の一つの方法として覚えておいてください。
秋元 今回ご紹介した相続の様々なルールを知っておけば、それぞれの事情にあった最善の方法で相続ができますよね。
堂薗 そうですね。相続に関する新しいルールは法務省のホームページでご紹介しています。
簡潔にまとめたパンフレットなども掲載されているので、「法務省 相続法」で検索して、是非、ご覧になってください。
秋元 いろいろな相続の方法があって、その中からチョイスすればいいと思うと、安心感が違うよね。
JOY 今の段階では、あまり遺産や遺言書が自分の中で考える優先順に入っていないけど、後々揉める可能性もあるから、今日、知ることが出来て良かった。
参考:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)(法務省)