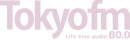8月7日(日)の放送では、爬虫類・恐竜研究家の富田京一(とみた・きょういち)さんをゲストに迎え、恐竜の魅力についてたっぷりと語っていただきました。

(左から)ホラン千秋、富田京一さん
恐竜は絶滅していなかった!?
恐竜といえば“絶滅した”とされていますが、富田さんは「恐竜は絶滅していません。地下シェルターなどに住んでいない限り、1日1回ぐらいは恐竜を見ていると思います と断言。その回答にホランも驚きを隠せません。
富田さんいわく、ティラノサウルスやステゴサウルスなどは滅んでしまったものの、「今でも世界中に1万1,000種類ぐらい生きています。(恐竜が)いない大陸はないですし、北極や南極にもいます」と説明します。絶滅してしまった恐竜は足腰がとても頑丈すぎるあまり、「足を崩して座ったり体を丸めたりするのが苦手だったので冬眠ができなかった。それが原因で大きい恐竜はダメージを受けたのだと思う」と分析します。
では、どんな恐竜が生き残っているのかというと「鳥は全部恐竜なんです。鳥は空を飛べるので、(寒さなどで住みづらい)苦手な場所だったら別のところにすぐに引っ越せる。移動能力が幸いしたのではないか」と見解を示します。
富田京一が注目する化石スポット
恐竜の化石が発見されている場所は、「海の近くの崖など、危ない場所が多い。海に(地層が)削られて化石が発見されるケースが多いのと、化石ができる場所が水辺に近いところが多いので、山のなかよりも海や水辺に近いほうが発見されやすい」と言います。
また、「化石は地層ありき」と富田さん。鳥以外の恐竜がいた時代は限られおり、「大体2億4,000万年前~6,600万年の間の地層ではないと、まず出てこない。この時代に限定される」と解説します。
おすすめ化石スポット①北海道むかわ町
ここで、富田さんが現在気になっている化石スポットを教えてもらうことに。まずは北の地域で注目している場所として、北海道むかわ町を挙げます。「ここは、日本で発見された恐竜のなかでも最も完全体に近い。わりと大きくて頭から尻尾までほとんど揃っている植物食恐竜(草食恐竜)の化石が見つかっています。しかも、他の恐竜と比べて“腕がとても細い”“背骨の突起が逆の方向を向いている”などオリジナリティのある恐竜が見つかっているので、そういう意味でも興味深い」と力を込めます。
※このエリアにある博物館:むかわ町立穂別博物館
おすすめ化石スポット②岩手県久慈市
次に挙げたのは、琥珀の産地としても知られる岩手県久慈市。「そもそも久慈市の琥珀は、恐竜が生きていた白亜紀の樹液が固まったものなので、それ自体が化石なんです」と話します。
また、この地域では恐竜だけでなく、「同じ時代に生きていたワニやカメなど、いろいろな動植物の化石が一挙に見つかっています。なので、(当時の)生態系がまるごと保存された環境なんです。また、地元の研究者や地元と連携して若い研究者も集まってきていて、発掘もどんどん進んでいる。勢いもあるし、チームワークがある」と期待を寄せます。
※このエリアにある博物館:久慈琥珀博物館
おすすめ化石スポット③熊本県天草市御所浦町(ごしょうらまち)
南のほうで注目の場所として挙げたのは、熊本県天草市御所浦町です。ここは複数の島々からなる離島の町で、「島自体がバームクーヘンみたいで、恐竜が生きていた時代の地層がむき出しになっています。海岸に上陸して道を歩いていると、アンモナイトや恐竜と同じ時代に生きていた生物の化石がポロポロと坂道から落ちてくるんです」と言います。
※このエリアにある博物館:御所浦白亜紀資料館(現在、全面リニューアル工事中)
奥深き恐竜の世界に触れたホランは、「北から南までいろいろなところで発掘されているんですね! 恐竜って昔は実在していて、今はどこかファンタジーみたいな世界で恐竜の時代だけを切り取って考えてしまいがちだけど、その前に何があったのか、その後にどうなっていったのかなど、今も生きている動物とのつながりを考えると、すごくロマンがあるというか、宇宙が広がっているなって思いますね!」と感じ入っていました。
北海道 岩手県 熊本県
Back issuesバックナンバー