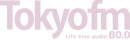6月5日(日)の放送では、前回に引き続き、ソルトコーディネーターの青山志穂(あおやま・しほ)さんをゲストに迎え、塩の魅力についてたっぷり語っていただきました。

(左から)ホラン千秋、青山志穂さん
江戸時代から続いている塩の製法
塩の粒の形や大きさ、ミネラルのバランスについて、青山さんは「基本的には、製法でコントロールできる。どういう製法で(理想の)塩に仕上げるか、というところに日本人のモノづくりの魂が“ドン!”とつぎ込まれていて面白い」と語ります。
日本は国土が狭いうえに、平らで広い沿岸が少ないため「(海水を)窯で煮詰める方法が多い」と言います。窯に入れる前段階に「濃縮」と呼ばれる工程があり、「そのやり方がものすごくバラエティ豊か」と声を大にします。
青山さんによると、海水を10倍ぐらいに煮詰めて濃縮していくと塩の粒ができるそう。粒ができあがるギリギリぐらいまで濃くしてから窯で炊いたほうが「同じ熱量で大量の塩がとれるので効率がいい」と説明。そのため、「いかにコストをかけずに効率的に濃縮するか、という技術がすごく発達している」と言います。
例えば、石川県・能登半島の揚げ浜式塩田での塩づくりは、砂地に海水をまき、太陽と風の力でそれが乾くと、「表面の部分は、砂に塩がくっついて結晶になるんです。その砂をトンボを使って手作業でかき集めてザルの上に砂を置き、そこにまた海水をかけると砂についた塩が溶けて、下にちょっと濃い塩水が落ちるんです」と解説します。
この製法はものすごく手間がかかり、何度か体験したことがあるという青山さんは「“ザ・苦行”という感じでした(笑)」と振り返るほど。そんな手間暇をかけて作られた揚げ浜式塩田の塩は、青山さんいわく「おいしいバターの後味がするような、バター感のあるこってりとした塩」と説明します。
ちなみに、塩の専売制度が実施された際、各地域にあった伝統的な作り方は一度なくなってしまいましたが、この揚げ浜式塩田の製法だけは文化財としての価値が認められ、江戸時代から唯一続いているところが一軒だけあるのだそう。現在、この製法で塩づくりをしている製塩所は10軒ぐらい残っていて「能登半島のところにズラッとあるので、ドライブすると楽しいですよ」とオススメしました。
塩の味わいを見分けるポイント
青山さんによると、しょっぱさが強いか弱いかで、合う食材や料理が変わるため「パッケージの裏に書かれている食塩相当量を見てほしい」とアドバイス。自然塩の食塩相当量の平均値は92~95ぐらい。この範囲に該当する塩はいわゆるバランスの取れたタイプで、それより高いとしょっぱめ、80台から低くなるにつれてまろやかな味わいになるので、食塩相当量を目安にするといいそう。例えば、味の強い食材にはしょっぱさの強い塩、逆に野菜など繊細な味の食材には、食塩相当量の低いまろやかなタイプの塩が合いやすいと説明します。
また、日本海側で作られた塩は、海風の香りが残っているものや磯っぽい塩が多いため魚と合いやすく、前回紹介した海藻エキスの入った藻塩も「魚との相性バッチリ!」と太鼓判を押します。ただ、ひとえに魚といっても、マグロのように大トロと赤身では脂の量が異なるため、大トロならしょっぱさの強い塩、赤身にはまろやかなタイプの塩のほうが合うそうです。
同じ食材でも塩によって違う味に!?
この日、スタジオにはきゅうりのスティックを用意。大分県の「つるみの磯塩」と、石川県の揚げ浜式塩田で作られた「大谷塩」をホランが食べ比べてみることに。
まずは、まろやかタイプのつるみの磯塩をつけてひと口頬張ると、「あっ、塩気もあるけど甘みがありますね」とホラン。青山さんいわく、つるみの磯塩との相乗効果によってきゅうりのなかの甘みが引き立っているのだそう。
続いて、焼いてサラサラに仕上げてある大谷塩をつけてかじると、ホランは「うわっ、全然違う! こっちのほうがシャープな感じがするけど角がない!」とビックリ。こちらは有塩バターのような後味が特徴で、「つるみの磯塩は先に甘みがくるけど、焼き塩(大谷塩)は先に塩気がくる。面白い!」と驚きます。
2週にわたって塩の奥深さについて語ってくれた青山さん。最後に、「家にも、いただきものなどで意外と把握していない塩があると思うので、とりあえず全員集合させて、トマトでも肉でも好きな食材で食べ比べをしてみるのが第一歩目です。そうすると、(自分に)合う塩、合わない塩があるので『これはおいしい』『これはマズい』とわちゃわちゃするのが楽しいと思う」と話します。
実際に味の違いを実感したホランは、「お子さんのいるご家庭は自由研究にすると面白いかも! 食塩相当量の数値を書いて、どういう味で何に合うか自分で確かめてみると超楽しい気がする!」と声を弾ませると、青山さんも「(塩による食べ比べは)食育にもすごくいいので、お子さんのいるご家庭にはめちゃめちゃオススメです!」と力説していました。
石川県 大分県
Back issuesバックナンバー