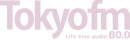7月18日(日)の放送では、前回に引き続き、影絵師で音楽家の川村亘平斎(かわむら・こうへいさい)さんが登場。川村さんの作品づくりに迫りました。

(左から)ホラン千秋、川村亘平斎さん
川村流・作品づくりのこだわり
川村さんが、自身の作品づくりでまずやることとして、影絵の物語をつくる地域に実際に足を運んで、地元の図書館に行き、「その地域について書かれている文献資料や本をひと通り読む」のだそう。民話や神話から着想を得て、現代風に物語をつくっていくことが多いため、「“これは物語の軸になりそうだな”と思うような話をまず探す」と言います。
例えば、“湖に大蛇が出た”という話だった場合は、「まず、その湖に行ってみる。それで、“どうしてここに大蛇が出たのだろう?”と考えながら周囲を歩いてみると、ものすごくデカい川が流れていたり、霧がかった崖の上から滝が落ちていたり……そういう景色と物語が徐々にリンクし始めるんです。そこからおぼろげに物語を組み上げていく」と説明。
そして、大枠の物語像ができたところで「その地域の人たちとワークショップをしながら、僕が調べてきた話をシェアしながら対話をしていくなかで(より具体的な)ストーリーをつくっていく」と、自身のスタイルを語ります。
新作づくりで新たな試みも
1つの物語を完成させるまで、大まかなあらすじや絵コンテを決めるのに約1ヵ月、そして、人形づくりと地域の人たちとのワークショップにおよそ1ヵ月費やすそうで、「コロナ前は月1本ペースで新作の創作活動に励んでいた」と言う川村さん。
最近では、香川・小豆島の方から影絵制作の依頼があり、現地に行ったそう。そこでは、「いわゆる昭和史というか、戦後を生きてこられた70代の方たちにいろいろな話を伺うことができた。そこで、物語をつくるときに、その話のなかに登場した動物たちが“(その話を)語り直す”という形にしてみたんです。ある種、神話化して、(語ってくれた)事実を影絵にした」と言います。
つまり、これまでのように、その地域に根づいている民話や神話をモチーフにするのではなく、「“いま、ここから始まる民話をつくる”みたいなことを、小豆島ではやってみた」と新たな試みだったことを振り返ります。
そうして完成した新作を上演したところ、来場していたおじいちゃんから「実は、あの山のうえのほうに、盲目の人の目を治した伝説の洞窟があるんじゃよ」と新たな情報を聞き、今年4月に再び小豆島を訪れたそうです。川村さんによると、その洞窟は「瑪瑙(メノウ)の洞窟」と呼ばれており、なかを調べてみると、宝石にも使われる“瑪瑙”の石が出てきたそう。
「小豆島は、石で有名な島なんです。それで、石にまつわる民話以前のちょっとしたエピソードが、洞窟に行ったことをきっかけに、いろいろと聞けるようになってきたので、今後も物語をつくらせてもらえそう」と期待を寄せます。
地方へ赴く“影絵”ならではの醍醐味
そんな川村さんのエピソードに、ホランは「その土地で生活をしていると、当たり前すぎて生活のなかに溶け込んでしまって、あえてそれを語ることをしないものが意外とたくさんあるじゃないですか。そういうところにこそ、伝えていきたいような、物語になる要素が隠れているんでしょうね」と感じ入った様子。
川村さんも、「地方に行くと、日本人の僕らでさえ知らないようなルールがある。外から来た人の目線で、そこの地域のものやことを影絵を使って提案すると、そこに住んでいた人たちも“これって、こんなにおもしろかったんだね!”って、あらためて気づいてもらえるのは、すごくいいと思う」と大きくうなずきます。
そして、「僕は影絵というツールを使っているので、これが10年、20年……50年と、どこかの地域で続いていけばいいなとすごく思っています。ただ、そのツールが影絵じゃなくても、自分たちの(住む地域の)まわりのものを知って、なにか形を変えてみんなで(物語を)つくると“おもしろい”ということを、各地域の人たちが思い立ってくれれば。そこから進むものって、たくさんある」と思いを語りました。
Back issuesバックナンバー