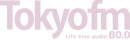7月11日(日)の放送では、影絵師で音楽家の川村亘平斎(かわむら・こうへいさい)さんが登場。影絵の魅力をたっぷりと語ってくれました。

(左から)ホラン千秋、川村亘平斎さん
ガムラン音楽の先にあった影絵との出会い
川村さんが影絵に興味を持ったきっかけは、大学生のとき。そもそもは打楽器を学ぼう思って入った大学に、インドネシア・バリ島の民族音楽であるガムランを教えている先生がいて、「ガムランを勉強しようと19歳のときにバリに通うようになった」と振り返ります。
そのガムランを学ぶ延長線上に影絵の伴奏音楽があり、勉強していくうちに、「(現地の人から)『影絵、やってみなよ』と声をかけてもらうことが多くなって、いつの間にか影絵をやることに(笑)。それで、自分でどんどん影絵をつくるようになった」と言います。
影絵人形劇「ワヤン・クリット」とは?
川村さんの影絵は、インドネシアの伝統的な影絵人形劇で「ワヤン・クリット(Wayang Kulit)」と呼ばれるもの。ワヤンは“影”、クリットは“皮”を意味し、「牛の皮でできた人形を使うんですけど、その人形のデザインも日本ではあまり見慣れない感じのもの」と言います。
この日は、川村さんがホランの目の前で即席の影絵を披露。変幻自在に演じる役の声を使い分けながら、ライトで人形を照らし、壁に影を映し出します。それを見たホランは「(人形は)操り人形をぺしゃんこにしたイメージ。それを持って、光で照らしてスクリーンに映し出すということなんですね!」と驚きの声をあげます。
川村さんいわく、バリの影絵は日本で言うところの冠婚葬祭や村のお祭りなどのときに、神社でおこなわれる奉納演武のようなイメージだそうで、「影絵師が1人でいろいろなキャラクターの声色を使い分けながら話すので、かなり落語っぽい。また、完全なエンターテインメントとしてもやるんですけど、宗教的なことや儀式的なことにも(影絵は)出てくる」と言います。
インドネシアでは、インドからやってきた古い物語を元にしたものが多いそうですが、「日本の伝統芸能は“守っていくもの”というイメージですけど、インドネシアだと、古典的な物語から影絵師が“外伝(スピンオフ)”をつくっていくことがミッションとして課されている」と認識の違いを語ります。
影絵のこだわりは「シンプルにおもしろいこと」
川村さんの影絵は、日本で披露するといつも驚かれるそう。とはいえ、日本で影絵を披露するときは、「いろいろな地域に行って、地元の人たちとそこに残っている話を掘り起こし、ワークショップをしながら(物語を詰めていって)、その話を披露しています」とこだわりを語ります。
川村さんが影絵をやるうえで大事にしているのは「シンプルにおもしろいこと」。そのために、ときには5メートルほどの巨大な人をスクリーンに映し出すことも。話が難しくて置いていかれてしまうより、単純に「“デカいってすごい!”その迫力に驚いてほしい」と言います。
その思いを聞いたホランは、「いまはコンピュータ・グラフィックス(CG)でなんでもできちゃう時代じゃないですか。だけど、すごく原始的でシンプルな方法でこれだけ表現の幅があるんだ、っていうことにすごく驚きました!」と感心しきり。
プロジェクションマッピングやCGは、色も多彩でサイズも大きく迫力満点ですが、「それは“コンピュータが映しているんだな”と思って見ているから、普通に映像として見てしまうんです」と川村さん。それに対して、「影絵は、 “あれって、人間が動かしているんだよね!?”っていう(視点で見ている)スクリーンに映った絵に加えて、“スクリーンの裏でどうやっているの?”っていう、頭のなかで思考が2つ回っちゃうんですよ。それこそが影絵を見続けてしまう理由の1つですね」と魅力を語ります。
最近では、1度訪れた地域の方から、「2年ぶりに『もう1回、作品をつくってください』と言われることがちらほらと増えてきた。継続して同じ地域で影絵を上演することが必要だと思ってくれる人たちが増えてきたなという印象」と変化を実感している様子。
「それはやっぱり、自分たちが住んでいた地域の物語だったり、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さんやお母さんから聞いてきた話のリアリティが徐々に薄れてしまっていて、それを僕が影絵を使って(伝統を)つなぎ直そうとしていることに共感してくれていると思う」と手応えを語ります。
今回の話を聞いたホランは、「“影”という怪しさや儚さのようなものが、人生を重ねれば重ねるほど暗いイメージで捉えてしまいがちだけど、影って“光の輪郭”じゃないですか。光が存在してこそ影も存在するから、いろいろな人生経験を積むほど、すごく心の芯に刺さる気がします。影絵というもののすごさを再確認したので、多くの人にも感じていただきたい」とすっかり魅了されていました。
Back issuesバックナンバー