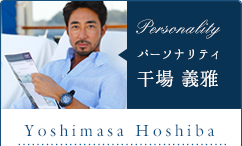����������������Τϡ�����Ū�˳������롢ǽ���������ռԤ�������Ƿ������Ǥ���
��ݤȤ��������dzڴ���̤��ơ����⳰�Υ����ƥ����ȤȤ⼡���˥���ܥ졼�Ȥ�¸���
������ˡ���˾����졢�Х�������¤Ǥ���դηи�������ޤ���
����ʸ���Ǥ��롢ǽ���ռԤˤ��ƹ�ݿͤǤ������Ҥ���ˡ�������ι�Τ��ä����������Ƥ����ޤ���

������600ǯ�ۤ����Ǥ����͡������βȤϼ�Į���夫��ȸ����Ƥ��ޤ�����������������ή�줬����Ȥ������ϸ����Ƥ��ޤ��͡�
�����ָݤȤ����Τϲ����य�餤�����Ǥ�������
�����ָݤˤ��羮����ޤ��ơ�����ݡס־��ݡפȤ�����������ʬ�����ꡢ�⤷���Ͼ��ݤ���ָݡפȻפäƤ�ä��������¿���Τǡ��Ƥ�ʬ���Ȥ��ơ��礭���������ספȤ����������⤷�Ƥ��ޤ����ڴ�γ��ʬ���ȹͤ����顢�ݤ��礭���ݤȾ������ݡ����ץ��������㤦��Ǥ��͡�
�����ֺ���Ϥɤ�ʺ���ˤʤ��Ǥ�������
������ƹ�����μ���ȴ���Ƥ��ơ�ξ�̤��Ϥγפ�ϤäƤ��ޤ���
�������߱��λ����ʤɤϡ�����������Ѥ���ʤ��Ǥ�������

�����ָݤιͤ������ä��ꡢ�������ä���ǰ�Τ��ä�ʹ���ơ��Ӥä��ꤷ�ޤ����͡�
�����ָ���ʸ���������Ƥ����͡��ʥ��ͥ륮�������Ķ����ꡢ�Ῡ�ˤ����뤹�٤ơ��͡���ʸ���ˤ����������κ���ϡ����줷�Ƥ����Ǥ����ʹ֤�õ�濴�Ȥ����忴��������ɤ���ʬ�Ǥ⤢�������ɡ�ȿ���Ѥ������ǤȤ��Ƥ���ޤ���͡��͡��ʤ�Τ���Ƥ������ʹ֤ϼ�ʬ���֤��Ƥ�櫓�Ǥ��硩���⡢���β�����ʤ���Ǽ�����ʤ�����������ȡ��߱����μ��٤ι⤤���ˡ��פꥫ��˴��礵���ơ���������������夲����Ǥ�����Ǥġ�����Ϲ⤤�����Ф�櫓�Ǥ��������ɡ��פˤ�Τ�������ô���������Ǥ���͡���������ȡ��פμ�̿��̤����ˤʤä��㤦��Ǥ���
�����֤ʤ�ۤɡ��Τ�����ô���礭���ʤ�ޤ���͡�
�����֤�����ʹ֤������ˤʤäư����������Ĵ�١פȤ����������餷�����դ��Ĥ���Ƥ�櫓�Ǥ�����͡���Ĵ�١פȤ����Τϡ����λ��ˤ����Τ�����������ʤ�Ǥ���

���ڡֺǶᡢ���롼�������ܤǤ���夲���Ƥ����¿���ΤǤ��������ܤΥ��롼�������桹���ӤƤ��ʤ��ơ�2011ǯ���餤�λ����ˤ��ȡ����֥��롼����ڤ���Ǥ���Τϥ���ꥫ�ʤ�Ǥ��衣
���Υ���ꥫ�ʤΤ��Ȥ����ȡ�����ꥫ�ϥɥ�ǡ������Υ衼���åѤ��̲ߤ�������ä�����ʤ��Ǥ���������ꥫ�ͤ��ɥ��������ޤ��٤ˤϤɤ������餤���Τ����Ȥ���������ȯ�������Τ���ι�ʤ�Ǥ��͡�����ꥫ�ʤ�ǤϤΡ�����Ū�ʹͤ����Ǥ��͡�
�֥��롼����ڤ����ϡ���
��2���ܤ����ʥ���3���ܤˤϰճ��ˤ�ץ���ȥꥳ�����ܤ�15���ܤʤ�Ǥ��衣�ɤ����ƿ��Ӥʤ����Ȥ����Τϡ����ܤ����ʤ��Ǥ����������ϱ���������뤷�������������⤬�⤤�Ǥ���͡���ι�Ȥ����ȡ�����ʤ��ǯ��ˤʤäƤ���Ԥ��Ȥ���������⤢��ޤ��͡�
���ܤ����äƶ��٤ǡ����٤ߤ��Ȥ�ʤ��Ȥ����Τ⡢���롼�����������ʤ���Ĥ���ͳ�Ǥ��͡���äѤ곤���äơ��ޥ�ݡ��Ĥ�ӡ�������Ȥ�����Ū�ǡ��������뤤������Ǥ���͡��������٤����ܤμ���ϳ�ή���ȤƤ⤭�Ĥ��ơ���������������˷�ӤĤ��ʤ��Ǥ���͡�
�ɤ����Ƥ⥯�롼�����������ʤ��ä����ɡ����줫�����������ޤ��͡���ǯ�ϥ��롼����ǯ�ȸ����ơ��Ĥ��˻���褿�ͤʵ������ޤ��������������������������祤��������ޤ��Τǡ����ͤ˳ڤ���Ǥ������������Ȼפ��ޤ��͡�