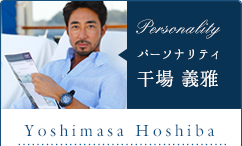ŗ£·ī¤“¾čĮ„¤¤¤æ¤Ą¤Æ¤Ī¤Ļ”¢ĘüĖܤņĀåɽ¤¹¤ė²ķ³Ś»Õ¤ĪÅģµ·½Ø¼ł¤µ¤ó¤Ē¤¹”£
äŹäÅ”Ź¤Ņ¤Į¤ź¤”Ė¤ņĆę擤ĖĶĶ”¹¤Ź³Ś“ļ¤ņ±éĮÕ¤µ¤ģ¤Ž¤¹¤¬”¢³¤³°¤Ē¤Ī²»³Ś³čĘ°¤ā¤µ¤«¤ó¤Ē”¢Ī¹¤Ī·Šø³¤āĖÉŁ¤Ē¤¤¤é¤Ć¤·¤ć¤¤¤Ž¤¹”£
ÅĮ¾µŹø²½¤Ē¤¢¤ė²ķ³Ś¤ĪĮÕ¼Ō¤Ė¤·¤Ę”¢¹ńŗŻæĶ¤Ē¤¢¤ėÅģµ·¤µ¤ó¤Ė槔¹¤ŹĪ¹¤Ī¤ŖĻƤņ¤Ŗ¤¦¤«¤¬¤¤¤·¤Ę¤¤¤¤Ž¤¹”£
“³¾ģ”ÖäŹäÅ”Ź¤Ņ¤Į¤ź¤”Ė”¢ćł”Ź¤·¤ē¤¦”Ė¤Ī²»æ§¤ņÄ°¤«¤»¤Ę¤¤¤æ¤Ą¤¤Ž¤·¤æ¤±¤É”¢ĮĒĄ²¤é¤·¤¤²»æ§¤Ē¤¹¤Ķ”£¤“Ī¾æʤā³Ś“ļ¤ņ¤µ¤ģ¤Ę¤¤¤æ¤Ī¤Ē¤¹¤«”©”×
Åģµ·”Ö¤³¤Ī²»¤ņ”¢ĄĪ¤ĪæĶ¤ĻÅ·¤«¤é¹ß¤źĆķ¤°ø÷¤ņɽ¤·¤æ¤ó¤Ē¤¹¤č”£Åģµ·²Č¤Ļ1400ĒÆĮ°¤«¤é”¢¤³¤Ī³Ś“ļ¤ņ¤ä¤ė¤æ¤į¤Ī²Č¤Č¤·¤ĘĀøŗߤ·¤Ę¤¤¤æ¤ó¤Ą¤±¤É”¢¤ä¤é¤Ź¤±¤ģ¤Š¤¤¤±¤Ź¤¤¤ļ¤±¤Ē¤ĻĢµ¤«¤Ć¤æ¤Ī¤Ē”¢ĖĶ¤Ļ¼«Ķ³¤Ą¤Ć¤æ¤ó¤Ē¤¹¤č”£¤Ē¤ā”¢¾®¤µ¤¤ŗ¢¤«¤é²»³Ś¤¬¹„¤¤Ą¤Ć¤æ¤ó¤Ē¤¹”£ĮÄÉć¤Ļ±éĮÕ²Č¤Ē¤·¤æ¤¬”¢Éć¤Ļ¾¦¼Ņ„Ž„ó¤Ē³¤³°¶ŠĢ³¤¬Ā椫¤Ć¤æ°Ł”¢ĖĶ¤Ļ¤ŗ¤Ć¤Č³¤³°¤Ė½»¤ó¤Ē¤¤¤æ¤ó¤Ē¤¹¤č”£²ķ³Ś¤Č¤Ļ¤Ū¤É±ó¤¤“Ķ¤Ē¤·¤æ¤Ķ”×
“³¾ģ”Ö¤½¤ģ¤¬²æøĪ”¢¤½¤¦¤¤¤¦Ę»¤ĖæŹ¤ó¤Ą¤ó¤Ē¤¹¤«”©”×
Åģµ·”Ö„ķ„Ć„Æ¤ä„ø„ć„ŗ¤Ė¶½Ģ£¤¬¤¢¤Ć¤æ¤Ī¤Ē”¢„Š„ó„ɤĒ„®„攼¤ņĆʤ¤¤æ¤ź¤·¤Ę¤Ę”¢¤½¤Ć¤Į¤ĪŹż¤ĒæȤņ¤æ¤Ę¤č¤¦¤Č¹ā¹»¤Īŗ¢»×¤Ć¤Ę¤¤¤Ž¤·¤æ”£¤Ē¤ā”¢¤É¤¦¤»²»³Ś¤ĪĘ»¤Ź¤é”¢Åģµ·²Č¤Č¤·¤Ę²ķ³Ś¤ĖĢܤņøž¤±¤Ę¤ā¤¤¤¤¤ó¤ø¤ć¤Ź¤¤¤«¤ČøĄ¤ļ¤ģ¤Ę”£¤½¤ģ¤Ė³¤³°¤Ė½»¤ó¤Ē¤¤¤æŹ¬”¢¼«Ź¬¤¬ĘüĖÜæĶ¤Č¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶Æ¤«¤Ć¤æ¤Ē¤¹¤Ķ”£ĘüĖÜæĶ¤¬ĘüĖܤĪŹø²½¤ņĒŲÉé¤Ø¤ė¤Č¤¤¤¦¤Ī¤Ļ”¢øŲ¤ź¤ĪÉōŹ¬”¢ĄÕĒ¤¤ĪÉōŹ¬¤Ē¤¹¤“¤Æ¤¤¤¤¤ó¤ø¤ć¤Ź¤¤¤«¤Č»×¤Ć¤æ¤ó¤Ē¤¹¤č”×
“³¾ģ”Ö¤½¤Ī»×¤¤¤¬½ŠĶč¤æ¤Ī¤Ļ¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤Ē¤¹¤«”©”×
Åģµ·”Ö¹ā2¤Æ¤é¤¤¤Ē¤¹¤Ķ”£ĘüĖÜæĶ¤Ą¤Č¤¤¤¦„¢„¤„Ē„ó„Ę„£„Ę„£¤ņµ¤¤Ė¤¹¤ė¤č¤¦¤Ė¤Ź¤Ć¤æ¤Ī¤Ļ”¢Ćę³ŲĄø¤Æ¤é¤¤¤Īŗ¢¤Ē¤·¤æ”×
“³¾ģ”Ö½»¤ó¤Ē¤¤¤æ¤Ī¤Ļ”¢¤É¤Į¤é¤Ī¹ń¤Ą¤Ć¤æ¤ó¤Ē¤¹¤«”©”×
Åģµ·”Ö1ŗŠ¤«¤é7ŗŠ¤Ž¤Ē¤¬„愤¤Ī„Š„󄳄ƤĒ”¢Ćę1”¢Ćę2¤ņ„į„„·„³„·„Ę„£¤Ē²į¤“¤·¤Ž¤·¤æ”£³°¹ńæĶ¤ĪŹż¤¬ĘüĖܤņ“Ö°ć¤Ć¤ĘĒ§¼±¤ņ¤·¤Ę¤¤¤æ¤ź”¢øķ²ņ¤·¤Ę¤ėÉōŹ¬¤Ļ¤¤Į¤ó¤ČĆĪ¤Ć¤Ę¤ā¤é¤¤¤æ¤¤¤Č”¢¾®¤µ¤¤ŗ¢¤«¤é»×¤Ć¤Ę¤¤¤æ¤ó¤Ē¤¹¤č”×
“³¾ģ”Ö¹ńŗŻæ§¤¬Ė¤Ē¤¹¤Ķ”Ź¾Š”Ė”×
Åģµ·”Ö²ķ³Ś¤Č¤¤¤¦ĘüĖÜŹø²½¤ņ¤ä¤ė¤č¤¦¤Ė¤Ź¤Ć¤æ¤Ī¤Ļ”¢»Åøž¤±¤é¤ģ¤Ę¤¤¤ė¤č¤¦¤Ź±ļ¤ņ“¶¤ø¤æ¤ó¤Ē¤¹¤č¤Ķ”£„Ō„¢„Ī”¢„®„攼”¢„Ł”¼„¹”¢„É„é„ą”¢¤É¤ģ¤āæĶ¤Ī¤ņø«¤Ę¤¤¤Ę”¢½ŠĶč¤ė¤č¤¦¤Ė¤Ź¤Ć¤æ¤ó¤Ē¤¹¤č”×
“³¾ģ”Ö½¬¤Ć¤æ»ö¤Ļ¤Ź¤Æ¤Ę½ŠĶč¤ė¤č¤¦¤Ė¤Ź¤Ć¤æ¤ó¤Ē¤¹¤«”£¤¹¤“¤¤¤Ē¤¹¤Ķ”×
Åģµ·”Ö²ķ³Ś¤ņ¤ä¤ė¤Ī¤ĖĮ“Į³“Ų·ø¤Ī¤Ź¤¤³Ś“ļ”¢Ą¾ĶĪ„Ż„Ƅׄ¹¤Č¤«¤ņ¤ä¤Ć¤ĘĶč¤æ»ö¤¬”¢äŹäŤĪĪɤµ¤ņ°ś¤½Š¤¹¤Ī¤Ė¤ā¤Ī¤¹¤“¤ÆĪɤ«¤Ć¤æ¤Ē¤¹¤Ķ”×
“³¾ģ”Ö°ģČÖŗĒ½é¤Ė¼ź¤Ė¤·¤æ³Ś“ļ¤Ļ²æ¤Ą¤Ć¤æ¤ó¤Ē¤¹¤«”©”×
Åģµ·”Ö³Ś“ļ¤Ē¤Ļ¤Ź¤¤¤ó¤Ē¤¹¤±¤É”¢ĖĶ¤ĻĶÄĆÕ±ą¤Ī»ž¤Ė„Ó”¼„Č„ė„ŗ¤Ė¤¹¤“¤Æ„Ļ„Ž¤ź¤Ž¤·¤æ”£„Ó”¼„Č„ė„ŗ¤Ė¤Ź¤ź¤æ¤¤¤Č»×¤Ć¤Ę”¢ĆŹ„Ü”¼„ė¤ņ„®„攼¤Ī·Į¤ĖĄŚ¤Ć¤Ę”¢¤½¤³¤Ė»å¤ņÄ„¤Ć¤Ę”¢²»¤ā¤·¤Ź¤¤¤ó¤Ą¤±¤É”¢¤½¤ģ¤ņŹś¤Ø¤Ę¤¤¤ė¤Ī¤¬”¢¼«Ź¬¤Ē¤Ļ¤½¤ģ¤ņ³Ś“ļ¤Ą¤Č»×¤Ć¤Ę¤¤¤Ž¤·¤æ”×
“³¾ģ”ÖÅģµ·¤µ¤ó¤Ī„ė”¼„ĤņƵ¤Ć¤Ę¤¤¤Æ¤Č”¢„Ó”¼„Č„ė„ŗ¤Ė¤Ö¤ĮÅö¤æ¤ė¤Č”¢¤½¤ģ¤Ļ°Õ³°¤Ē¤¹¤Ķ”Ź¾Š”Ė”×
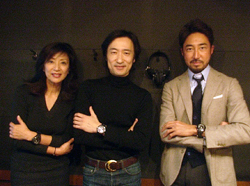
„Æ„ė”¼„ŗĮ„¤Č¤¤¤¦¤Ī¤Ļ”¢°ģ¤Ä¤Ī³¹”£
³¹¤¬¤½¤Ī¤Ž¤ŽĘ°¤¤¤Ę¤¤¤ė¤Ī¤Ē”¢æåĘ»²°¤µ¤ó”¢„Ś„ó„²°¤µ¤ó”¢Åŵ¤²°¤µ¤ó”¢¤Ŗ°å¼Ō¤µ¤ó¤Č”¢¤¢¤é¤ę¤ė榼ļ¤ĪŹż¤¬¾čĮ„¤·¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£
Į„¤¬Ę°¤¤Ź¤¬¤é„Ś„ó„¤āÅɤė”¢æåĘ»¤¬µĶ¤Ž¤ģ¤Š½¤Ķż¤ā¤·¤Ž¤¹”£
„ģ„¹„Č„é„ó¤ĒøĄ¤Ø¤Š”¢Ä«¤ĻÄ«¤“ČÓ¤Ī„ę„Ė„Õ„©”¼„ą¤ņĆå¤ĘĘƤ”¢Ćė¤Ė¤Ź¤ė¤ČĶĪÉž¤ĖĆåĀŲ¤Ø”¢°ć¤¦¤ŖŹ¤Ų”£
Ģė¤Ė¤Ź¤ģ¤Š”¢Ģė¤Ī„¦„§„¤„攼¤Č¤Ź¤źĘƤƔ£
1æĶ¤Ī„¦„§„¤„攼¤µ¤ó¤Ļ5Ćå”Į6Ćå¤Ī„ę„Ė„Õ„©”¼„ą¤ņ»ż¤Į”¢Ä«¤«¤éČÕ¤Ž¤Ē”¢»ž“ÖĀÓ¤Ė¤č¤Ć¤Ę°ć¤¦„ę„Ė„Õ„©”¼„ą”¢¤ŖŹ¤ĒĘƤ¤¤Ę¤¤¤ė¤ó¤Ē¤¹”£
„Æ„ė”¼„ŗĮ„¤Ė¤Ļ”¢ø«¤Ø¤Ź¤¤½ź¤Ė¤āĘƤ¤¤Ę¤¤¤ėæĶ¤¬¤æ¤Æ¤µ¤ó¤¤¤ė¤ó¤Ē¤¹”£
¤½¤¦¤¤¤¦æĶĆ£¤ņø«¤Ę²į¤“¤¹¤Ī¤ā”¢¤Ž¤æĢĢĒņ¤¤¤Ē¤¹¤Ķ”£