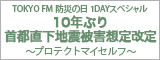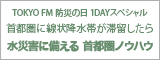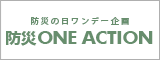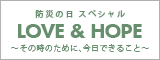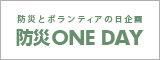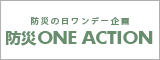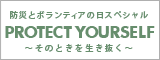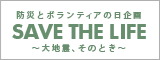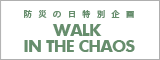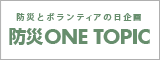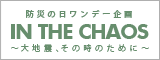2024年06月08日
08:25 家の耐震基準 知ってほしい事
今朝は、『家の耐震基準』についてお伝えします。
地震が多い日本では、
住宅を建築する時に建物の耐震性の高さが求められます。
耐震基準は、今まで複数回見直されています。
耐震基準は大きくわけて、3つの時期に分けられます。
防災工学が専門の九州大学 浅井光輝准教授の解説です。
『新耐震か旧耐震かっていうのは、
1981年の基準かどうかって事でよく使われます。
ただそれが、ずっと続いているわけではなくて、
1995年の阪神淡路大震災で多くの木造家屋が倒壊して、
大きな被害につながったって事もあるので、
建築基準をもう一度見直そうっていう事が2000年にもう一度行われて、
そのときに、震度6に対しての強化がされている。震度6強に対しても
壊れないような設計に対しても改定が行われたのが2000年なんですけれども、
そこのアップデートよりも1981年のアップデートの方が大きかったので、
旧耐震・新耐震という言葉で分ける事が多いのですが、
厳密にいえば、2000年にアップデートされている。
インフラ構造物に対しても、同じ様に、橋梁に対しての設計基準もかなり
強化されて、基準を満たしていないと、補修・補強をして道路で使われている。
インフラ構造物は、耐震設計がされている。今は補強されているか、
新しい設計で使われている。』
浅井先生の解説にもあった様に、耐震基準は、
1981年以前・以降、そして2000年以降と大きく
3つの時期に分けられています。
2000年の基準は新耐震基準で建築された多くの木造住宅が
1995年の阪神淡路大震災で倒壊・半壊した事をきっかけに
木造住宅をメインに制定された基準です。
家の備えとして、1981年以降に建てられた建物に住んでいるか?
という点が防災の観点から言われていますが、
この時期以降の建物に住んでいると安全といえるのでしょうか?
浅井先生はこう話を続けます。
『一言、言えるのは、
1981年以降の建築基準で建てられた基準であっても
震度6になったときに、倒壊するかどうかの保証はない。
震度5で設計されているので、それより大きな地震がきたときに
倒壊はいつおきてもおかしくない。40年以上の建物が当時の強度を
持っているかと言われると弱くなっているのは、事実なので、
震度5もつかどうかを基準で作られたもので、
それよりも強度が弱くなっていて震度6が来たら、
まったく保証がないというのは事実なのでは、
底は把握しておいた方がいいと思います。』
新耐震基準を満たしている住宅に住んでいたとしても、
維持管理を丁寧にやる事が大切です。
また。地震による災害の中で起きる、
『液状化』は、建物が傾いたりする可能性があります。
また、震度6強以上で発生する揺れの
周期が長い長周期地震動については、
今の建築基準法では想定されていません。
長周期地震動は、タワーマンションのような高い建物程
想定外の被害が出やすくなります。
新耐震基準の建物でも絶対安心とは言い切れない為、
事前にハザードマップを確認したり、耐震対策がなされているか
チェックしておきましょう。
音声ファイルはこちら
地震が多い日本では、
住宅を建築する時に建物の耐震性の高さが求められます。
耐震基準は、今まで複数回見直されています。
耐震基準は大きくわけて、3つの時期に分けられます。
防災工学が専門の九州大学 浅井光輝准教授の解説です。
『新耐震か旧耐震かっていうのは、
1981年の基準かどうかって事でよく使われます。
ただそれが、ずっと続いているわけではなくて、
1995年の阪神淡路大震災で多くの木造家屋が倒壊して、
大きな被害につながったって事もあるので、
建築基準をもう一度見直そうっていう事が2000年にもう一度行われて、
そのときに、震度6に対しての強化がされている。震度6強に対しても
壊れないような設計に対しても改定が行われたのが2000年なんですけれども、
そこのアップデートよりも1981年のアップデートの方が大きかったので、
旧耐震・新耐震という言葉で分ける事が多いのですが、
厳密にいえば、2000年にアップデートされている。
インフラ構造物に対しても、同じ様に、橋梁に対しての設計基準もかなり
強化されて、基準を満たしていないと、補修・補強をして道路で使われている。
インフラ構造物は、耐震設計がされている。今は補強されているか、
新しい設計で使われている。』
浅井先生の解説にもあった様に、耐震基準は、
1981年以前・以降、そして2000年以降と大きく
3つの時期に分けられています。
2000年の基準は新耐震基準で建築された多くの木造住宅が
1995年の阪神淡路大震災で倒壊・半壊した事をきっかけに
木造住宅をメインに制定された基準です。
家の備えとして、1981年以降に建てられた建物に住んでいるか?
という点が防災の観点から言われていますが、
この時期以降の建物に住んでいると安全といえるのでしょうか?
浅井先生はこう話を続けます。
『一言、言えるのは、
1981年以降の建築基準で建てられた基準であっても
震度6になったときに、倒壊するかどうかの保証はない。
震度5で設計されているので、それより大きな地震がきたときに
倒壊はいつおきてもおかしくない。40年以上の建物が当時の強度を
持っているかと言われると弱くなっているのは、事実なので、
震度5もつかどうかを基準で作られたもので、
それよりも強度が弱くなっていて震度6が来たら、
まったく保証がないというのは事実なのでは、
底は把握しておいた方がいいと思います。』
新耐震基準を満たしている住宅に住んでいたとしても、
維持管理を丁寧にやる事が大切です。
また。地震による災害の中で起きる、
『液状化』は、建物が傾いたりする可能性があります。
また、震度6強以上で発生する揺れの
周期が長い長周期地震動については、
今の建築基準法では想定されていません。
長周期地震動は、タワーマンションのような高い建物程
想定外の被害が出やすくなります。
新耐震基準の建物でも絶対安心とは言い切れない為、
事前にハザードマップを確認したり、耐震対策がなされているか
チェックしておきましょう。
音声ファイルはこちら