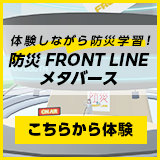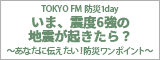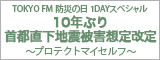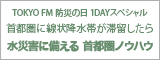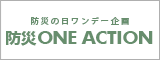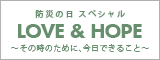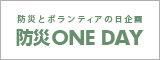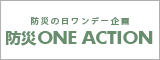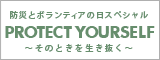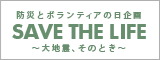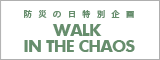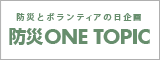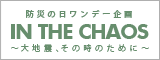2025年03月08日
08:25 岩手県大船渡市の森林火災 専門家に聞く
今朝は、岩手県大船渡市の大規模山林火災について
専門家の話を交えてお伝えします。
この山林火災での焼失面積は
3月4日時点でおよそ2600ヘクタール。
また建物被害は少なくとも84棟と報告されています。
京都大学防災研究所
特定准教授・峠嘉哉さんに伺いました。
延焼が続く理由について、
現段階で、どのような条件で大規模化したかについて、
今後の調査研究をしてみないと詳細は分からないとしたうえで、
一般的に山林での火災が燃え広がる条件として、
『乾燥』と『強風』そして、
気象条件だけでなくこのような事もあげられると言います。
この様な理由をあげた上で、
今は、過去にどういう事例があったかを、
振りかえる事が非常に重要だと言います。
峠さんが事例としてあげたのが、
2017年5月に岩手県釜石市で起きた尾崎半島林野火災です。
焼失面積は、413ヘクタールで、
この時は、出火当日に数百ヘクタールが燃え、
非常に速いスピードで燃え広がりました。
また、その後の調査で
「樹冠火(じゅかんか)」というものが起こった事が分かったといいます。
樹冠火という言葉をはじめて聞いた方もいらっしゃると思います。
峠さんの解説です。
今回の山林火災で、樹幹火が起こったのかは、
これからの調査を待たないと分かりませんが、
過去には起きた火災から備える事、学ぶことができます。
山の近くに住む方にとっては、
山林火災は恐ろしい災害の一つです。
一方で山や森林が近くにない都市部などに住む
あなたにも、影響がないわけではありません。
各地で山林火災が起きる事で
地球温暖化や気候変動が進んでします可能性があります。
都市部など各地の気温が上昇して真夏日や猛暑日、
熱帯夜の日数が増えて熱中症の危険性も高まります。
また、降水量の不足による水不足や、局所的に大雨が降る豪雨と
それに伴う洪水や土砂崩れなどの二次災害が起こる可能性もあります。
この時期は、乾燥した状態が続くので火の取り扱いも含めて
あらためて注意しましょう。
音声ファイルはこちら
専門家の話を交えてお伝えします。
この山林火災での焼失面積は
3月4日時点でおよそ2600ヘクタール。
また建物被害は少なくとも84棟と報告されています。
京都大学防災研究所
特定准教授・峠嘉哉さんに伺いました。
延焼が続く理由について、
現段階で、どのような条件で大規模化したかについて、
今後の調査研究をしてみないと詳細は分からないとしたうえで、
一般的に山林での火災が燃え広がる条件として、
『乾燥』と『強風』そして、
気象条件だけでなくこのような事もあげられると言います。
この様な理由をあげた上で、
今は、過去にどういう事例があったかを、
振りかえる事が非常に重要だと言います。
峠さんが事例としてあげたのが、
2017年5月に岩手県釜石市で起きた尾崎半島林野火災です。
焼失面積は、413ヘクタールで、
この時は、出火当日に数百ヘクタールが燃え、
非常に速いスピードで燃え広がりました。
また、その後の調査で
「樹冠火(じゅかんか)」というものが起こった事が分かったといいます。
樹冠火という言葉をはじめて聞いた方もいらっしゃると思います。
峠さんの解説です。
今回の山林火災で、樹幹火が起こったのかは、
これからの調査を待たないと分かりませんが、
過去には起きた火災から備える事、学ぶことができます。
山の近くに住む方にとっては、
山林火災は恐ろしい災害の一つです。
一方で山や森林が近くにない都市部などに住む
あなたにも、影響がないわけではありません。
各地で山林火災が起きる事で
地球温暖化や気候変動が進んでします可能性があります。
都市部など各地の気温が上昇して真夏日や猛暑日、
熱帯夜の日数が増えて熱中症の危険性も高まります。
また、降水量の不足による水不足や、局所的に大雨が降る豪雨と
それに伴う洪水や土砂崩れなどの二次災害が起こる可能性もあります。
この時期は、乾燥した状態が続くので火の取り扱いも含めて
あらためて注意しましょう。
音声ファイルはこちら