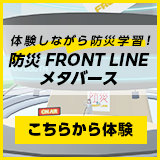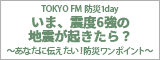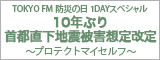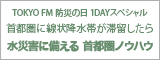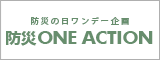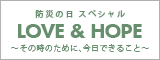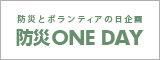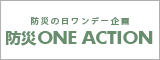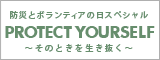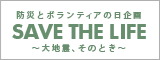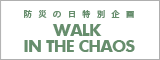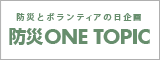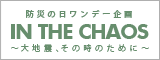2025年03月15日
08:25 東日本大震災から14年「復興ツーリズムって?」
東日本大震災から14年が経ちました。
3月11日午後2時46分ごろ、
東北沖でマグにチュード9.0の巨大地震が発生し、
宮城県栗原市で震度7を観測。
岩手、宮城、福島県を中心とした太平洋沿岸部を巨大な津波が襲い、
東京電力福島第一原発事故も発生しました。
また、東京23区でも、高層ビルなどを大きくゆっくりと揺らす
長周期地震動も観測され、震源から遠く離れた東京や大阪でも被害がでました。
災害関連死をふくめた東日本大震災の死者と行方不明者は、
合わせて2万2千228人にのぼり、
避難生活を余儀なくされている人は2万7615人となっています。
発生から14年の時が経ち、記憶が風化するとともに、
震災を知らない世代も増えてきました。
今朝は、「東日本大震災の教訓を学ぶ」と題してお伝えします。
震災の記憶や教訓、防災対策について学ぶことができる
サイトや書籍など多く出版されています。
今回番組でご紹介したいのは、
『被災地に行って教訓を学ぶ』という事です。
復興が進んでいる地域を中心にとくに力をいれている
防災学習があるそうなのですが・・・。
東北大学災害科学国際研究所の今村文彦教授に伺いました。
今村教授
今その状況を見ていただくような、
例えば防災学習ツーリズムまたは復興ツーリズムということで、広くですね、
国内外の方々に来ていただくような取り組みが進んでいます。
だいぶ復興が進んで逆にですね、当時の状況が分かりづらいところはあるんですが、
遺構であったり伝承施設ではしっかり当時の状況を、語りべさんであったり、
いろんな資料を見ていただきながら、現地で学習とかいろんな学びをしていただいております。
福島の特に浜通りでは、ホープツーリズムということで
、希望を皆さんと語るということで、まだ本当に復興が始まったばかりではあるんですが、
その状況も見ていただいて、福島の課題であったり新しい取り組み、光と影と呼ぶんですけども、」
そこも見ていただくようなツアーがあります。
東北を旅しながら被災地から学ぶ『復興ツーリズム』は、
自治体が企画しているツアーもあれば、
旅行会社などが企画している復興ツーリズムなどさまざまです。
また、日帰りプランから1泊2日かけてまわるプランなど、
旅のスケジュールに合わせてくみこむ事ができます。
復興ツーリズムは、学びだけではなく、
震災の記憶を風化させない、被災地の観光をまもる事や
多くの人が被災地を訪れてその地に住むみなさんと交流する事で
被災者の方々が元気になるという様々な側面があります。
復興ツーリズムは国も推進をしています。
被災地に行ったことのないかた、東日本大震災についてお子さんに
伝えたいと思っている方に特におすすめです。
春休みに被災地を訪れてみてはいかがでしょうか?
東日本大震災から14年。
あなたに伝えたい事、今村さんのメッセージです。
今村教授:
我々ですね。
東日本大震災から学んだ1番大きなものは、
備え以上のことはできなかったということです。
実は宮城県沖とかですね、
過去の地震、津波に対して一定の事前防災であったり取り組みはやっていたんですけども、
それを超えたところでは非常に難しかったと。
防潮堤を超えた津波が広域に、また原子力事故も起きましてで、
はるかに想定を上回ってしまったわけです。
今後もそういう状況が生まれる可能性もありますので、ぜひ、備え以上のことはできないので、
だからこそ今、事前の防災であったり備えっていうのを十分とっていただきたい。
それが個人のレベルからコミュニティ、また国全体でですね、取り組んでいただきたいなと思います。
『備え以上の事は』できない。
いつ起きるかわからない災害に備えて、
あなたができる防災の準備をしてましょう。
防災備蓄や非常用持ち出し袋の点検も忘れずに。
音声ファイルはこちら
3月11日午後2時46分ごろ、
東北沖でマグにチュード9.0の巨大地震が発生し、
宮城県栗原市で震度7を観測。
岩手、宮城、福島県を中心とした太平洋沿岸部を巨大な津波が襲い、
東京電力福島第一原発事故も発生しました。
また、東京23区でも、高層ビルなどを大きくゆっくりと揺らす
長周期地震動も観測され、震源から遠く離れた東京や大阪でも被害がでました。
災害関連死をふくめた東日本大震災の死者と行方不明者は、
合わせて2万2千228人にのぼり、
避難生活を余儀なくされている人は2万7615人となっています。
発生から14年の時が経ち、記憶が風化するとともに、
震災を知らない世代も増えてきました。
今朝は、「東日本大震災の教訓を学ぶ」と題してお伝えします。
震災の記憶や教訓、防災対策について学ぶことができる
サイトや書籍など多く出版されています。
今回番組でご紹介したいのは、
『被災地に行って教訓を学ぶ』という事です。
復興が進んでいる地域を中心にとくに力をいれている
防災学習があるそうなのですが・・・。
東北大学災害科学国際研究所の今村文彦教授に伺いました。
今村教授
今その状況を見ていただくような、
例えば防災学習ツーリズムまたは復興ツーリズムということで、広くですね、
国内外の方々に来ていただくような取り組みが進んでいます。
だいぶ復興が進んで逆にですね、当時の状況が分かりづらいところはあるんですが、
遺構であったり伝承施設ではしっかり当時の状況を、語りべさんであったり、
いろんな資料を見ていただきながら、現地で学習とかいろんな学びをしていただいております。
福島の特に浜通りでは、ホープツーリズムということで
、希望を皆さんと語るということで、まだ本当に復興が始まったばかりではあるんですが、
その状況も見ていただいて、福島の課題であったり新しい取り組み、光と影と呼ぶんですけども、」
そこも見ていただくようなツアーがあります。
東北を旅しながら被災地から学ぶ『復興ツーリズム』は、
自治体が企画しているツアーもあれば、
旅行会社などが企画している復興ツーリズムなどさまざまです。
また、日帰りプランから1泊2日かけてまわるプランなど、
旅のスケジュールに合わせてくみこむ事ができます。
復興ツーリズムは、学びだけではなく、
震災の記憶を風化させない、被災地の観光をまもる事や
多くの人が被災地を訪れてその地に住むみなさんと交流する事で
被災者の方々が元気になるという様々な側面があります。
復興ツーリズムは国も推進をしています。
被災地に行ったことのないかた、東日本大震災についてお子さんに
伝えたいと思っている方に特におすすめです。
春休みに被災地を訪れてみてはいかがでしょうか?
東日本大震災から14年。
あなたに伝えたい事、今村さんのメッセージです。
今村教授:
我々ですね。
東日本大震災から学んだ1番大きなものは、
備え以上のことはできなかったということです。
実は宮城県沖とかですね、
過去の地震、津波に対して一定の事前防災であったり取り組みはやっていたんですけども、
それを超えたところでは非常に難しかったと。
防潮堤を超えた津波が広域に、また原子力事故も起きましてで、
はるかに想定を上回ってしまったわけです。
今後もそういう状況が生まれる可能性もありますので、ぜひ、備え以上のことはできないので、
だからこそ今、事前の防災であったり備えっていうのを十分とっていただきたい。
それが個人のレベルからコミュニティ、また国全体でですね、取り組んでいただきたいなと思います。
『備え以上の事は』できない。
いつ起きるかわからない災害に備えて、
あなたができる防災の準備をしてましょう。
防災備蓄や非常用持ち出し袋の点検も忘れずに。
音声ファイルはこちら