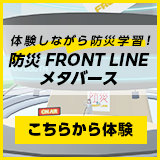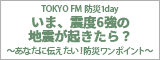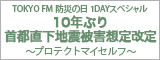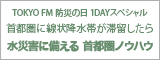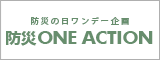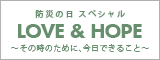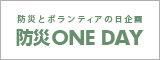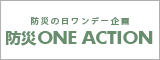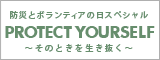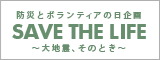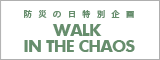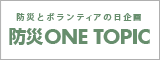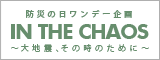2024.01.27
08:25 看護師の被災地医療支援
今朝は、「被災地の医療支援」についてご紹介します。
東日本大震災や熊本地震をはじめ、国内外31の被災地で
医療支援・救助活動を行ってきた、辻直美さんにお話しを伺いました。
日本には災害に関わる2tつ看護師の仕事があるそうです。
災害ナースもチームの一員となる災害医療派遣チーム=
DMATが作られたのは、阪神淡路大震災がきっかけです。
災害ナース、災害支援ナースとして活動してきた辻さんは、
阪神淡路大震災の被災者の1人。当時の様子を振り返りこう話します。
阪神・淡路大震災では、初期の医療体制が遅れたこと等から
助けられた命が助けられなかったという「避けられた災害死」が
およそ500人いたと後になって報告されています。
この教訓を生かし誕生したのがDMATです。
1月1日に起きた、能登半島地震でも
災害医療派遣チーム=DMATが救助活動等をおこない、
災害支援ナースが被災地で医療支援を行っています。
能登半島地震からまもなく1か月。
辻さんは、災害が長期化する中で、
衛生環境やいつもと違う状態で暮らしている事によるストレス。
持病の悪化などが心配される時期だと話します。
軽減する為には、
徐々に被災者が自分たちで暮らしていくと言う基盤を作ることが求められます。
それぞれの役割をして生きる目的を作ること、
復興に向けての準備
日常にしていたことを徐々に戻していく。
EX 散髪、美容、趣味など
日常生活における潤い
私たちにできる支援の1つが募金です。
TOKYO FMをはじめとする、JFN38局では、
石川県能登地方を震源とする地震で被災した皆さまを、
救済、支援するための「JFN募金」を受け付けています。
あなたから寄せられた募金は、
「JFN募金」事務局が取りまとめて全額を被災地に送り、
被害に遭われた方の救済、支援活動に役立てられます。
ぜひ、ご協力ください。
くわしくはTOKYO FMトップページにある「JFN募金」のバナーからご覧ください。
音声ファイルはこちら
東日本大震災や熊本地震をはじめ、国内外31の被災地で
医療支援・救助活動を行ってきた、辻直美さんにお話しを伺いました。
日本には災害に関わる2tつ看護師の仕事があるそうです。
災害ナースもチームの一員となる災害医療派遣チーム=
DMATが作られたのは、阪神淡路大震災がきっかけです。
災害ナース、災害支援ナースとして活動してきた辻さんは、
阪神淡路大震災の被災者の1人。当時の様子を振り返りこう話します。
阪神・淡路大震災では、初期の医療体制が遅れたこと等から
助けられた命が助けられなかったという「避けられた災害死」が
およそ500人いたと後になって報告されています。
この教訓を生かし誕生したのがDMATです。
1月1日に起きた、能登半島地震でも
災害医療派遣チーム=DMATが救助活動等をおこない、
災害支援ナースが被災地で医療支援を行っています。
能登半島地震からまもなく1か月。
辻さんは、災害が長期化する中で、
衛生環境やいつもと違う状態で暮らしている事によるストレス。
持病の悪化などが心配される時期だと話します。
軽減する為には、
徐々に被災者が自分たちで暮らしていくと言う基盤を作ることが求められます。
それぞれの役割をして生きる目的を作ること、
復興に向けての準備
日常にしていたことを徐々に戻していく。
EX 散髪、美容、趣味など
日常生活における潤い
私たちにできる支援の1つが募金です。
TOKYO FMをはじめとする、JFN38局では、
石川県能登地方を震源とする地震で被災した皆さまを、
救済、支援するための「JFN募金」を受け付けています。
あなたから寄せられた募金は、
「JFN募金」事務局が取りまとめて全額を被災地に送り、
被害に遭われた方の救済、支援活動に役立てられます。
ぜひ、ご協力ください。
くわしくはTOKYO FMトップページにある「JFN募金」のバナーからご覧ください。
音声ファイルはこちら
2024.01.20
08:25 常温で保管・お湯が必要ない「乳児用液体ミルク」
1月1日に起きた能登半島地震、発生から20日です。
被災地の避難所には、現在およそ900人が避難していると言われています。
避難者の中には乳幼児もいます。
現在、乳幼児がいる家族が離乳食等の
食事を十分に確保できていなかったり、
断水やお湯が沸かせない事で
粉ミルクを溶かせないといった状況が続いています。
今朝は、お湯で溶かす事なく、常温で保存できる
「乳児用液体ミルク」についてお伝えします。
災害時に断水や停電してもそのまま飲める「液体ミルク」
2016年の熊本地震でフィンランドから緊急輸入され、
その後、国内での製造・販売が行われる様になりました。
液体ミルクは、お湯の調乳が不要な事や
常温で保管可能といったメリットがある一方、
価格が高く消費期限が短い商品が多い事がデメリットとして挙げられます。
しかし、能登半島の地震の様に停電や断水が長期化する中で、
赤ちゃんにとって液体ミルクがあるかないかは重要です。
国際災害レスキューナースの辻直美さんはこのように話します。
完全母乳で育てたいなどご家庭によって方針は様々あると思いますが
ミルクの味を赤ちゃんに知ってもらう事は災害時大切な事かもしれません。
さて、都内の自治体で乳児用液体ミルクを備蓄しているのは、
新宿区、文京区など18区です。
一方、備蓄していないのは、世田谷区や足立区など5区。
台東区のように備蓄はしていないけれど、災害が起きた時に
ドラッグストアから調達できる協定を結んでいる区もあります。
液体ミルクを製造する明治と日本気象協会が今年6月に実施した
全国調査では、474の自治体のうち47.5が備蓄していると回答。
年々備蓄率は増えているものの半数弱にとどまっています。
辻さんは、お母さん、お父さんに向けてこのように話します。
辻さんの本、地震・台風時に動けるガイド -大事な人を護る災害対策では、
家族を護る自宅の防災について紹介されています。
家族構成はご家庭それぞれです。
今こそ、ご自宅の備蓄の確認を。
音声ファイルはこちら
被災地の避難所には、現在およそ900人が避難していると言われています。
避難者の中には乳幼児もいます。
現在、乳幼児がいる家族が離乳食等の
食事を十分に確保できていなかったり、
断水やお湯が沸かせない事で
粉ミルクを溶かせないといった状況が続いています。
今朝は、お湯で溶かす事なく、常温で保存できる
「乳児用液体ミルク」についてお伝えします。
災害時に断水や停電してもそのまま飲める「液体ミルク」
2016年の熊本地震でフィンランドから緊急輸入され、
その後、国内での製造・販売が行われる様になりました。
液体ミルクは、お湯の調乳が不要な事や
常温で保管可能といったメリットがある一方、
価格が高く消費期限が短い商品が多い事がデメリットとして挙げられます。
しかし、能登半島の地震の様に停電や断水が長期化する中で、
赤ちゃんにとって液体ミルクがあるかないかは重要です。
国際災害レスキューナースの辻直美さんはこのように話します。
完全母乳で育てたいなどご家庭によって方針は様々あると思いますが
ミルクの味を赤ちゃんに知ってもらう事は災害時大切な事かもしれません。
さて、都内の自治体で乳児用液体ミルクを備蓄しているのは、
新宿区、文京区など18区です。
一方、備蓄していないのは、世田谷区や足立区など5区。
台東区のように備蓄はしていないけれど、災害が起きた時に
ドラッグストアから調達できる協定を結んでいる区もあります。
液体ミルクを製造する明治と日本気象協会が今年6月に実施した
全国調査では、474の自治体のうち47.5が備蓄していると回答。
年々備蓄率は増えているものの半数弱にとどまっています。
辻さんは、お母さん、お父さんに向けてこのように話します。
辻さんの本、地震・台風時に動けるガイド -大事な人を護る災害対策では、
家族を護る自宅の防災について紹介されています。
家族構成はご家庭それぞれです。
今こそ、ご自宅の備蓄の確認を。
音声ファイルはこちら
2024.01.16
18:17 今年確認したい「水災保険」
2024年1年の始めに確認して貰いたい、保険についてお伝えします。
今年大きく変わるのが水災保険です。
防災システム研究所所長で
防災危機管理アドバザーの山村武彦さんの解説です。
山村さん:
今までは、一律で保険料が決まっていたんですが、
5段階の等級に、1等地から5等地まで分かれるんですね。
特に水害の危険が高いのが5等地。
そうすると保険料が高くなります。
高いところでは、およそ1.5倍になる可能性があります。
今のうちに危険度の高いところは、保険料の見直しや
更新をしておきましょう。
床上浸水や家が流されてしまった時の水害に対応する
水災保険は、火災や落雷の被害を補償する火災保険と一緒に契約します。
火災保険の契約数はおよそ2千万件で、
このうち水災保険の付帯率は、およそ65%
水害のリスクが低い地域を1等地、
逆に高い地域を5等地と分類。
5等地について山村さんのお話です。
山村さん:
東京の周辺ですと葛飾区ですとか、
荒川区、江戸川区周辺の地域は5等地に指定される。
必ずしも山間地だけではない、都市部も一部入っているので
あなたの住んでいる街が何等地なのか確認して、
早めに入った方が良い場合もあるので確認すると良いと思います。
損害保険料率算出機構で検索すると
あなたの住んでいる街がどのグループかわかります。
この水災保険は、河川の氾濫だけでなく
内水氾濫も保障に入ります。
最後に保険の重要性について山村さんのお話です。
山村さん:
確認していないと、
もしかしたら入っていない人もいるかもしれない。
水災保障に特約をつけていない場合があるので、
お見舞金だけになってしまう可能性がある。
自分の家の保険がどうなっているのか。
地震保険、火災保険、自動車保険で車両保険に入っていないと
内水氾濫で車が浸水しても保険料がもらえないという事になるので
そういった保険の確認もしておきましょう。
災害に備えて保険の確認を
音声ファイルはこちら
今年大きく変わるのが水災保険です。
防災システム研究所所長で
防災危機管理アドバザーの山村武彦さんの解説です。
山村さん:
今までは、一律で保険料が決まっていたんですが、
5段階の等級に、1等地から5等地まで分かれるんですね。
特に水害の危険が高いのが5等地。
そうすると保険料が高くなります。
高いところでは、およそ1.5倍になる可能性があります。
今のうちに危険度の高いところは、保険料の見直しや
更新をしておきましょう。
床上浸水や家が流されてしまった時の水害に対応する
水災保険は、火災や落雷の被害を補償する火災保険と一緒に契約します。
火災保険の契約数はおよそ2千万件で、
このうち水災保険の付帯率は、およそ65%
水害のリスクが低い地域を1等地、
逆に高い地域を5等地と分類。
5等地について山村さんのお話です。
山村さん:
東京の周辺ですと葛飾区ですとか、
荒川区、江戸川区周辺の地域は5等地に指定される。
必ずしも山間地だけではない、都市部も一部入っているので
あなたの住んでいる街が何等地なのか確認して、
早めに入った方が良い場合もあるので確認すると良いと思います。
損害保険料率算出機構で検索すると
あなたの住んでいる街がどのグループかわかります。
この水災保険は、河川の氾濫だけでなく
内水氾濫も保障に入ります。
最後に保険の重要性について山村さんのお話です。
山村さん:
確認していないと、
もしかしたら入っていない人もいるかもしれない。
水災保障に特約をつけていない場合があるので、
お見舞金だけになってしまう可能性がある。
自分の家の保険がどうなっているのか。
地震保険、火災保険、自動車保険で車両保険に入っていないと
内水氾濫で車が浸水しても保険料がもらえないという事になるので
そういった保険の確認もしておきましょう。
災害に備えて保険の確認を
音声ファイルはこちら
2024.01.06
08:25 令和6年 能登半島地震
今朝は、1月1日に起きた
「令和6年能登半島地震」についてお伝えします。
石川県志賀町(しかまち)で震度7を観測した能登半島地震。
倒壊家屋などからの救助作業は難航していて、
警察や消防による捜索が続いています。
避難者の数も日が経つごとに増えています。
5日現在、石川県全体で3万3千人を超えている状況です。
被災した地域では、水や食料、簡易トイレなど様々な物資が不足しています。
たとえば、輪島市では、1万1681人と避難者は1万人を超えていますが、
人数に対して、食料は、3千食、
水(500ml)5千本しか届いていないという事です。
本来であれば、毎日、3万食、水、(500ml)、5万本が必要ですが、
なかなか支援の手が届かない状況です。
こうした中、
何かできないかと思っている方もいらっしゃると思います。
石川県では、
個人からの支援物資について
現在は受け入れが困難な状況で、「現段階では控えてほしい」としています。
石川県健康福祉部によりますと、個人からの支援物資については、
少ない量のものを仕分けして現地におくる必要があるため、
作業効率や人道確保の観点から、
現在のところ受け入れが困難な状況になっているようです。
この為、県は、
「SNSでは個人からも支援物資を受け付けている」という
情報が一部で拡散していますが、
現段階では控えてほしいと呼びかけています。
また、現地に直接届けるのも
救命活動の妨げになるために控えてほしいという事です。
一方、企業からのまとまった量の支援物資については、
県の厚生政策課で受け付けているという事です。
そのうえで、支援を考えている企業はすぐに物資を送るのではなく、
必要な物資の確認や調整のため、
事前に県の担当課に連絡してほしいという事です。
また、災害ボランティアの受付はまだ整っていません。
現在、石川県のウェブサイトでは、
「災害ボランティアの募集は行っておりません」
市役所・社会福祉協議会等に、電話でのお問い合わせを控えて
いただきますようお願い致しますと書かれています。
現時点で現地に問い合わせる事や自治体に問い合わせる事は
災害復旧の妨げとなってしまう事があります。
ボランティア活動を考えている方は、
県のWEBサイトを随時チェックし状況を確認しましょう。
また、受付が開始するまでに準備しておくことも大切です。
政府広報オンラインでは、被災地を応援したい方へ災害ボランティア
活動のはじめ方と題し、事前に心得ておきたい情報が掲載されています。
帽子やヘルメット、軍手やゴム手袋、長袖長ズボンといった
持ち物リストを紹介しているほか、食事や宿泊先、往復の交通手段を確保するなど、
事前に必要な備えをして被災地にはいる事などが分かり易く掲載されています。
またボランティア活動保険に加入する事も大切です。
災害義援金についてです。
石川県は日本赤十字社石川県支部と石川県共同募金会
と連携して、おとといから義援金を受け付けています。
詳しくは、石川県のHPをご確認ください。
また、ふるさと納税の仕組みを利用した寄付や募金も行われています。
ふるさと納税のポータルサイトを運営する「さとふる」は、
石川など16自治体向けの寄付を募っています。
返礼品を希望しない寄付で、さとふるが寄付決済手数料を負担。
申し込み金額の全額が自治体に届けられます。
1000円以上1円単位で指定した金額を寄付できるという事です。
音声ファイルはこちら
「令和6年能登半島地震」についてお伝えします。
石川県志賀町(しかまち)で震度7を観測した能登半島地震。
倒壊家屋などからの救助作業は難航していて、
警察や消防による捜索が続いています。
避難者の数も日が経つごとに増えています。
5日現在、石川県全体で3万3千人を超えている状況です。
被災した地域では、水や食料、簡易トイレなど様々な物資が不足しています。
たとえば、輪島市では、1万1681人と避難者は1万人を超えていますが、
人数に対して、食料は、3千食、
水(500ml)5千本しか届いていないという事です。
本来であれば、毎日、3万食、水、(500ml)、5万本が必要ですが、
なかなか支援の手が届かない状況です。
こうした中、
何かできないかと思っている方もいらっしゃると思います。
石川県では、
個人からの支援物資について
現在は受け入れが困難な状況で、「現段階では控えてほしい」としています。
石川県健康福祉部によりますと、個人からの支援物資については、
少ない量のものを仕分けして現地におくる必要があるため、
作業効率や人道確保の観点から、
現在のところ受け入れが困難な状況になっているようです。
この為、県は、
「SNSでは個人からも支援物資を受け付けている」という
情報が一部で拡散していますが、
現段階では控えてほしいと呼びかけています。
また、現地に直接届けるのも
救命活動の妨げになるために控えてほしいという事です。
一方、企業からのまとまった量の支援物資については、
県の厚生政策課で受け付けているという事です。
そのうえで、支援を考えている企業はすぐに物資を送るのではなく、
必要な物資の確認や調整のため、
事前に県の担当課に連絡してほしいという事です。
また、災害ボランティアの受付はまだ整っていません。
現在、石川県のウェブサイトでは、
「災害ボランティアの募集は行っておりません」
市役所・社会福祉協議会等に、電話でのお問い合わせを控えて
いただきますようお願い致しますと書かれています。
現時点で現地に問い合わせる事や自治体に問い合わせる事は
災害復旧の妨げとなってしまう事があります。
ボランティア活動を考えている方は、
県のWEBサイトを随時チェックし状況を確認しましょう。
また、受付が開始するまでに準備しておくことも大切です。
政府広報オンラインでは、被災地を応援したい方へ災害ボランティア
活動のはじめ方と題し、事前に心得ておきたい情報が掲載されています。
帽子やヘルメット、軍手やゴム手袋、長袖長ズボンといった
持ち物リストを紹介しているほか、食事や宿泊先、往復の交通手段を確保するなど、
事前に必要な備えをして被災地にはいる事などが分かり易く掲載されています。
またボランティア活動保険に加入する事も大切です。
災害義援金についてです。
石川県は日本赤十字社石川県支部と石川県共同募金会
と連携して、おとといから義援金を受け付けています。
詳しくは、石川県のHPをご確認ください。
また、ふるさと納税の仕組みを利用した寄付や募金も行われています。
ふるさと納税のポータルサイトを運営する「さとふる」は、
石川など16自治体向けの寄付を募っています。
返礼品を希望しない寄付で、さとふるが寄付決済手数料を負担。
申し込み金額の全額が自治体に届けられます。
1000円以上1円単位で指定した金額を寄付できるという事です。
音声ファイルはこちら
2023.12.30
08:25 2023年の災害
「2023年の災害」という視点で
防災システム研究所所長で
危機管理アドバイザーの
山村武彦さんの解説と共に振り返ります。
世界的に見ると、
今年、2月にはトルコ・シリア大地震という
マグニチュード7.8の地震が発生して、
およそ5万6千人の犠牲者が出ました。
また、9月にはモロッコ地震、
10月にはアフガニスタンで地震が発生しました。
日本は、たまたま大きな災害を引き起こす様な
大きな地震はありませんでした。
そんな中でも山村さんは、
5月に起きた、
能登半島地震についてこう指摘します。
関東大震災から100年の年でもありましたが、
この100年間に、100人以上の犠牲者が出た大地震は
日本では、16回発生しています。
平均すると、6年に1度、大地震が発生している計算です。
直近の大地震は、2016年の熊本地震。
発生から7年経っています。
またいつどこで大きな地震が発生してもおかしくありません。
山村さんは、
2023年は、記憶に残る年になったと話します。
世界気象機関やコペルニクス気候変動サービスなどが
地球の気温が観測史上最高を更新したと発表。
国連のグテーレス事務総長は、
地球温暖化が終わって、
地球沸騰の時代がきたとコメントしました。
コペルニクス気候変動サービスは、
2024年は更に気温が高くなる可能性があると予測しています。
お正月に家族防災会議を開いて、
我が家の備蓄はどうなのか?
停電・断水・充電対策・非常用のトイレ対策について
確認する事をおすすめします。
音声ファイルはこちら
防災システム研究所所長で
危機管理アドバイザーの
山村武彦さんの解説と共に振り返ります。
世界的に見ると、
今年、2月にはトルコ・シリア大地震という
マグニチュード7.8の地震が発生して、
およそ5万6千人の犠牲者が出ました。
また、9月にはモロッコ地震、
10月にはアフガニスタンで地震が発生しました。
日本は、たまたま大きな災害を引き起こす様な
大きな地震はありませんでした。
そんな中でも山村さんは、
5月に起きた、
能登半島地震についてこう指摘します。
関東大震災から100年の年でもありましたが、
この100年間に、100人以上の犠牲者が出た大地震は
日本では、16回発生しています。
平均すると、6年に1度、大地震が発生している計算です。
直近の大地震は、2016年の熊本地震。
発生から7年経っています。
またいつどこで大きな地震が発生してもおかしくありません。
山村さんは、
2023年は、記憶に残る年になったと話します。
世界気象機関やコペルニクス気候変動サービスなどが
地球の気温が観測史上最高を更新したと発表。
国連のグテーレス事務総長は、
地球温暖化が終わって、
地球沸騰の時代がきたとコメントしました。
コペルニクス気候変動サービスは、
2024年は更に気温が高くなる可能性があると予測しています。
お正月に家族防災会議を開いて、
我が家の備蓄はどうなのか?
停電・断水・充電対策・非常用のトイレ対策について
確認する事をおすすめします。
音声ファイルはこちら
2023.12.27
08:25 看護師の被災地医療支援
今朝は、「看護師の被災地医療支援」についてご紹介します。
東日本大震災や熊本地震をはじめ、国内外31の被災地で
医療支援・救助活動を行ってきた、辻直美さんにお話しを伺いました。
日本には2つ災害に関わる看護師の仕事があるそうです。
災害ナースもチームの一員となる災害医療派遣チーム=
DMATが作られたのは、阪神淡路大震災がきっかけです。
災害ナース、災害支援ナースとして活動してきた辻さんは、
阪神淡路大震災の被災者の1人。当時の様子を振り返りこう話します。
阪神・淡路大震災では、初期の医療体制が遅れたこと等から
助けられた命が助けられなかったという「避けられた災害死」が
およそ500人いたと後になって報告されています。
この教訓を生かし誕生したのがDMATです。
1月1日に起きた、能登半島地震でも
災害医療派遣チーム=DMATが救助活動等をおこない、
災害支援ナースが被災地で医療支援を行っています。
能登半島地震からまもなく1か月。
辻さんは、災害が長期化する中で、
衛生環境やいつもと違う状態で暮らしている事によるストレス。
持病の悪化などが心配される時期だと話します。
軽減する為には、
徐々に被災者が自分たちで暮らしていくと言う基盤を作ることが求められます。
(被災者が自分たちで生活をしていくために、避難所で自治会を作っていき、
①それぞれの役割をして生きる目的を作ること、
②復興に向けての準備
③日常にしていたことを徐々に戻していく。
EX 散髪、美容、趣味など
④日常生活における潤い。
私たちにできる支援の1つが募金です。
TOKYO FMをはじめとする、JFN38局では、
石川県能登地方を震源とする地震で被災した皆さまを、
救済、支援するための「JFN募金」を受け付けています。
あなたから寄せられた募金は、
「JFN募金」事務局が取りまとめて全額を被災地に送り、
被害に遭われた方の救済、支援活動に役立てられます。
ぜひ、ご協力ください。
くわしくはTOKYO FMトップページにある「JFN募金」のバナーからご覧ください。
東日本大震災や熊本地震をはじめ、国内外31の被災地で
医療支援・救助活動を行ってきた、辻直美さんにお話しを伺いました。
日本には2つ災害に関わる看護師の仕事があるそうです。
災害ナースもチームの一員となる災害医療派遣チーム=
DMATが作られたのは、阪神淡路大震災がきっかけです。
災害ナース、災害支援ナースとして活動してきた辻さんは、
阪神淡路大震災の被災者の1人。当時の様子を振り返りこう話します。
阪神・淡路大震災では、初期の医療体制が遅れたこと等から
助けられた命が助けられなかったという「避けられた災害死」が
およそ500人いたと後になって報告されています。
この教訓を生かし誕生したのがDMATです。
1月1日に起きた、能登半島地震でも
災害医療派遣チーム=DMATが救助活動等をおこない、
災害支援ナースが被災地で医療支援を行っています。
能登半島地震からまもなく1か月。
辻さんは、災害が長期化する中で、
衛生環境やいつもと違う状態で暮らしている事によるストレス。
持病の悪化などが心配される時期だと話します。
軽減する為には、
徐々に被災者が自分たちで暮らしていくと言う基盤を作ることが求められます。
(被災者が自分たちで生活をしていくために、避難所で自治会を作っていき、
①それぞれの役割をして生きる目的を作ること、
②復興に向けての準備
③日常にしていたことを徐々に戻していく。
EX 散髪、美容、趣味など
④日常生活における潤い。
私たちにできる支援の1つが募金です。
TOKYO FMをはじめとする、JFN38局では、
石川県能登地方を震源とする地震で被災した皆さまを、
救済、支援するための「JFN募金」を受け付けています。
あなたから寄せられた募金は、
「JFN募金」事務局が取りまとめて全額を被災地に送り、
被害に遭われた方の救済、支援活動に役立てられます。
ぜひ、ご協力ください。
くわしくはTOKYO FMトップページにある「JFN募金」のバナーからご覧ください。
2023.12.23
08:25 Jアラートの種類
北朝鮮が今週18日(月)に大陸間弾道ミサイルを発射しました。
17日にも発射をしていて、日本政府は2日間連続の発射に対して
警戒感を強めています。
今朝は、【Jアラートの種類】という視点でお届けしていきます。
Jアラートとは、緊急地震速報やテロ攻撃のように、
時間の余裕がない緊急を要する災害や事態が発生した時に、
市町村の防災無線やスマホなどを通してあなたに警報が届くシステムです。
Jアラートは、全国瞬時警報システムとも呼ばれています。
消防庁が開発し、2007年から自治体に設備の導入がはじまりました。
弾道ミサイルのような国民保護に関する情報は、内閣官房から、
緊急地震速報や津波警報などは、気象庁から出す事になっています。
また、同時に国から携帯電話などの通信サービスの会社にも情報が配信され、
携帯電話利用者にエリアメールや緊急速報メールを通して
アラームが鳴る設定となっています。
自治体ごとにJアラートの訓練やテストを定期的に行っていて、
最近では、11月15日にJアラート全国一斉情報伝達試験が実施されました。
Jアラートに対応している災害は、
「国民保護関係情報」と「地震関係・気象の情報」に分けられます。
国民保護関係情報は、具体的にお伝えすると、
弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、
ゲリラ、特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報があります。
着弾する可能性や攻撃された時に、
この様なことがあった場合Jアラートが鳴ります。
鳴ったときの行動としては、
屋外にいる場合は、近くの建物や地下街などに屋内に避難する。
自動車を運転している時は、
緊急車両の妨げにならないように鍵はつけたまま、道路の端に停車する。
屋内にいる場合は、ドアや窓をすべて閉める。
ガス、水道、換気扇を止める、ドア、壁、窓ガラスから離れましょう。
地震関係・気象情報は、
緊急地震速報、津波警報、特別警報です。
緊急地震速報は、
アラートが鳴ってから数秒から数十秒以内に地震が発生する可能性があります。
短い時間で安全な場所に逃げる事はできないので、
身を守る事を一番に考えましょう。
屋外にいる場合は、
安全の確保、ブロック塀の倒壊やビルの外壁、窓ガラスの落下に備えて
危険な場所から離れる。海の近くにいたら、海から離れ頑丈なビルに避難する。
屋内にいる場合、
大きな家具から離れて頑丈な机の下に隠れる。
スーパーや施設にいる時は、係員の指示に従って行動しましょう。
特別警報のJアラートが鳴った時は、すでに気象災害が発生している可能性が
高いです。安全の確保を第一に考え、避難所に難しい時には、
2階以上の建物に垂直避難をしましょう。
屋外のスピーカーは、1年に4回行われている全国一斉情報伝達試験の時に、
自宅でアラームが聞こえるか確認しておく事をおすすめします。
Jアラートは、身の危険が差し迫った時に発令される警報システムです。
場合によっては、アラートが鳴ってから数秒の行動で命を守れるかの分かれ道
になります。アラートが鳴ったときの行動を常にシュミレーションしておきましょう。
実際にJアラートが鳴っても、それがなんの合図なのかわからない方もいるようです。
そうならない為にもどんな音が鳴るか確認すると共に、
実際にアラートが鳴って計画通りに行動できるか試してみましょう。
音声ファイルはこちら
17日にも発射をしていて、日本政府は2日間連続の発射に対して
警戒感を強めています。
今朝は、【Jアラートの種類】という視点でお届けしていきます。
Jアラートとは、緊急地震速報やテロ攻撃のように、
時間の余裕がない緊急を要する災害や事態が発生した時に、
市町村の防災無線やスマホなどを通してあなたに警報が届くシステムです。
Jアラートは、全国瞬時警報システムとも呼ばれています。
消防庁が開発し、2007年から自治体に設備の導入がはじまりました。
弾道ミサイルのような国民保護に関する情報は、内閣官房から、
緊急地震速報や津波警報などは、気象庁から出す事になっています。
また、同時に国から携帯電話などの通信サービスの会社にも情報が配信され、
携帯電話利用者にエリアメールや緊急速報メールを通して
アラームが鳴る設定となっています。
自治体ごとにJアラートの訓練やテストを定期的に行っていて、
最近では、11月15日にJアラート全国一斉情報伝達試験が実施されました。
Jアラートに対応している災害は、
「国民保護関係情報」と「地震関係・気象の情報」に分けられます。
国民保護関係情報は、具体的にお伝えすると、
弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、
ゲリラ、特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報があります。
着弾する可能性や攻撃された時に、
この様なことがあった場合Jアラートが鳴ります。
鳴ったときの行動としては、
屋外にいる場合は、近くの建物や地下街などに屋内に避難する。
自動車を運転している時は、
緊急車両の妨げにならないように鍵はつけたまま、道路の端に停車する。
屋内にいる場合は、ドアや窓をすべて閉める。
ガス、水道、換気扇を止める、ドア、壁、窓ガラスから離れましょう。
地震関係・気象情報は、
緊急地震速報、津波警報、特別警報です。
緊急地震速報は、
アラートが鳴ってから数秒から数十秒以内に地震が発生する可能性があります。
短い時間で安全な場所に逃げる事はできないので、
身を守る事を一番に考えましょう。
屋外にいる場合は、
安全の確保、ブロック塀の倒壊やビルの外壁、窓ガラスの落下に備えて
危険な場所から離れる。海の近くにいたら、海から離れ頑丈なビルに避難する。
屋内にいる場合、
大きな家具から離れて頑丈な机の下に隠れる。
スーパーや施設にいる時は、係員の指示に従って行動しましょう。
特別警報のJアラートが鳴った時は、すでに気象災害が発生している可能性が
高いです。安全の確保を第一に考え、避難所に難しい時には、
2階以上の建物に垂直避難をしましょう。
屋外のスピーカーは、1年に4回行われている全国一斉情報伝達試験の時に、
自宅でアラームが聞こえるか確認しておく事をおすすめします。
Jアラートは、身の危険が差し迫った時に発令される警報システムです。
場合によっては、アラートが鳴ってから数秒の行動で命を守れるかの分かれ道
になります。アラートが鳴ったときの行動を常にシュミレーションしておきましょう。
実際にJアラートが鳴っても、それがなんの合図なのかわからない方もいるようです。
そうならない為にもどんな音が鳴るか確認すると共に、
実際にアラートが鳴って計画通りに行動できるか試してみましょう。
音声ファイルはこちら
2023.12.16
08:25 防災気象情報見直しについて
河川の氾濫や土砂災害などから身を守る為に
気象庁などが発表する「防災気象情報」
この見直しが検討されています。
今朝は、「防災気象情報」の見直しについてお伝えします。
住民の避難行動に直結する情報なのにわかりにくいという意見が多い事が、
気象庁が2022年、防災気象情報について全国2千人に
聞いたWEBアンケートでそんな実態が見えてきました。
情報ごとに理解度を尋ねたところ、
「詳細に理解している」との回答が最も多かったのは、
大雨警報で68.5%。ただ大雨警報に土砂災害や浸水害の区別が
あると知っているのは、27.2%にとどまりました。
情報全体の印象については、多すぎてわかりにくいが、
55.1%と最も多く、
次に、多かったのが「どれが避難の判断の参考となる情報かがわかりにくい」
でした。
自治体が、情報を出すのに戸惑うケースもあります。
今年7月に記録的な大雨に見舞われた秋田市では、
避難指示を出せないまま警戒レベルで最高の「緊急安全確保」を出しました。
内水氾濫を知らせる浸水害の情報は、避難指示に相当するものが
今は、設定されていません。
こうした事から、気象庁と国土交通省は、
今月6日に有識者による検討会を開いて改善点を示しました。
見直しの対象は、河川の氾濫を示す、「洪水」や
排水できずに住宅地に起きる内水氾濫の「浸水害」、
そして「土砂災害」と「高潮」に関する情報です。
例えば、土砂災害を例にすると、
最高レベルは、「大雨特別警報」ですが、
その下は、「土砂災害警戒情報」さらにその下は、「大雨警報」となっています。
このばらつきのある名称を、今後、統一感のあるものに変える方向です。
さらに、大雨警報の発表基準を引き下げて信頼度を高めます。
また、情報が混じっているものもあります。
洪水では、同じ警戒レベルに市町村単位の「洪水警報」と
河川単位の「氾濫警戒情報」があります。
高潮の「特別警報」と「警報」も同じで、いずれも整理し直すという事です。
情報が複雑なのは、災害が起きる度に新しく作ってきた事が挙げられます。
1999年の広島豪雨で「土砂災害警戒情報」ができ、
2011年の紀伊半島の大水害を教訓に、「特別警報」がうまれました。
複雑さがましたため、内閣府は2019年に5段階の警戒レベルを導入し
ましたが、情報の複雑さ等は改善されず、今まで精査する時間もなかった為、
情報がいびつになったまま運用されてきたという背景があります。
今後はよりわかりやすい名称の付け方がポイントになりそうです。
気象庁の担当者にお話をお伺いしたところ、
名称に数字を入れるなど、わかりやすくする予定だという事です。
検討会は、来年6月頃に改善案をまとめる予定で
運用が始まるのは、数年後になる見通しです。
今朝は、防災気象情報の見直しについてお伝えしました。
音声ファイルはこちら
気象庁などが発表する「防災気象情報」
この見直しが検討されています。
今朝は、「防災気象情報」の見直しについてお伝えします。
住民の避難行動に直結する情報なのにわかりにくいという意見が多い事が、
気象庁が2022年、防災気象情報について全国2千人に
聞いたWEBアンケートでそんな実態が見えてきました。
情報ごとに理解度を尋ねたところ、
「詳細に理解している」との回答が最も多かったのは、
大雨警報で68.5%。ただ大雨警報に土砂災害や浸水害の区別が
あると知っているのは、27.2%にとどまりました。
情報全体の印象については、多すぎてわかりにくいが、
55.1%と最も多く、
次に、多かったのが「どれが避難の判断の参考となる情報かがわかりにくい」
でした。
自治体が、情報を出すのに戸惑うケースもあります。
今年7月に記録的な大雨に見舞われた秋田市では、
避難指示を出せないまま警戒レベルで最高の「緊急安全確保」を出しました。
内水氾濫を知らせる浸水害の情報は、避難指示に相当するものが
今は、設定されていません。
こうした事から、気象庁と国土交通省は、
今月6日に有識者による検討会を開いて改善点を示しました。
見直しの対象は、河川の氾濫を示す、「洪水」や
排水できずに住宅地に起きる内水氾濫の「浸水害」、
そして「土砂災害」と「高潮」に関する情報です。
例えば、土砂災害を例にすると、
最高レベルは、「大雨特別警報」ですが、
その下は、「土砂災害警戒情報」さらにその下は、「大雨警報」となっています。
このばらつきのある名称を、今後、統一感のあるものに変える方向です。
さらに、大雨警報の発表基準を引き下げて信頼度を高めます。
また、情報が混じっているものもあります。
洪水では、同じ警戒レベルに市町村単位の「洪水警報」と
河川単位の「氾濫警戒情報」があります。
高潮の「特別警報」と「警報」も同じで、いずれも整理し直すという事です。
情報が複雑なのは、災害が起きる度に新しく作ってきた事が挙げられます。
1999年の広島豪雨で「土砂災害警戒情報」ができ、
2011年の紀伊半島の大水害を教訓に、「特別警報」がうまれました。
複雑さがましたため、内閣府は2019年に5段階の警戒レベルを導入し
ましたが、情報の複雑さ等は改善されず、今まで精査する時間もなかった為、
情報がいびつになったまま運用されてきたという背景があります。
今後はよりわかりやすい名称の付け方がポイントになりそうです。
気象庁の担当者にお話をお伺いしたところ、
名称に数字を入れるなど、わかりやすくする予定だという事です。
検討会は、来年6月頃に改善案をまとめる予定で
運用が始まるのは、数年後になる見通しです。
今朝は、防災気象情報の見直しについてお伝えしました。
音声ファイルはこちら
2023.12.09
08:25 冬のブラックアウトに備える
大きな地震が発生したら、数日から1週間程度
「ブラックアウト」と呼ばれる大規模停電が起きる可能性があります。
そこで今朝は、
「冬場のブラックアウトに備える」という視点でお届けします。
2018年9月に最大震度7を観測した、
北海道胆振東部地震では、およそ295万戸が停電。
この地震では、街中の信号が消え、市役所などに、
スマートフォンの充電をしたい人の列ができました。
また、覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、
2022年3月の福島県沖の地震では、
首都圏などでおよそ200万戸以上が停電しました。
冬場は、停電が長期化すると住宅内が屋外並みに冷えて、
低体温症などになる恐れもあります。防寒対策を心がける事が大切です。
関東南部の山沿いの地域にお住まいの方は特に、
「電気を使わない暖房器具をおうちに置いておきましょう」
灯油のストーブは、最近お家に置いてあるご家庭も少なくなってきましたが、
電気を使わない為、いざという時に非常に役立ちます。
また、カセットコンロを準備しておくと温かい料理を作る事もできる為
身体も部屋も温める事ができます。
更に、災害が起きた時、「布団の使い方」も工夫してみましょう。
健康機器の開発・販売を手掛けている「オムロンヘルスケア」は
ホームページ上で、布団の使い方のコツを紹介しています。
毛布は、体の下に敷くと体の熱を受け止めて保温する事ができます。
また、羽毛布団を身体の上に直接かけると体温を感知して羽毛が膨らんで
保温性を高める事ができるそうです。
ちょっとした工夫で保温効果を高められます。
ご自宅で一度試してみてる事をオススメします!
毛布、布団の冬用寝具、ダウンコートやウインドブレーカー、
スキーウエアなど保温効果が高い衣類も停電中の防寒アイテムとして
活用できます。
アルミシートや防寒シートは室内の保温に役立ちます。
アルミシートは窓ガラスに貼る事によって、屋外の冷気を遮断する事が
キレイできます。梱包に使用する気泡シートは、アルミシートや防寒シート
に比べると保温効果は下がりますが、代用として使う事もできます。
湯たんぽも災害の時に役に立ちます。
湯たんぽには様々な種類がありますが、持続力や温かさが特に重要になる
停電の時は、熱が伝わりやすい金属製の湯たんぽがおすすめです。
冬は停電が起こりやすい季節でもあります。
停電による寒さを防ぐためには、
電気を使わない暖房器具や防寒アイテムを上手に活用しましょう。
また、灯油など暖房器具の燃料は多めにストックして
急な停電に対応できるように備えておきましょう。
音声ファイルはこちら
「ブラックアウト」と呼ばれる大規模停電が起きる可能性があります。
そこで今朝は、
「冬場のブラックアウトに備える」という視点でお届けします。
2018年9月に最大震度7を観測した、
北海道胆振東部地震では、およそ295万戸が停電。
この地震では、街中の信号が消え、市役所などに、
スマートフォンの充電をしたい人の列ができました。
また、覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、
2022年3月の福島県沖の地震では、
首都圏などでおよそ200万戸以上が停電しました。
冬場は、停電が長期化すると住宅内が屋外並みに冷えて、
低体温症などになる恐れもあります。防寒対策を心がける事が大切です。
関東南部の山沿いの地域にお住まいの方は特に、
「電気を使わない暖房器具をおうちに置いておきましょう」
灯油のストーブは、最近お家に置いてあるご家庭も少なくなってきましたが、
電気を使わない為、いざという時に非常に役立ちます。
また、カセットコンロを準備しておくと温かい料理を作る事もできる為
身体も部屋も温める事ができます。
更に、災害が起きた時、「布団の使い方」も工夫してみましょう。
健康機器の開発・販売を手掛けている「オムロンヘルスケア」は
ホームページ上で、布団の使い方のコツを紹介しています。
毛布は、体の下に敷くと体の熱を受け止めて保温する事ができます。
また、羽毛布団を身体の上に直接かけると体温を感知して羽毛が膨らんで
保温性を高める事ができるそうです。
ちょっとした工夫で保温効果を高められます。
ご自宅で一度試してみてる事をオススメします!
毛布、布団の冬用寝具、ダウンコートやウインドブレーカー、
スキーウエアなど保温効果が高い衣類も停電中の防寒アイテムとして
活用できます。
アルミシートや防寒シートは室内の保温に役立ちます。
アルミシートは窓ガラスに貼る事によって、屋外の冷気を遮断する事が
キレイできます。梱包に使用する気泡シートは、アルミシートや防寒シート
に比べると保温効果は下がりますが、代用として使う事もできます。
湯たんぽも災害の時に役に立ちます。
湯たんぽには様々な種類がありますが、持続力や温かさが特に重要になる
停電の時は、熱が伝わりやすい金属製の湯たんぽがおすすめです。
冬は停電が起こりやすい季節でもあります。
停電による寒さを防ぐためには、
電気を使わない暖房器具や防寒アイテムを上手に活用しましょう。
また、灯油など暖房器具の燃料は多めにストックして
急な停電に対応できるように備えておきましょう。
音声ファイルはこちら
2023.12.02
08:25 洋服の備え冬用にチェンジ
防災FRONTLINEでは、災害が起きた時に役立つ情報をお届けしています。
12月に入り、今年も残り1か月となりました。
今年は、夏の気候から急に冬がやってきて大慌てで衣替えをされた
方もいらっしゃるのではないでしょうか?
非常用持ち出し袋の中身を冬用に変えましたか?
季節にあった準備をしていないといざという時に、使えない!
という事になってしまいます。そこで、
今朝は、非常用持ち出し袋の中から「洋服」の備えについて考えます。
季節の変わり目のタイミングで、非常用持ち出し袋の中身が使えるか。
という点検とともに行っていただきたいのが、「衣類」の準備です。
衣類の備えは、食料などと違って、命に直結するものではないと思われがち
ですが、実は、命を守るために、とても重要なんです。
東日本大震災では、低体温症が原因で亡くなった方もいました。
これからの時期に、もし地震や津波が起きたら。想像してみてください。
服の備えをしていないと低体温症の危険が高まります。
先ほどもお伝えしましたが、普段着ている洋服の衣替えと合わせて
「災害備蓄用の衣類」も衣替えしましょう。
衣替えの時に、「非常用の衣類も衣替えしなきゃ」と思い起こす
事ができれば、常に季節にあった衣類を用意する事ができます。
備える衣類は、「季節に合っている」だけでなく、「サイズが合っている」
事も重要です。特にサイズがすぐに変わってしまう子供の場合は、
その時々のサイズに合ったものに交換しておきましょう。
それでは、何枚くらい用意しておけば良いのでしょうか?
避難所に届く支援は、まずは食料からというのが一般的です。
避難所で衣類が手に入るまでは3日程かかる場合は多いそうです。
衣類の支援が受けられるまで最低「3日分」を目安に用意しておきましょう。
下着・肌着・女性は、カップ付きの肌着を入れておくと便利です。
靴下は、くるぶし丈ではなく、足を守る事を考えて、
「クールソックス」も準備しておくと良いでしょう。
その他、ズボン、トレーナー、防寒着・室内履き等、
家族の人数×3日分の用意を考えましょう。
また、こんなポイントも抑えておきましょう。
衣類の裏に名前を書いておく事、
避難所でのトラブルや取り間違えを防ぐ事ができます。
密封して、水濡れ防止:せっかく用意した衣類が濡れないように、
チャック付きのビニール袋や衣類用の圧縮袋なども活用して
密封して保管しておきましょう。
意外と手が回っていない事が多い衣類の備え。
一度用意してみると量が多く、かさばる事に気が付きます。
今まで用意してこなかったという方は、
保管場所や保管方法から考える必要があるかもしれません。
今まで用意してこなかった場合はぜひ今から、
もう備えている場合は、洋服がこの季節にあっているか点検を。
衣類の備えは被災時にはとても重要です。
音声ファイルはこちら
12月に入り、今年も残り1か月となりました。
今年は、夏の気候から急に冬がやってきて大慌てで衣替えをされた
方もいらっしゃるのではないでしょうか?
非常用持ち出し袋の中身を冬用に変えましたか?
季節にあった準備をしていないといざという時に、使えない!
という事になってしまいます。そこで、
今朝は、非常用持ち出し袋の中から「洋服」の備えについて考えます。
季節の変わり目のタイミングで、非常用持ち出し袋の中身が使えるか。
という点検とともに行っていただきたいのが、「衣類」の準備です。
衣類の備えは、食料などと違って、命に直結するものではないと思われがち
ですが、実は、命を守るために、とても重要なんです。
東日本大震災では、低体温症が原因で亡くなった方もいました。
これからの時期に、もし地震や津波が起きたら。想像してみてください。
服の備えをしていないと低体温症の危険が高まります。
先ほどもお伝えしましたが、普段着ている洋服の衣替えと合わせて
「災害備蓄用の衣類」も衣替えしましょう。
衣替えの時に、「非常用の衣類も衣替えしなきゃ」と思い起こす
事ができれば、常に季節にあった衣類を用意する事ができます。
備える衣類は、「季節に合っている」だけでなく、「サイズが合っている」
事も重要です。特にサイズがすぐに変わってしまう子供の場合は、
その時々のサイズに合ったものに交換しておきましょう。
それでは、何枚くらい用意しておけば良いのでしょうか?
避難所に届く支援は、まずは食料からというのが一般的です。
避難所で衣類が手に入るまでは3日程かかる場合は多いそうです。
衣類の支援が受けられるまで最低「3日分」を目安に用意しておきましょう。
下着・肌着・女性は、カップ付きの肌着を入れておくと便利です。
靴下は、くるぶし丈ではなく、足を守る事を考えて、
「クールソックス」も準備しておくと良いでしょう。
その他、ズボン、トレーナー、防寒着・室内履き等、
家族の人数×3日分の用意を考えましょう。
また、こんなポイントも抑えておきましょう。
衣類の裏に名前を書いておく事、
避難所でのトラブルや取り間違えを防ぐ事ができます。
密封して、水濡れ防止:せっかく用意した衣類が濡れないように、
チャック付きのビニール袋や衣類用の圧縮袋なども活用して
密封して保管しておきましょう。
意外と手が回っていない事が多い衣類の備え。
一度用意してみると量が多く、かさばる事に気が付きます。
今まで用意してこなかったという方は、
保管場所や保管方法から考える必要があるかもしれません。
今まで用意してこなかった場合はぜひ今から、
もう備えている場合は、洋服がこの季節にあっているか点検を。
衣類の備えは被災時にはとても重要です。
音声ファイルはこちら