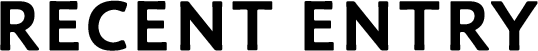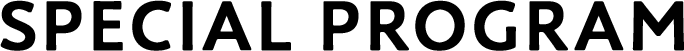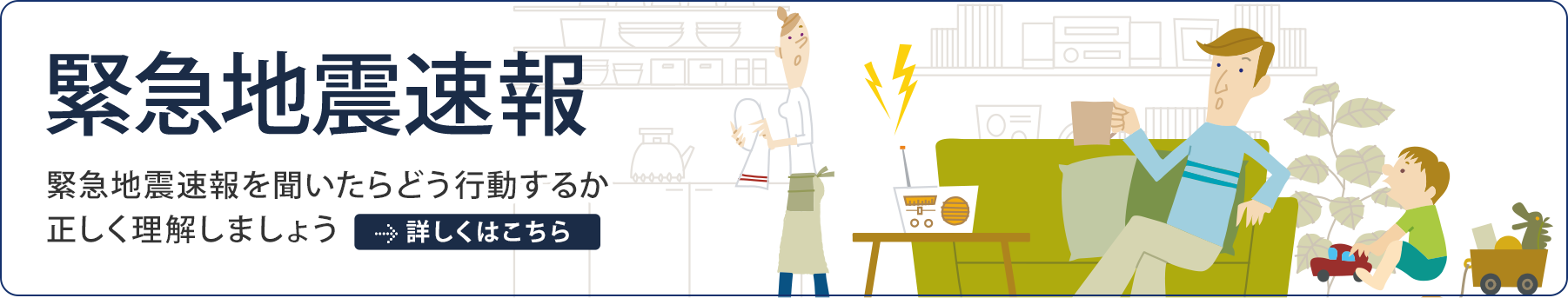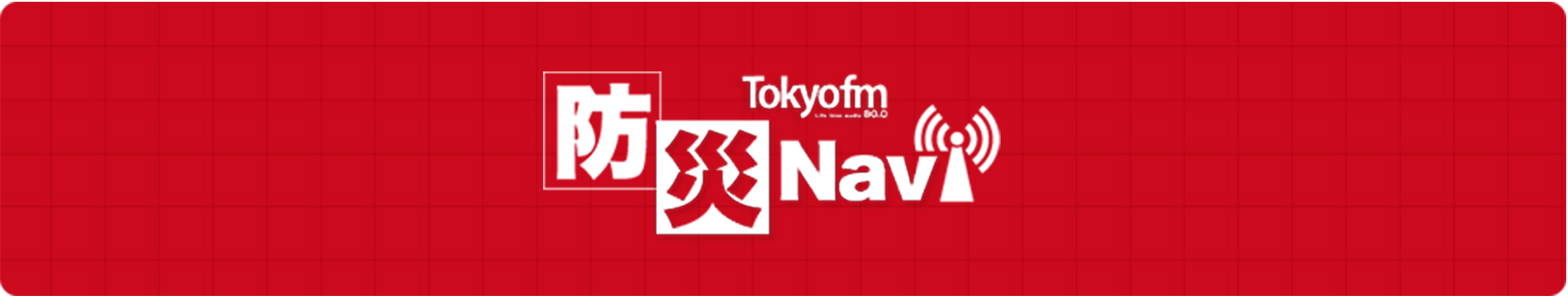先月、渋谷駅前の商業施設「渋谷サクラステージ」で
大規模災害が起きた時に帰宅困難者を受け入れる訓練が行われました。
今朝は、訓練の様子と渋谷区の対策についてお伝えします。
今回の訓練では、マグニチュード7.3の首都直下地震が起きたと想定。
およそ120人が参加し、施設内や外で被災した想定で一時避難場所や
街中からサクラステージに移動する流れの確認が行われました。
【音声 15秒】
受付では、一時滞在希望者に備蓄品受け渡しのチェックカードと
区が用意した、水とパンが入った袋が配られていました。
区の想定では、平日の日中に交通機関が止まってしまった場合、
渋谷区周辺ではおよそ6万人が帰宅困難者となると想定していて
そのうち、およそ2万人は勤務先や通学先が近くにないと予想しています。
どこで、どう受け入れるかが課題の一つとなっています。
渋谷駅周辺の帰宅困難者受け入れ施設は25カ所あります。
訓練の場となった「渋谷サクラステージ」は、
最大2935人の受け入れが可能とあっていて、この人数の3日分の
食料と水、ブランケットなどを備蓄していて館内10カ所を一時滞在
施設の場として活用できるようになっています。
また、今回はこんな訓練も行われました。
東急不動産と渋谷区が締結している
『渋谷区地域防災に関する包括連携協定』の中に盛り込まれている
災害用ドローンの情報伝達訓練です。
この様な訓練は、渋谷駅周辺にある、およそ100の事業所と団体で作る
『渋谷駅周辺帰宅困難者対策協議会』が2014年から行っていて、
今回で9回目です。協議会の座長を務める
東急株式会社の高橋俊之(たかはしとしゆき)専務はこう話します。
再開発が進んでいるのは渋谷区だけではありません。
定期的に地域と連携した防災訓練を行う事が
求められているのではないでしょうか?