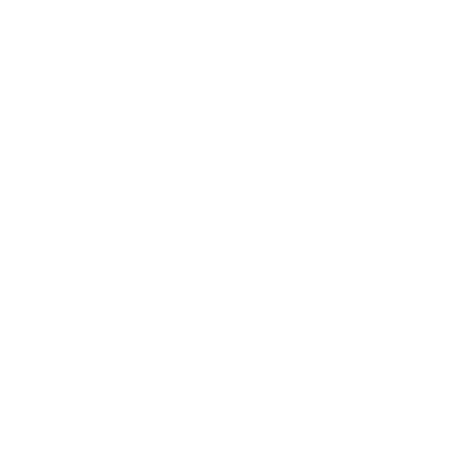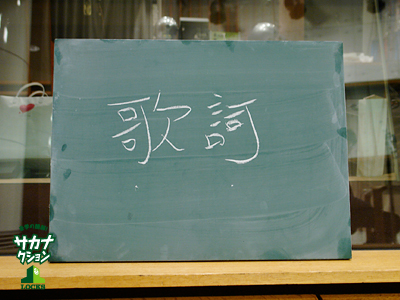
今回のサカナLOCKS!は、The SALOVERSの古舘佑太郎君をゲストに迎えます。少し前にオンエアした授業、宿題「歌詞が好きな曲と、好きな歌詞を教えて!」の中で紹介したThe SALOVERSの「夏の夜」を聴いた山口一郎先生が「天才だね、話してみたいな〜」と絶賛したことがキッカケでこの対談が実現しました。11歳の年の差、ふたりに共通しているのはミュージシャンという肩書き。どんな対談になったのでしょうか。

山口「よろしくお願いします。」
古舘「お願いします!」
山口「よく来てくれましたね。」

古舘「いや、なんかもう……、生徒のみんなに言いたいことがあって、普通に生きていて、「サカナクションの一郎さんが褒めていて、来いって言ってる!」って、突然、ゲリラ的な報告が来たんですよ(笑)」
山口「ははは!(笑) もう、それ、めっちゃ嫌な先輩感、丸出しだね。」

古舘「いや…! 嫌とかじゃなかったんですけど、嬉しいとか言うよりも、現実味が無かったです。「うわ……まじか…!」みたいな。」
山口「そもそものきっかけなんですが、このサカナLOCKS!の授業の中で、生徒のみんなに、「歌詞が好きな曲と、好きな歌詞を教えて!」という宿題を出したんですよ。その中の1曲がThe SALOVERSの「夏の夜」だったんですね。僕は、先に歌詞を見てから曲を聴いたんですよ。もうね……歌詞に描かれている世界が、僕の世代じゃ絶対に感じることができない景色だし、この宿題に提出されてきた歌詞っていうのは、ほとんどが "名言" ばっかりだったんだよね。こう……相田みつをさん的な……、社会的に言う、名言ですよ。その中で、この古舘君の「夏の夜」っていう歌詞は、文学的で渋かったし、こういう感覚で音楽をやっている若い世代がいるんだっていうのは衝撃だった。どんな人なんだろう……古舘君って、どんなやつなんだろうって(笑)。そして、先輩からの呼び出し的に、「お前ちょっと良い歌作るじゃねぇか、ちょっとラジオ来いよ!」って感じで(笑)、今回は本当に申し訳ないんですけど、呼び出させていただきました。」
古舘「そうなんすね(笑)」
山口「僕、普段ラジオをやる時に足を組んだりしていないんだけど、今、なんか足を組んだりしちゃっているのは、多分、先輩面をなんとか出そうとしているんだと思う(笑)。もう、僕の方がやりづらいところがあったりで……(笑)。」
古舘「本当ですか(笑)。いや、もう、全然……! あの、僕のことをどんな人間だろうって思われた時に、今、スマホLOCKS!の中で、サラバLOCKS!やってるんですけど、それはちょっと聞いて欲しくないなって思いました。」
山口「え、なんで?」
古舘「かなり下世話なことばかり言っていて……」
山口「下世話って?」

古舘「下ネタばっかり言っていて……なので、その……それを聞かれると、「夏の夜」の人間性がぶっ壊れるんじゃないかって(笑)。」
山口「いや、違うじゃん! この歌詞を見て、俺は、こいつ変態だなって思ったよ。」
古舘「え、マジっすか……。」
山口「うん。変態なやつしか、良い曲は作れないから。……っていう、自分なりの考えがあるんだけど。でも、この歌詞は本当に素晴らしいと思いました。で、今日はいろんなことを僕からも質問するから、古舘君も僕に質問して。一応……先生だから!(笑)」
古舘「はい。本当に、聞きたいことというか、生々しい相談というか……もう、いっぱいありますね!」
山口「もう、何でも言って! じゃあ、交代にいく?」
古舘「そうですね!」

山口「じゃあ、僕から古舘君に聞こうかな。古舘君さ、この「夏の夜」を書いたのは、18才の時だって言ってたじゃん。初めて曲を書いたのは何才?」
古舘「16……ですかね。」
山口「書こうと思った理由は何?」
古舘「書きたいなって思っていたんですけど、全然書けなくて……」
山口「それは、歌を書きたいと思っていたの? 言葉じゃなくて?」
古舘「はい。言葉とギターで、曲を作りたいって思っていたんですけど、できないので、コピーをずっとやっていたんです。本当のきっかけは、その当時付き合っていた子と別れて、それまで僕はガキ大将じゃないですけど、「自分最強!」って思って生きてきたんですね。自分に自信がいっぱいあったんですけど、そのタイミングで、その自信が一気になくなっちゃって。」
山口「彼女にフラれて?」
古舘「はい。それでなんかもう……、うわーって、やるせなさというか、自分というものを否定されたような気持ちになって。それからですかね。16の時に書き始めたのは。そしたら、オリジナルがいっぱい書けるようになって。」
山口「へぇ〜……。じゃあ、なんかある?僕に。」
古舘「え! もう、いいんですか?(笑)。」
山口「ははは(笑)。うん、とりあえず、ほら、一個一個、交代だから(笑)。」
古舘「えーっと……、じゃあ、しょっぱなから、具体的な歌詞のことを言っても良いですか?」
山口「うん。」

古舘「これは悩みなんですけど……、この「夏の夜」を書いたのは18才の時で、ハッキリ言って、こんな曲はもう書けないと思っているんですね、正直。」
山口「うん、分かる分かる。」
古舘「やっぱり、僕は20代になって、18才の頃とは違って。歌詞は経験を積んだりうまくなればなるほど、下手になっていっちゃってる気がして……正直、難しいんです、すごく。それってどうしたらいいんですかね?」
山口「それね……、それ、めちゃくちゃよく分かりますね。」
古舘「もう、いろんな人の顔が浮かんだりとか、自分が何を書きたいのか分からなくなったりとか、そういう平日の夕方あたりが一番しんどくて、そういう時って……」
山口「でもね、それはずーーーっと続くよ。」
古舘「えっ……。」
山口「プロなんだから。あと、でかいステージを踏めば踏む程、もっと如実になる。」
古舘「え、まじっすか……。」
山口「なる、なる。」

古舘「僕はなんか、こういう自分の状況だからそういう時期が続いているのかなって思って、もっといろんな人が共感してくれたり、大きなステージに立てば、自分に自信が持てて、歌詞に困らないのかなって……。」
山口「逆、逆。たくさんの人に届けるっていうことが、大きいステージに立つと、要するに、1万人、2万人の人が、自分を観に来るわけじゃん。そうすると "この2万人に向けて曲を作らなきゃいけないんだ" って、現実的にその人を見る訳だから。それに、いろんな人がいるじゃん。いろんな音楽を好きな人がいて、いろんな性格の人がいてさ。そういういろんな人がいる中で、自分の音楽を届けなきゃいけなくなってくるわけだから、そうなると、書くのがものすごく難しくなるけど、そういう状況でしか書けないものもあるんだよね。」
古舘「その苦しみの中でも、新しいものが生まれる……。」
山口「そう。俺も生まれて初めて曲を書いたのは中学校2年生で、高校に入ってもずっと曲を作っていたけど、あの当時に作っていた曲を今歌うと、めちゃめちゃ新鮮だし、斬新だなって思うし、かっこいいなって思うけど、これを今応援してくれている人たちが聴いたらどう思うだろうって考えると、ちょっと難しいかなって思ったりするんだよね。」

山口「古舘君は今22才だけど、25才を過ぎたら、もっと鈍感になるから。今はビンビンに感性が立っているし、いろんな人と話す度に影響を受けるだろうし、新しい世界を見る度に、感じるものがあってさ……。例えば、この台本をペラっとめくって何か言葉を書けって言われても、書けるでしょう?」
古舘「そうですね。」
山口「書けるでしょ?……書けなくなるから。書くことの意味が変わるから。それが、25才を過ぎると変わるんだけど、俺の経験だけの話をすると、18から25までの中で、どれくらい感性の経験を貯めめることができるかで、30代でどういうものを作るか、関係してくると思うよ。」
古舘「まじっすか……。僕、10代の時に、そういうアンテナがすごく高くて、今22才の自分でも、もう鈍感になっている気がして……、すごく嫌なんですよね。でも、今、25才を過ぎた時のことを考えると、やっぱり今の方がアンテナが立っているってことですよね……。」
山口「全然立ってると思うよ。それに、10代の時とは違う感覚で見ているから、それは鈍感なんじゃなくて、違うものを感じているんだよね。それが25になると、身体が重くなるくらいの感覚で鈍感になると思うよ。」
古舘「うわ……、ヤバいっすね……。」
山口「俺が最初にヤバいかもって思ったときは、本を読んで、何とも思わなかった時。つまらないものでも、感動できたんだよ、昔は。だけど、つまらないものを、途中で読むのをやめたくなっちゃったんだよね。そうなった時に初めて、俺、鈍感になったかもって。集中力が落ちたかもって思ったんだよ。あと、擦れちゃったというか……擦れっ枯らしになったというか……。」
古舘「でも、歌詞はどんどん書いているわけじゃないですか、一郎さん。」
山口「うん。駄作も書かなきゃいけないし、1曲にかける時間が……古舘君、すぐ書けるでしょ?僕は、8ヶ月とかかかるから。1曲書くのに。」
古舘「うわ……、それ、めちゃくちゃしんどいですね。」
山口「だから、そうなっちゃうんだけど、それはたくさんの人に向けて音楽を作るっていう幸せの代償だったりしているんだよ。だから、俺の中では、音楽で得るものと、音楽で失うもの、絶対にバランスが取れていると思ってる。でっかいものを得たら、音楽以外のものは、必ず何かを失う。」
古舘「歌詞を書き続けている、その8ヶ月の間って、どのくらい歌詞と向き合っているんですか?」
山口「もう、ずーっとだよ。」
古舘「逃げたくなったりしないんですか?」
山口「逃げたくなったり……するけど、もう、それは受験勉強みたいな感じだよね。やらなきゃダメだし、自分に関わっている人もめちゃくちゃ多いわけだからさ。"サカナクション" で、ご飯を食べている人がいっぱいいるって分かってるしさ。自分の曲ができないとツアーも始められないし、かかっているお金とかも分かるじゃん。だから、責任が出てくる分、作るものも結果を出さないといけないからね。」

古舘「自分は22才なのに、変に頭でっかちになっちゃっている気がして……。どっちに行って良いのかなって。10代の純粋な気持ちのまま行った方が良いのか、大人になって、向き合う自分で行ったらいいのか……微妙な年頃のような気がして。」
山口「その……、音楽でどうなりたいかだと思うよ。俺は、どうして世の中に向けて音楽を発信しようと思ったか、アマチュア、インディーズじゃなくて、メジャーでやろうと思ったかって言うと、日本の音楽っていう文化を……極端なことを言うと、自分が良いと思ったものを、世の中の人が良いって言うようにしたいって思ったの。例えば、ゆらゆら帝国とか、めちゃめちゃ好きなんだけど、バンドとか、音楽の素晴らしさを知らないから評価されていないのであって、自分がバンドをやっている分、その良さを知っている自分がやっているからには、ちゃんと知らせていきたいって。メジャーで音楽をやっていくっていうのは、そういうことだって。音楽の面白さを知らせるために、知ってもらうために、自分は音楽を使いたいって思ったから。それこそ、10代の頃に書いていたような、純粋な、別に誰にも分かってもらえなくても良いって思って書くものじゃなくて、たくさんの人に分かってもらう曲を書きつつも、自分っていうものも書かなきゃいけない。その二面性を持つことが、表と裏だったりしたんだよね。」
古舘「…………叶わないっす(苦笑)。」
山口「古舘君は、どうなりたいかだと思うよ?」
古舘「正直に言うと、今の段階では、一個だけです。なんか僕、青春時代の10代の自分とか、同級生のみんなとか、そういうものがどんどん大人になっていっちゃうのが、ただただ寂しいっていうのがあって。まだまだ、そこに居たいのに、居れないから……せめて歌の中ではそこに居たいって、それしか考えていないですね。」
山口「うん、なるほどね。」
古舘「"音楽=青春、10代"って、その想いがまだまだ強いです。」
山口「じゃあ、青春だね、まだね。」
古舘「そうですね(笑)。なんか、終わってから思い出しているような気がしていたんですけど……まだ続いているんですかね、青春って。」

山口「どうだろうね……。俺は早くから仕事の音楽とそうじゃない音楽っていうのに気づいてやっていたから、青春っていう感覚ではなかったけど、古舘君はまだ衝動で音楽をやっているから……だからすごいものが作れるんだと思うし、周りを惹き付けるエネルギーがあるんだと思うんだよね。それが、今度は、自分が結婚して子どもができて、生活していかなきゃいけないってなったときに、作るものがどう変わるのか。今日も多分、メーカーの人とか事務所の人が来ていると思うけど、その人たちも、自分が結果を出さないと、ずっと居続けてくれるか分からないわけじゃん。周りも注目してくれるか分からないわけじゃん。自分が世の中に聴いてもらいたいって曲を1曲作った時に、それを届けてくれる人が近くにいなかったら意味が無いわけじゃん。」
古舘「そうですね……。」
山口「それを考えてから音楽を作り始めていくと、きっと変わって行くんだけど……でも、一個、最近俺が気づいたのは、昔書いた曲も、自分の曲なんだよ。他人が書いたわけじゃないじゃん。そんな自分も、自分の中に居るわけだから、それはそこで自信を持つっていうかさ……。完結しちゃって良いと思うんだよね。これを書いた自分が、これをやってるんだって。自分のストーリーみたいなものを確認していくっていうのも、大事だと思うんだよね。」
M 夏の夜 / The SALOVERS

ということで、そろそろ授業終了の時間なのですが、ふたりの話はまだまだ続きそうなので、来週も引き続き、この対談をお届けしていきます。
山口「なんか質問し合うって言っていましたけど、ひとつずつしか聞けなかったな〜。……まあ、対談前半はここまでで、来週も引き続きゲストにThe SALOVERSのボーカル・ギター、古舘佑太郎君をお招きします。」