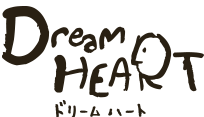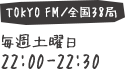2025年03月22日
今夜ゲストにお迎えしたのは、ジャーナリストの堀潤さんです。
堀潤さんは、1977年、兵庫県のお生まれです。
立教大学文学部ドイツ文学科をご卒業後、アナウンサーとして2001年NHKに入局。
『ニュースウォッチ9』のリポーター等、報道番組を担当され、2012年に渡米。
カリフォルニア大学ロサンゼルス校客員研究員として活動される中、市民ニュースサイト「8bitNews」を立ち上げ、2013年NHKを退局されました。
現在は、TOKYO MXで『堀潤 Live Junction』のMCを務めるなど、ジャーナリスト、キャスターとして、数多くのテレビ・ラジオ番組などに出演する一方、インターネットテレビ、SNS、執筆活動などを通じて、精力的に発信を続けていらっしゃいます。

──情報は信じるものではなく、選ぶもの
茂木:堀さん、今回のご著書『災害とデマ』は、「誰でも発信できる」ということに伴って、デマも生まれてしまうということですよね。これは難しいですね。
堀:ジレンマがありますよね。「8bitNews」を立ち上げた時には、「よし、皆で発信しよう!」と、無邪気に拳を上げていました。「お母さん、何か言いたいことがあるんだったら(発信しましょう)。当事者の発信って本当に強いんですよ。一緒にやりましょう!」とか。でも、茂木さんが仰ったように、誰もが発信できるからこそ、責任を取らない、色んな情報が拡散されまくっている。
だから最近では、皆に「一緒に発信しようぜ!」と言う前に、やっぱりこう言うんですよ。「1回踏み留まろう」と。発信したいと思っても、もう1回自分と対話をして、自分の中に生み出された確定的な言葉が見つかってから発信しよう、というぐらい、ちょっとブレーキを踏むようなことを呼び掛けるようになりました。
茂木:今回のテーマは『災害とデマ』なんですけど、ご自身が「取材中の安全を確保する」という意味でも、この「情報の真偽を見極める」というのは、ある意味では命がけですよね。
堀:そうですね。静岡県で豪雨災害が発生した時に、SNS上で「静岡が水に浸かってるぞ」というような、生成AIを使って大規模に水に浸かっている写真が拡散されていました。僕はその時に、まさにその現場で取材をしていたので、この情報にすごく惑わされました。
茂木:実際そうなっているのかもしれない、と思われたんですね。
堀:はい。「いや、おかしいな」と。こんなには浸かっていないけど、でも、確かに浸かっている現場ではあるんです。でもちょっと乖離があるなと思って。
そうしたら程なくして、生成AIで作った本人が「これは嘘です」と、「啓蒙のために出したんで」と言っていたんですけど。その時に、本当に浸かっているのに、一方で「浸かってない。あれはデマです」と言われてしまうと、「いやいや、デマだけど、(実際に浸かっている)現場があるのに」と。

茂木:それは難しいですね。
堀:こっちは、目の前のおばあちゃんとかがもう胸の下まで水が上がってきていて、一気に引いたから良かったけど、でも途方に暮れて座り込んでしまっているわけですよ。だから「皆来て!」と言いたいのに、「あの静岡の水害は嘘だったんだよね」と、「本人が言ってたじゃん」と言われてしまうと、「いえいえ、あれほどじゃないんですけど、水に浸かってはいて、おばあちゃんが…」ということを、何回も何回も説明を重ねなきゃいけないような状況になっていくので…。
本当に、それによって救助が遅れたりとか、支援が遅れたりすることになって、健康を害したりとか、場合によっては命を落としたりとかすることがあるので。SNS上で拡散されているその先というのは、あまりリアルな現場を見る機会は少ないと思うんですよね。そういうのは、やっぱり書き残しておかなきゃいけないなと思いました。
茂木:そうですか…。
堀:僕自身がパレスチナに行く時とかも、今度はSNS上にはあまり情報がないだけに、行ったら「まさか、ここもドローンの爆撃が起きていたとは」とか、酷い惨状を目の当たりにしたりとか、本当に難しいですね。出回り過ぎているデマもあれば、本当に起きてるのに誰も発信しなくて孤立している現場もあるという、このギャップ。いずれにしても、これを埋めるのは、やっぱり現地に足を運んで当事者の方々と1つ1つ検証していかないと、解消されないなと思います。
茂木:なるほどなぁ。
堀さん、このご著書『災害とデマ』ですが、なぜ今書かなければと思われたんですか?
堀:戦争の道具にも使われているから、というのが大きな理由でもありましたし、デマによって民主主義が壊されようとしているということも、この1~2年の間で次々と目の前に突き付けられてきたので。
茂木:これは、ご著書の後半に非常に迫力のある記述がありますね。元々、大学の時の研究テーマがその辺りだったんですよね。

堀:そうなんです。先ほど「ドイツ文学科卒業」と紹介して頂きましたけど、「ナチス・ドイツと大日本帝国のプロパガンダ」というのが僕が卒論に選んだテーマで、ドイツにも足を運んだりとかしました。そして一番ショックだったのは、ナチス・ドイツといえば、国民を動員してユダヤ人の方々を大量虐殺してしまうという、その過程において、音楽が使われ、映画が使われ、新しく登場した「放送」というメディアが使われ、という。
ドイツは、やっぱり自分たちでヒトラーを生んでしまったという悔恨があるから、非常に「メディアをどう民主的にするか」ということに関して試行錯誤を重ねてきました。
日本の場合は、戦前と戦後のメディアのプレイヤーが同じで、新聞社も放送局も一緒なんですよね。だからその境界線が曖昧だな、と。ひょっとしたらこれが、僕が抱いているメディアに対しての不信感の元凶なのかな、と、当時大学生ぐらいの時に思ったんですよ。
茂木:ですから、今回のご著書は『災害とデマ』なんですけど、一方で、副題としては『戦争とデマ』ということでもありますよね。
堀:そうですね。人々が混乱している時に一番恐ろしいものが、この情報だ、という。意図的に人々を惑わすこともできれば、意図せずとも大きな混乱を生み出すこともできてしまう。戦争や政治的な介入というのは、もっともっと大きなスケールで惑わす相手が出てきて、という。
なので、全く別物じゃないなということがあったので、順を追って、まず身近な、私達がよく知っている「災害の現場」から、そして次は「選挙の話」、最後は「戦争の話」と進めています。
茂木:堀さん、是非リスナーにアドバイスを頂きたいんですが。今本当に、それこそフェイクニュースだとか、デマとかがあるじゃないですか。いち受け手としては、どういうことに気を付ければいいですか?
堀:「情報というのは、『信じる・信じない』というものじゃない」ということは伝えたいですね。「堀さん、どのニュースを信じればいいんですか?」とか、「堀さん、どの人を信じればいいんですか?」とか、よく聞かれたんですけど、その度に「信じるっていうのは、『わからないから、その人を信じる』とか、『よくわからないけど、あれなら信じられる』とか。その『よくわからない』という状況で身を預ける先に、本当にそれが正しいかノーかがわからない時代になってますね」と。「だから情報というのは、『信じる・信じない』ではなくて、『選択するもの』だ」という。
選びたいなと思ったら、1個よりは2個あった方が、2個よりも3個、4個あった方が、自分としては色々考えられるな、という。だから、「情報は信じない。情報を選ぶ」。
茂木:なるほど。明言を頂きました 「情報は信じない。情報は選ぶ」、素晴らしいですね。
もうこの『災害とデマ』を読むだけでも色々考えるきっかけになりますけど、更に堀潤さんのお話を伺うと、いろいろ整理されてきていいですね。
堀:ありがとうございます。
茂木:この堀潤さんの素晴らしい本、私は名著と断言いたします。『災害とデマ』、ご興味を持たれた方は、集英社インターナショナル新書から発売されていますので、是非チェックしてみてください。

●堀 潤 さん (@8bit_HORIJUN) / X(旧Twitter)公式アカウント
●堀 潤 さん (@junhori79) / Instagram公式アカウント
●「8bitnews」公式サイト
●「8bitnews」公式YouTube チャンネル
●災害とデマ (インターナショナル新書) / 堀 潤 (著)
 (Amazon)
(Amazon)
●集英社インターナショナル 公式サイト
堀潤さんは、1977年、兵庫県のお生まれです。
立教大学文学部ドイツ文学科をご卒業後、アナウンサーとして2001年NHKに入局。
『ニュースウォッチ9』のリポーター等、報道番組を担当され、2012年に渡米。
カリフォルニア大学ロサンゼルス校客員研究員として活動される中、市民ニュースサイト「8bitNews」を立ち上げ、2013年NHKを退局されました。
現在は、TOKYO MXで『堀潤 Live Junction』のMCを務めるなど、ジャーナリスト、キャスターとして、数多くのテレビ・ラジオ番組などに出演する一方、インターネットテレビ、SNS、執筆活動などを通じて、精力的に発信を続けていらっしゃいます。

──情報は信じるものではなく、選ぶもの
茂木:堀さん、今回のご著書『災害とデマ』は、「誰でも発信できる」ということに伴って、デマも生まれてしまうということですよね。これは難しいですね。
堀:ジレンマがありますよね。「8bitNews」を立ち上げた時には、「よし、皆で発信しよう!」と、無邪気に拳を上げていました。「お母さん、何か言いたいことがあるんだったら(発信しましょう)。当事者の発信って本当に強いんですよ。一緒にやりましょう!」とか。でも、茂木さんが仰ったように、誰もが発信できるからこそ、責任を取らない、色んな情報が拡散されまくっている。
だから最近では、皆に「一緒に発信しようぜ!」と言う前に、やっぱりこう言うんですよ。「1回踏み留まろう」と。発信したいと思っても、もう1回自分と対話をして、自分の中に生み出された確定的な言葉が見つかってから発信しよう、というぐらい、ちょっとブレーキを踏むようなことを呼び掛けるようになりました。
茂木:今回のテーマは『災害とデマ』なんですけど、ご自身が「取材中の安全を確保する」という意味でも、この「情報の真偽を見極める」というのは、ある意味では命がけですよね。
堀:そうですね。静岡県で豪雨災害が発生した時に、SNS上で「静岡が水に浸かってるぞ」というような、生成AIを使って大規模に水に浸かっている写真が拡散されていました。僕はその時に、まさにその現場で取材をしていたので、この情報にすごく惑わされました。
茂木:実際そうなっているのかもしれない、と思われたんですね。
堀:はい。「いや、おかしいな」と。こんなには浸かっていないけど、でも、確かに浸かっている現場ではあるんです。でもちょっと乖離があるなと思って。
そうしたら程なくして、生成AIで作った本人が「これは嘘です」と、「啓蒙のために出したんで」と言っていたんですけど。その時に、本当に浸かっているのに、一方で「浸かってない。あれはデマです」と言われてしまうと、「いやいや、デマだけど、(実際に浸かっている)現場があるのに」と。

茂木:それは難しいですね。
堀:こっちは、目の前のおばあちゃんとかがもう胸の下まで水が上がってきていて、一気に引いたから良かったけど、でも途方に暮れて座り込んでしまっているわけですよ。だから「皆来て!」と言いたいのに、「あの静岡の水害は嘘だったんだよね」と、「本人が言ってたじゃん」と言われてしまうと、「いえいえ、あれほどじゃないんですけど、水に浸かってはいて、おばあちゃんが…」ということを、何回も何回も説明を重ねなきゃいけないような状況になっていくので…。
本当に、それによって救助が遅れたりとか、支援が遅れたりすることになって、健康を害したりとか、場合によっては命を落としたりとかすることがあるので。SNS上で拡散されているその先というのは、あまりリアルな現場を見る機会は少ないと思うんですよね。そういうのは、やっぱり書き残しておかなきゃいけないなと思いました。
茂木:そうですか…。
堀:僕自身がパレスチナに行く時とかも、今度はSNS上にはあまり情報がないだけに、行ったら「まさか、ここもドローンの爆撃が起きていたとは」とか、酷い惨状を目の当たりにしたりとか、本当に難しいですね。出回り過ぎているデマもあれば、本当に起きてるのに誰も発信しなくて孤立している現場もあるという、このギャップ。いずれにしても、これを埋めるのは、やっぱり現地に足を運んで当事者の方々と1つ1つ検証していかないと、解消されないなと思います。
茂木:なるほどなぁ。
堀さん、このご著書『災害とデマ』ですが、なぜ今書かなければと思われたんですか?
堀:戦争の道具にも使われているから、というのが大きな理由でもありましたし、デマによって民主主義が壊されようとしているということも、この1~2年の間で次々と目の前に突き付けられてきたので。
茂木:これは、ご著書の後半に非常に迫力のある記述がありますね。元々、大学の時の研究テーマがその辺りだったんですよね。

堀:そうなんです。先ほど「ドイツ文学科卒業」と紹介して頂きましたけど、「ナチス・ドイツと大日本帝国のプロパガンダ」というのが僕が卒論に選んだテーマで、ドイツにも足を運んだりとかしました。そして一番ショックだったのは、ナチス・ドイツといえば、国民を動員してユダヤ人の方々を大量虐殺してしまうという、その過程において、音楽が使われ、映画が使われ、新しく登場した「放送」というメディアが使われ、という。
ドイツは、やっぱり自分たちでヒトラーを生んでしまったという悔恨があるから、非常に「メディアをどう民主的にするか」ということに関して試行錯誤を重ねてきました。
日本の場合は、戦前と戦後のメディアのプレイヤーが同じで、新聞社も放送局も一緒なんですよね。だからその境界線が曖昧だな、と。ひょっとしたらこれが、僕が抱いているメディアに対しての不信感の元凶なのかな、と、当時大学生ぐらいの時に思ったんですよ。
茂木:ですから、今回のご著書は『災害とデマ』なんですけど、一方で、副題としては『戦争とデマ』ということでもありますよね。
堀:そうですね。人々が混乱している時に一番恐ろしいものが、この情報だ、という。意図的に人々を惑わすこともできれば、意図せずとも大きな混乱を生み出すこともできてしまう。戦争や政治的な介入というのは、もっともっと大きなスケールで惑わす相手が出てきて、という。
なので、全く別物じゃないなということがあったので、順を追って、まず身近な、私達がよく知っている「災害の現場」から、そして次は「選挙の話」、最後は「戦争の話」と進めています。
茂木:堀さん、是非リスナーにアドバイスを頂きたいんですが。今本当に、それこそフェイクニュースだとか、デマとかがあるじゃないですか。いち受け手としては、どういうことに気を付ければいいですか?
堀:「情報というのは、『信じる・信じない』というものじゃない」ということは伝えたいですね。「堀さん、どのニュースを信じればいいんですか?」とか、「堀さん、どの人を信じればいいんですか?」とか、よく聞かれたんですけど、その度に「信じるっていうのは、『わからないから、その人を信じる』とか、『よくわからないけど、あれなら信じられる』とか。その『よくわからない』という状況で身を預ける先に、本当にそれが正しいかノーかがわからない時代になってますね」と。「だから情報というのは、『信じる・信じない』ではなくて、『選択するもの』だ」という。
選びたいなと思ったら、1個よりは2個あった方が、2個よりも3個、4個あった方が、自分としては色々考えられるな、という。だから、「情報は信じない。情報を選ぶ」。
茂木:なるほど。明言を頂きました 「情報は信じない。情報は選ぶ」、素晴らしいですね。
もうこの『災害とデマ』を読むだけでも色々考えるきっかけになりますけど、更に堀潤さんのお話を伺うと、いろいろ整理されてきていいですね。
堀:ありがとうございます。
茂木:この堀潤さんの素晴らしい本、私は名著と断言いたします。『災害とデマ』、ご興味を持たれた方は、集英社インターナショナル新書から発売されていますので、是非チェックしてみてください。

●堀 潤 さん (@8bit_HORIJUN) / X(旧Twitter)公式アカウント
●堀 潤 さん (@junhori79) / Instagram公式アカウント
●「8bitnews」公式サイト
●「8bitnews」公式YouTube チャンネル
●災害とデマ (インターナショナル新書) / 堀 潤 (著)
 (Amazon)
(Amazon)●集英社インターナショナル 公式サイト