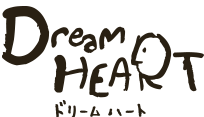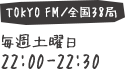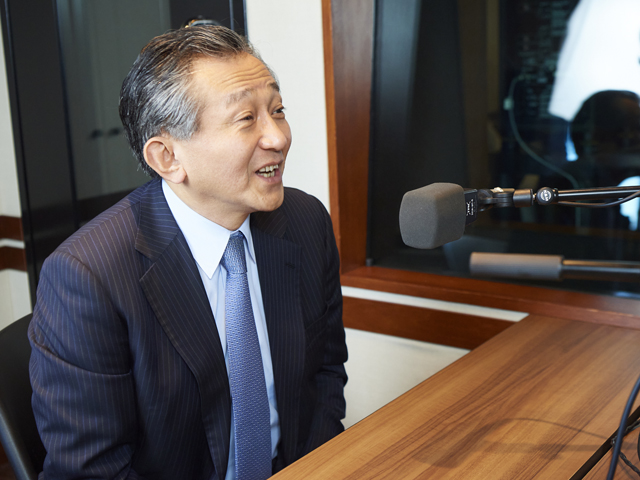2025年03月15日
「Dream Heart」は、日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし、その方の「挑戦」に、そして、「夢」に迫っていきますが、今週はスペシャルバージョン!
皆さんからお送りいただいたメッセージを、番組パーソナリティの茂木健一郎が、脳科学者として答えていきます!

──前頭葉のメタ認知
茂木:では、まず、こちらのメッセージから…。山口県 ラジオネーム <けんちゃん>さん。
茂木さん、私は幼少の頃から、人間関係に悩んでいます。
今はだいぶ上手くなったと思うのですが、嫌な事があると、まず、怒りが先に立ってしまいます。
もし、良い解消方法があれば、教えて下さい。
茂木:怒りが先に立ってしまうんですね。これはね、ある程度は仕方がないことなんです。
「怒り」、これは脳の扁桃体が出している不快のシグナルなんですけども、ある意味では生き物として素の反応なんですね。だから、「なんかちょっと嫌だなぁ」とか、「この人腹が立つな」と思うと怒りが出ちゃう、これは仕方がないんですけども…。その後なんですよね。
この扁桃体の怒りの反応というのは、ある意味ではね、時々、例えで「爬虫類の脳」と言われたりもしますけども、我々が進化の過程から持ってきた、1つの生き物としての働きなんですね。
それをどう解釈するか。そして、どのような行動に結びつけるか。これは前頭葉の働きなんですね。
この前頭葉というのは、人間が一番発達している、そして進化の過程で一番人間の脳の中で大きくなっている部位なんですけども、この前頭葉が扁桃体などを中心に、怒りの感情が生まれた時に、「それをどうしようか」というふうに解釈や判断をするわけですよね。
だから例えば、一番単純には、怒ったからちょっと怒鳴るとか、喧嘩しちゃうとか、これが1つのストレートな怒りの解釈でもあるんですが、他の解釈もできるんですよ。
例えばね、多くの場合、怒りがあるということは、実は自分が脅かされている時のことが多いんですね。
動物でもそうでしょう。ワンちゃんとか猫ちゃんとか、怒っている時というのはちょっと自分が脅かされている時ですよね。ですから、ひょっとすると、怒っている時はちょっと自分が圧迫されていると言うか、自分のスペースとか自分の立場が危うくなっている時かもしれないんですね。
そういう時には、相手に怒りをぶつけるよりは、自分の安全を確保するとか、自分をちょっと落ち着かせるとか、安心するとか、そういうふうにした方がいいことが多いんです。
あるいは、「怒り」と言うと、例えば嫉妬の感情とか、びっくりしたりとか、そういうことで怒ってしまうこともあるんですよね。
予想しなかった時に予想しないことが起こると、「どうしたらいいんだろう?」と戸惑ってしまって、その戸惑いの感情が怒りになったりする。まあ、色んな理由で怒るんですけども。
ですから、その怒りに結びついた様々な状況を、総合的に判断する。これが前頭葉の働きで、これがいわゆる「メタ認知」というものですね。
ですので、怒りが生まれることは仕方がないんですよ。人間なので、怒らないようにしようとすることは無理なんです。
問題は、「怒ってしまった後で、それをどう対処するか」、ということがとてもとても大事なんだと思います。
あと、実は脳は「行動主義」と言うんですけど、怒ったからと言って怒りの行動をすると、その行動によってまた心理が影響を受けてしまって、フィードバックして強まってしまうので、行動主義の考え方ですと「ちょっと微笑んでみようよ」と。心の中では怒っているだけど、作り笑顔でもいいので微笑んでみると、その「微笑む」という行動が脳の感情の中枢に作用して、怒りが和らぐということもあるんですね。
あと、深呼吸をする。これもね、落ち着かせるためにはとても大事です。
そのような形で、「笑顔を作ってみる」とか、「深呼吸をする」とか、こういう自分の行動を通して怒りの感情を抑えていく、ということも重要なやり方ではないかなと思います。
まず、怒ってしまう自分を否定しないでください。それは生き物として大切なことなので。
問題は、それをどのように解釈して行動に結びつけていくか、ということについて、今申し上げたようなことをヒントにしてくださったらな、と思います。
是非、この前頭葉の「メタ認知」を、少しずつ高めて頂けたらなと思います。けんちゃんさん、是非チャレンジしてみてくださいね。

──脳のデフォルトモードネットワーク
茂木:続きまして、埼玉県 ラジオネーム <ぱぱぱぱーや>さんからのメッセージです。
毎週様々なゲストの方と茂木さんのお話を楽しく拝聴しております。
色々な分野の方が出演するので、聴いているだけで視野が広がるだけでなく、学ぶことも多くあり、聴いた後、自分自身が少し成長できている気がしております。
これからも、為になる放送を楽しみにしています!
さて、茂木さんは気持ちが落ち込んだ時、どのように気持ちを切り替えていますか?
教えていただけたら幸いです!
茂木:僕はね、比較的陽気と言うか、朗らかな人と思われがちなんですが、そんな僕でも、当然落ち込むことはあるんですよね。
気分が落ち込んだ時にまず大切なのは、「自分のせいじゃないよ」ということです。今の世の中は「ポジティブシンキングが大事だ」とか言いますから、ちょっとでもネガティブで後ろ向きな気持ちになってしまうと、「それは良くないんだ」と罪悪感を感じたりしてしまいますけども、そんなことはないんですよ。
是非、落ち込んだ時には、まずそういう自分を受け入れて頂きたいな、と思うんですけども。
この「落ち込んだ気分」というのは、色々な要素で生まれます。例えば、脳内の神経伝達物質のセロトニンとかそういうものも関与してきますし、ドーパミンなんかも関与してくるんですけど、「失敗しちゃったな~」とか、「やる気が起きないな~」とか、そういう時に落ち込む状態になっているんです。その時というのは、実は基本的に脳は「ちょっと休みたいな」と思ってることは事実なんですよ。
この「休む」というのは、サボることとは違うんです。これはすごく重要なことで、脳は休んでいる時に、アクティブに活動をしている時とは別の活動をしています。眠っている時というのが一番わかりやすいですよね。寝ている時は脳が休んでいるんですけど、その時には記憶の整理をしたり、色んな老廃物を分解したり、新陳代謝をしたりという大事な役割をしているんです。
でも、起きている時でもちょっと休みたい時があるんですよね。そういう時は、何かをぐるぐる考えたりとか、色々迷ったりするんですけど、その時に活動しているのが、脳のいわゆる「デフォルトモードネットワーク」ですよね。
今まで経験したことを整理して、自分の中で腑に落ちるようにすると言うか、整頓すると言うか、そういう時間もとても大事なんですね。
ですから、気分が落ち込んだ時、僕もそうなんですけど、とりあえず休んでください。休むと言ってもどうすればいいのかと思うかもしれませんが、お風呂にゆっくり入るのでもいいし、好きな音楽を聴きながらソファーで目を瞑って寝転がっているのでもいいし。
あと、意外とオススメなのは、歩くこと。歩くと脳は休みます。
歩いているということは、もちろん体が動いているので心臓とかは一生懸命仕事をしているんですけど、歩いてぼんやり景色を眺めている時というのは、このデフォルトモードネットワークですね。脳がアイドリングして、その時に活動し始めるネットワークがありまして、これが色々脳の記憶の整理をしてくれたり、感情の歪みを取ってくれたりするんですね。
そうやって「整う」と、自然に元気になってくるんですよ。落ち込んだ時というのは、脳がちょっと「整えてください」とリクエストをしている、そういう時だと思ってください。その時に、無理してやる気出そうとしたりとか、仕事をしたりするとか(せずに)。まあ、締め切りがあったりとか、スケジュールとかで、仕方がない時もありますよ。
だけど、できれば、やっぱり休める時には休んで頂きたいなと、私は思いますね。
あと意外といいのは、アウトプットすることですね。例えば、自分の考えていることを一旦ノートなどに書き出してみる、と。これはね、先ほどから申し上げてるデフォルトモードネットワーク…色んな記憶を整理するネットワークのフィードバックのループを、外側に作るというイメージなんですけど、外に書き出すことで、より自分の思っていることなどが分かることもございます。
あと、セロトニンという意味においては、太陽に当たるというのが意外と大事なので、室内にいるよりは外に行って日差しを浴びたり、日差しの中で歩いたりするということもいいのかな、と思いますね。
とにかくね、落ち込まない人はいないんですから。落ち込んだのは、別にぱぱぱぱーやさんが悪いわけじゃないんです。どんな人でも落ち込みます。
そういう自分のことを「いいんだ」とまず受け入れて、そしてね、できれば少し脳を休めて頂くと、脳は元気になってきます。是非、心のゆとりを持って、落ち込んだ自分も素敵な自分ですから、受け入れて頂いて、時には脳をゆっくり休ませるということを試して頂けたらなと思います。

──無意識の垂れ流し
茂木:では、続きまして…、兵庫県 ラジオネーム <ヒサリナ>さんからのメッセージです。
いつも拝聴しております。
AuDeeの「ポジティブ脳教室で、茂木さんが、皆さんの質問に具体的にお答えされているのをお聴きして、とても参考になっています。
そこで、私もご相談があり、メールを送ってみました。
私は、人と会話をする時、自分の感想とか意見などを思うことがあっても、それを上手に言葉にする事が難しいと感じています。
「へー」とか「そうなんだー」などの簡単な言葉は思いつくのですが、具体的な言葉が思いつかないので、私の気持ちは伝わりません。
幼い時に、読書をあまりしてこなかったから?…など思ったりもしますが、何か方策があれば、ご指南をお願い致します。
茂木:そうですか。だけど、ヒサリナさんの文面はとても素敵な文面ですし、恐らく表現力はおありになるんだと思うんですよね。
これね、「脳科学的に『言葉を話す』ということがどういうことか」、ということについて、ヒサリナさん、そしてリスナーの皆さんにお伝えしたいことがあります。
「言葉を話す」というのは、言いたいことが頭の中で生まれてそれが出ていく、ということではないんですね。
皆さん、会話を思い出して頂きたいんですが、「まず、こういうことを言おう」と決めてから話すということも、あるとは思うんですよ。例えば、上司との大切な会話とか、友達に何か伝えなくちゃいけない時とか、「こういうことを言おう」と思ってから話すとは思うんですけど。でも、一番気楽な雑談とかそういう時には、勝手に言葉が出てきて、それで自分が「俺、こんなこと言ってるわ」と思う時はないですか?
あれが脳にとっては一番自然な状態なんです。
全く仕事になりますけど、私は1時間半ぐらいの講演会とかよくあるんですが、あらかじめ講演の内容を用意していくことはまずないんです。会場の方の反応とかを見ながら、臨機応変に内容を組み立てるんですが、90分喋るんですけど事前に何か用意しているわけではないんですね。勝手に言葉が出てくると言うか、脳の言葉で言うと「脱抑制」と言うんですけれども。
実はヒサリナさんの脳の中にも既にたくさんの言葉があるんですね。それはもう、今までの経験とかで積み重ねてあるんです。人と会話する時に一番自然にそれが出てくるのは、我々の意識がそれを邪魔しないことなんですね。
「うまく喋ろう」と思ったりとか、「今これを言おう」と思ったりすると、意外とうまく喋れないんです。ですから、逆に、もうある意味では「無意識の垂れ流し」と言うんですかね。そういう喋り方をするとうまくいくことが多いです。
ですので、よくお喋りな方っていらっしゃるでしょう? 僕は意外と人の話を聞くことも好きなので、「よくこの人喋るなぁ」と思いながらずっと頷いている時があるんですけど、そういう方は、ある意味では無意識の垂れ流しなんですね。無意識から、言葉がどんどん蛇口を捻ったように出ていって。だからあらかじめ内容が用意されていて、「よし、これを喋るぞ」と言って喋るわけではないわけなんです。
ヒサリナさんも、是非、言葉を出す時のイメージをそういうふうにして頂くと、喋りやすいのかな。事前に「喋ろう」、「こういうことを決めよう」と思って喋るのではなくて、自然に言葉が出てくる、という…だから、リラックスすると言うんですかね。緊張せずに自分を素直に出す、ということを心掛けて頂くと、話し上手になるのかなと思ったりも致します。
一方で、聞き上手ということもすごくいいことなんですよ。ヒサリナさんは、この文面読ませて頂く限り、相手の話を聞いて「へ~、そうなんだ」という相槌は打たれていると思うので、もうこれで十分だ、という言い方もできます。
ですから、聞き上手なヒサリナさん。その自分の中で色んな言葉がもうストックされているはずなんですよ。あとは、蛇口を捻ってそれを出すだけなんですね。是非、今度試してみてください。
脳は、最初に話すことを準備してからそれを出すのではなくて、むしろ無意識の中から言葉が出て行って、自分でもちょっとびっくりすることがある。そういう状態になった時に、実は一番よく話すことができます。
私ごとでございますが、「雑談力」について書いた本もございます。『最高の雑談力 結果を出している人の脳の使い方』、こちらが徳間書店が出ていますので、もし興味があったら読んでみて頂けたらなと思います。

●今夜ご紹介したような、茂木さんへのご質問メールは、すべて、メッセージフォームへお送りください。
お待ちしております!
●音声配信アプリ「AuDee」では、「茂木健一郎のポジティブ脳教室」を配信中です。
こちらでも、みなさんからのご質問にお答えしています。
(毎週・土曜日、夜10:30に更新)
●茂木健一郎(@kenichiromogi) / X(旧Twitter)公式アカウント
皆さんからお送りいただいたメッセージを、番組パーソナリティの茂木健一郎が、脳科学者として答えていきます!

──前頭葉のメタ認知
茂木:では、まず、こちらのメッセージから…。山口県 ラジオネーム <けんちゃん>さん。
茂木さん、私は幼少の頃から、人間関係に悩んでいます。
今はだいぶ上手くなったと思うのですが、嫌な事があると、まず、怒りが先に立ってしまいます。
もし、良い解消方法があれば、教えて下さい。
茂木:怒りが先に立ってしまうんですね。これはね、ある程度は仕方がないことなんです。
「怒り」、これは脳の扁桃体が出している不快のシグナルなんですけども、ある意味では生き物として素の反応なんですね。だから、「なんかちょっと嫌だなぁ」とか、「この人腹が立つな」と思うと怒りが出ちゃう、これは仕方がないんですけども…。その後なんですよね。
この扁桃体の怒りの反応というのは、ある意味ではね、時々、例えで「爬虫類の脳」と言われたりもしますけども、我々が進化の過程から持ってきた、1つの生き物としての働きなんですね。
それをどう解釈するか。そして、どのような行動に結びつけるか。これは前頭葉の働きなんですね。
この前頭葉というのは、人間が一番発達している、そして進化の過程で一番人間の脳の中で大きくなっている部位なんですけども、この前頭葉が扁桃体などを中心に、怒りの感情が生まれた時に、「それをどうしようか」というふうに解釈や判断をするわけですよね。
だから例えば、一番単純には、怒ったからちょっと怒鳴るとか、喧嘩しちゃうとか、これが1つのストレートな怒りの解釈でもあるんですが、他の解釈もできるんですよ。
例えばね、多くの場合、怒りがあるということは、実は自分が脅かされている時のことが多いんですね。
動物でもそうでしょう。ワンちゃんとか猫ちゃんとか、怒っている時というのはちょっと自分が脅かされている時ですよね。ですから、ひょっとすると、怒っている時はちょっと自分が圧迫されていると言うか、自分のスペースとか自分の立場が危うくなっている時かもしれないんですね。
そういう時には、相手に怒りをぶつけるよりは、自分の安全を確保するとか、自分をちょっと落ち着かせるとか、安心するとか、そういうふうにした方がいいことが多いんです。
あるいは、「怒り」と言うと、例えば嫉妬の感情とか、びっくりしたりとか、そういうことで怒ってしまうこともあるんですよね。
予想しなかった時に予想しないことが起こると、「どうしたらいいんだろう?」と戸惑ってしまって、その戸惑いの感情が怒りになったりする。まあ、色んな理由で怒るんですけども。
ですから、その怒りに結びついた様々な状況を、総合的に判断する。これが前頭葉の働きで、これがいわゆる「メタ認知」というものですね。
ですので、怒りが生まれることは仕方がないんですよ。人間なので、怒らないようにしようとすることは無理なんです。
問題は、「怒ってしまった後で、それをどう対処するか」、ということがとてもとても大事なんだと思います。
あと、実は脳は「行動主義」と言うんですけど、怒ったからと言って怒りの行動をすると、その行動によってまた心理が影響を受けてしまって、フィードバックして強まってしまうので、行動主義の考え方ですと「ちょっと微笑んでみようよ」と。心の中では怒っているだけど、作り笑顔でもいいので微笑んでみると、その「微笑む」という行動が脳の感情の中枢に作用して、怒りが和らぐということもあるんですね。
あと、深呼吸をする。これもね、落ち着かせるためにはとても大事です。
そのような形で、「笑顔を作ってみる」とか、「深呼吸をする」とか、こういう自分の行動を通して怒りの感情を抑えていく、ということも重要なやり方ではないかなと思います。
まず、怒ってしまう自分を否定しないでください。それは生き物として大切なことなので。
問題は、それをどのように解釈して行動に結びつけていくか、ということについて、今申し上げたようなことをヒントにしてくださったらな、と思います。
是非、この前頭葉の「メタ認知」を、少しずつ高めて頂けたらなと思います。けんちゃんさん、是非チャレンジしてみてくださいね。

──脳のデフォルトモードネットワーク
茂木:続きまして、埼玉県 ラジオネーム <ぱぱぱぱーや>さんからのメッセージです。
毎週様々なゲストの方と茂木さんのお話を楽しく拝聴しております。
色々な分野の方が出演するので、聴いているだけで視野が広がるだけでなく、学ぶことも多くあり、聴いた後、自分自身が少し成長できている気がしております。
これからも、為になる放送を楽しみにしています!
さて、茂木さんは気持ちが落ち込んだ時、どのように気持ちを切り替えていますか?
教えていただけたら幸いです!
茂木:僕はね、比較的陽気と言うか、朗らかな人と思われがちなんですが、そんな僕でも、当然落ち込むことはあるんですよね。
気分が落ち込んだ時にまず大切なのは、「自分のせいじゃないよ」ということです。今の世の中は「ポジティブシンキングが大事だ」とか言いますから、ちょっとでもネガティブで後ろ向きな気持ちになってしまうと、「それは良くないんだ」と罪悪感を感じたりしてしまいますけども、そんなことはないんですよ。
是非、落ち込んだ時には、まずそういう自分を受け入れて頂きたいな、と思うんですけども。
この「落ち込んだ気分」というのは、色々な要素で生まれます。例えば、脳内の神経伝達物質のセロトニンとかそういうものも関与してきますし、ドーパミンなんかも関与してくるんですけど、「失敗しちゃったな~」とか、「やる気が起きないな~」とか、そういう時に落ち込む状態になっているんです。その時というのは、実は基本的に脳は「ちょっと休みたいな」と思ってることは事実なんですよ。
この「休む」というのは、サボることとは違うんです。これはすごく重要なことで、脳は休んでいる時に、アクティブに活動をしている時とは別の活動をしています。眠っている時というのが一番わかりやすいですよね。寝ている時は脳が休んでいるんですけど、その時には記憶の整理をしたり、色んな老廃物を分解したり、新陳代謝をしたりという大事な役割をしているんです。
でも、起きている時でもちょっと休みたい時があるんですよね。そういう時は、何かをぐるぐる考えたりとか、色々迷ったりするんですけど、その時に活動しているのが、脳のいわゆる「デフォルトモードネットワーク」ですよね。
今まで経験したことを整理して、自分の中で腑に落ちるようにすると言うか、整頓すると言うか、そういう時間もとても大事なんですね。
ですから、気分が落ち込んだ時、僕もそうなんですけど、とりあえず休んでください。休むと言ってもどうすればいいのかと思うかもしれませんが、お風呂にゆっくり入るのでもいいし、好きな音楽を聴きながらソファーで目を瞑って寝転がっているのでもいいし。
あと、意外とオススメなのは、歩くこと。歩くと脳は休みます。
歩いているということは、もちろん体が動いているので心臓とかは一生懸命仕事をしているんですけど、歩いてぼんやり景色を眺めている時というのは、このデフォルトモードネットワークですね。脳がアイドリングして、その時に活動し始めるネットワークがありまして、これが色々脳の記憶の整理をしてくれたり、感情の歪みを取ってくれたりするんですね。
そうやって「整う」と、自然に元気になってくるんですよ。落ち込んだ時というのは、脳がちょっと「整えてください」とリクエストをしている、そういう時だと思ってください。その時に、無理してやる気出そうとしたりとか、仕事をしたりするとか(せずに)。まあ、締め切りがあったりとか、スケジュールとかで、仕方がない時もありますよ。
だけど、できれば、やっぱり休める時には休んで頂きたいなと、私は思いますね。
あと意外といいのは、アウトプットすることですね。例えば、自分の考えていることを一旦ノートなどに書き出してみる、と。これはね、先ほどから申し上げてるデフォルトモードネットワーク…色んな記憶を整理するネットワークのフィードバックのループを、外側に作るというイメージなんですけど、外に書き出すことで、より自分の思っていることなどが分かることもございます。
あと、セロトニンという意味においては、太陽に当たるというのが意外と大事なので、室内にいるよりは外に行って日差しを浴びたり、日差しの中で歩いたりするということもいいのかな、と思いますね。
とにかくね、落ち込まない人はいないんですから。落ち込んだのは、別にぱぱぱぱーやさんが悪いわけじゃないんです。どんな人でも落ち込みます。
そういう自分のことを「いいんだ」とまず受け入れて、そしてね、できれば少し脳を休めて頂くと、脳は元気になってきます。是非、心のゆとりを持って、落ち込んだ自分も素敵な自分ですから、受け入れて頂いて、時には脳をゆっくり休ませるということを試して頂けたらなと思います。

──無意識の垂れ流し
茂木:では、続きまして…、兵庫県 ラジオネーム <ヒサリナ>さんからのメッセージです。
いつも拝聴しております。
AuDeeの「ポジティブ脳教室で、茂木さんが、皆さんの質問に具体的にお答えされているのをお聴きして、とても参考になっています。
そこで、私もご相談があり、メールを送ってみました。
私は、人と会話をする時、自分の感想とか意見などを思うことがあっても、それを上手に言葉にする事が難しいと感じています。
「へー」とか「そうなんだー」などの簡単な言葉は思いつくのですが、具体的な言葉が思いつかないので、私の気持ちは伝わりません。
幼い時に、読書をあまりしてこなかったから?…など思ったりもしますが、何か方策があれば、ご指南をお願い致します。
茂木:そうですか。だけど、ヒサリナさんの文面はとても素敵な文面ですし、恐らく表現力はおありになるんだと思うんですよね。
これね、「脳科学的に『言葉を話す』ということがどういうことか」、ということについて、ヒサリナさん、そしてリスナーの皆さんにお伝えしたいことがあります。
「言葉を話す」というのは、言いたいことが頭の中で生まれてそれが出ていく、ということではないんですね。
皆さん、会話を思い出して頂きたいんですが、「まず、こういうことを言おう」と決めてから話すということも、あるとは思うんですよ。例えば、上司との大切な会話とか、友達に何か伝えなくちゃいけない時とか、「こういうことを言おう」と思ってから話すとは思うんですけど。でも、一番気楽な雑談とかそういう時には、勝手に言葉が出てきて、それで自分が「俺、こんなこと言ってるわ」と思う時はないですか?
あれが脳にとっては一番自然な状態なんです。
全く仕事になりますけど、私は1時間半ぐらいの講演会とかよくあるんですが、あらかじめ講演の内容を用意していくことはまずないんです。会場の方の反応とかを見ながら、臨機応変に内容を組み立てるんですが、90分喋るんですけど事前に何か用意しているわけではないんですね。勝手に言葉が出てくると言うか、脳の言葉で言うと「脱抑制」と言うんですけれども。
実はヒサリナさんの脳の中にも既にたくさんの言葉があるんですね。それはもう、今までの経験とかで積み重ねてあるんです。人と会話する時に一番自然にそれが出てくるのは、我々の意識がそれを邪魔しないことなんですね。
「うまく喋ろう」と思ったりとか、「今これを言おう」と思ったりすると、意外とうまく喋れないんです。ですから、逆に、もうある意味では「無意識の垂れ流し」と言うんですかね。そういう喋り方をするとうまくいくことが多いです。
ですので、よくお喋りな方っていらっしゃるでしょう? 僕は意外と人の話を聞くことも好きなので、「よくこの人喋るなぁ」と思いながらずっと頷いている時があるんですけど、そういう方は、ある意味では無意識の垂れ流しなんですね。無意識から、言葉がどんどん蛇口を捻ったように出ていって。だからあらかじめ内容が用意されていて、「よし、これを喋るぞ」と言って喋るわけではないわけなんです。
ヒサリナさんも、是非、言葉を出す時のイメージをそういうふうにして頂くと、喋りやすいのかな。事前に「喋ろう」、「こういうことを決めよう」と思って喋るのではなくて、自然に言葉が出てくる、という…だから、リラックスすると言うんですかね。緊張せずに自分を素直に出す、ということを心掛けて頂くと、話し上手になるのかなと思ったりも致します。
一方で、聞き上手ということもすごくいいことなんですよ。ヒサリナさんは、この文面読ませて頂く限り、相手の話を聞いて「へ~、そうなんだ」という相槌は打たれていると思うので、もうこれで十分だ、という言い方もできます。
ですから、聞き上手なヒサリナさん。その自分の中で色んな言葉がもうストックされているはずなんですよ。あとは、蛇口を捻ってそれを出すだけなんですね。是非、今度試してみてください。
脳は、最初に話すことを準備してからそれを出すのではなくて、むしろ無意識の中から言葉が出て行って、自分でもちょっとびっくりすることがある。そういう状態になった時に、実は一番よく話すことができます。
私ごとでございますが、「雑談力」について書いた本もございます。『最高の雑談力 結果を出している人の脳の使い方』、こちらが徳間書店が出ていますので、もし興味があったら読んでみて頂けたらなと思います。

●今夜ご紹介したような、茂木さんへのご質問メールは、すべて、メッセージフォームへお送りください。
お待ちしております!
●音声配信アプリ「AuDee」では、「茂木健一郎のポジティブ脳教室」を配信中です。
こちらでも、みなさんからのご質問にお答えしています。
(毎週・土曜日、夜10:30に更新)
●茂木健一郎(@kenichiromogi) / X(旧Twitter)公式アカウント